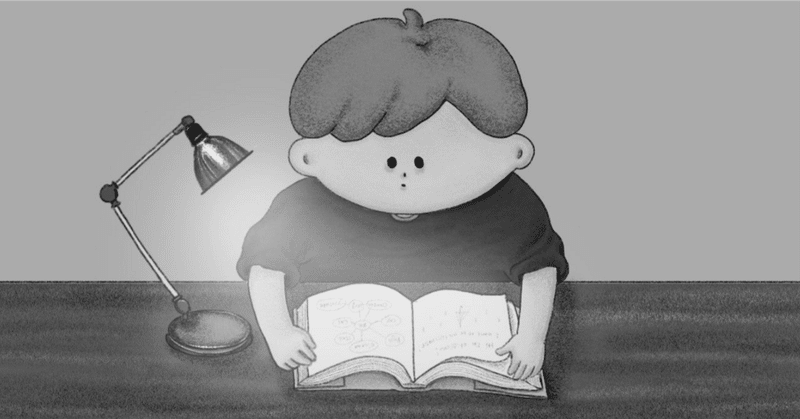
予備試験民法 94条2項
0 はじめに
こんにちは。今日も記事を読んでいただきありがとうございます。
今日は、予備試験や司法試験の民法でも頻出の94条2項について考えていきたいと思います。私は学者や予備校講師というわけではないので、あくまで私の考えたことをお伝えするものであるということをご留意の上、お読みくだされば幸いです。
1 94条1項
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
予備試験・司法試験の民法において、94条2項はかなりの頻出分野となっています。しかし、94条2項については、ロースクールのみならず、大学法学部に入った人であっても、民法の授業でかなり最初の方に学習するため、知っているという方も多いと思います。
そのためか、予備試験・司法試験において民法94条2項が問われた場合、多くの人が一通りの論点を書くことができるかと思います。
(1) 要件
94条1項は、まず、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」が「無効」であることを規定しています。ここでは、要件が「相手方と通じてした」「虚偽の意思表示」で、効果が「無効」であることが読み取れます。
「相手方と通じてした」というのが、いわゆる「通謀」と呼ばれるもので、「虚偽の意思表示」が「虚偽表示」と呼ばれるもので、94条1項は「通謀虚偽表示」と呼ばれることが多いです。
意思表示は、動機→内心的効果意思→表示意思→表示行為という過程を経てなされることが多いですが、一般的には内心的効果意思以降の部分を指すと考えておけば良いと思います。
そして、「虚偽の意思表示」とは、意思表示の過程における内心的効果意思と表示行為の不一致のことをいいます。
また、「相手方と通じてした」とは、表意者とその相手方の間で、虚偽の意思表示があるように装う合意をしていることをいいます。
(2) 効果
「相手方と通じてした」「虚偽の意思表示」、つまり表意者が通謀虚偽表示を行った場合、それによる意思表示は「無効」となります。
例えば、Aさんが自分の債権者から土地を差し押さえられるおそれがあったため、これを免れるために、Bさんと協議して土地の登記名義をBさんに移すことにして、AB間で売買がないにもかかわらずこれをあったものと装った場合、「相手方と通じてした」「虚偽の意思表示」に当たります。
そうすると、AB間の売買は94条1項の要件を満たすため、「無効」であるという効果が生じることになります。
このように通謀虚偽表示が無効とされるのには、以下のような理由があります(多分覚えなくてもいいと思います)。こちらの理由については、平野教授の『コア・テキスト民法Ⅰ民法総則[第2版]92頁』に挙げられていたものです。
法律効果を発生させる意思がない。
当事者(特に相手方)を保護する必要がない。
表意者の債権者を保護する必要がある。
以上、とりあえず、94条1項については、「相手方と通じてした」「虚偽の意思表示」という要件を満たす意思表示は「無効」であり、具体的事案が「相手方と通じてした」と「虚偽の意思表示」に当たるのかを当てはめることが重要になると認識しておく必要がありそうです。
2 94条2項
(1) 94条2項の意義
94条1項には、次のような効果もあります。
(虚偽表示)
第94条
②前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
つまり、94条1項の通謀虚偽表示による意思表示の無効は、「善意の第三者に対抗することができない」という効果です。
これは、上述の例を使うと、Aさんが自分の債権者から土地を差し押さえられるおそれがあったため、これを免れるために、Bと協議して土地の登記名義をBに移すことにして、AB間で売買がないにもかかわらずこれをあったものと装った場合において、Bさんが自分に土地の登記名義があることをいいことに善意のCさんに対して土地を売却してしまったとき、AさんはCさんに対してAB間の売買が無効であることを主張することができない、ということを意味します。
このような効果が認められるのには、以下の理由があります。
虚偽の外観を信頼して取引をした第三者の取引安全を保護する必要がある(取引安全保護制度)。
虚偽の外観を信頼した第三者を犠牲にしてまで自ら外観を作出した者を保護する必要はない。
この理由は今後何度か登場する「権利外観法理」という考え方を用いる場面で何度か使うものになるので、ここで覚えておくのがいいと思います。
「権利外観法理」は、民法においては、有名なものとして、表見代理(119条、110条、102条)や表見受領権者(478条)といった場面で登場します(なお、192条の即時取得は表見法理ではないので注意しましょう)。
では、「無効であることを対抗することができない」とは、表意者が善意の第三者に対して「虚偽表示による無効を主張することができない」ことを意味しますが、これはどのような状態を意味するのでしょうか。
この点は、特に予備試験の受験生の方であれば、要件事実を勉強する必要がありますから知っておかなければなりません。
ア 法定承継説
法定承継説とは、94条2項の効果、つまり「無効であることを対抗することができない」ことによって、表意者と善意の第三者との間で直接取引があったのと同様の効果を生じるとする考え方です。
これは、94条1項による「無効」が94条2項によって「有効」に変わるのではなく、表意者と相手方の間の意思表示があくまで「無効」であることを前提に、表意者と第三者との間で「有効」な取引があったとします。
上の例で説明すると、Aが、AB間の売買の虚偽表示による無効を、善意のCに対して対抗できない結果、AからCに対して直接土地が売買されたものと扱われる、という効果が生じることになります。
上の例で、AがCに対して、土地所有権に基づく妨害排除請求として所有権移転登記抹消登記手続請求をしたとします。このとき、Aは、請求原因としてAが土地所有権を有していることを主張します。
これに対して、Cは、Aの請求は認められないというために、AB間で土地の売買契約が締結されたことを主張します。売買契約が締結されれば、他人物売買でない限りそれだけで売買の目的物の所有権が移転するため、この主張が認められれば、Aの主張は認められず、Cの反論が奏功します。これを所有権喪失の抗弁といいます。
Cの反論が認められた場合、Aは土地の所有権を失ったことになるため、Aの請求は認められないことになってしまいます。そのため、Aは、再反論として、94条1項に基づき、Cが反論で主張した売買契約は虚偽表示により無効であると主張します。
Aの再反論が認められたとすると、AB間の売買契約はなかった、つまりAからBに土地の所有権が移転したことはなかったことになるため、Aはなお土地の所有権を有していることになります。
そこで、Cは、自分は94条2項の「善意の第三者」に当たるため、Aの94条1項による「無効」の再反論は認められない、と再々反論することになります。
法定承継説からは、この再々反論は、AB間の売買契約は無効であるものの、AC間に直接所有権が移転したという主張を意味します。そうすると、この再々反論は、Aの虚偽表示による無効の再反論(再抗弁)を前提としつつその効果を失わせる(有効に変える)主張ではなく、Aの虚偽表示による無効の再反論(再抗弁)によってCの反論が認められない結果となったことを前提とした、Aの所有権を失わせる別の所有権喪失の抗弁に位置づけられることになります。
このように、一つ目の抗弁が認められないことを条件に主張する二つ目の抗弁を、予備的抗弁といいます。
以上から、法定承継説からは、94条2項に基づく抗弁は、予備的抗弁に位置づけられることになります。
イ 順次取得説
これに対し、順次取得説は、94条2項の効果、つまり「無効であることを対抗することができない」ことによって、表意者と相手方の意思表示が有効になり、善意の第三者は表意者の相手方から有効に所有権を取得することができる、とする考え方です。
この考え方によれば、上の例で、Cの94条2項に基づく再々反論は、AのCに対する94条1項に基づく虚偽表示による売買契約の無効の再反論(再抗弁)の効果を失わせるものとして、再々抗弁に位置づけられることになります。
このように、94条2項の効果について、法定承継説に立つか、順次取得説に立つかによって、94条2項に基づく主張がどこに位置づけられるかについて差が生じるため、注意が必要です。予備試験では要件事実が問われますので、この点については必ず理解しておくようにしましょう。
ウ 論文式試験で注意すること
一般的に、民法の論文式試験では、必ずしも要件事実にガチガチに従った構成で答案を書く必要はないとされており、その意味で正面から法定承継説と順次取得説の対立が現れない限り両説の対立をそこまで意識する必要はないです。
しかし、以下の場合には、法定承継説と順次取得説とで法律構成の説明に違いが生じるので、その場合には両説を意識した論述が求められます。
上の具体例で、さらにBが善意のCだけでなく善意のDにも土地を譲渡したといった場合、Dも94条2項の「善意の第三者」に当たることになります。
この場合、結論からいえば、CとDは177条の対抗問題としてその優劣が決せられることになります。
論文式試験では、できれば「なぜ177条の対抗問題になるのか」について説明したほうがいいです。このとき、その説明の仕方で法定承継説と順次取得説の違いが現れます。
つまり、法定承継説の立場からは、CもDも共に94条2項の「善意の第三者」に当たるわけですから、その効果としてAからC、Dへとそれぞれ土地が譲渡されたことになります。そうすると、法定承継説の立場からは、「C、DはAを中心とした二重譲渡の譲受人の関係に立つ」ため177条の対抗問題になると説明することになります。
これに対し、順次取得説の立場からは、CさんもDさんも共に94条2項の「善意の第三者」に当たる結果、その効果としてAさんからBさんに土地所有権が移転し、BさんからCさん、Dさんへとそれぞれ土地が譲渡されたことになります。そうすると、順次取得説の立場からは、「C、DはBを中心とした二重譲渡の譲受人の関係に立つ」ため177条の対抗問題になると説明することになります。
このように、要件事実以外の場面でも法定承継説と順次取得説の理解を前提とした論述が問われる場合はあるので、注意しておく必要があります。
(2) 「善意の第三者」
まず、「第三者」の意味について、当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽表示による意思表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を意味するとされています。
この「第三者」の意味は、何回も唱えて必ず暗記しておきましょう。
次に、「善意」とは、表意者と相手方との間の意思表示が虚偽表示に当たることについての善意、つまり虚偽表示であることを知らなかったことを意味します。
「善意」や「無過失」については、「何についての」善意・無過失か、ということを常に意識するようにしましょう。
ここからは、みなさんが知っている論点になります。以下の論点については、正直特に解説することはなく、みなさんがご存じの論証をペタッと貼り付けるしかありません。当てはめ以外で差はつきません。
ア 「善意」とは無過失も必要か
まず、94条2項の「善意」とは、無過失であることを要するか、という点に争いがあります。
正直なところ、予備試験や司法試験で無過失必要説を採る受験生はいないと思うので、無過失であることまでは不要である、と結論を書けばいいと思います。判例も無過失不要説に立っています。
理由については、①条文上「善意」しか要求されていないこと、②表意者の帰責性が大きいこととの利益衡量上「無過失」を要求すべきではないこと、を書けばいいと思います。
イ 「第三者」として保護されるためには登記も必要か
次に、94条2項の「第三者」として保護されるためには、登記が必要か、という点にも争いがあります。
この点についても、登記必要説を採る受験生はかなり少ないと思います。なので、登記は不要である、と結論を書けばいいと思います。判例も登記不要説に立っています。
理由については、①条文上登記は要求されていないこと、②表意者と第三者は前主後主の関係に立ち対抗関係には立たないこと、③表意者の帰責性が大きいため権利保護要件としての登記も不要であること、を書けばいいと思います。
予備校の本によっては「対抗要件としての登記が必要か?」という論点と「権利保護要件としての登記が必要か?」という論点に分けて説明されている場合もありますが、理由付けのところでまとめて書けば十分だと思います(上の②と③)。判例も545条1項ただし書の「第三者」について登記が必要としていますが、それが対抗要件としての登記なのか権利保護要件としての要件なのかはよく分かりません。なので、まとめて書けばいいと思います。
ウ 「第三者」には転得者も含まれるか
さらに、94条2項の「第三者」には転得者が含まれるか、という論点もあります。
この点についても、転得者も含まれる、という結論を書けばいいと思います。
理由については、第三者と転得者について別異に取り扱うべき理由がないこと、を挙げればいいと思います。
この論点は、次で説明する善意の第三者からの転得者の場面とは逆に、悪意の第三者からの善意の転得者の場面で登場します。転得者も「第三者」に含まれるとする見解からは、善意の転得者も94条2項によって保護されることになります。
エ 善意の第三者からの悪意の転得者
最後に、善意の第三者からの悪意の転得者はどのように取り扱われるのか、という点について、法律構成をどのように考えるべきなのかの議論があります。
この点については、絶対的構成と相対的構成という考え方を押さえておく必要があります。
絶対的構成というのは、善意の第三者が現れた時点で表意者は善意の第三者に対して94条1項による無効の効果を対抗できなくなる結果、善意の第三者からの転得者は94条2項によって保護される善意の第三者の地位を承継するとする考え方です。
これに対し、相対的構成というのは、転得者が保護されるためには転得者自身が94条2項の「善意の第三者」に当たる必要があるとする考え方です。
これについては、ほぼ全ての受験生が絶対的構成の立場に立つと思いますので、みなさんも絶対的構成で書くのがいいと思います。
理由としては、①相対的構成を採ってしまうと、善意の第三者が悪意の転得者から債務不履行責任を追及されるおそれがあり、善意者保護を図った94条2項の趣旨に反すること、②絶対的構成の方が法律構成として簡明であること、③絶対的構成の方が法律関係の早期安定に資すること、を挙げるとよいと思います。
そして、絶対的構成の立場に立ち、上記の理由、結論を述べた後、転得者が善意の第三者を意図的に介在させた(「わら人形」などと呼ばれる)というような特段の事情がある場合には、転得者は例外的に善意の第三者の地位を援用することが許されない、ということも付け加えるのがいいと思います。
3 さいごに
今回は民法94条について長々と書いてきました。
論点については少しでも法律の勉強を始めた方であれば結構なじみ深いものであり、比較的簡単だと思います。
しかし、法定承継説や順次取得説の対立など、細かいところを頑張ろうとすると意外と難しい条文でもあります。
このページをみて参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
