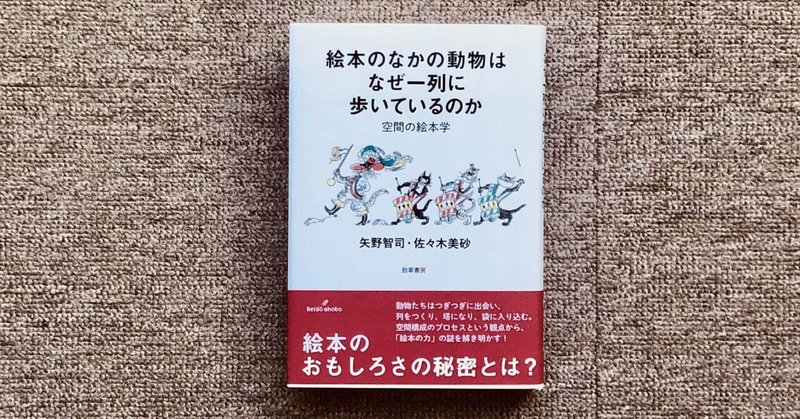
「絵本のなかの動物はなぜ一列に歩いているのか 空間の絵本学」(矢野智司・佐々木美砂著、勁草書房)
読了日: 2023/11/9
絵本をテーマにした著作を読むのは初めてでした。なんとなくそそられるタイトルだったので、ほしいものリストに入れておきながら図書館をあたったのですが、いつも貸し出し中でほかの方への興味もそそっていたのでしょう。躊躇したのですが結局購読しました。
小生にとって記憶に残っている絵本は残念ながらないのですが、最近では大人が自身用に購入するケースもあるようで、そのあたりの魅力にも本書では少し触れています。
これまで絵における美術論的アプローチや、文章における物語論的アプローチは、これまでの絵本研究にはあったそうです。本書は「空間構成のプロセス」と「均衡回復」という検討をもとに多くの絵本を類型化(体系化)してパターンを分析しようとするものです。
このアプローチにより、「積み木型絵本」(行列型、積み込み型、積み木型)と「入れ子型絵本」(てぶくろ型、入れ子型)に分類されています。この分類プロセスが各章にて記載され、それぞれの参考へ本も紹介されています。
絵本をじっくり見てゆくことはおそらくしないとは思いますが、この参考絵本を見て回ると本書の魅力がより体験できるのだろうと想像します。そして全体のまとめを10章(終章)の「絵本世界論構築に向けての12のテーゼ」にて括られています。
論理だけを連ねるのではなく、作例も掲載されているので納得感が増します(致し方ないですが、掲載作例がモノクロであることが残念でした)。
日本語の絵本ではオノマトペを用いて効果的な構成になるケースが多いようですが、これは『言語の本質』(今井むつみ、秋田喜美著、中公新書)とも一部関連あります。他方例えば英語などではオノマトペの活用はあまりないようで(この点も『言語の本質』に記載あり)、逆に”韻を踏む”リズム感の構成が役立つのではないかと感じました。
さて、タイトルの『絵本のなかの動物はなぜ一列に歩いているのか』の”一列”は本書内容のすべてをカバーする類型ではありません。しかしながら、このタイトルから想像する絵は誤差はあれど多くの人にイメージしやすい描写だと思います。実際には列以外のさまざまな集合や場面があるのですが(あることが読了後に分かりました)、動物が一列に歩く様子は絵本を想像するにもっとも適当に感じました。前半部を読んでいるうちは、あれ一列の体系はあまり主体系ではないな、と感じましたが読了後は納得しました。
ところで、著者の矢野智司氏(京都大学名誉教授、教育学)の京都へと佐々木美砂氏が転居されてきたところからより継続的に本研究が進められ、本書出版にいたったそうです。近隣での出会いによる本であることは少し親近感がわいてきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
