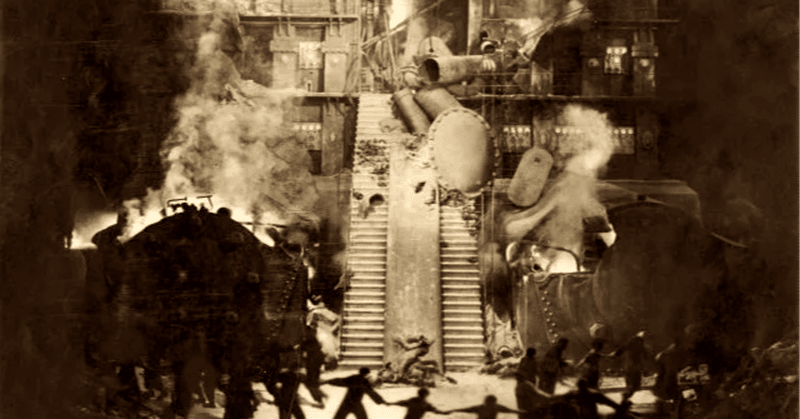
【試論「人工知能概念はいつから存在したといえそうか?」7パス目】「適者生存」理論の実際の生存競争の現場における驚くべき多様性について
以下の投稿ではデボン期(4億800万年前~3億6000万年前)、甲殻類(エビやカニの祖先)による捕食を忌避して汽水域(河川と海洋の接続部)に逃げ込んだ魚類の先祖が、海洋生物の大量絶滅を契機に海に戻る景色を描きました。
汽水域(河川と海洋の接続部)、または(さらに陸の奥に踏み込んだ)淡水域に生息していた甲殻類が海に戻って新たな「百獣の王=食物連鎖の頂点」の座を獲得したのもこの時代の話です。
サメなどの軟骨魚類は、前期デボン紀には存在していたが、歯の化石には、それよりも古いシルル紀末期のものもあるため、厳密に言えば、起源は前代のシルル紀にあると考えられる。サメの祖先は不詳であるが、棘魚類に求める説が強い。例えばデボン紀の地層から知られるドリオドゥスは、棘魚類と軟骨魚類の共通の特徴を持っている。代表的なデボン紀の軟骨魚類として、全頭類のクラドセラケが知られる。捕食生物であり、少なくとも5対の鰓を有し、硬い歯、背びれ、尾びれの形状と、現生のサメと変わらない形態をしていた。現生のサメを含む板鰓類も出現しており、初期のグループとしてCtenacanthiformesなどが知られる。
ところで海外ネットには古くから鮫の脳の外観が女性の子宮の形と似てるのに注目して「女性は子宮で考える=鮫の様に考える」と揶揄するmemeが存在したりします。



この様に鮫は蹴球(匂いを感じる感覚器官)が異様に発達していて、これと脳を結ぶ臭索も太く、それが卵巣と子宮本体を結ぶ卵管に重なって見える訳です。これを「(大海に滴った一滴の血液を嗅ぎつけて集まってくる)貪欲さ」と結びつけようという作戦なのですね。
てかここの山田の作画テキトーすぎんか?🤔😅#僕ヤバ pic.twitter.com/PTI22HsLus
— X・ッシュ🩻/市川digi太郎 (@reocrocche) April 23, 2024
イメージ的には九井 諒子「ダンジョン飯」に登場する「悪食王ライオスの呪い」みたいな感じ?



しかしこの伝統的memeには「内臓自体には普通、海綿動物(Sponge)並の知性しか存在しないものなのに、その時点でもう鮫並みなら総合力で女の圧勝じゃないか」なる伝統的返しが存在します。以下の投稿で触れた考え方の応用という訳ですね。
神経細胞が全身に分散しているクラゲやイソギンチャクの場合、内臓感覚の延長線上で感覚器官からの入力に従って全身の筋肉を操っている。ちなみに人間の消化器官にも同程度以上の神経が張り巡らされており、相応の「知性」や学習能力を備えている事が明らかになっている。
Spongeにはスラングで「居候」「大食漢」という意味もあります。悪口合戦なので同時に「男の方がよっぽど食うじゃねぇか!!」「この役立たずの穀潰しめが!!」と罵り返している訳です。

そして自明の場合としてSpongeなる表現、充血して大きくなる男性器も揶揄の対象に含めています。「お前らこそち○こでしか物を考えないくせに!!」むしろ最初にこちら側の罵倒が存在し、それへの返しとして「鮫の脳=子宮」表現が派生したとする説も。


それにつけても「通常時$${\frac{1}{6}}$$」なる認識は衝撃…私は父方の故郷が長崎だったので、子供の頃親に連れられて里帰りすると、その日の磯狩りの成果を適当に煮込む磯鍋の相伴に預かったものですが、そこにアメフラシが混ざっていると拳大くらいの奴が小指くらいに縮んでたのを思い出しました(毒を蓄えてる可能性がある上、内臓も抜いてないし見るからに美味しくなさそうなので、食べずに捨ててた)。
「首から上なんて飾りです」なる生存戦略
ここで興味深いのがアメフラシだけでなく貝類なども多くが「脳」を備えてない割に「目」はあって存外活発に動き回る事。ヴィーガン(菜食主義者)の中には「二枚貝には中枢神経がないので実質植物」「特にカキやホタテなどは植物プランクトンや藻やデトリタス(生物の死骸や排出物)しか食べないので実質植物」なる方便で積極的にタンパク質補給限に利用している人もいるそうですが、本当にこれらの生物は「知性など備えてない」と簡単に断じてしまってよいものなのでしょうか?
ホタテガイは何を感じ、何を思っているのか?
ヴィーガンを6年だかやってた人が身体を壊して恐る恐る鶏肉を食べたら一気に体調が回復するわ脳汁が出過ぎたのか人間を含め全ての生物は終わることがない捕食と被捕食の輪廻の中に生きていると悟りを開いた話 頭がおかしくて好き
— lillilMиMиMиizluv (@lillilmimimiiz) May 9, 2024
「当事者」に直接理由を尋ねる方法はいまだに見つかってない為、以下はあくまで憶測に過ぎないのですが…
人工知能を「予測誤差を最小限に減らすアルゴリズム」と一言で要約し、生物の「快を求め、不快を避ける本能」を対峙させるものとする。

この本能自体はごく原始的な単細胞生物ですら備えており、ここでいう「快」が「それなりに十分に」生存に有利な条件に、「不快」が「それなりに十分に」生存に不利な条件に対応している主体のみが淘汰を生き延びる構造になっている事自体は想像に難くない。
走性(英語: taxis,複数形 taxes)は、方向性のある外部刺激に対して生物(または細胞)が反応する生得的な行動で、運動性を示し刺激による移動が明らかな場合をいう。刺激源に向かう場合を"正"、反対方向に向かう場合を"負"と表現する。
正の走性(positive taxis):例えば、原生動物鞭毛虫類のミドリムシ(ユーグレナ)属は光を当てると光源に向かって移動する。ここでの方向性をもつ刺激は光で、生物の指向性(方向を示すような)運動は光に対してである。つまり、光が刺激なので、刺激源に向かうことから正を付け正の走光性と呼ぶ。
負の走光性(negative taxis):光の届きにくい海中、濁った湖中などのプランクトンには生命維持の為にある種の負の重力走性が必要と考えられるが、そのような無脊椎動物はこれを感知する感知器官を備えていない為、未知のメカニズムが存在すると推測され、日本の国立遺伝学研究所などで研究が進められている。
また刺激の種類によって走光性(phototaxis=光刺激への反応)、走圧性(barotaxis=圧力刺激への反応)、走化性 (chemotaxis=化学的刺激への反応)走地性(geotaxis=重力への反応)などと呼び分けられる上、感覚器官のタイプによって、生物が反応の方向を決めるために絶え間なく環境のサンプルを取り続ける屈曲走性 (klinotaxes) 、左右対称の感覚器を反応方向を決めるために用いる転向走性 (tropotaxes)、転向走性に類似しているが定位運動を確立するのに一つの器官で十分な目標走性 (telotaxes) に分類される。
ここでいう「主体」は個体の場合は細胞の集合、コロニー(群)の場合は個体の集合によって構成され、それぞれの単位ごとにその準安定状態(metastable state)を観測される事になる。人工知能自体はこの観点において「観察対象」となる条件を満たしておらず、かつまた将来満たす事もないと思われる。
真の安定状態では無いが、大きな乱れが与えられない限り安定に存在できるような状態。準安定状態は小さな乱れに対しては安定であるが、大きな乱れが与えられると不安定になり、真の安定状態へ変化してしまう。
準安定状態は非平衡状態なので、いつかは真の安定状態へ変化するが、その変化の時間が非常に長いのが特徴である。
準安定状態(metastable)にある魔が実際には存在しないと考えるべき理由は存在しない。実際酵素は準安定状態にあるマックスウェルの魔といってよく、これは早い粒子と遅い粒子とを区別するかわりに、おそらく何かこれに相当する操作によって、エントロピーを減少させるのであろう。生体とくに人間自身もこの考え方で見る事が出来よう。酵素や生体は確かにどちらも準安定な状態にある。酵素の安定な状態とは効目のなくなる事であり、また生体の安定な状態は死ぬ事である。全ての触媒はしまいには効かなくなってしまう。触媒は反応速度を変えるものであって、真の平衡状態を変えるものではない。しかし触媒も人間もどちらも、十分はっきりした準安定状態をもつので、これらは比較的恒久性のある状態と考えてよいほどである。
こうした相似性が観測される一方「カンブリア爆発期(5億4200万年前~5億3000万年前)に視覚と視覚情報を処理する脊髄を手に入れた」左右相称動物(Bilateria)」と、あえてこのトレンドに乗らなかった放射相称動物(Radiata)の間には決定的な情報処理速度の違いが生じる展開を迎えたのです。
そして人類史の時代に入ると、さらなる「情報処理速度革命」が勃発。
このシリーズでいうところの「大数学者や大物理学者の時代(大航海時代~1848年革命の頃)」に勃発した「科学諸表革命」。1617年に英国の数学者ヘンリー・ブリッグス(Henry Briggs,1561年~1630年)が常用対数表を出版し、これを手計算する対数尺も発明されて以降多くの計算結果が出版される様になり、科学計算の負担が大幅に軽減される事になった。
1616年、ブリッグスはエディンバラのネイピアを訪ね、対数について話し合った。翌年も同様の目的でネイピアを訪ねている。これらの話し合いで対数の底を10に変更するというブリッグスの提案が受け入れられ、1617年に1000までの常用対数を計算した結果を Logarithmorum Chilias Prima と題して出版した。
1624年には、3万個の自然数(1から20,000までと90,000から100,000まで)の常用対数を小数点以下14桁まで計算した対数表 Arithmetica Logarithmica を出版。また、正弦と正接の対数値の数表も数百の角度ごとに小数点以下14桁まで計算したものを完成し、さらに正弦関数の数表を15桁、正接関数と逆余弦関数の数表を10桁まで計算した。これらは1631年ゴーダで印刷され、1633年に Trigonometria Britannica の名で出版された。
このシリーズでいうところの「機械学習と意味分布論の時代(第二次世界大戦期~現在)」の発端となったコンピューター革命。それまで科学諸表出版の裏方として働いてきた計算手(Computer)の機械化に端を発している。
電子計算機が実用化される以前の時代において、研究機関や企業などで数学的な計算を担当していた人間のことである。現在では「コンピュータ」と言えば電子計算機を指すが、当時は"computer"という語の成り立ちが表す通り「計算する人間」のことであった。数人から数百人のチームを構成し、巨大で複雑な計算を分担し同時に並行して行った。
19世紀までは若手研究者がこの仕事を任されることが多く(当時の研究職の男女比に従えば当然のことであるが)計算手は男性ばかりであった。しかし、エドワード・ピッカリング(Edward Charles Pickering, 1846年~1919年)がハーバード大学天文台の計算手やデータ解析要員として女性を多く採用したことで、その後女性が計算手となる機会が増加し、また天文学分野での女性研究者の進出へと繋がった。さらに第二次世界大戦中は徴兵によって男性研究者が減ったため、計算手は専ら女性の仕事となった。ENIACの最初の6人のプログラマは、弾道計算のための計算手として雇われていた女性の中から選ばれた。
しかし時代の流れは常に一筋縄ではいかないものです。
ゼロックス社長のデヴィッド・カーンズは、のちにアルトのプレゼンテーションを「テクノロジーの祭典」と呼び、「テクノロジーの未来を見たと誰もが口々に言っており、非常に印象深かった」と振り返っている。だが、プレゼンテーションを終えたPARCのチームは、幹部のそんな熱意などまったく感じなかった。
それどころか、その場で実際に体験できる時間を設けた際、アルトの前に座ってキーボードを操作し、マウスを試していたのは、ゼロックスの幹部ではなく彼らの妻たちだった。キーを打つのは女性事務員の仕事と考えているらしい夫たちは心を動かされた様子もなく、腕組みをして会場の端から遠巻きに眺めているだけだった。
研究員のひとりは、ある幹部役員がこう言ったのを耳にしている。「男であんなに早くキーを打てる人間は見たことがないな」。つまり、明らかに目のつけどころを間違えていたのだ。
のちにゼロックスは、アルトの後継機種の商品化に動き出している。従って、ゼロックスがFutures Dayで示されたテクノロジーにまったく興味をもたなかったとは言い切れない。しかし、テイラーがあのときに見た幹部たちの反応──無関心と無理解と拒絶が入り混じったもの──は、考えてみれば当然とも言える。
当時のゼロックスは、収益の大半が複写機の用紙販売によるものだった。ところがカリフォルニア発の新興勢力は、オフィスワークの未来はスクリーンにこそあると主張した。それが現実のものになれば、「紙」の未来は揺らぐことになる。
ゼロックスがオフィスのペーパーレス化に危機感を抱いていたとすれば、PARCが提唱した技術のうち、やがてこの会社が市場にもち込んで利益を上げるものがレーザープリンターだったのも驚くには当たらない。これだけが唯一、紙を消費する技術だったのだから。
日本の大手メーカーが「ワープロは無くならない」と予想してた事が話題ですが、この事から分かるのは「未来は予測できない」という事で、我々にできるのは「あらゆる可能性に備えて分散する事」だけです。
— ネア (@stop_zouzei) May 2, 2024
日本人は「絶対正しい予想」がある前提で政府に全ベットですが、市場や地方に権力を移すべき。 pic.twitter.com/ozcTkAhXml
藤井七段が放った一手をAIと比較して話題になっていることに対し「そもそも棋士のひらめきが日ごろ軽視されている」と加藤一二三先生がツイートしており、将棋とAIの未来やご自身の姿勢を豊かで美しい言葉で語ったこの方を好きになったのだったと思い出した 高校生の時にネットで読んだ50年前の文章 pic.twitter.com/FIwfu0OGr3
— 🫂´- (@Xv5Pp) June 29, 2020
ここに挙げた様な「情報処理速度革命」と進化論の関係が何処に行き着くか自体についてはそれほど論じられていない様です。どうやら「同一基準による準安定状態の推移」を連続的に語るのが難しいからみたいですね。その一方で「生存競争に勝ち抜いてきた自然界の仕組みに学ぶ」バイオミミクリー(Biomimicry=生物模倣)なる研究分野が登場してくる困った状況…
はてさて私達は一体どちらの方角に向けて漂流してるんでしょうか? そんな感じで以下続報…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
