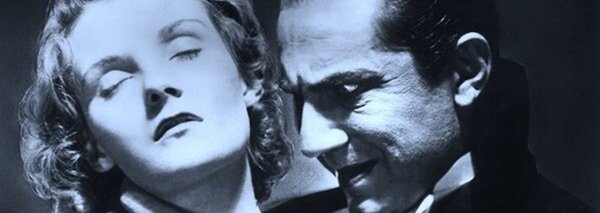Yasunori Matsuki
名乗るほどでもないインターネットと路上の観察者。
最近の記事
- 固定された記事

【対陣地戦用弾薬庫】「ツイフェミ」や「反生成AI派」は「反ワク派や親露派にまではなりきれない迷妄アカウントの自分探しの旅」?
こちらの投稿の続き。 https://twitter.com/YazMatsuki/status/1850730114021306637 プロパガンダは、特定の思想、信念、またはアジェンダを広めることを目的とした情報活動であり、個人や集団の意見や行動を影響し、操作することを狙っています。政治的な宣伝、広告、社会的運動など多岐にわたる分野で使用されますが、常に特定の目標や結果を意識して情報が選別・操作されている点に特徴があります。プロパガンダの特徴と限界について以下で説明し
- 固定された記事
マガジン
記事

【第三世代フェミニストの弾薬庫】線形代数とフェミニズム①第三世代フェミニズム運動の前身としての1990年代サイバー・フェミニズム運動。
以下では「式が多過ぎる連立方程式は解けない」という問題から「最小二乗法による近似値の計算」なる技法が発明され、そうした数値最適化手段が統合される形で現在の人工知能技術が現れる様子を俯瞰しました。 そもそも「連立方程式が解ける」とはどういう事でしょうか?線形代数的にいうとそれは「完全な形で行列の対角化(Diagonalization)に成功する事」を意味しています。 $$ \begin{cases} 5x-4y+6z=8\\ 7x-6y+10z=14\\ 4x+9y+7z

【挑戦してよかった事】とあるハードボイルド文学論争に決着をつけた「オイラーの公式の近似性」と「ベイズ更新のメモリレス性」。
以下の投稿で久し振りにダシール・ハメット((Samuel Dashiell Hammett 、1894年~1961年)の名前に言及した折に思い出したのが、かつてネット上で発生した、とある「ハードボイルド文学論争」の顛末。 まずは私のハードボイルド・ファンボーイ(オタク)としての立ち位置について言及しておきましょう。一言でいうとレイモンド・チャンドラーの未完作「プードル・スプリング物語(Poodle Springs)」を補完書して1989年に完成させたロバート・B・パーカー(