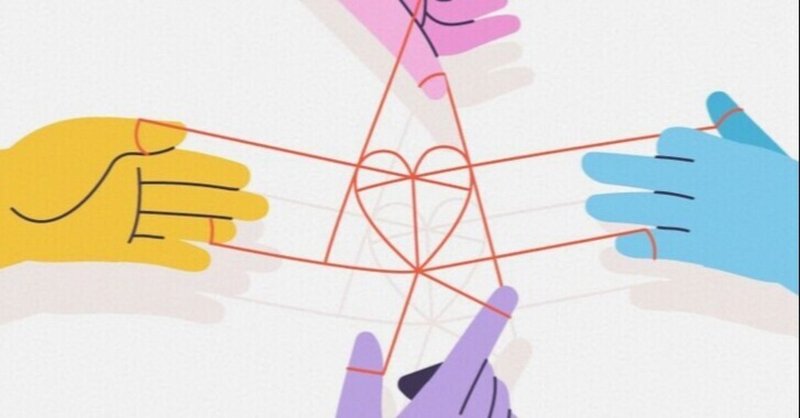
どうすればチームは結束するか? 弱さを見せ合えるチームビルディングとは
「弱さを見せあうとはこういうことか…」
2020年もあと残り数日。今年はコロナの影響で仕事の内容、仕事自体が大きく変わった方も多いのではないでしょうか。環境変化が大きい中でも、仕事では周りのメンバーと連携しながら付加価値高く動くことが求められます。
そんな中で、最近改めてチームビルディングについて考えさせられる出来事がありましたのでシェアしたいと思います。
心理的安全性とは
チームビルディングでよく語られるのが「心理的安全性」という言葉。「サイコロジカル・セーフティ(psychological safety)」の日本語訳です。1999年に生まれた言葉だそうで、まだ比較的新しい概念ですね。
【心理的安全性】
チームにおいて、他のメンバーが自分が発言することを恥じたり、拒絶したり、罰をあたえるようなことをしないという確信をもっている状態であり、チームは対人リスクをとるのに 安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態。
この概念は「プロジェクト・アリストテレス」というGoogleのプロジェクトでより知られるようになりました。Googleが分析した結果「優れたチームを作るためのただ唯一の鍵は『心理的安全性』を持てるかどうかである」との結論を出しました。
プロジェクト・アリストテレスを象徴するエピソードはこんな内容です。
チームリーダーが、自分が大きな病(癌)に犯されていることをメンバーに伝えたところ、メンバー間のの関係性が単なる役割を超えたものとなり、メンバーが次々に自分の弱みを語りだし、結果的にチームの結束力が高まった。
メンバーが常日頃から仕事や生活の中での心配事や自分の弱みを共有するチームの方が、そうではないチームよりも生産性が高く、結果、プロジェクトの成功確率が高くなるということですね。
結束力を強くする工夫(写真の活用)
最近、この心理的安全性を高める工夫に触れることがありました。それは「子供の頃の写真をメンバーと共有する」こと。先日ひょんなことから、チームメンバーの子供の頃の写真をミーティングで見る機会がありました。そこから、彼の過去のエピソードを皆で談笑しながら共有することになりました。恥ずかしそうにしながらも、当時どんな振る舞いをしていたのか、その頃のエピソードが人格形成に影響を与えたことを知り、メンバーは彼をより深く知ることとなりました。
仕事では各メンバーが決められた役割を果たし、チームとして結束していますが、ともすると「役割を果たす人」というドライな関係になりがちです。「子供の頃の写真の共有」は価値観形成に影響を与えたエピソードを話すことで、メンバーを「血の通った人」として強く認識し合うことができます。
そんなエピソードから、人間誰しも順風満帆ではなく、常に発展途上な存在であることがお互いに認識し合えます。そうした空気感をチームメンバーと共有することで、お互いの成長を応援し、弱みをカバーし合う空気を醸成することができます。
子供の頃の写真を人に見せるのは恥ずかしい気持ちもあるかも知れません。しかし、だからこそ共有する。「恥ずかしい」という一線を越えることで、一気に打ち解けることができます。
弱さを見せ合える組織とは
チームビルディングで改めて読み直して、なるほどという気づきがあったのがこちら「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか」。
先の見えないVUCAの時代には特に、リーダーはより難解な意思決定をスピーディに行うことが要求されます。そのためには柔軟な思考と行動を取れる人材の育成が必要です。
個人のWill(やりたいこと)とCan(できること)、そしてMust(すべきこと)この3つが合致しなければ、組織にも個人にもお互い不幸な関係になります。個人の成長が組織の成長になるという関係が理想ですね。
この本にはそのヒントが詰まっています。チームビルディング、組織をより高みに導きたいと考えている人には是非オススメの一冊です。
この本ではDDOという考え方が登場します。
DDO=Deliberately Developmental Organization
発達指向型組織のことです。
一見すると難解で理解しにくいですが、言い換えれば「どんどん上を向いて成長して行ける組織」ということですね。
この本の面白いところは成人の成長を3段階で解説しています。「成長」というと「子供が大人になる」というニュアンスで考えがちですが、この本は「大人も3段階に成長せよ」と説きます。
①環境順応型知性(まずはその場になじんで順応する)
②自己主導型知性(組織の中で自分の判断基準を確立する)
③自己変容型知性(自己の価値基準の限界に挑戦し矛盾や対立を受容する)
現在のコロナ禍では否応なくこの③の段階に直面させられているとも言えます。環境変化と素直に向き合い、課題解決に動ける人間は発達志向型組織をドリブンする人材として成長していけます。
「弱さを見せる」の本当の意味
先にご紹介した心理的安全性とDDOをおさらいします。
Google心理的安全性:弱さをさらけ出し、お互いの存在を認め、何でも言い合える組織にする
DDO:弱さをさらけ出し、その弱さに対してお互いに克服するように刺激し合い、組織として強く成長する
この二つは一見似ているように見えますが異なる概念です。DDOは一言で言えば「組織として弱さから逃げるな!」と言いうニュアンス。DDOは心理的安全性を担保した上で、更に高みを目指せという感じです。
この書籍では弱さを隠し、放置することについてショッキングな内容が語られています。
現代社会にありふれた組織、つまり、自分の弱さを隠すという「もう一つの仕事」に誰もが明け暮れている組織の状況を考えてみてほしい。経営者は、そのような仕事しかしていない人にフルタイムの給料を支払っている。しかも、弱点を隠している人は、その弱点を克服するチャンスも狭まる。その結果、組織は、その人の弱点が日々生み出すコストも負担し続けることになる。
だからこそ、弱さを引きずり出し、組織ぐるみでそこから逃げずにたたき上げて克服する、それこそが発達型組織であると説く。
なるほど、なかなか耳の痛い内容ですが、おそらくは正しいですね。結構スパルタな内容です。
しかし、この考え方を理解した上で、現状の置かれている組織に目を向けると自分ゴト化できる所も多いように思います。
この「弱み」を「現状できていないことを隠さずに素直に表出させる」と理解すると、今年はコロナの影響でそれが自然にできた組織も多いように思います。
幸か不幸か、ロバート・キーガン氏が語る、発達指向型組織の入り口に、多くの組織が直面していると言えるのではと改めて思います。
組織が成長するための3つの考え方
この書籍にはホーム、エッジ、グルーヴという3つのコンセプトが登場します。
ホーム:自分をさらけ出せる環境
エッジ:個人の限界(エッジ)まで挑戦する強い欲求
グルーヴ:発達を促す慣行と仕組み
これら3つの総和で個人も、そして組織も発達(成長)していけると説きます。
「ホーム」はGoogleの心理的安全性の領域。そしてコロナの環境により、否応なく「エッジ」の必要性を突き付けられているのが今だと思います。
これを機会と捉え、その先の仕組みとしての「グルーヴ」を整えるチャレンジをすることで、組織は次のステージに上れるのではと思います。
まとめ
コロナによってチームの結束力の在り方を考えさせられた一年。ポジティブに捉えると、個人も組織も変化対応することが求められ、成長の機会があったとも取れます。
お互いの弱さを見せ合うことで、心理的安全性を担保することができます。「子供の頃の写真を共有する」のはその人の過去のエピソードと共に価値観や考えの源泉を知れ、結束力向上に有効です。
そして、組織として「弱さ」を認め、それを補い合う意識と、チームで克服していく行動が重要ですね。
危機とは「危険」+「機会」
何事も「機会(チャンス)」と捉え、ポジティブに行動を変えて行こうと思います。
今年の自分の仕事、自分が所属する組織を改めて振り返り、次のステップに進むために何が必要か、改めて考えてみるのも良いのではないでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!ヒントにしていただければと思います。スキ、フォローもとても励みになります。 サークルをオープンしましたのでお気軽にご参加ください😌https://note.com/yawarakamegane/n/n3f4c11beb4c0
