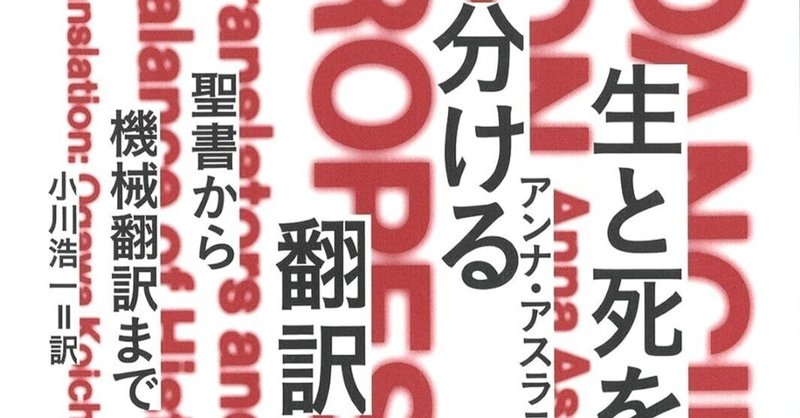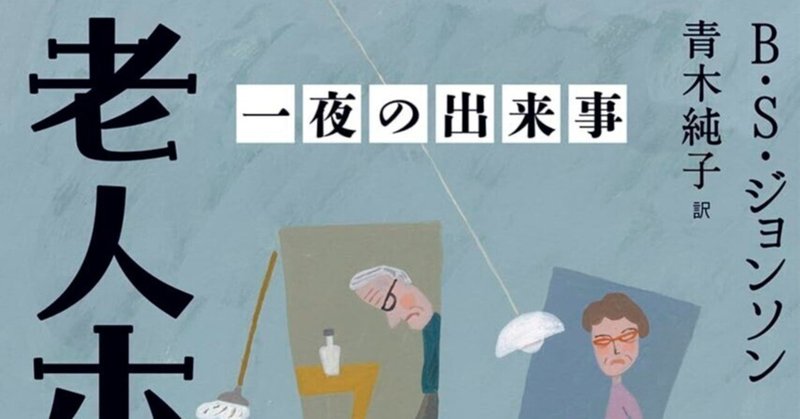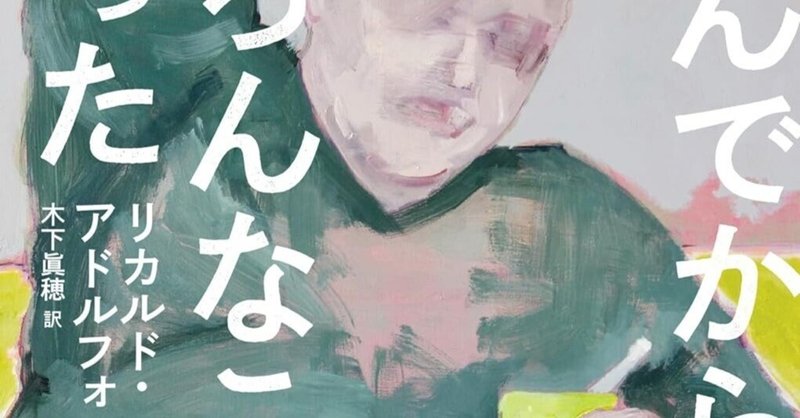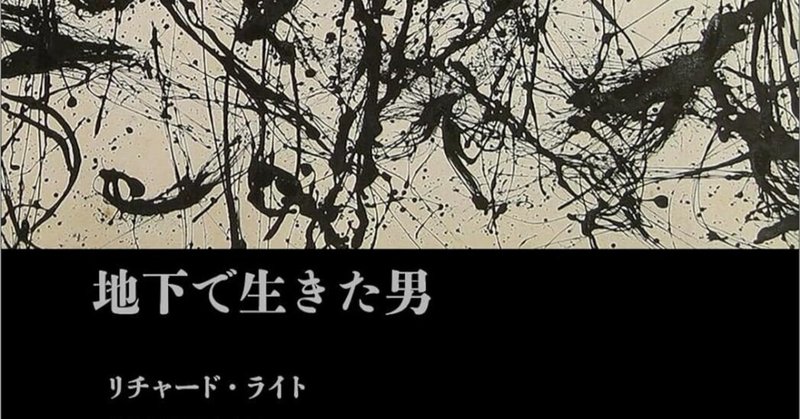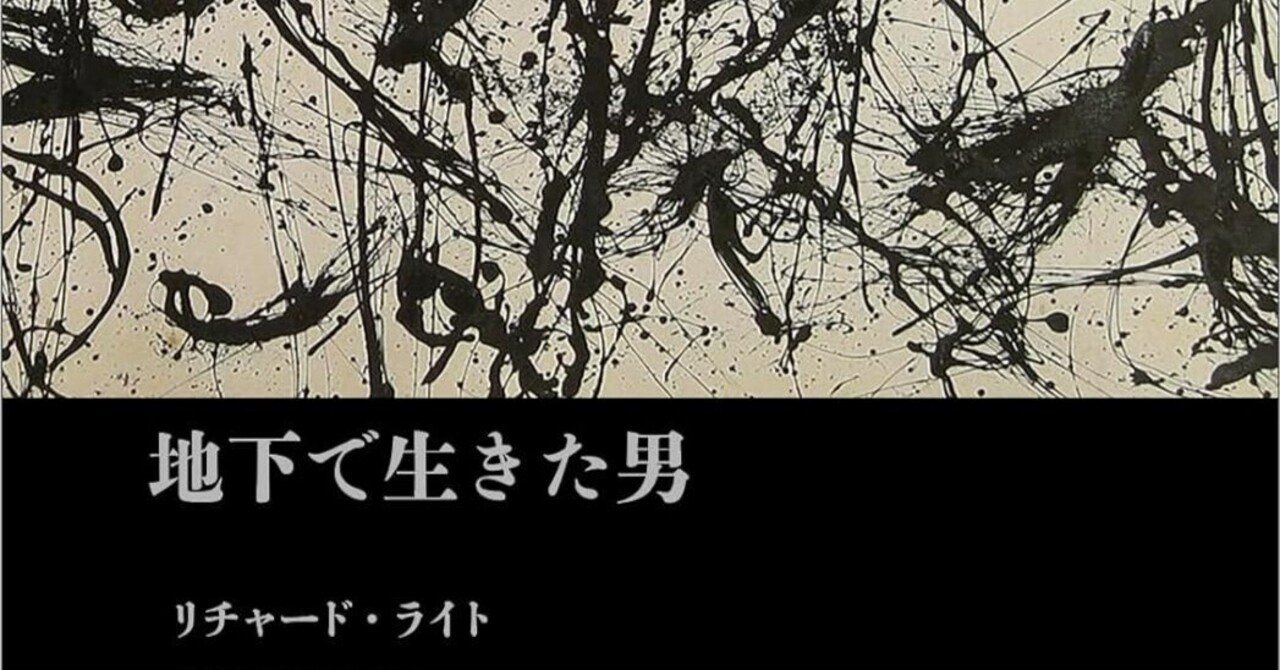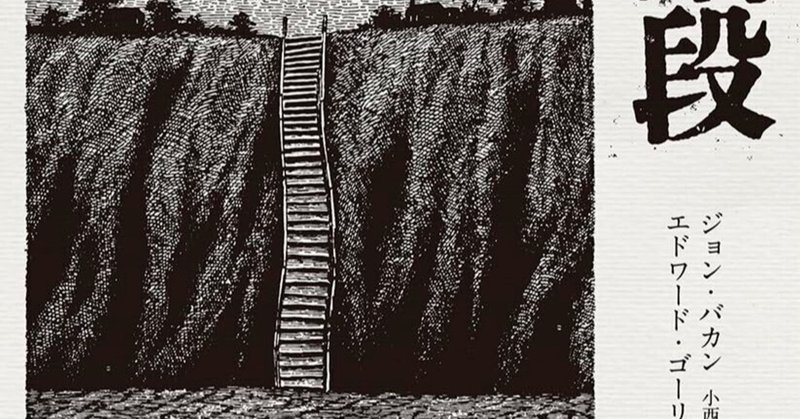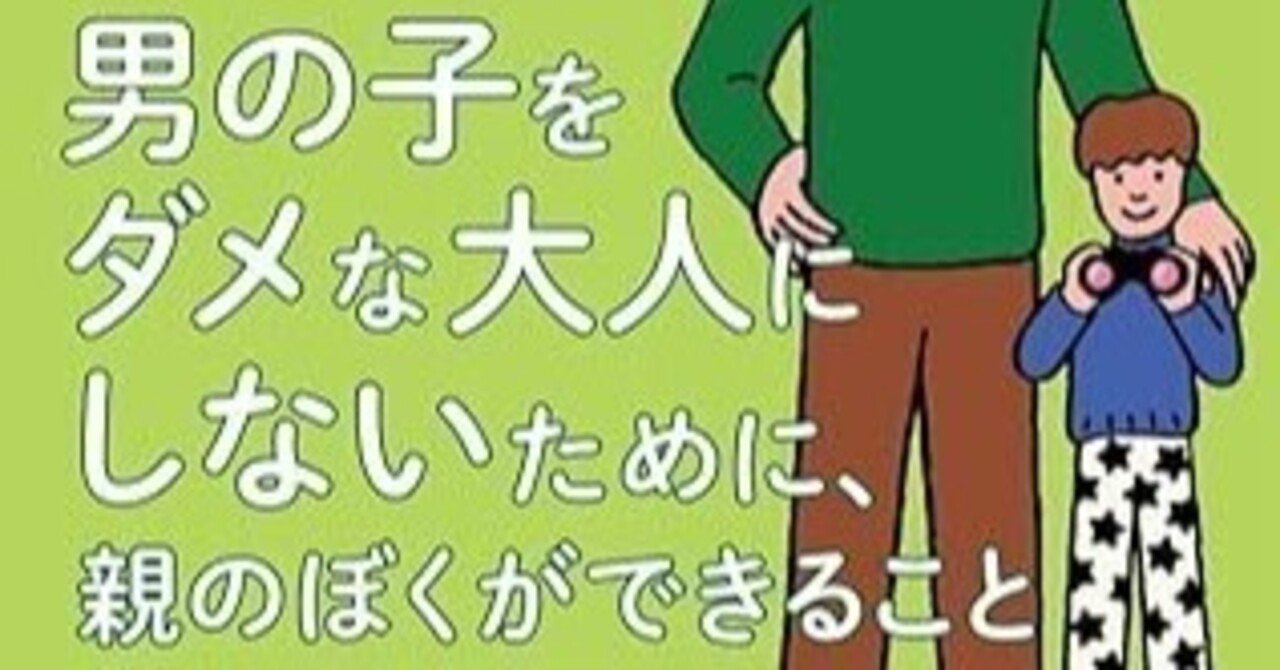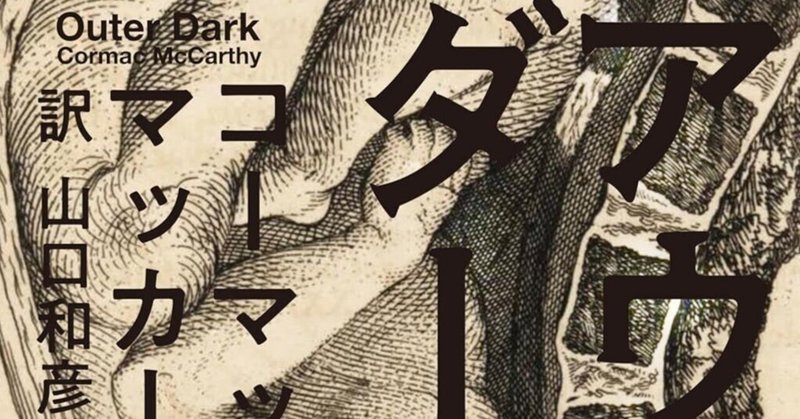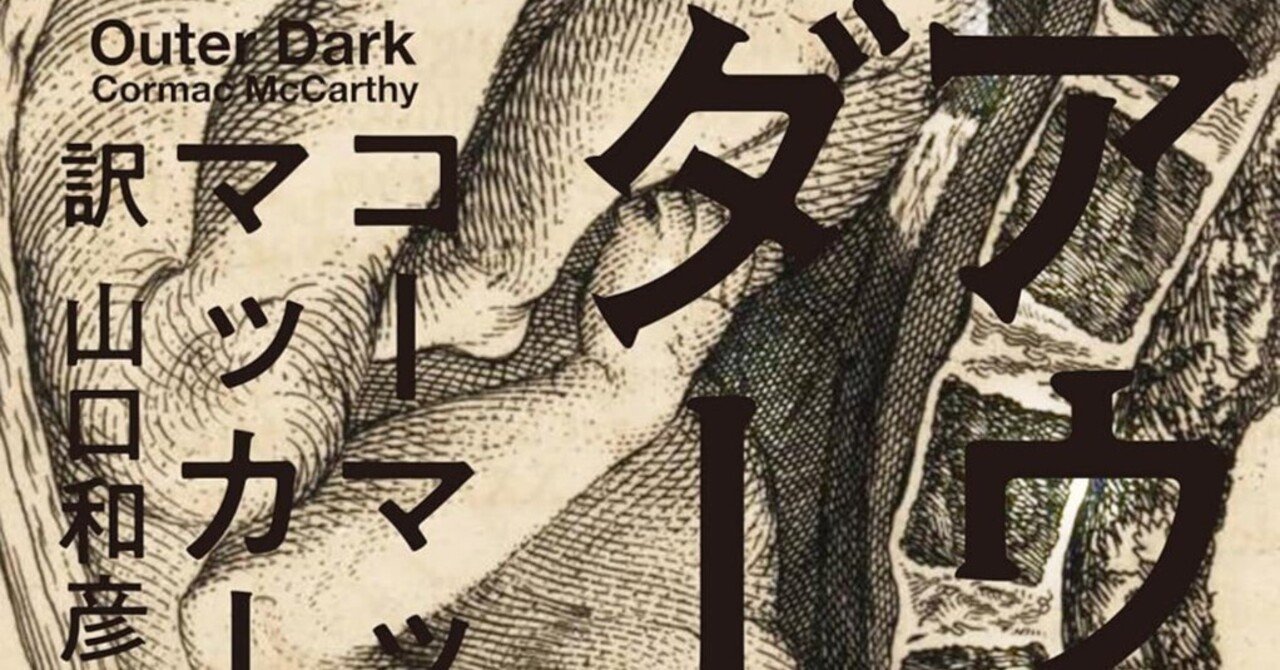最近の記事
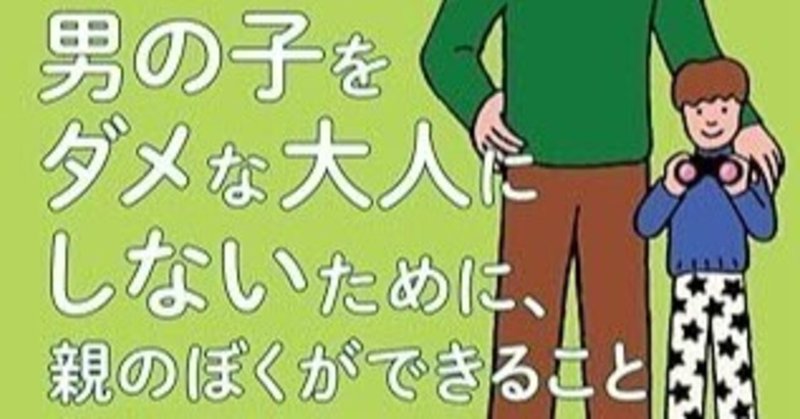
田籠由美評 アーロン・グーヴェイア『男の子をダメな大人にしないために、親のぼくができること――「男らしさ」から自由になる子育て』(上田勢子訳、平凡社)
「有害な男らしさ」から脱却しよう――特に男の子をもつ父親は一度読んでみてはどうだろうか 田籠由美 男の子をダメな大人にしないために、親のぼくができること――「男らしさ」から自由になる子育て アーロン・グーヴェイア 著、上田勢子 訳 平凡社 ■世の中に潜在する歪んだ形の男らしさを、著者は「有害な男らしさ」と呼ぶ。悲しくても男だから泣けない、男たるもの人の助けを求めない、キレイなものや可愛いものは女向けだから近づかない、生意気な女は黙らす! 育児なんか女がするものだ! ……そ
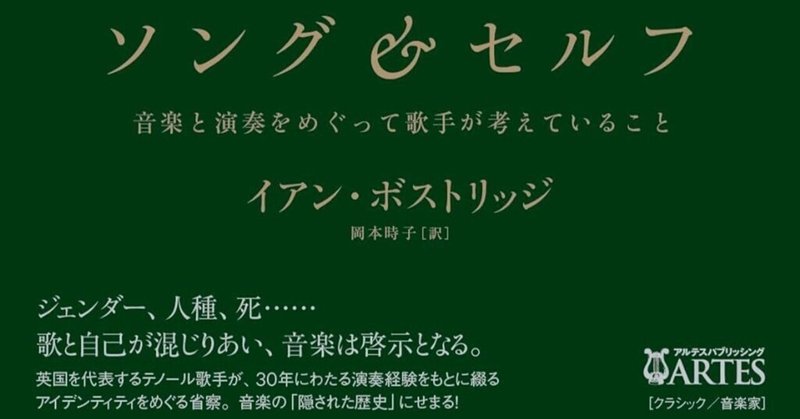
眞鍋惠子評 イアン・ボストリッジ『ソング&セルフ――音楽と演奏をめぐって歌手が考えていること』(岡本時子、アルテスパブリッシング)
音楽好きのあなたへ――音楽家の心の内をのぞき、音楽への新しいアプローチを 眞鍋惠子 ソング&セルフ――音楽と演奏をめぐって歌手が考えていること イアン・ボストリッジ 著、岡本時子 訳 アルテスパブリッシング 音楽好きのあなたへ――音楽家の心の内をのぞき、音楽への新しいアプローチを ■イギリスを代表する世界的テノール歌手による音楽とアイデンティティにまつわる評論集である。「世界に名だたるスーパーテナーの書いた評論ってどんなもの?」と思われる向きもあるかもしれない。著者イアン・
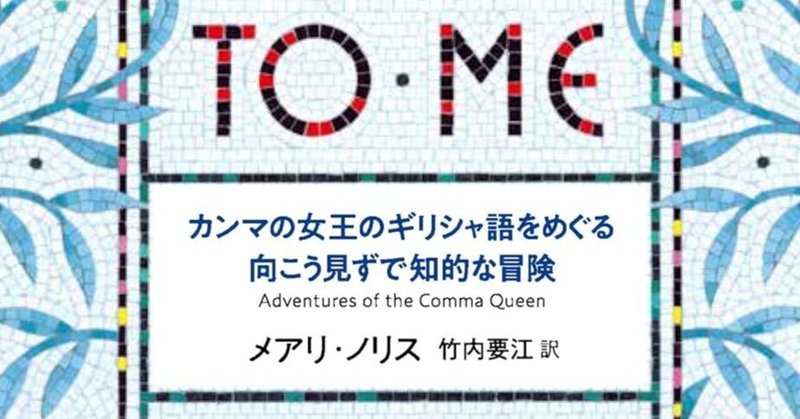
玉木史惠評 メアリ・ノリス『GREEK TO ME――カンマの女王のギリシャ語をめぐる向こう見ずで知的な冒険』(竹内要江、左右社)
愛しいギリシャ――ちんぷんかんぷんな人生の救世主 玉木史惠 GREEK TO ME――カンマの女王のギリシャ語をめぐる向こう見ずで知的な冒険 メアリ・ノリス 著、竹内要江 訳 左右社 愛しいギリシャ――ちんぷんかんぷんな人生の救世主 ■推薦するという意味の「推す」から派生した「推し」は、熱心に支持する対象を表す俗語として日常的に使われる。 雑誌『ニューヨーカー』で校正者として二十四年間勤務し、カンマの女王として知られる著者メアリ・ノリスの「推し」は、アイドルでもゲームアプリ