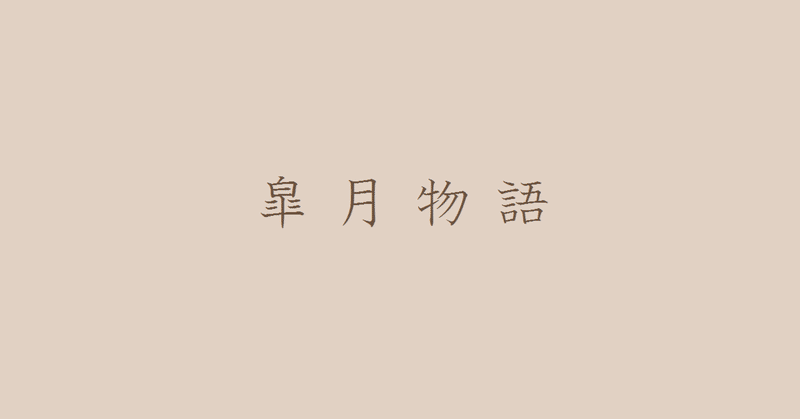
この涙はそんな美しいものではない(皐月物語 126)
月曜日の朝、藤城皐月はいつもより遅く目を覚ました。通学服に着替えていると、洗面所からドライヤーの音が聞こえてきた。及川祐希の高校へ行く前のルーティーンだ。今週は皐月には修学旅行があり、祐希には文化祭がある。このビッグイベントを気分よく迎えたいので、昨夜のモヤモヤした気持ちを早めに解消しておこうと思い、皐月は祐希に絡みに行った。
「おはよう」
「おはよう。今朝は4人で食事みたいだよ。さっき小百合さんが台所に入って行った」
屈託のない祐希を見て、皐月は少し気が楽になった。制服に着替え、鏡の前で髪を整えていた祐希はほとんど身だしなみが仕上がっていた。
「へぇ、珍しいな。あのママが早起きするなんて。昨夜は随分遅くまで頼子さんと飲んでいたのに」
「じゃあ皐月も遅くまで起きていたんだ」
「うん、ちょっと寝付けなくてね。そのせいで今朝は少し寝坊しちゃった」
皐月は鏡越しに祐希と話すのが好きだ。鏡を見ながら祐希と話しているとまるでシネマのワンシーンようで、恋愛映画の主役になったような気になる。でも鏡に映っている主演男優の背が低いのだけは気に入らない。
皐月は身支度を終えたが、祐希はまだ目元を気にしてメイクをしていた。何をそんなに細かいところを気にしてるんだろうと不思議だった。
「ねえ……目の周り、おかしくない?」
「別におかしくないけど」
「私もあまり眠れなかったんだ。目の下にクマができちゃって。ヤダな……」
皐月は横にいる祐希の顔を見た。鏡に映る虚像とは違い、近くで見る祐希の顔は肌がキメ細かく艶めかしかった。毎度のことながら、祐希から放たれる芳香に心が乱される。
「大丈夫。クマなんて全然わかんなくなってるから」
「ホント?」
この朝、初めて祐希と皐月の目が合った。しばらく見つめ合っていた二人だが、先に目を逸らしたのは皐月だ。祐希の恋人の竹下蓮なら祐希を上から見下ろしているだろう……そう思うと皐月は敗北感に苛まれ、自分がまだ背の低い子供だというのが嫌になってしまった。
「じゃあ俺、先に下に行ってる」
「ちょっと待って」
皐月は祐希に両手で顔を挟まれて引き寄せられた。キスでもするつもりなのかと一瞬喜んだが、そんな雰囲気でもない。
「皐月って昨日、メイクした?」
「ああ……したよ。どうしてわかった?」
「アイメイクがちょっと残ってる。落とし残しかな、昨日は気が付かなかった。……ちょっと大人しくしてて。落としてあげるから」
昨夜は満の家を出る前に、満が慌てて皐月のメイク落としをしていた。皐月には慣れた手つきで手早くメイクを落としていたように見えたが、それが少し雑だったとことに気付かなかった。
「皐月、メイクしたんだね。男のメイクなんて生理的に無理って言ってたくせに」
「満姉ちゃんがメイクさせろって言うからさ……いろいろ奢ってもらったから断れなかったし、しょうがないだろ」
「ふ~ん。で、メイクされてみてどうだった?」
祐希はシェイククレンジングを含ませた綿棒で皐月の目の周りを撫でていた。
「格好良くなったと思う。満姉ちゃんは喜んでいたし、コンカフェの女の子たちからも綺麗だって褒められた」
「へ~、見たかったな……。今度、私にもメイクさせてよ」
「いいよ。面白かったし、そういうのちょっと興味でてきた」
「じゃあ女の子みたいにししゃおうかな」
祐希はメイク落としを終えた。綿棒を捨てた後、また皐月の頬に両手を添えた。
「皐月は化粧映えする顔だよね。どんなメイクをしても綺麗になりそう。羨ましい……」
「祐希だって綺麗な顔してるじゃん。初めて会ったときからずっとそう思ってた」
「本当?」
「うん、本当」
皐月は祐希にそっと口づけをした。薄目を開けて鏡を見てみると、まるで恋愛ドラマのキスシーンみたいだった。
「ねえ、祐希もキスしてるところを鏡で見てみなよ」
祐希の見やすい角度でもう一度キスをすると、祐希の息が乱れ始めた。舌を絡めているうちに、皐月は祐希や自分に恋人がいようがどうでも良くなってきた。悩んでもどうせ苦しくなるだけだ。この刹那の幸せが永遠に続けばいいと思った。
だが快感と不快感が入り混じり、気持ちよくなるほど心はざわついて、幸福感を得ることはできなかった。それでも祐希が幸せそうにしているのが皐月には救いだった。
6年4組の教室に入るといつも通り、最初に松井晴香、小川美緒、惣田由香里の三人組と顔を合わせた。いつも賑やかな三人を見ると和む皐月だが、土曜日にイオンで晴香に入屋千智と一緒にいるところを見られているので、そのことで何か言われるんじゃないかと少し緊張した。
「おはよう」
彼女たちも皐月に挨拶を返し、美緒が最初に皐月の変化に言及した。
「藤城君、髪切ったんだね」
「あっ、わかった?」
「うん。格好良くなったよ。カラーも紫が鮮やかになった」
「へへっ。今週は修学旅行だから、ちょっとはお洒落にしないとね」
皐月は以前、美緒のヘアーを褒めたことがあった。きっと美緒はその時の恩を返してくれたのだろう。美緒の気遣いに和やかな気持ちになっていたところ、晴香が神妙な顔をして皐月に話しかけてきた。
「イオンで会った子って、藤城の彼女?」
避けられないことだとは思っていたが、こうもストレートに聞かれるとかえってすっきりする。皐月は晴香のこういう率直なところが好きだ。
「違うよ。あの時、友達って紹介したじゃん」
美緒と由香里の反応を見ると、晴香はまだ彼女たちにこの話をしていなかったようだ。
「そうだけどさ……美耶に何て説明したらいいのか……」
「見たまま言えばいいよ。あの子のことは噂になってるみたいだだけど、松井の言葉なら筒井も信用するだろ」
千智とのことが噂になっているのは皐月も知っていた。憶測の域を出ない噂なので、言いたいように言わせておけばよいと思っていた。だが、噂の真偽を直接聞かれた時には友達だと答えるようにしている。千智が好奇の目に晒されるのは嫌だからだ。千智のことをただの友達とは思っていないが、皐月には他にも好きな子がいるので、人には恋人だと紹介できない。
「なんだ。噂の子ってただの友達だったんだね。じゃあさ、これまで以上に美耶ちゃんと藤城君のこと応援しちゃおうかな」
由香里が楽しそうに皐月を囃し立ててきた。筒井美耶は誰からも好かれるキャラなので、クラス中の女子から皐月との恋愛を応援されている。その美耶の応援団の筆頭が由香里であり美緒だ。
由香里は自分の恋愛よりも友達の恋愛の方に関心があり、晴香の月花博紀への想いを一番近くで支えている。美緒は1学期の時、皐月と美耶と席が近かったせいか、美耶と皐月が付き合うことを本気で願っている。
「筒井に俺のことを推すのはやめたほうがいいな。筒井には俺なんかよりもっといい奴が相応しい」
「なによ。藤城君がだいぶマシになってきたから応援しようって思ってんのに」
「惣田は俺のことを過大評価をしてるんだよ。俺みたいなクズなんか親友にくっつけようとしてんじゃねえよ」
今まで皐月はクラスの女子から美耶との仲を応援されることが嬉しく、からかわれることにさえ快感を覚えていた。それは家族や友人たちでは満たされなかった孤独感が、女子からのおせっかいで埋め合わされているような気がしていたからだ。
いたたまれなくなった皐月はそっとその場を離れた。皐月はもう、恋愛に関しては自分のことを人から応援されるような男ではないと思っていた。純潔は失われ、体液で汚れている……由香里や晴香、美緒ら処女たちと話をしているうちに皐月は自分のことをこんな風に思い、つらくなっていた。
皐月が自分の席へ行くと、同じ班の三人の女子がいつもと同じことをしていた。後ろの席の吉口千由紀は本を読んでいて、隣の席の二橋絵梨花と前の席の栗林真理は受験勉強をしている。晴香たちとは違うこの三人組の関係が皐月は好きだ。この空気は皐月をいつも安堵させる。
「おはよう」
「おはよう」
いつも真っ先に挨拶を返してくるのは絵梨花だ。最近はいつも勉強する手を止めて皐月の話相手になっている。千由紀は顔を上げて挨拶をするとすぐに読書に戻り、真理は顔も向けず声だけで挨拶を返す。機嫌のいい時だけ振り向いて絵梨花との会話に加わる。
「藤城さん、髪を切ったんだ。また格好良くなったね」
真理が慌てて振り向いて絵梨花を見た。涼しげな目が開き、怜悧な顔が阿呆みたいになっていた。
「ありがとう」
下手なことは言えないな、と真理を見た皐月は言葉に詰まり、ただ穏やかに微笑むことしかできなかった。
「皐月の髪の毛、色が鮮やかになってる。染め直したんだ」
取ってつけたように真理が会話に加わってきた。
「うん。黒に戻そうか迷ったんだけど、修学旅行までは派手にしておこうかなって思って」
「どうして黒に戻そうなんて思ったの?」
「うん……稲荷中学って校則が厳しいじゃん。そろそろ気持ちを切り替えようかなって思って」
皐月は以前、校門の前で4年生の石川先生から言われた言葉を気にしていた。身だしなみの乱れは心の乱れ……この言葉が皐月の中に澱のように残っていた。因果関係はないけれど、身だしなみを整えれば今の私生活になんらかのいい影響があるかもしれないと思った。
「藤城君って、つまんないこと考えるんだね」
今まで本を読んでいた千由紀に辛辣な言葉を浴びせられた。皐月は勝手に千由紀のことを自分の味方だと思っていたので、この言葉は効いた。
「そうだね……自分でもつまんないって思うよ」
皐月はランドセルの中身を机の中に入れ、席を立ってランドセルを片付けに行った。一人になりたくてもなれない教室がこんなにも居心地が悪いとは感じたことがなかった。
皐月は晴れない気持ちで学校生活を送った。浮つかず穏やかに、無難に今日一日を過ごした。そして誰ともつるまずに一人で学校を出た。帰り道で仄かに期待感を抱きながら検番の前を通っても、二階の稽古場には芸妓の気配がなかった。
明日美は家にいるに違いない……そう思うと皐月はいてもたってもいられなくなり、明日美に電話をした。
「もしもし。皐月だよ。今大丈夫?」
「大丈夫よ。どうしたの?」
「今から行ってもいい?」
「いいよ。待ってる」
電話連絡が上手くいき、皐月はホッとした。メッセージでは連絡がつかないかもしれないと思い、苦手な電話をかけた。皐月は明日美の優しい声に救われた。
通学路の細い路地を抜け、右へ曲がるところを左へ曲がって明日美のマンションへ行った。エントランスの暗証番号は覚えている。パパッと番号を入力して中へ入ると、エレベーターから同じクラスの伊藤恵里沙が出てきた。恵里沙は同じクラスのインフルエンサーの新倉美優やお調子者の長谷村菜央と仲がいい。
「あれっ? なんで藤城君がここにいるの?」
「うん。ちょっと友達のところに寄り道。伊藤ってここに住んでたんだ」
「そうだよ。ねえ、友達って噂になってる5年生の可愛い子?」
「そんなわけないだろ。もしそうなら伊藤と彼女は同じ通学班ってことになるじゃん」
「あっ、そうか!」
「俺の友達っていうか、親の友達でもある人に用があってね。じゃあ、また学校で」
恵里沙なら雑に誤魔化しても大丈夫だと思い、皐月はエレベーターの扉を閉めた。学校の教室で見る恵里沙とは違い、プライベートの恵里沙は一人でいるせいか力の抜けた感じが素朴で可愛かった。恵里沙は本来、穏やかな子なんだろう。存在感の強い美優と一緒にいるのは神経を使うのかもしれない、と皐月は恵里沙のことを気に掛けずにはいられなかった。
明日美の部屋の前に来た皐月にもう緊張感はなかった。インターホンを押すと明日美が出てきた。白いパーカーを着て白のジャージを穿いていたので、家でくつろいでいたのかなと思い、少し安心した。明日美は軽くメイクをして、髪をポニーテールにまとめていた。自分のために急いで可愛くなったと思うと皐月は嬉しくなった。
「急に来ちゃって、ごめんね」
「何言ってんの。いつでも来てって言ったでしょ。上がって」
千智と選んだ新しい靴を脱ぎ、皐月は明日美の部屋に上がった。居間は相変わらず真っ白で統一されていて、生活感のある物が何もなかった。居間の片隅にランドセルを下ろしたが、テーブルの上には何も出ていなかったので、座っていいのか判断が付かずその場に立ち尽くした。
「座ってて。お茶を入れてあげる」
この部屋には明日美の匂いで満ちていた。服に沁み込んだ明日美の匂いに祐希が反応するだろうと思うと、皐月は少し気が重くなってきた。
「皐月から家に来てくれて嬉しいな」
「うん。会いたくなっちゃって……」
明日美はタンブラーを一つだけ持って来て、皐月の横に座った。軽いアイメイクとリップだけのほぼスッピンなのに、明日美は息を呑むほど美しかった。
「髪の毛切ったのね。いいじゃない。女の子みたいに髪が長かった時の皐月も可愛かったけど、今の髪型の皐月は格好いいね」
「ありがとう。明日美は女性的な俺のことが好きなのかと思ってたから、髪を切ってちょっと不安だったんだ」
「中性的な皐月もいいよ」
明日美に髪をなでられた。身体を寄せて来て、髪をつまんで弄び始めた。
「綺麗な紫……。私もこういう色にしてみたいな」
「芸妓ってカラーしちゃダメなの?」
「この辺りだけで芸妓をするならいいかもしれないけど、私は余所にも仕事で行くことがあるからダメかも。他はみんな伝統的っていうか、豊川が緩いんだけどね」
一度廃れた豊川芸妓を再興するために、老芸妓で組合長の京子が改革をした。伝統を尊重しながらも、若い芸妓を集めるために現代のセンスを取り入れた自由な芸妓を目指す方針を打ち立てた。そのため、豊川の芸妓はコンパニオンみたいだと誹謗中傷を受けることもあるが、明日美や満、薫など若い女の子の芸妓が増え始めている。若い女の子の収入を確保するために、京子の娘の玲子がクラブの経営を始め、芸妓とホステスを兼任させている。
「昨日、満姉ちゃんと名古屋に服を買いに行ってきた。満姉ちゃんはロリィタファッションの服を着て、ピンクのウィッグをつけてたよ。まるで西洋人形みたいだった」
「へぇ~。可愛い満ちゃん、見たかったな~」
「写真撮ったけど、見る?」
「写真あるの? 見る見る」
皐月はいつか明日美に写真を見せることになると思い、嫉妬を呼び起こす可能性のある写真を全て隠した。これは明日美だけへの対策ではなく、真理や祐希に見られてもいいように配慮してある。
「わあっ! 満ちゃん、可愛いっ! 私も満ちゃんとデートしたかったな」
「そんなこと言ったら満姉ちゃん、悶絶して喜んじゃうぞ」
皐月は明日美のことが大好きな満にこの言葉を聞かせてあげたいと思った。
「皐月の着てる服って満ちゃんが選んだのだよね。……このテーパードパンツは私と一緒に買ったのだ。どっちもよく似合ってるね」
「このベスト、古着屋で買ったんだ。頼子さんが昔こういうベストが流行ってたって言ってたよ」
「満ちゃんってこういう昔の服が趣味だったんだ……。意外だな。あの子ならもっと派手な服を選ぶかと思ってた」
皐月は満との関係を全く疑っていない明日美を見て安心した。秘密を守ることは絶対だ。
「満姉ちゃんは自分の趣味を勧めるんじゃなくて、俺に似合いそうな服を選んでくれたみたい。でも、このベストってレディースなんだよね。やっぱり俺って女っぽい服が似合うのかな?」
「皐月は綺麗な顔をしてるからね。でも男っぽい服だって似合うよ」
「自分で選んで買った服もあるよ。そっちは全然女っぽくないから。また今度着て来るね」
今日の皐月は情緒不安定で、学校では誰と話していてもどこか寂しいと思っていた。だが明日美と話をしているうちに徐々に気持ちが安らいできた。この感情は真理と一緒にいる時と少し似ているなと皐月は感じていた。
明日美は皐月のスマホを手にして過去の写真を見ていた。その中には祐希や千智の写真も残してある。皐月としては彼女たちの写真を見た明日美の反応を見てみたいと思い、厳選して残しておいた。皐月も明日美にくっつくようにスマホの画面を見た。
「電車の写真がたくさんあるね。皐月って本当に電車が好きなんだね~」
「最近は車も好きになってきたよ。明日美のレジェンド・クーペは凄く良かったし、満姉ちゃんの乗ってるビートも面白かった」
ビートの写真も撮ってあったので、明日美に見せながら車の説明をした。意外にも明日美はビートに強い興味を示した。
「機会があったら私も満ちゃんのビートに乗せてもらいたいな。でも、どうしてビートのことを知ってるのって満ちゃんに怪しまれちゃうか。皐月に教えてもらったとは言えないよね」
皐月は明日美と満、両方の秘密に関わっていることが意外にも安全だということに気が付いた。だが、一度綻べばあっけなく壊れてしまうのは間違いないだろう。明日美と満、二人との関係を皐月が続けたいと思えば二人を強力な秘密で縛らなければならない。そのためには悪い男にならなければならないと思うと、あまりいい気はしなかった。
「この子は頼子さんのお嬢さんね。可愛い」
「祐希って言うんだ」
「ここって豊川稲荷?」
「そう。頼子さんたちが小百合寮に引っ越してきた日にお稲荷さんを案内したんだ。これはその時の写真」
明日美は皐月が祐希と一緒に暮らしていることを知っている。それなのに明日美は祐希に対して一切の嫉妬を見せない。望ましい展開のはずだが、皐月にはそのことが少し不満だった。
「この4人で写っている写真……皐月の髪がまだ長かった頃だね。可愛いね」
この頃から皐月は2度、髪を短くした。今見ると、よくこんな頭をしていたものだと思う。しかも祐希と千智はこのころの自分と仲良くなった。祐希も千智もバカなんじゃないかと思った。
「この男の子、格好いいね。皐月の友達?」
博紀を見た女はみんな同じ反応をする。皐月は少しムッとした。
「こいつは博紀って言って、同じ町内の奴。クラスも同じで、ファンクラブまである」
「へぇ~。じゃあ、モテるんだね」
「運動もできて、勉強もできる。性格もいいからモテモテだね。俺なんかとは大違いだ」
明日美に嫉妬させたいと思っていたのに、自分が博紀にヤキモチを焼いてしまったのは皐月の思惑外れだった。
「皐月は私にモテているんだからいいじゃない。可愛いな~」
明日美は昔のように皐月のことを抱き寄せて猫可愛がりをし、頬や髪にキスをしてきた。
「皐月だって頭が良くて性格がいいじゃない。運動は知らないけど」
明日美に抱かれながら、今日の自分は恋愛関係よりもこういう一方的に愛されるのを望んでいたのではないかと思い、久しぶりに子供のように甘えた。だが、明日美の体が小さくなっていて、昔とはちょっと包まれた感触が違っていた。
「この女の子、なんか凄いね。こんなに綺麗な子って現実にいるんだね」
明日美がスマホの画面をピンチアウトして千智の顔を食い入るように見た。この反応は皐月の予想以上だった。
「えっ? 明日美の方が美人だよ?」
「……ありがとう」
皐月の言葉を適当な相槌で流し、明日美は他の千智の写真を探していた。
「この綺麗な子に皐月のこと取られちゃうかな……」
言葉ほど明日美の顔は深刻には見えなかった。皐月には明日美の本心が良くわからない。
「取られるわけないじゃん。心配しなくてもいいよ」
皐月は体勢を直し、明日美の頬にキスをした。明日美は動かないで写真を見続けていた。
「でも、やっぱり若い子同士の方がお似合いだと思う……」
明日美から伝わってくる生気が急に衰えた。皐月には明日美から出ている光も翳っているように見えた。
「明日美って、つまんないこと考えるんだね」
教室で千由紀に言われたことを、皐月は主語を変えてそのまま言った。言ってみて初めて千由紀の言いたかったことがわかったような気がした。
「似合うとか似合わないとか、そんなの他人がどう思うかってことだろ? どうだっていいじゃん、そんなこと」
ずっと甘えていたいと思っていたが、そういうわけにはいかなくなった。皐月は千智を見慣れているからもう何とも感じないが、初見だと千智の美しい顔立ちは衝撃的なようだ。これも皐月の想像を上回っていた。
「もしも私が死んだら、この子に皐月のことをお願いしたいな」
「何バカなこと言ってんだよ……」
明日美は常に心臓の病気のことを気にしているのが皐月には哀しかった。そして複数恋愛をしている自身の疾しさが穢らわしく、悲しかった。
「泣かないで」
そっと涙を拭ったつもりでも、明日美に気付かれてしまった。バレたのなら隠してもしょうがないと思い、皐月は明日美に憚ることなく涙を拭いたが、いつまでも涙が止まらない。明日美は席を立ち、隣の寝室からティッシュの箱を持って来た。この白い部屋には手に届くところに何も置いていない。
「私……死なないように身体に気をつけてるよ。だから、泣かないで」
この涙はそんな美しいものではなかった。自分のことが嫌になって泣いていただけだ。こんな汚い自分をやさしく慰める明日美のことを思うと、満と約束した秘密を守ることがつらくなってきた。明日美を裏切っていると思うといたたまれなくなるが、皐月はもう明日美から離れられなくなっていた。
「死んだら許さないから」
「うん……」
明日美をきつく抱きしめると、勢い余ってラグマットに倒れ込んでしまった。下着をつけていない明日美の体は温かく、柔らかかった。だがこの時、男になろうという気がまるで起きなかった。皐月はただ、明日美の胸に頬をうずめてじっとしていることしかできなかった。
最後まで読んでくれてありがとう。この記事を気に入ってもらえたら嬉しい。
