
ケルアックハウスのこと〜抜け殻となった「作家の痕跡」をめぐる話
以下の記事は某メディアに掲載されずにお蔵入りしたものです。
伊勢市主催の「クリエイターズ・ワーケーション2020」が盛り上がっていますが、関連する話題だと思いますので公開いたします。
* * *
地方創生が盛り上がるなか、空き家再生に取り組む人が増えていますね。この動きがポピュラーになったのはごく最近のことですが、海外では古民家や空き家の修復事業が昔から行われてきました。今日はフロリダのある事例を取り上げたいと思います。
●旅人の元祖、ジャック・ケルアック
アメリカの黄金時代と言えば1950年代です。いまではオールディーズとして親しまれている楽曲が口ずさまれ、モータリゼーションが進展して郊外に家がどんどん建つようになった時代。家電が普及して家事負担は激減。カラーテレビ放送が始まり、マスメディアの形態が大きく変わり始めていました。文字通りアメリカは資本主義国家の盟主となり、軍事超大国として君臨したのです。
そんな繁栄の時代に背を向け、ジャズとドラッグで無軌道な放浪生活を送りながら、文学作品を書き続けた若者達がいました。「ビートニクス」と呼ばれた彼らは、ミニマリズムやマインドフルネス、ノマドなどという21世紀初頭のトレンドを半世紀以上前に体現したグループでした。その中心にいたのがジャック・ケルアックです。
そのケルアックが1957年7月から翌年4月まで暮らした家が、本稿の主役です。代表作『路上(新訳版では「オン・ザ・ロード」)』が出版されたとき暮らしていた場所ですが、その所在地を知る者はいませんでした。ケルアックの伝記類にもこの家の存在は一切書かれていません。詳細を知っていたのは家族とごく親しい友人だけでした。
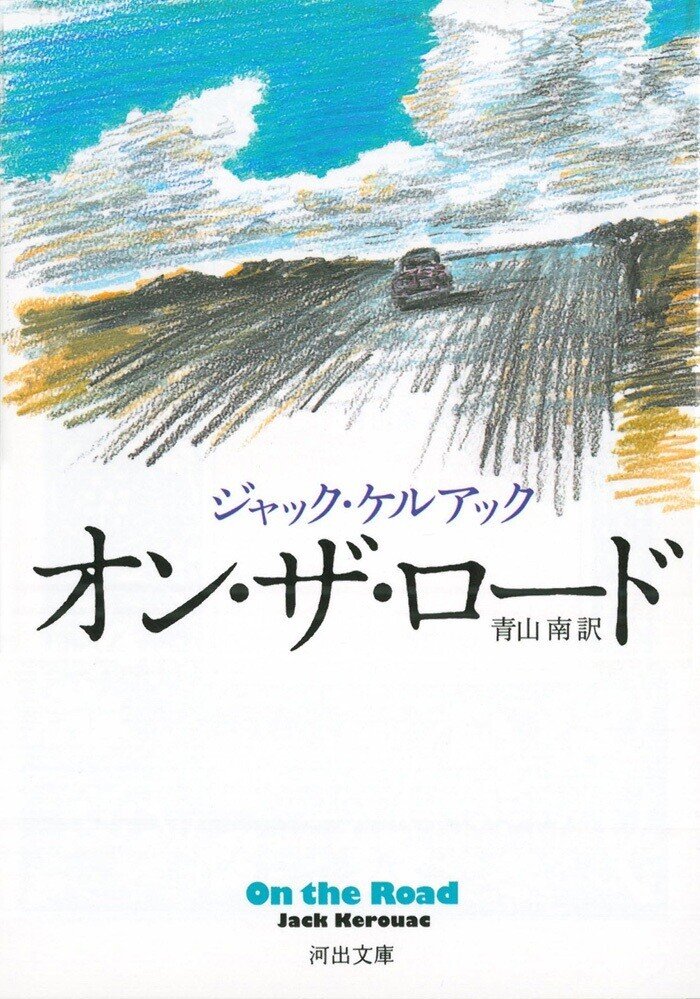
しかしこの家が建っているオーランドには「ケルアックが住んでいた」という都市伝説が残っていました。この噂話に着目し、事実関係を掘り起こしたのがアメリカの三大テレビ・ネットワークの一つ NBC のオーランドエリア・リポーターでフリーライターのボブ・キーリングです。
キーリングはケルアックの義理の兄弟で遺産管理人でもあるジョン・サンパスに連絡を取りました。そしてケルアックの残したメモの中からケルアックハウスの住所を特定したのです。1996年のことでした。
せっかく発見されたケルアックハウスでしたが、築75年と古いばかりでなく、ずっと放置されていたため倒壊寸前。とても住める状態ではありませんでした。
●ケルアック・プロジェクト始動
ケルアック・ハウスは、ウインターパークというのんびりした住宅街の一角に取り残された廃墟でした。木造平屋建て。白いペンキ塗りの質素な造りです。もともとは第二次大戦の独身帰還兵のために建てられた家でした。
英語で”Florida Cracker House” (Cracker=米国南部の貧乏白人、の意。侮蔑語)と俗称されるこの家に、ケルアックと母親は40ドル近い家賃を払っていました。入居当時、まだ『路上』は出版されておらず、母子の収入は二人合わせて200ドルに満たなかったと言います。
ケルアック親子が住んでいたことが明らかになったため、この家に文化的価値があることがはっきりしました。しかしフロリダ州政府は保存の意向を示しませんでした。
そこでキーリングは『オーランド・センティネル』誌に4千ワードの記事を寄稿し、この家の発見とその価値についてアピールしたのです。
事は動き出しました。この記事を読んで関心を持った起業家で、書店オーナーでもあるマーティー・カミンズとジャン・カミンズがキーリングに連絡を入れます。彼らはこの家の購入と改装を決意し、有望な作家にレジデンス(滞在制作)させる「ケルアック・プロジェクト」を立ち上げたのでした。
アメリカには寄付や社会貢献活動の文化があります。さっそく地元の篤志家が1万ドルを寄付。さらに全国誌『USA Today』でも取り上げられたお陰で、アメリカの小売チェーン「コール・ナショナル・コーポレーション」の代表取締役、ジェフリー・コールの関心を引くことに成功します。コールはケルアックの大ファンだったのです。学生時代のコールは、偶然の出会いを期待してケルアックが出没するというニューヨークのジャズクラブをハシゴしたこともあったと言います。そんなコールは気前よく10万ドルもの支援金を渡しました。こうして多くの人の支えと情熱によって、このプロジェクトは走り出したのです。
●世界中から作家が引き寄せられる聖地
多くの人々の支えにより、ケルアックハウスは大改修を終えました。改装後のハウスには著名な作曲家であるデイビット・アムラムや、『路上』の主人公のモデルとなった故ニール・キャサディの妻、キャロラインなどが訪れました。
そればかりではありません。この家には平均38倍の競争を勝ち抜いた若手作家たちが、3ヶ月間住み込んで自作の創作に励んでいるのです。参加は1度に一人だけ。滞在期間中、作家はケルアックの家を独り占めすることが出来ます。いったいどんな心持ちがするのでしょう。その至福は想像するしかありません。
残念ながらケルアックがつかっていた家具は残されていませんが、この家で撮影された肖像写真やケルアックが使っていたしたタイプライターが飾られており、気分を盛り上げてくれます。
筆者が取材した2013年5月下旬の取材時点で、このプロジェクトは既に10年以上運営されており、利用者の数は40人を越えていました。アメリカ国内だけでなく、海外から挑戦して見事滞在の権利を勝ち得た作家も複数います。なんと日本から応募して、最終審査まで残った人までいるそうです!
いまなお世界中に根強い人気を持つ作家の引力をまざまざと見せつけられるようですね。
たとえて言うならば、青森に建つ太宰治の「斜陽館」が若手作家支援のために貸し出されたとしたら、ケルアックハウスの状況に近いと言えるでしょうか。
実際「レジデンスの夢こそ叶わないものの、ぜひこの目で見たい」と、聖地巡礼に訪れるファンは結構いるそうです。
●地元と外部の温度差
ケルアックハウスを中心に渦を巻く熱気について書き連ねてきました。ところがです。地元オーランドでは、誰もこの家のことを知らないのです……!
どういうことかというと、そもそもケルアックはフロリダに馴染めなかったのです。1950年代のフロリダは非常に保守的な土地でした。当時全米を湧かせたエルビス・プレスリーも、ここフロリダではひんしゅくを買っていました。実際、ニューヨークやサンフランシスコで『路上』がセンセーションを巻き起こしていたにも関わらず、フロリダの書店にはケルアックの著作は1冊も置かれていなかったのです。そんな土地で自由な生き方を標榜するケルアックが受け入れられるのは難しかったのでしょう。
彼がオーランドにやって来たのは、母親と姉一家が仕事の関係で移住してきたためでした。ケルアック家はカナダのフランス語圏から移民してきた一族で、母語はフランス語です。ケルアック自身、小学校に上がるまで英語が話せなかったと言います。移民の多くは家族思いです。だからこそケルアックも家族との繋がりを大切にしていました。後を追うようにしてこの町に移ってきたのもそのためです。
一般に自治体の文化政策・文化施設の運営方針には二つの方向性があると言われます。
・地元還元型
・外部へのアピール型
「地元還元型」の分かりやすい例は、市民ホールでしょうか。住民の「趣味の発表会」利用、あるいは税金の使い道として誰もが納得できる折り目正しいオーケストラやクラッシックバレエの公演。そうしたイベントに利用されるのが地元還元型の施設です。地域住民への一種の福利厚生と言えます。しかし内向きの需要を指向しているため、外部の人からは評価されません。観光客が足を運ぶこともあまりないでしょう。
これに対して外部へアピールするタイプの文化施設もあります。具体例として(異論はあるかも知れませんが)「金沢21世紀美術館」を挙げたいと思います。ここは現代美術の専門美術館です。金沢市民への福利厚生を考えるのであれば、難解な現代アートよりも郷土の画家や地元民の絵を展示できる「市民ギャラリー」の方が適切だと言えるかもしれません。しかしそうしなかったのは文教都市としての金沢市を対外的にアピールしたかったからでしょう。「うちの街はこんなに進んだことに取り組んでいますよ」というイメージ戦略。計画の段階では、そこで行われる展示が住民に愛されるかどうかは未知数だったと思います。しかしアート業界での評価は高まるし観光客もやって来る。そんな施設の典型例です。
ケルアックハウスは民間の NPO が運営していますが、後者の系統に数えられるでしょう。特別なイベントの日を除けば選ばれた作家だけに門戸を開いているのですから、閉鎖的な施設とさえ言えます。そもそもケルアックが住んでいたという事実さえ、ほとんど知られていなかったのです。住民の感覚として、他人事感が強くなってしまうのでしょう。
文化施設を地域に定着させるという行為は、一筋縄ではいきません。
●個人と公共の折り合い
「地元では受け入れられていないけれど、特定の業界では大きな評価を受けている」という事例は、ネット社会の進展に伴って、これからどんどん増えていくことでしょう。
先例と言えそうな事件がありました。
ニューハンプシャー州に「マクダウェル・コロニー」というアメリカ最古のアーチスト・コロニー(私立の芸術家村)があります。1896年にはじまったインディーズ型のレジデンス施設で、これまでに6千人以上のアーチストを受け入れてきました。
有名なところでは
・『カラー・パープル』の作者アリス・ウォーカー
・『我が町』のソーントン・ワイルダー
・ゲイ小説の古典『ジョバンニの部屋』のジェームズ・ボールドウィン
・『ポーギーとベス』の文筆家デュボーズ・ヘイワード
らが滞在し、パフォーマンス・アーティストのメレディス・モンクは通算6回も利用しているといいます。
しかしこの名門コロニーは2006年に岐路に立たされました。
地元自治体が長年にわたって続けてきた税の免除を、突如取りやめることにしたのです。自治体側の主張によると、本来年間15万6千ドルほどの固定資産税がかかる物件にも関わらず、9千ドルに優遇していたそうなのです。
この件は裁判で争われましたが、争点となったのは「芸術家村は慈善事業に値するのか?」でした。
作家や芸術家が短期滞在することで、地域社会はどんな恩恵を受けるのか?
そんなあやふやなことのために税金を免除することに意味があるのか?
という訳です。
ニューハンプシャー州最高裁の出した判決は「地元住民に直接利益が還元されるわけではないかも知れないが、社会全体にとって有益な事業である」というものでした。つまり自治体側の敗訴が確定したのですが、その後コロニー側と自治体側の関係がどうなったのかは分かりません。
本来個人的な活動であるはずの創作に公共性はあるのか?
もしあるとしたら、それは現実社会でどう扱われるべきなのか?
個人と社会の関係性を考える上で古くて新しい問題ですが、あなたの街でも問われる日が来るかもしれません。
* * *
ケルアックハウスに興味をお持ちの方は、以下のマガジンや電書もどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
