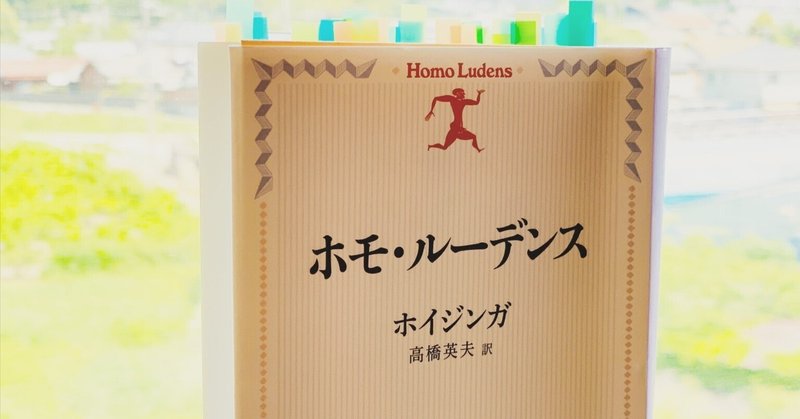
日常生活から、敢えて離れて「演じる」こと。ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』を読む(1)第1章「文化現象としての遊びの本質と意味」
文化の読書会、今回からはヨハン・ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(中公文庫版)を読みます。ちなみに、講談社学術文庫版もあります(持ってます)。
なぜ、この本にしたのか。今回は、私から提唱した記憶があります。
別に、私自身「遊び」が上手だという意識はありません。何なら苦手意識すらあります(笑)だからこそ、なのかもしれません。読みたくなったのは。
※ほかの方からしたら、「よう遊んどるやないか」ってつっこまれるかもですが(笑)
同時に、がっつり細かく計画を立てていくのも苦手。つねに「遊び」の部分を用意しときたい人間でもあります。そういう意味で、「遊び」というのをどう捉えるのかは、興味があるところでした。
遊びといえば、カイヨワも有名ですが、まずはホイジンガから読んでみたいなと。そういうわけで、今回から数回にわたって、ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』を読んでいきます。
摘 読。
文化現象としての遊び
ホイジンガは遊びを文化現象として捉え、生物学的機能としては捉えない。もちろん、人間以外の動物においても、人間と同じように遊びをしている。そこでは、生活維持のための直接的な必要を超えて、生活行為にある意味を添えるものが「作用し(プレイ)」ている。この点を深く掘り下げていこうとするのが、本書の狙いと言える。
そのなかで、まずホイジンガが注目するのは、「おもしろさ」という点である。ここで採り上げられる「遊び」は、誰にでも簡単に認められる、無条件に根源的な生の範疇の一つとしての遊び方である。これは、一つの全体性として捉えられる。その際に留意しておきたいのが、遊びとは単にある本質を成り立たせている素材というだけのものではないという点である。ここに、ホイジンガは「精神」の存在を見出す。この意味で、遊びは余剰なものであり、かつ非理性的である。
では、遊びとはどのような内実を持つのか。ホイジンガは、まず文化因子という面から考察を始める(中公文庫、22頁)。遊びは、「日常」生活とは区別される、はっきりと規定された行為としての様態をあらわしている。これは、文化の至るところに見出される。その際、人間は遊びを社会的構造体として、そのさまざまな具体的形式のなかで、じかに観察する。この遊びは、何らかのイメージを心のなかで操ることから始まる。つまり、現実をいきいきと活動している生の各種の形式に置き換え、その置換作用によって一種現実の形象化をおこない、現実のイメージを生み出すということが、遊びの基礎となっている。
これを可能にするのが、言語である。そして、この遊びを可能にするのが、比喩である。比喩には、言葉の遊びが隠れている。これによって、人間は存在しているものに対する表現=第二の架空世界を、自然界の他に創造している。その一つのあらわれが神話である。神話を可能にするのが想像力豊かな魂であるが、これは冗談と真面目の境界のうえを戯れている。祭祀もまた、現世の幸福の保証を手に入れようとして、さまざまな神聖な行事や奉献、供儀や密儀をおこなっているわけだが、これも純粋な遊びとしておこなわれている。
しかも、ホイジンガによれば、文化を動かすさまざまな大きな原動力の起源は、この神話と祭祀のなかにある。法律と秩序、取引と産業、技術と芸術、詩、哲学、そして科学、みなそうである。これらは全て遊びとして行動するということを土壌として、そのなかに根を下ろしている。
さて、この遊びは、一般的に「真面目」の反対として位置づけられることが多い。しかし、ホイジンガはこの見方を否定する。というのも、仮に周りから見ると滑稽だったとしても、遊んでいる当人たちは真剣であったりする。そうなると、より自立的な範疇として遊びを捉える必要が出てくる。しかも、遊びは賢愚という対比の外にあるのみならず、真偽や善悪といった対比からも外れている。そう考えると、遊びは楽しい気分や快適さと結びついていたり、また人間に与えられた美的認識能力のうち、最も高貴な天性である(とホイジンガが考える)リズムとハーモニーが織り込まれていたりする点で、美的(aesthetic)な営みとして位置づけることができる。
遊びの形式的な特徴:非日常性の自由と、遊びにおける秩序/規則
このような点から、ホイジンガは遊びを「一つの自由な行動」「日常、あるいは本来の生ではないこと」「日常生活から、その場と持続時間とによって区別されるという意味での完結性と限定性」という3つの点から特徴づけている。
この点を考えてみよう。遊びが自由である、とは、遊びが日常生活から、ある一時的な活動の領域へと踏み出していくということを示している。その意味で、遊びと真面目という対照関係はいつも流動的である。この二つはいつも境を接していて、相互に変化しうる。
では、遊びの境とはどのような特徴を持つのか。それは、利害関係を離れているという特徴である。遊びは日常生活とは別のものとして、必要や欲望の直接的満足という過程の外にある。むしろ、欲望の過程を一時的に停止させる(33頁)。そのことゆえに、遊びが生活全体の伴奏や補足になったり、時に生活の一部分にさえなったりする。そして、その限りにおいて、遊びは生活の文化機能として不可欠なものとなる。
同時に、遊びは日常生活とは別の局面であるがゆえに、「自ずと進行して終わりに達し、完結する」。時間と空間の限界内で「おこなわ(プレイ)」れて、そのなかで終わる。その進行のあいだ、全体を支配しているのは運動、動きである。そこには反復の可能性がつねに存在する。さらに、時間的制限以上に大きな意味を持つのが、空間的制限である。いかなる遊びにおいても、前もって自ずと区画された遊びの空間、遊びの場の内部でおこなわれる。それは、その領域だけに特殊な、そこにだけ固有な、種々の規則の力に司られた、祓められた場であり、周囲からは隔離され、垣で囲われて聖化された世界である。この内部では、一つの固有な、絶対的秩序が統べている。この点に関して、ホイジンガは遊びを秩序そのものであるという(37頁)。この秩序整然とした形式を創造しようとする衝動が、遊びを活気づける美的因子なのである。それを規定する性質こそが、リズムとハーモニーなのである。
この遊びにおいて、もう一つ重要な役割を持っているのが「緊張」である。これは、やってみないことにはわからないという意味での不確実さのなかで、何かが「成就」しなければならないというような特徴を持つ。この緊張のなかで、遊び人さまざまな能力が試練にかけられることになるわけである。
ここまでにおいて、遊びには固有な秩序と緊張があると述べられてきた。ヴァレリーは遊びの規則に対して懐疑ということはあり得ないという。というのも、規則が犯されるや否や、遊びの世界はたちまち崩れ落ちてしまうからである(39頁)。その点で、遊びの維持は公正(フェア)という概念と緊密に結びついている。
ただ、この遊びをぶち壊した連中が、自分たちだけですぐに新しい規則を持った新しい共同体をかたちづくるということもあり得る。こういったアウトロー、革命家、秘密クラブ員、異端の徒たちは、集団を組織する力がひじょうに強く、しかもそういう場合、ほとんどつねに高度な遊びの性格を示す(41頁)。
ここで問題となっている遊びの共同体は、遊びが終わった後も持続する傾向がある。ある例外的な状況のなかにいたという感情、共同で世間の人々のなかから抜け出し、日常の規範を一旦は放棄したのだという感情は、その遊びが持続する時間を超えて、後々までその魔力を残す。そういった特徴が、遊びに「何か秘密の雰囲気に取り巻かれていることを好む」という色彩をもたらす。遊びの領域のなかでは、日常生活の掟や慣習はもはや何の効力も持っていない。それをよくあらわしているのが、仮装や扮装である。変装した人や仮面をつけた人は、他人の役を、別の存在を「演ずる(プレイ)」。
以下は、ここまでのホイジンガの遊びに対する見方を総括したものである。
その外形から観察したとき、われわれは遊びを総括して、それは「本気でそうしている」のではないもの、日常生活の外にあると感じられているものだが、それにもかかわらず遊んでいる人を心の底まですっかり捉えてしまうことも可能な一つの自由な活動である、と呼ぶことができる。この行為はどんな物質的利害関係とも結びつかず、それからは何の利得ももたらされることはない。それは規定された時間と空間のなかで決められた規則に従い、秩序正しく進行する。またそれは、秘密に取り囲まれていることを好み、ややもすると日常世界とは異なるものである点を、変装の手段でことさら強調したりする社会集団を生み出すのである。
演じる表現としての遊び:遊びと祝祭
遊びは何ものかを求めての闘争であるか、あるいは何かをあらわす表現であるかのどちらかである。ホイジンガは、「最も表現が優れているものを選び出すために競争というかたちを取る」として、遊びの特質を「表現する」という点に見出そうとする(44頁以下)。したがって、遊びは神秘的現実化というかたちを取る祝祭なのである。
その一つの典型が、祭祀である。祭祀とは、何かを表出して示すこと、劇的に表現してあらわすことである。つまり、物事を継承化してイメージを創り出すことによって、現実にとって代わるものを生み出す行為である。そして、遊びを通じて、遊びのなかで、人間は表現された出来事をあらためて現実化し、世界秩序が保たれるのを助けるのである。フロベーニウスによれば、これは精神の必然的な移調作用の過程である。生徒自然の感動によって受けた衝撃状態から、自然感情が反射的に凝縮されて、詩的な着想や芸術形式となる。ただ、フロベーニウスの説明はホイジンガにとっては不十分なものであり、さらにそこから進もうとする。というのも、フロベーニウスにとって、遊びとは何か別のものを表現する目的を持った行為であるということになるからである。ホイジンガは、この「遊ぶ」という事実そのものを重視する。
ホイジンガによれば、遊びとは祭儀的行為の神聖な感動状態が結びついている。そこにおいては「プレイする」という特性が必ず備わっている。その点で、ホイジンガはプラトンによりながら遊びと聖事は同一であると指摘する(55−59頁)。その点を解すれば、「何のために」「なぜ」遊ぶのかというような問いは誤っているということになるわけである。遊んでいる人は、その全身全霊をそこに捧げる。「ただ遊んでいるだけだ」という意識はずっと奥のほうに後退し、遊びと分かちがたく結びついている喜びは緊張に変わるだけでなく、昂揚感や感激にも転化する。この遊びの気分の両極をなす感情は、快活と恍惚である。遊びの精神が崩れてしまったときや、陶酔がさめ、遊びに失望がしょうじたときに、遊びは妨げられてしまうことになる。
このように遊びと聖事を同一的に考えるとき、祝祭はまさに遊びと同じ特徴を持つことになる。そして、イェンゼンによれば、その根底には「これは、本当のことではないのだ」ちう意識がちゃんとあるという。クリスマスのサンタクロースに扮する父親もそうである。その点で、「佯ってそのふりをする」ことが、この遊びのなかには存在する。これに関して、ホイジンガは「人間とは瞞されることを欲するものなのである」と述べている。信仰と信仰以外のものとの統一が成し遂げられて切り離せないものとなったり、神聖な真面目さと単なる見せかけや「楽しみごと」が結びついたりするのも、この遊びと聖事との同一性を考えれば、よく理解できることなのである。遊びという概念においては、本当に信じていることと、信じているらしく見せかけることとのあいだの区別が消えてしまう。このことを、ホイジンガは「子供と詩人が未開人とともに棲んでいる」(72頁)と表現する。この日常生活から連れ出されて、現実界とはどこか違った別の境界に引き込まれる、それこそが遊びの領域の特徴なのである。
私 見。
冒頭から、なかなかおもしろい。ホイジンガの「遊び」に対する基本的な捉え方が、ここに端的に示されているようにも思える。
ホイジンガの「遊び」の議論に関して、カイヨワがこの規則という面に関して批判的に論じていたように記憶しているのだが、たしかにホイジンガの議論において、遊びには規則があるということが強調されている。実際、遊びにおいてルール破りはその公正さを失わせるがゆえに、忌避される。にもかかわらず、ホイジンガは遊びの規則をぶち壊したやつが新しい遊びの共同体をつくってしまうことに言及しているのも、すこぶる興味深いところだ。いわゆるunderground cultureというのは、それまでの(固定化してしまった)遊びの規則をぶち壊すところに、ひとつの快楽が存在している。それゆえに、アングラがひとつのかたちとして成り立ってしまったときには、それがアングラのもともと持っていた美的側面を喪失させることにもなりかねないわけである。ここは、アントレプレナーが自ら創設した企業や制度などから自ら離脱してしまうひとつの原因を言い当てているようにも思う。
そして、ホイジンガが「遊び」に関して、演じる(play)ということを強調している点も、すこぶる魅かれる論点である。例えば、能で「狂女物」というジャンルがある。ここでは、子どもと生き別れた母親が「狂って」芸を見せながら、子どもを探してさすらい歩くという要素が、ほぼ必ず入る。この〈クルイ〉が一つの芸なのである。その際、この母親(女性が多いが、稀に男が狂うものもあって『高野物狂』という名曲もある)は、ほんとうに心神喪失しているわけではない。むしろ、どこかに冷静な面を保っている。その意味で『三井寺』という曲の母親などは「佯狂」、つまり狂っていることを佯っていると位置づける伝書もある。そして、周囲の人間は、これをはやし立てるのだが、その芸を楽しんでいるという側面も濃厚にある。ちなみに、狂女物でもっとも有名なのは『隅田川』だが、この曲だけは子どもが亡くなってしまっていて、会えない結末(子方が亡霊としてすれ違うさまは、涙なしに観れない)である。観客は悲劇的結末であることを知りながら、母親のクルイなどを「楽しむ」のである。
また、能のなかには紫式部の霊が石山寺で舞う『源氏供養』や、和泉式部の霊が誓願寺で舞う『誓願寺』といった作品がある。これらは平安時代の文芸人が舞うという王朝趣味もあるにはあるが、それ以上に寺で女性が舞うという宗教と祝祭(そこには、芸能者という存在が二重写しに浮かび上がる)、そこに通底する「遊び」の感覚が漾曳する。だからこそ、こういった曲ではノリが必要になる。それがないと、重くなって退屈になる。
企業においても、似たようなことが言えそうだ。ここでいう「遊び」とは全社運動会とか社員旅行とかをさすのではない(別に、それらを否定していないので、念のため)。むしろ、企業としての日常生活を逸脱することが許されているという感覚だろう。
そして、本章においてすでに遊びと比喩が採りあげられているのも注目に値する。後章で遊びと詩といったテーマも採りあげられることになるが、現実描写とそれを超えてしまうことを可能にする機能を持つ言語に着目しているのは、やはり魅かれる論点である。こここそ、アントレプレナーシップの詩学的なアプローチということになるだろう。
今回の章は、ホイジンガの「遊び」についての基本的な捉え方が述べられていた。これからの章では、より詳細なところや具体的なあらわれなどが論じられることになる。
ちなみに、この本が書かれたのは1938年。もうヒトラーが政権をとったあと、第二次世界大戦がはじまる前年である。暗い影は差していた。そのようななかで、この本が書かれたことの意義についても、この本を読みながら考えたい。ホイジンガもまた強制収容所に入れられた一人である。釈放はされたものの、第二次世界大戦の終結を見ることなく、1945年2月に亡くなっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
