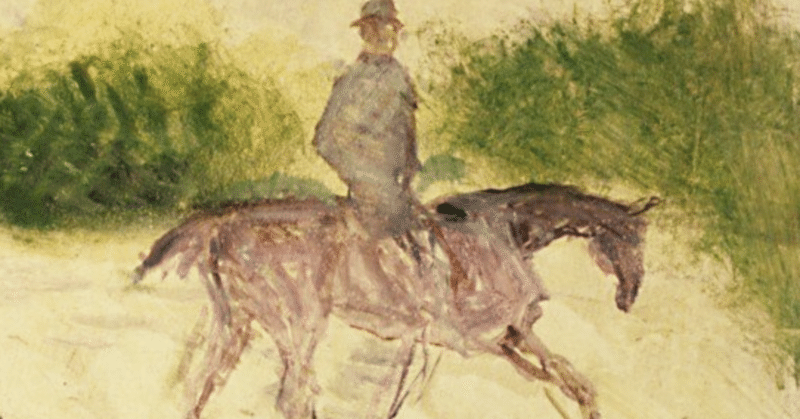
檀君神話のおはなし
朝鮮半島についての歴史を霊媒で垣間見ることはありましたが、特に言及せずにいました。
何故かというと、かの国の人は何かと言えば騒ぐイメージが強かったからです。
少しでもネガティヴな情報を話せば
「本当はこうじゃないの!!!!」
と猛反発されかねません。
それは一向に構わないですし
「そうですね。その通りです。変なこと言ってごめんなさいね」
と謝罪するのも全然良いんですけど、そういったやりとりが発生すると分かっているのに敢えてそういった行動に出るほど挑発的でありたくなかったというのもあります。
という訳で、朝鮮史の様々な方々と話を訊くだけに留めていたのですが、ある日突然降ってきました。
ダン
done
終わりという意味です。
もうこれ以上はないよ、という。
最初は意図が分からず、適当にネット検索をしていたのですが、ふと。
あ、檀君か。
と気付きました。
ダンくん ね。
檀君神話についてよく知らないですし、原本も見ないとわからんぞ、と調べてみたら「三国遺事」という私撰史書が元になっているという情報まで漕ぎ着けました。
私撰とは、個人的に編集したという意味があります。
高麗の高僧一然による、独自の調査に寄る自費出版の歴史書らしいです。
彼によれば
「朝鮮半島という地は暦が存在しなくてね。私が作ったのですよ。暦というのは普通、王族が定めるものなのだが、彼らは唐に使者を送るばかりでそういった政には関心がなかったようなのだ。そこで、私が筆頭となって市民と適当にお金を出し合って、倭から学者を呼んで暦を作ってもらった。それを書いたのが三国遺事だ」
ということです。
原本を読んでいないので
「そうなんですか…」
としか言えないんですけどね。
国会図書館でそれっぽい書籍を調べたところ、ガリ版書籍が読みづらくて、段々面倒になって読むのを辞めたのですが
「とにかく資料が少なくて。そして文字を書ける者と紙が少なくて、記録を残そうにも残せなかったのだね」
という記述を見つけました。
大体の系図と、あらゆる事件事故のあらましが書いてあるようですが、なんだかピンときません。
一然氏によれば
檀君というのは、現在の暦でいう10世紀の朝鮮半島の王である。
彼には複数の妃がいた。
見た目は
十二国記
白銀の墟 玄の月
の表紙の方に似ていらっしゃる。

この絵の通りではなく、あくまでもイメージ図であるので、本気にしないように。
くれぐれも勝手に持ち出して、歴史作品の中に彼を出すようなことはあってはならない。
檀君のお怒りを買うぞ、とのことです。
そして、市民で定めた暦ですけれど
檀君の即位の年が12であったということから拾弐の月を定め、そこから偶数・奇数と交互に日を巡るようにした
のが始まりです。
ネットで調べたところ、一般的に檀君神話とは
太古の昔、桓因という天帝の庶子に桓雄がいた。
桓雄が常に天下の人間世界に深い関心をもっていたので、天符印三筒を与えて天降りさせ、人間世界を治めさせた。
部下3000人を率いた桓雄は、太伯山上の神壇樹下に下りて神市とした。
かれは風伯、雨師、雲師をしたがえて穀・命・病・刑・善・悪をつかさどり、人間の360余事を治めさせた。
このとき一匹の熊と一匹の虎が洞窟で同居していて、人間に化生することを念願していた。
桓雄は一把のヨモギと20個のニンニクを与えて、100日間日光を見ないように告げた。熊は日光を避けること37日目に熊女になったが、虎は物忌みができず人間になれなかった。
桓雄は人間に化身した熊女と結ばれ、檀君王倹を産んだ。
檀君は中国の堯帝が即位して50年目の庚寅の年に、平壤を都として朝鮮と呼んだ。
のちに都を白岳山の阿斯達に移して、1500年間も国を治めた。
周の武王が即位した己卯年に、箕子を朝鮮に封ずると、壇君は阿斯達からかくれて山神となった。
寿命が1908歳であった。
とあるようですが、これは史実ではありません。
十二支の寓話みたいなものです。
順番通りに辿り着いた動物から十二支を決定する、みたいな。
桓雄という人が、主にお金を集めた人です。
非常に賢い若者でした。
そして、天符印三筒が集めたお金です。
風伯、雨師、雲師というのは、倭から連れてきた学者。
彼らは北陸出身のようでした。
語学に堪能で、非常に優しかった。
穀・命・病・刑・善・悪
というのは、月の名前です。
大事そうな字、というだけで、深い意味はありません。
部下3000人というのは、話を盛りすぎています。
実際は30人。
30人の朝鮮市民が彼らを迎えに行った。
その30人になぞらえて、暦を作ることにしました。
12の月
30の人
360日。
このとき一匹の熊と一匹の虎が洞窟で同居していて、人間に化生することを念願していた。
桓雄は一把のヨモギと20個のニンニクを与えて、100日間日光を見ないように告げた。熊は日光を避けること37日目に熊女になったが、虎は物忌みができず人間になれなかった。
これは、檀君の妻の中でも特に抜きん出ていた妃ですね。
お虎さん
お熊さん
そんな感じです。
彼女らに
「一把のヨモギと20個のニンニクを与えて、100日間日光を見ないようにした」
とありますが、一種の我慢比べです。
洞窟の中に閉じ込めて、与えた食料だけで生きのびた方が暦に名を残せる、という。
この二人は実は檀君に嫌われていまして、どちらが死んでも良かったようです。
お熊は37日生きのびました。
お虎は3日で死んでしまいました。
お虎は子を産んだばかりで、大層弱っていたからですね。
お熊は38日目に泣き言を言いましたので、そこで出してやりました。
そうして、熊を奇数、虎を偶数。
奇数は陽
偶数は陰
として、交互に暦の基準として採用することになりました。
檀君は中国の堯帝が即位して50年目の庚寅の年に、平壤を都として朝鮮と呼んだ。
この年から暦をスタートさせた、という意味です。
堯帝とは古代中国神話の王君となっておりますが、実際は唐の時代の方のようです。
陶唐君。
のちに都を白岳山の阿斯達に移して、1500年間も国を治めた。
一月が陰陽15日。
計30日。
のカレンダーの内訳です。
周の武王が即位した己卯年に、箕子を朝鮮に封ずると、壇君は阿斯達からかくれて山神となった。
寿命が1908歳であった。
檀君は、暦を使い始めて19年目の8月に亡くなりました。
そういう意味の内容ですね。
夭逝されたようですが、苦労も多かったので仕方なかったと思われます。
ちなみに、この暦は檀君死去、すぐに廃れて朝鮮半島は再び暦の存在しない状態に戻りました。
それから、日朝併合まで朝鮮にはカレンダーというものが存在しませんでした。
と、かの高僧はおっしゃっておりますね。
つまり、檀君は朝鮮の始祖ではなく、一統治者であった、とのことです。
檀君暦の使い方
穀・命・病・刑・善・悪を陰陽で分け、15日をそれぞれ熊と虎で分けます。
1月 穀陽
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
2月 穀陰
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
3月 命陽
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
4月 命陰
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
5月 病陽
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
6月 病陰
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
7月 刑陽
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
8月 刑陰
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
9月 善陽
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
10月 善陰
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
11月 悪陽
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
12月 悪陰
1熊
2熊
3熊
4熊
5熊
6熊
7熊
8熊
9熊
10熊
11熊
12熊
13熊
14熊
15熊
1虎
2虎
3虎
4虎
5虎
6虎
7虎
8虎
9虎
10虎
11虎
12虎
13虎
14虎
15虎
打ち出してみましたが、こんな感じです。
一然氏は 8月の刑陰を打つ際に
「ここです。この月に檀君が亡くなりました。熊の13日ですね」
と仰っていました。
どこかで閏月の調整が必要と思うのですが、そこまで思考が至るまで暦が育たなかったようですね。
たった20年しか持たなかった。
閏月に気付くのは100年はかかりますからね。
「四季がズレている」
と気付き、宮廷全体で相談して定めるのですね。
この暦は口伝にて御伽噺として受け継がれていったのでしょう。
使わないのか?と思いますが。
まあ、大体想像が付きますよね。
「なんで暦って決まっているの?」
と言い出す人があったのでしょう。
漢字と同じです。
「必要性がない」
という結論に達し、いつしか忘れ去られていったのだと思います。
暦そのものが、ある種の束縛であるためですね。
ここに日本人は関係ないですよ。
そもそも倭の朝廷は、そのような出来事があったことすら知りませんでした。
私は霊媒で一然というお坊さんに訊ねただけですので、意図とか全くないです。
一然さんは気さくでよい方ですね。
尋ねたら、丁寧に教えてくださりました。
所詮は霊媒情報ですし
信憑性とか訊かれても困るのですが、会話の内容がこんな感じだったよ、とだけ。
だから
「ちがうの、こんなのじゃないのよ」
と言われても困ります。
神話と実情って、結構違います。
神話は神話。
大抵は史実が元になっていますけれど、子に御伽噺・昔話として聞かせたりすると、内容って歪みますよね。
段々、ファンタジー要素が含まれてくる。
これはどこの国も同じです。
そういうわけで、どんなに胸が踊るような魔法みたいな神話を耳にしたとて、本気にしてはいけないのですね。
そもそも、いつの時代の事件かも不明ですからね。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
