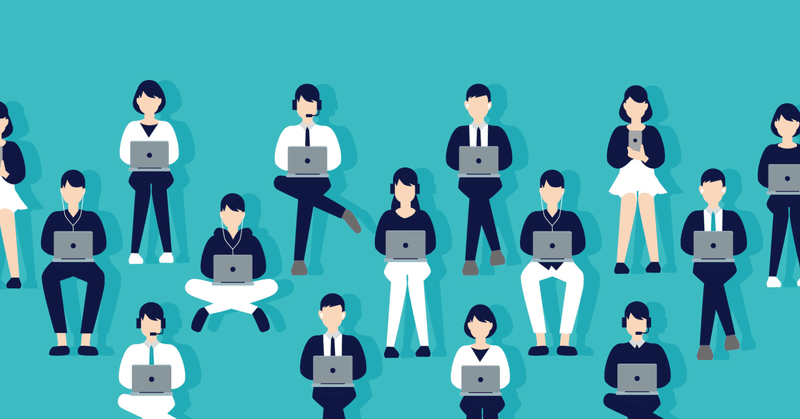
【Vol.8】フルリモートでの他拠点マネジメント
現在2022年5月14日土曜日、21時26分。
狂信的にハマりつつあるStray Kidsが、なななんと
23時00分〜NHK「Venue101」にコメント出演します…!!
頑張ってそれまでに、
転職前のビジネススキル棚卸しシリーズ(?)最終回を投稿します!
(転職後にまた新たなシリーズ始める予定←詳細未定)
前回は「決裁者」「影響者」「推進者」など複数のステイクホルダーが意思決定に関与する場合の進め方に関してでした。
今回はフルリモートでの他拠点マネジメントに関して、大まかなまとめです。
福岡在住で、東京や大阪の他拠点のメンバーから構成されるチームのプレイングマネージャーを務めていました。
その際の気づきや取り組みを綴っていきたいと思います。
できれば、マネジメントはやりたくない
偏った完璧主義ゆえの生きづらさ
私は自分自身のことをとても「偏っている」人間だと思っています。
興味ある・ない。
こだわる・こだわらない。
得意・苦手。
許容できること・許せないこと。
20代前半(新卒入社の会社の時)は、その「偏り」に無自覚で
自分の見ている世界が全てに近く、自分の正しさだけを信じていました。
時に生きづらさや困難を自分で招いしてまうこともありました。
分かりやすく言うと、今の3倍くらい自己中心的&性格が悪かったです(苦笑)
「マイペースがハイペース」
いくつかの会社・そのフェーズ・役割を経てスタンス・スキル・スタイルが変遷していきますが、変わらないこと。
それは、思い立った時のActionの速さ。
決断から実行、という大きなものもあれば、日々のタスク処理なども。
これは仕事のみならずプライベートにおいても同様です。
「迅速・効率良く。そして、キッチリやり遂げたい」思考は年々増しているかもしれません。
(料理など「頑張らない」と決めていることは、とことん手を抜く)
「自分のスタンスを人に求めすぎない、押し付けない」ことも徐々に学んできたものの、根底の性格もあり、マネジメントという「相手と同じ目線に立ち、共に同じ目標に向かう」ことは、私にとって試練が多かったです。
年齢やキャリア、市場価値など全く先のことを考えなくて良ければ
プレイヤーとして自分のペースで、自分のことだけやっていたいな…と思うことは正直何度もありました。
チームビルディングは「オンライン完結」できない
これまでのnoteで「オンライン商談」のメリット、ノウハウを発信してきましたが、「顧客」という一定の距離感ゆえ実現できたと思います。
マネジメントは、顧客対応とは異なります。
時に苦言を呈したり、嫌われ者になる必要もあります。
そのためには、ベースとしての信頼関係構築が大切。
正直に言うと、オンライン環境下では「余談が生まれにくい」ため
「業務外のパーソナルな部分に触れるキッカケを持ち辛かった」です。
物理的な距離に加えて、育児という時間の制約もあるため
娘寝かしつけて、家事終わらせて確実に時間が空くのは22時前後。
そんな時間から19時〜20時にはすでに仕事を終えてるメンバーに
「オンライン飲みしよ〜」と気軽に誘うことも躊躇う。
性格・物理的事情・時間の制約を考えると、私がマネージャーになったことで、メンバーには大変な苦労をさせてしまっていたんだろうな、と思います。
通常はオンラインのチームコミュニケーションでも、対面をおり混ぜ、思い立ったら「すぐに顔を合わせることができる」「食事や飲みに行ける」これができると、手っ取り早く、且つ仕事以外のお互いのことを理解できるシンプル&効果的です。(私はこれが十分にできなかった)
そうは言っても自分の環境は変えることができないので、
「なるべく(できれば最初に)一定期間顔を合わせる」
ここをなんとか目指して頑張るしかありません!
(入社から現在も県を跨ぐ移動が難しい状況続き、実現難易度高めでしたが)
ここから先の具体的な内容は
オンラインでいきなり、オンラインで全て、というより
「対面で一定期間交流した状態」を理想とした上で、読み進めてもらえればと思います。
「回向返照」 今の自分にできること
私の好きな言葉の一つです。
外に答えを求めるのではなく、自分の内面を見つめなさい、という教え。
他者のアドバイスを受け入れることは大切ですが、
自分の環境や状況が異なる場合は、同じ方法では乗り越えることができないことも多々あります。
今の自分にできることは?
マネジメントにおいても、悩みながら、壁にぶつかりながら
そして(オンラインなので)人知れず落ち込みながら。試行錯誤してきました。
複数人のリーダー育成が急務
改めて痛感したこと。
これは、私がプレイングマネージャーだったため
一定、自分の案件や数字責任を持っている前提になりますが
オンライン環境下では
1人あたりの密なコミュニケーションが取れる相手は
できれば3人以内が良い、と思いました。
1人のマネージャー、
3人のリーダー、
それぞれに3人ずつメンバー、
合計で13人のチーム
このあたりがギリギリ限界ではないでしょうか。
リーダーが新任・発展途上であれば
1人マネージャー、2人リーダー、メンバー2人ずつで合計7名ほどだと安心です。
オンラインで最初に対面で関係性を構築したとしても、日々の業務だけではなくメンタル面のケアの考慮も必要です。
そのため、密に接点を持てるキャパを超えてしまうと、空中分解のリスクもあります。
マネージャーはチーム目標達成に並行して、リーダー育成(複数人)が急務です。
ミスリードを経てFS施策強化
THE MODEL式の分業方営業の場合は、ISから供給されたアポに対してFSが商談を行います。
チーム数字が不調な際、商談数・キャンセル率・リスケ率にベクトルを向けてしまいました。
そこで「どうやったらISからのアポ数が増えるか・リスケ・キャンセル減るか」ばかりを考えてしまいましたが、ふと「商談数が増えたら受注につながるのか?」と自問したところ、まだまだ受け手(FS)サイドの課題が多いことに気づきました。
ある時からFSの提案率・受注率UPのみに最大注力しました。
差配の変更・随時調整
事前想定時に資料、デモ、進め方も確認
問い合わせと決裁者商談への同席の徹底
提案率が低い=上申してもらえてないため上申資料の作成強化
単価アップ施策(基本提案プラン整備、事前想定で最適オプションも選定&デモ準備)
初訪のみならず進行中も常に想定ネックと対策、細かなフォロー
追客や顧客コミュニケーションも介在
上記の取り組みを徹底。
アポの内容を見て適した人材に商談差配し、決裁者商談や問い合わせは極力同席して温度感の高い案件を確実に決めることを心掛けました。
また、受注をゴールとせず運用浸透を目指すこと、
受注後のCSSへの連携の大切さ、具体的な引き継ぎに関しても根気強く伝えるようにしました。
メンバー(ヒト)ではなく、商談(コト)にベクトルを向ける
「**さんはヨミの精度が低いから、そこを改善しないといけない」
「□□さんは追客後いつの間にか顧客とコンタクト取れず失注が多い」
メンバー課題に対して、相手を変えようとするとお互いに良いことはありません。
もっと具体的に、1件1件の商談をどうすれば受注できるか、の作戦会議を増やすようにしました。
そうすれば「メンバーの**さんを変える」という私が1人で掲げる目標から
「**さんと一緒に○○社を受注する」という共通目標を2人で追うことに変わります。
そちらの方が、お互い心も健やかです。
1人1人との定期コミュニケーション
自己認識している課題の確認
まだ自己認識していない課題の棚卸
本人への期待する点
案件の具体的な会話以外に、月次など定期的な会話で上記も会話していました。
「商談数」「提案率」「受注率」「受注単価」「リードタイム」
各項目に○△×をつけてもらい、自己認識と他者評価の擦り合わせも。
ただ感覚的に「不調だ」と思考停止に陥ることを防ぎ、
定量からも判断し自ら課題と適切な打ち手に気づいてもらう、という目的でもあります。
受注額だけではなく、受注の内訳を把握する
個人の売上構成や内訳を分解し、得手不得手の把握。
商談相手(決裁者・導入責任者・担当者など)
リードソース(白地・過去失注先・紹介・問い合わせなど)
業界業種(得意分野は何か)
リードタイム(即決得意?長期追客案件から?)
失注理由の分解
受注より失注の方がサンプル数が多いので、ここも丁寧に整理。
提案率が低い、受注率が低い場合は単に「課題だ」と言うのではなく
「さしみ(3:4:3)のどれ?」と確認していました。
3割…誰が商談しても受注できる
4割…営業の実力よって受注できるかも
3割…誰が商談しても失注する
※「誰が商談しても失注する」が多すぎる場合は、リードマネジメントの見直しも必要。
業界業種に偏り→そこを強化する
決裁者商談が弱い→重要商談同席
上申してフェーズアップが苦手→上申フォロー見直し
と、要因分解して打ち手をセットで考えていきます。
個人数字の進捗や案件の詳細は個別で
営業は結果に波がつきものです。
不調な時にチーム会で進捗共有って、なかなかの心の負荷。
オンラインだとサインを読み取りにくいこともあるため、尚更配慮が必要です。
数字進捗や案件詳細の確認は(週次など)個別で会話。
その個人足し上げから、チームの着地、残目標までの取り組みを整理。
チームミーティングはコミュニケーション中心、みんなでできる取り組みなど前向きな場になるよう心掛ける。
チームミーティングにはチェックインを行い
「最近した大きな買い物」「最近ハマっているもの」など仕事無関係のお題を連番で考え、極力笑顔からミーティングを開始できるよう努めていました。
読み返してみると
申し訳ないくらいどれも目新しい情報はなく、どこかで聞いたことあるtipsばかり…!
繰り返しになりますが、「対面の方が相談しやすい」「対面の方が打ち解けやすい・信頼関係築きやすい」だろうなと、メンバーに対してずっと申し訳ない気持ちを抱えながら奮闘してきた日々でした。
明日の今頃は、東京に向かう飛行機を降りて電車・もしくはホテルに到着している頃。
今後のnoteでは(StrayKidsの発信を挟みながら)
少し落ち着いたら新しい環境・仕事の事も投稿していきたいと思います!
転職前のビジネススキル棚卸しシリーズ、読んでいただきありがとうございました〜!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
