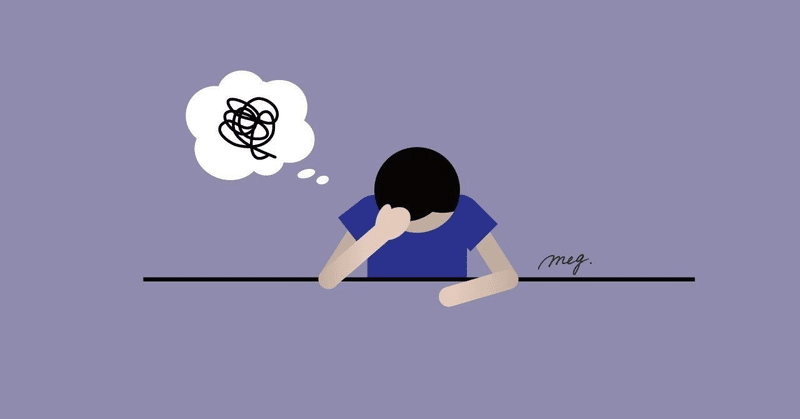
【Vol.3】ロープレ病にならないために
1週間ほど娘の手術&付き添い入院しており、前回投稿から少し時間が経ってしまいました。
次の会社への入社までに、予告していた全12回に渡る投稿が間に合う気が全くしないです(震)
これまでの棚卸踏まえ、可能な範囲で投稿していきたいと思います〜
前回記事では商談の冒頭部分を中心に紹介させて頂きました。
メンバー同席時「ロープレのような進め方だな」と顧客置き去り状態を目の当たりにすることがありました。
かくいう私自身も転職直後、まだ自分の流れを掴めていない時代。先輩に同席して頂き「会話が噛み合ってなかった」とフィードバックを受けたことも(苦笑)
今回は初歩的な内容ですが、上記の体験踏まえ商談時の「概要説明」「ヒアリング」「提案」に渡り、気を付けていたことをまとめたいと思います。
ロープレと商談は目的が異なる
商談は事前準備が肝と言う大前提の中で、その「事前準備」は①汎用的な商談全般に関わる準備 ②個社ごとに向けた準備 に分解されます。
ロープレや提案資料のプラッシュアップなどは前者に該当。
後者に関しては、以前の記事にまとめています。
事前準備をしっかり行い、想定ロープレも実施した。だけど商談がうまくいかない。
上記の経験があれば、ロープレ、商談、それぞれの目的にまずは立ち返ると良いかもしれません。
ロープレ(練習)の目的は「自分」が「引き出しを増やす」こと
商談(本番)の目的は「相手」が「購買決定する」こと
とてもシンプルなことですが、主語も述語も異なります。
商談は顧客など「相手」ありきですので「ロープレや事前準備の通りに進める」に終始していては、その目的が達成できないかもしれません。
ロープレ(練習)の目的は「自分」が「引き出しを増やす」こと
では、この「引き出しの増やし方」について。
<input>
抽象的な表現ですが、例えば商談において100項目の理解が必要な場合
「(10ページに分けて)100項目全て覚える」→全体
「1ページ1メッセージ、全部で10のメッセージにまとめる」→要点
この双方ができるようになるイメージです。
「一言でいうと何か」の整理をし、詳細や事例などの肉付けをしていきます。
<output>
ロープレは、まず①通しで全体を話す、より実践に近く②質問に対して回答・ネックに対し切り返しを加えながら話す、この2パターンがあると思います。
ロープレ相手役を務める際は、下記を意識していました。
正しいか
わかりやすいか
やってみたい(契約・購入したい)か
この中で一番大切なことは、伝えている内容が「1. 正しいか」です。
これらに加え
「時間配分」もチェック。何にどれ位の時間を使っているか、とそのバランスをフィードバックするようにしていました。
会社概要、サービス概要、事例、デモ、想定ネックと切り返し…など、inputとロープレによるoutputを繰り返す。ここは鍛錬です。
商談(本番)の目的は「相手」が「購買決定する」こと
ロープレと違い、商談には顧客という「相手」が登場します。
1人1人持っている背景知識・リテラシーの違い・その商談におけるモチベーションが異なる、と言うことを忘れてはいけません。
事前準備段階での「想定と異なる」ことが起きる、これが商談です。
ロープレのように正しく、わかりやすく伝えることができたか(その結果購買意欲向上に繋がったか)も大切ですが
商談ステップを確実に進めることがゴールとなります。
そのため商談は「自分が準備した内容を披露する」のではなく「相手の関心どころに合わせ適切に」進める必要があります。
本質を引き出し、臨機応変に進める
商談の構成
色々と試行錯誤&ブラッシュアップをしてきましたが、最近は下記の商談構成に落ち着きました。
本日の流れ整理(所要時間、商談の構成、進め方の確認)
アイスブレイク
概要説明(どんな会社・product・提供価値)
ヒアリング(productを正しく理解して頂いた上で)
プレゼン(どのように使えるか)
クロージング(できることの整理)
区切りながら進め、どこで失敗したか振り返ることでWeekPointの克服や商談のリカバリーに繋げます。
潔く省く・捨てる
自分が伝えたいこと(準備した流れ・ロープレで覚えた内容)の押し付けは厳禁です。
相手の課題・ニーズに対して必要な情報を即座に見抜き、それ以外は躊躇なく捨てます。
例えば、導入事例を複数パターン準備していても、商談中にその相手は「他社がどうか、と言うことに全く関心がない」ことが分かれば準備した事例を一切伝えない。
相手の業種に合わせてデモ画面を作り込んだが、そもそも想定していた事業とは別部署での検討になりそう、と判明すれば入念に準備した個別のデモは一切使わず、その検討しうる部署に近しい汎用的なデモ画面に切り替える。
入念な準備内容に対し、実際は2〜3割しか使わなかった、というケースも珍しくないです。
商談構成も通常は概要説明→ヒアリング→提案(デモ)の流れが多いですが、相手が商談におけるモチベーションが低く、冒頭での課題抽出があまりにも難しそうと判断した合は急遽変更。
最低限の概要のみスライド1〜2枚で説明し、デモをしながら、ヒアリング。
このように柔軟に変えています。
質問には回答の前に、まず意図を確認
前述の「相手の課題・ニーズに対して必要な情報を即座に見抜く」タイミングは ①ヒアリング ②相手からの質問 この2つ。
ここでは後者について整理したいと思います。
質問を受けた場合は、
目線が合っているか (合っていない場合は再度前提や概要を端的に伝える→再度目線合わせ)
意図の確認 (なぜそれを質問しているのか、質問の背景にあることは?)
→具体的な質問に対して、具体例で答えるのではなく質問の背景(先方の本質的に聞きたい意図の部分)に対して回答する
これらを踏まえた上で
回答前に「(その質問をされるのは背景として)***という理解で相違ないですか?」
回答後には「質問のお答えになっていましたか?」と的外れではないか確認します。
また、商談構成上後ほど説明しよう、と思っていた内容を早々に質問された場合は順序に捉われすぎない(その場で解決する)ことも留意。
とはいえ、相手の質問の全てに回答しているとペースが乱されたり、商談が進捗しないリスクもあります。
①必ず先に伝えておくべき前提となる情報と、②柔軟に対応した方が良いことは切り分け整理。
後者の場合はすぐに回答し、説明の順序を入れ替えていました。
事前想定・仮説に固執せず、相手の質問の背景を理解した上でシンプルに答える。相手のニーズに沿った柔軟な進め方を意識していました。
4つの「不」解消ポイント
Salesforce流・THE MODELを取り入れた営業形式の場合、あまりにも有名かと思いますが、改めて。
私がこの4つの「不」解消のために留意していたことです。
「不信」の突破 笑顔、相槌のタイミング、言葉、スピード
「不要」の突破 適切なサービス概要の案内
「不適」の突破 目の前の企業の業務フローと商談者の管轄範囲・責任領域の掌握
「不急」の突破 課題解決の重要性と要する期間から逆算して提案
商談時はとにかく、自然な笑顔を相手が商談終えてZOOMから退出するまで絶やさない。
自分も相手も自然と微笑むことができるよう、リラックスしてオンライン商談を進めるための配慮を絶やさないように努力していました。
(話についてこれているか、聞き取りにくくないか、資料投影方法が見づらくないか、など)
商談同席は成長の近道
鮮度高く”その場”でフィードバック
これまでのnoteを拝見頂いている方はお気づきかもしれませんが
私は「(困ったときは適切に相談するので)基本は自分のやり方で伸び伸びやらせて欲しい」気持ち強め。商談同席されることは、あまり気が進まないタイプです・・
※メンバーも私に同席されると変な緊張感持って、内心嫌だったと思います(苦笑)
気が進まない気持ちは今も変わりませんが、商談に同席してもらうことで、確実に成長速度がアップしたと思います。
<自分の商談に同席してもらった場合>
商談後にお礼、自分の振り返り・反省点を簡潔に伝えた上て「フィードバックお願いします」と依頼。
ダメ出しされたり、苦言を呈されるのは誰だって心地よいものではないのですが、「商談を客観視してもらえる」「(自分の反省点や今後の留意点を)”その場で”理解・解決できる」このメリットは大きいです。
<メンバーの商談に同席した場合>
まずは「自分ではどうだった?」と良かったこと、うまくいかなかったことなどを、自分の言葉で語ってもらいます。(自己認識と他者認識に乖離がないか)
その上で気になった点は、意図を確認。
良かった点は、次どういうケースでも応用できそうかを整理
改善点は否定で終わらず「次(同じケースの時)はどのように進めると良いか」もセットで伝えるよう心がけていました。
以前のnoteでも「オンライン商談は録画できることがメリット」とお伝えしてます。
input・議事録・引き継ぎの観点では録画が大活躍することは間違いないのですが、outputに対するフィードバックとして、商談同席は非常に有用 です。
今回は商談時の「概要説明」「ヒアリング」「提案」に渡り、気を付けていたことをロープレと比較しながら紹介しました。
次回は「ヒアリング」におけるポイントをまとめたいと思います。
ここまで長文に目を通してくださり、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
