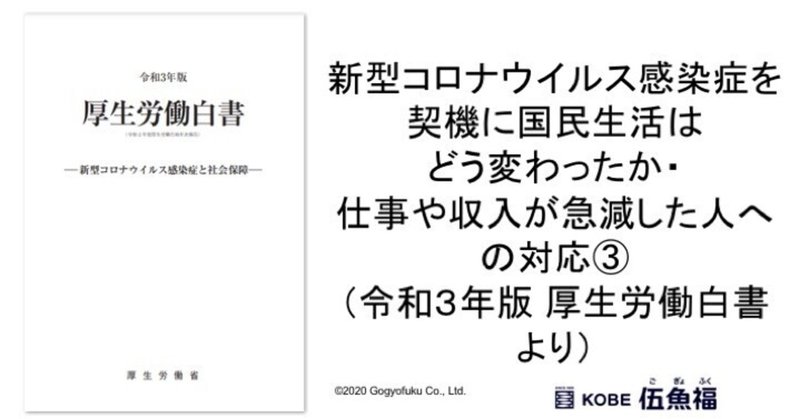
新型コロナウイルス感染症で特に大きな影響を受けた人々・活動への対応 仕事や収入が急減した人への対応③(令和3年版 厚生労働白書より)
本日は、「第1部 新型コロナウイルス感染症と社会保障」の「第1章 新型コロナウイルス感染症が国民生活に与えた影響と対応」、「第2節 特に大きな影響を受けた人々・活動への対応」より「1 仕事や収入が急減した人への対応」の続きを紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1 仕事や収入が急減した人への対応
(3)住まいに困っている人への支援
(住居を失うおそれが生じている者に対して、住居確保給付金の支給とともに、入居から定着までの一貫した支援を制度化)
離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある生活困窮者に対しては、求職活動等を要件として、原則3か月間、家賃相当額を支給する住居確保給付金の仕組みがある。
今般、新型コロナ感染拡大の影響を踏まえ、離職や廃業には至っていないが、休業等に伴う収入減少によりこうした状況と同程度の状況にあり、住居を失うおそれが生じている者に対しても支給可能としている。加えて、感染拡大の影響が長期化する中での特例措置として、2020(令和2)年度の新規申請者については、最長9か月の支給期間を12か月まで延長可能とし、受給期間を終了した後に2021(令和3)年2月から同年6月末までの間に申請した者については、3か月間の再支給を可能にした(図表1-2-1-12)。

2020年4月から2021年3月までの支給実績は、累計支給決定件数が139,761件、累計支給決定額が306億円となっている(図表1-2-1-13)。

また、シェルター等を退所した者等に対しては、従前より生活困窮者自立支援制度による居住支援が行われてきたが、新型コロナ感染拡大の影響等により、住居が不安定になる者や、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の制度間を行き来する者の増加が見込まれたことから、令和2年度第二次補正予算により盛り込まれた居宅生活移行緊急支援事業により、生活困窮者と生活保護受給者の居住支援を一体的かつ一貫的に実施することとされた(図表1-2-1-14)。

こうした取組みが広がることにより、住居確保が困難となった者の安定的な居住生活が可能となることが期待される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
離職等により、家賃の支払いが困難になった方への支援です。
失業手当と同様「求職活動」をしていることが条件となっていますが、本当に困っている方にはとても良い制度だと思います。
コロナ禍が始まってから、さまざまな支援の仕組みが整備されてきたんですね。マスコミの報道や国会での質疑など、不備な点ばかりが強調されがちですが、全体像を知った上で、公平・公正な判断ができるようにしたいです。
「厚生労働白書」なので、厚生労働省側のスタンスでまとめられていますのでその辺を割り引く必要があるとは思いますが、国としてもかなり手厚く、幅広くさまざまな支援が行われてきたという印象を受けます。
最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan
