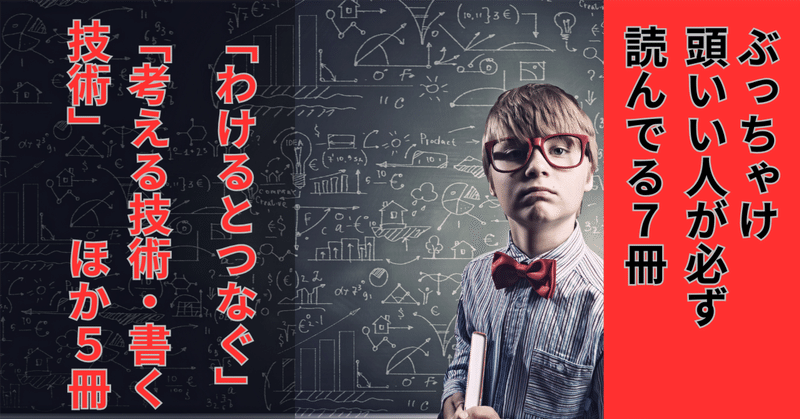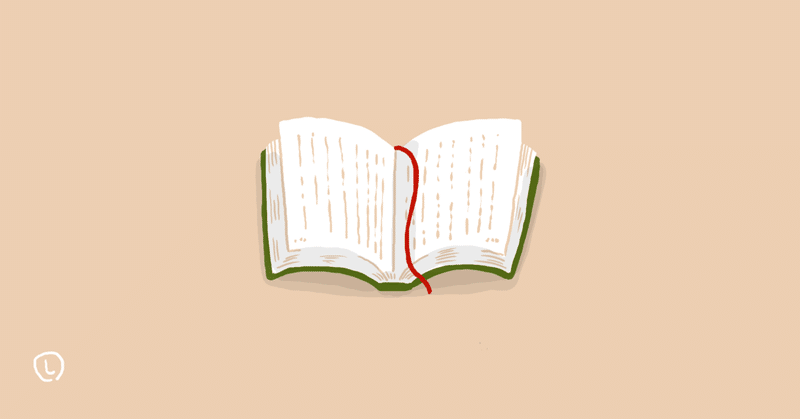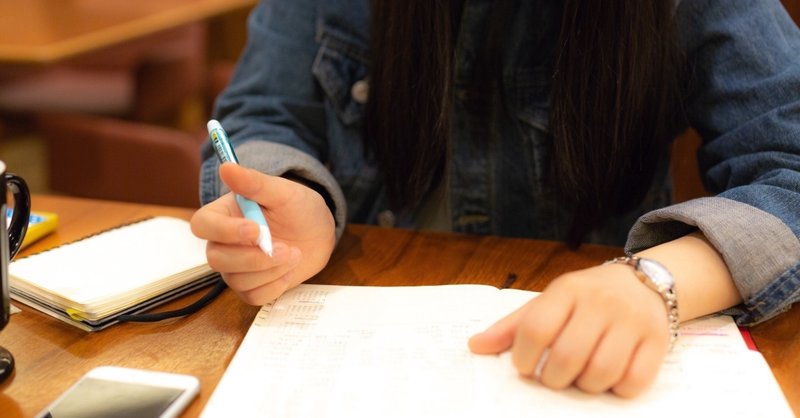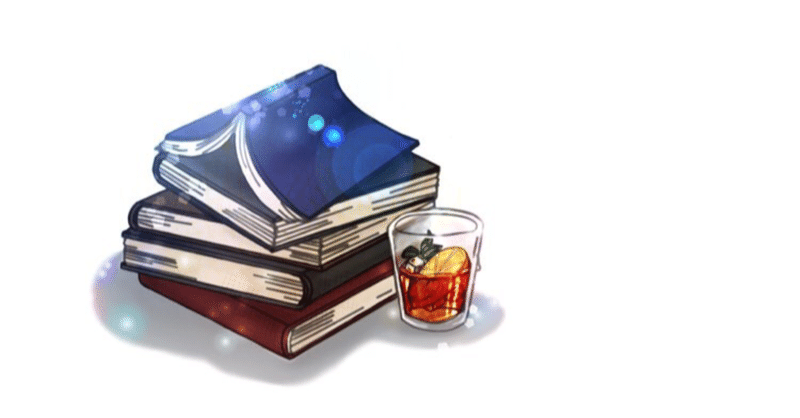記事一覧
わからなくても読み進めてみる
本を読んでいたら、意味がわからない文章にあたることが、しばしばある。ここで、まずはわからない単語を、辞書で引く人は多いだろう。ぼくも基本はそうする。しかし、いくら単語の意味を詳しく調べても、どうしてもわからないことがある。
そんなとき、その箇所はいったん棚に上げて、先を読み進めてみる。あるいは、それより前の部分を読み返してみる。そうすると、案外かんたんに、わからなかった部分がわかるようになったり
ぶっちゃけ頭いい人が必ず読んでる7冊教えて下さい。
前回「上級日本語教室第4項」
どうしてそんなに賢いの?ぼくの後輩にすごく頭のいいのがいる。
そこらの偽物が会ったらショック死するくらいの頭脳だ。
高3の秋に急に大学へ行きたくなり、2科目に絞って勉強してたったの3か月で慶應義塾大学のSFCに進学する猛者である。
それまで大学受験のための勉強なんてほとんどしていなかったという。
もともと料理好きだったので、レストランに就職すると豪語していたのだ
読書における「お口直し」
ラーメンを食べているとき、お口直しに水を飲んでから再度食べると、こんな味だったのか!と思うことがある。
以前は、パンチのあるスープじゃないと物足りないと思っていた。濃い味のものを、一気にたいらげるのが好きだった。お口直しの意味なんて知らなかった。
しかし、休憩を挟んで食べることを覚えてからは、ダシの味などもわかるようになってきた。これはカツオ節からとったダシだな、とか。
一気にがっつくのもい
文章を文字通りに読む。これを意識すると、読み方が変わる。もちろん行間を読むような深読みも、大事だと思う。しかし、著者の主張を理解することを主眼におけば、自分の解釈を持ちこみすぎない方がいい。特に、情報を得ることが目的の読書では、それが当てはまる。
電子書籍、最大のメリット
電子書籍のメリットは何だろうか。その一つの解答を得た。
それは、絶版本、稀覯(めったに出回らない)本など、従来の出版ビジネスでは出されないような本を、読めるようにしたということである。
これは学者の内田樹さんが書いた『街場のメディア論』という本に書かれていたことだ。これには目から鱗が落ちる気がした。
ぼくは今まで、電子書籍と紙の書籍にはどのような違いがあるのだろうと考えることがあった。上記の
本への書き込みと道路標識
本にメモを書き込むことは、本の内容の理解に非常に役立つと思います。
メモする方法としては、文法を意識することが挙げられます。また、キーワードを目立たせる方法もあるでしょう。
文法を意識することについて、私が重要だと思うのは、副詞と接続詞です。それだけ意識すればいいということではないですが、この二つは少なくとも重視すべきです。そこを囲ったり、目立つ色の線を引いたりするとよいです。
なぜなら、接
読むだけだとフワフワした知識しかつかない
僕は読書をする。そして、たしかに知識は増えている。しかし、増えているだけだ。まるで表面だけで繁殖し、拭けばすっかり取れてしまうカビのような知識だ。
もちろん、それらの知識が役に立つと実感することもある。ただ、それが偶然の産物にすぎないことが多い。
もっと目的意識を強く持ち、それに向かった勉強に集中した方がいいのかもしれない。しかし、僕は一つのことに縛り付けられるのが苦手である。たまに集中して何
本を所有するメリット
本は、買って手元に置くだけでも、それなりの意味がある。そのメリットは複数ある。
まず、手元に本があることで、手に取りやすくなる。読もうと思ったときに読みたい本が手元になくて、「まあいいか」となってしまう。そういうことがなくなる。
第二に、自分の本にすることで、その本に愛着が湧く。何年も前に読んだ本を再読して、昔の気持ちを思い出すかもしれない。
第三に、本の並びを見ているだけで勉強になる。例え
合わない人がいるのと同様に、合わない本もある。最も効率的なのは、自分に合う本を読むこと。
合わない本は、読みかけでいい。最初から最後まで読む必要なし。