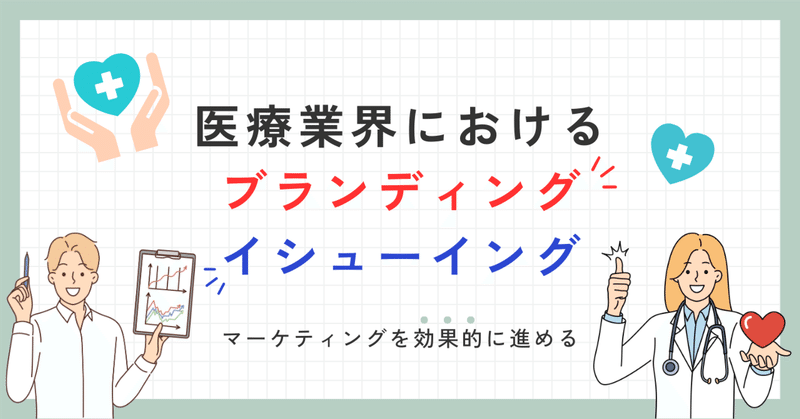
医療業界におけるブランディングとイシューイング
おはようございます!
昨日まで東京出張、本日は上下all-on-4 イミディエートopeの山田優貴です!!!(筋トレしてるからいける。)
本日は、《医療業界におけるブランディングとイシューイング》というテーマでお話ししていこうと思います!
ブランディングだのイシューイングだのとカタカナが並んでいて、少し読み込むのを躊躇う方もいるかもしれませんが、私たち医療業界にとって、マーケティングをより効果的に進めるために特に大切なポイントとなってきますので、是非ご一読いただければと思います。
ブランドの価値を伝える?
突然ですが、『自己紹介しましょう!』となった時に、
「●●株式会社で●●という部の●●長しております●●●●と申します。本日はどうぞよろしくお願いします」
的な、いわゆる基本構文の単語だけを入れ替えた自己紹介を良く耳にしますよね。
もちろん、自分も含めて。
では果たして、この自己紹介でその人の価値をどこまで認識できますかね。
・聞いたことある会社か、知らない会社か
・高い身分の役職か、面白そうな役職か
・よくある名前か、珍しい名前か
こんな感じ程度しか認識できないですよね。
ましてや大人数であればあるほど、“一押し”や“一芸”がないと、その人を認識し、記憶するというところまでになかなか至りません。
ブランドには2つの構成因子があります。
ブランドを因数分解すると、機能的価値を表す「知覚品質」と情緒的価値を表す「感覚品質」に分けることができます。
冒頭の肩書きばかりの自己紹介は、まさしく知覚品質をオンパレードしたものです。
例えばこれに、ベラベラと居住地とか、年収とか、出身大学とか、資格とか入れたら、聞いている方が恥ずかしくなってしまうくらいの完璧な知覚品質の出来上がりです。笑
というわけで、自己紹介と同様、商品やサービスといったブランドの価値を伝えるときについても、こんな知覚品質一辺倒な紹介で済ませていないでしょうか。
特に健康や医療、美容といったヘルスケアの商材の場合、その機能的価値である「知覚品質」を構成するものには、
1. 有効性
2. 安全性
3. 簡便性
4. 経済性
等があげられます。
もう一方の情緒的価値「感覚品質」を構成するものは、どの商材にも共通して、
1. 共感性
2. 安心感
3. 事前期待値
4. 事後満足度等
があります。
すでにお気づきかもしれませんが、世の中にあるヘルスケア商材の「価値」を伝えようとするとき、おおよそ機能的価値だけで差別化を図ろうとしていることが多いんです。
つまり、あの恥ずかしい自己紹介と全く変わらないことをしているということです。
たとえば、
「○○の有効性については、ウチの会社の商品Aの方があの会社の商品Bに比べて1.5%高いという結果が得られています。すごいでしょ!」
とか、
「経済性について、ウチの商品Aをご利用いただいた場合、あの会社の商品Cに比べて年間500円お安くなります。お得でしょ!」とか。
でも、これだけではなかなかユーザーは動いてくれないんですよね。
価値を伝えるもう一つの要素には、ユーザーのニーズから発想した「情緒的価値」があって、実はこれを抑えておかないとなかなかアクションには至らないのです。
ブランドの価値が伝わる?
ここで大切になってくるのが『ブランディング』です。
ブランドにINGがついたブランディングとは、商材価値が伝わるようにするための手法です。
ブランドの機能的価値「知覚品質」と情緒的価値「感覚品質」をもって、物語をつくる作業になります。
ユーザーにとって私たちが提供する医療サービス(特に自費治療)や、ヘルスケアの商材を「あ~、いいもんだなぁ」と享受するにあたっては、商材の機能的価値だけでなく、この商材をもって「(病気といった)損失を回避したい」のか、「(健康といった)利得に接近したい」のか、ユーザーのそのどちらかのニーズ、もしくは両方のニーズに明確に応えてあげる『情緒的価値』を示してあげることが大切になってきます。
たとえば、損失を回避したい人には、あなたのその強い義務感に応える機能がこの商品にはあります、利得に接近したい人なら、その強い理想像に応える機能がこの商品にはあります、といった具合に。
ブランディングの決め手は、機能に情緒をプラスして!です。
ライザップとか、見事にユーザーをキャッチしたブランディングですよね。
イシューイングとは
イシューイングとは、意中の相手にその価値を気づかせるためのいわゆる“根回し”のことを言います。
イシュー(ISSUE)を直訳すると「課題」「話題」となりますが、つまり、イシューイング(ISSUE+ing)は、根回しのための「課題」づくり、「話題」づくりを意味します。
私たち医療業界やヘルケアの業界では、このイシューイングがとても大事な作業になります。
健康について、私たちは価値あるものとちゃんと認識しています。
でも、一つひとつの健康行動に対して、『誰のために?何のために?なぜ?』といった健康行動を目的化することは、結構、難しいんですよね。
巷にあふれる健康課題は、ほとんどは他人ゴトです。
それをそのまま自分ゴトとして解釈できる人はまずいません。
そこで、他人ゴトと自分ゴトの間に、「世の中ゴト」をつくるためのアプローチが必要になってくるんです。
たとえば、ヘルスケアビジネスないしヘルスプロモーション史上、最もイシューイングに成功した例が、「メタボ」ではないでしょうか。
世の中に多く存在する「中年太り」の人に健康課題を気づかせ、健康行動に導きました。
中年太り=健康課題という世の中ゴトをつくるために、「メタボ(メタボリックシンドローム)」というキャッチーなワードと付随するPRキャンペーンをメディアで実施していったのですが、コレこそが、ユーザーに「あなたは生活習慣病予備軍である」ということを認知させるための“根回し”なのです。
その根回しをしておいてから後に、「わが社の商品、買ってください!」と、食品会社が広告プロモーションをしていく、という流れです。
健康課題を社会的価値として伝える
軍用ステルス機はレーダーにも映らないことから、それを文字って「ステマ」と称したステルスマーケティングがいつしか話題になりました。
企業関係者がスパイのように暗躍しながら、自社の商品やサービスを褒めたり称えたりして紹介します。
その後、「ネイティブ広告」という、記事なのか広告なのかわからないような記事体広告が話題になりました。
影響力を持つ人がいかにも記事で語っているかのように、商品やサービスを評価します。
あまりに頻繁に出回ってしまったので、いまでは、その片隅に「広告」と表示することが業界ルールになりました。
ステマが「評判」をつくり、ネイティブ広告が「評価」をつくるという目的の違いこそあれ、どちらもイシューイングというアプローチの一つですよね。
大事なのは、イシューイングが堂々とできるかできないかです。
商業活動の前に、社会活動としてイシューイングを位置づけることで、健康課題を社会的価値として伝えることができます。
このように、健康課題を社会的価値としてきちんと伝えることが、医療業界やヘルスケアビジネスには求められるわけです。
商品やサービスを突然提案して、誘惑して、その人が幸せになれるかと言ったら、そうではないんですよね。
その人の持つ健康課題を「課題」として認識してもらうことではじめて、商品やサービスの価値が伝わります!
何事も“根回し”って大切ですね、といったお話でした〜!
今日も頑張ってまいりましょう〜!
