
薬膳の色と味で必要な食材が分かる人が次に知っておくこと
今日は、令和四年三期の「きちんとわかる薬膳の基礎(全五回)」の3回目。五臓一つ一つの働きとそのシステムが弱った時に起こりやすい不調の前半でした。
#きちんとわかる薬膳の基礎(全五回)の三回目終了。
— モーリー薬膳ラボ代表|森澤孝美@簡単エイジングケア薬膳講師 (@yakuzen__molly) November 10, 2022
五臓の働きと弱った時に出る症状、おすすめの食材の選び方食材事典の見方まで。
体系立てられている中医学。覚えることがたくさんと感じますが、繋がっているので徐々にわかるようになります。来週のツアーでリアルにお会いできるのが楽しみ。 pic.twitter.com/Y9R3OwY7OM
私が薬膳に興味を持ち勉強し始めた頃は、こんなにネットで情報を調べることができなくて、本を買って読んでいました。
今はSNSでも有益な情報が見つかりますし、便利になった反面、同じような情報ばかりの事もあります。
それは、食材の効能についての記事。
秋になったら白いものと辛味の物を選びましょうとか寒くなったら体を温める性質の食材を食べましょうというようなものです。
今日の講座では、例えば秋に弱りやすい「肺」のシステムに良い色の白い食材、味で言えば辛味の食材以外にもあることをお伝えしました。
食材は講座+食材事典で身につける
食材は、数えきれないほどの種類がありますよね。
お茶や調味料を入れたら、それを一つ一つ講座でやっていたら時間がいくらあっても足りません。
そのため、主なものをお伝えした後は食材事典の使い方も学んでいただきご自身で調べていくらでも使える食材のバリエーションを増やしていただけるようにしています。
その一つが「帰経」です。
帰経とは何?
帰経とは、どの経絡に作用するかというもの。
経絡はツボとツボを結ぶ見えない線です。
五臓のそれぞれが経絡とも関係するので、白くなくても帰経が「肺」なら、その食材は「肺」に良いという食材のグループに入っています。
一例ですが、水菜は緑の葉野菜なので、「肝」のシステムに良さそうですが、帰経が「肺」です。

そのため、「肺」のシステムにおすすめの食材として紹介されていることもあります。
色と味で必要な食材が分かるようになった人が次に知っておくと良いこと
色や味で、今の自分に何が必要なのかが分かるようになった人が、食材を選ぶ時に次に知っておくと良いことは、帰経です。
色や味が自分の知っているものではなくて、本やテキストのおすすめ食材グループに入っていたら、帰経がその五臓の帰経なのかを食材事典で確かめてみてくださいね。
薬膳を始めたばかりの時は、とにかく手元に食材事典がいつでも見られるようにして、スーパーでも見る、キッチンでも見るようにして効能や性質を覚えてください。
食材を使いながら覚えた方が単なる暗記より身に付きます。
私も、一番最初に買った食材事典はキッチンでよく見ていたので、濡れてよれよれのページがあります(笑)
食材は沢山あるので、講座で学んでいるのは時間がもったいないので、自分でも食材事典で調べて行く習慣をつけましょう。
【関連記事】
食べたいものをストイックに我慢するのではなく「なかったことにする薬膳」のメソッドでプラマイゼロにする方法を無料で学べる7日間のメール講座です。お申込みはこちら▼

簡単な質問に答えると、中医学で起こりやすい不調が分かる無料診断です。
下のバナーをクリックしてお答えください。▼
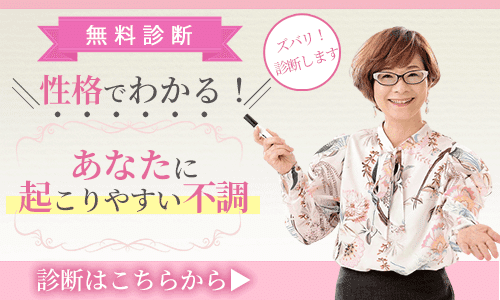
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
