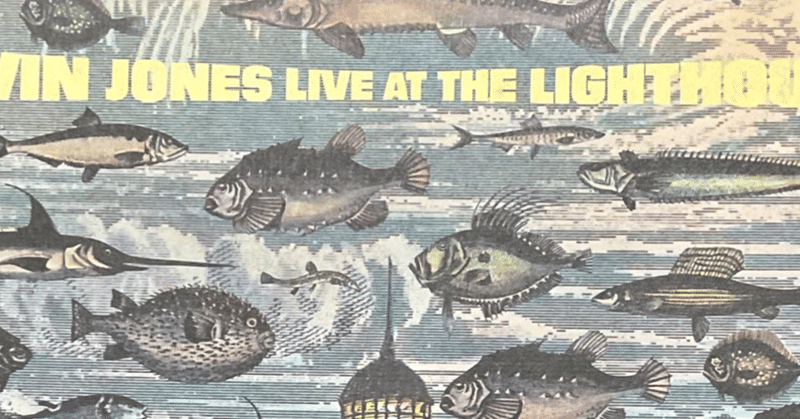
Steve Grossman研究-70-80年代のスタイル変遷を検証する― その5 フュージョンへの最接近、不適応、そして行方不明(笑) 79年~81年
79年からの数年間、グロスマンの活動は単発的になる。多分New Yorkにはいたのだろうが、特にパーマネントなグループに加入してはいなかったようだ。 マイルスとかエルビンとか大物とやっていたわけでもなく、あんなに仲良しだったStone Alliance一派とも袂を分かってしまった(同グループの80年のアルバムではグロスマンは外れてボブミンツァーが入ったりしている)。というわけ で、活動のトレースは結構難しいのだが、たまたま持っている何枚かのアルバムを元に当時の状況を検証してみる。
時代の産物"Perspective"
さて、欧州ではアコースティック回帰の動きを見せていたグロスマンであるが、本国米国ではNYフュージョンムーブメントに翻弄されている(って当人翻弄されたつもりはないと思うが)。
それが典型的に表れたのが、1979年発表のリーダーアルバム、”Perspective” といえるだろう。本作は、メジャーレーベルであるアト ランティックからリリースされているが、誰がこんな作品を企画したんだろうか(笑)。まさに時代の産物と言えるなあ。ビニール盤のジャケットには録音日付 は記載されておらず、1979年リリースとだけわかる。まあ、録音も1979年と考えておいて大まかに間違いはないだろう。


このアルバムがどれだけフュージョンに振れているかは参加ミュージシャンを見るとわかるので、面白いからそのまま書いてみる。
Steve Grossman: Soprano and Tenor Saxophone
Bugzy Feiton : Guitar
Barry Finnerty: Guitar
Onaje Allan Gumbs: Keyoboards
Masabumi Kikuchi: Piano
Mark Egan: Bass
Marcus Miller: Bass
Steve Jordan: Drums
Victor Lewis: Drums
Lenny White: Drums
Sammy Figueroa: Congas
Rapchael Cruz: Percussion
マーカスにスティーブジョーダンだぜ。これって”TOCHIKA”と同じだな。ギターもバズフェイトンとバリーフィナティだもん。NYフュージョン最前線(笑)。
で、このメンバーでやる曲はCreepin’(これはスティービーワンダーの曲だがStone Allianceでもカバーしてた)とか、グロスマンオリジナルのKing Tut、KatonahなどStone Allianceやグロスマンリーダーでおなじみの曲。もう少し工夫すればいいのに(笑)。といいつつ、異色なのはやはりA面4曲目のThe Crunchiesという曲だろうか。異常にさわやかなフュージョンでソプラノ吹いてる。ナベサダのモーニングアイランドとかに入っていてもおかしくないぞ。おそらく現存する音源の中でもっとも非グロスマン的なテイクだといっても過言ではあるまい。菊地雅章はPastel2という幻想的な曲を提供し、自ら ピアノを弾いている。
グロスマンのプレイは、曲も曲だし、まあ、変わらずグロスマンだ(The Crunchiesを除く)。フュージョンサウンドをバックにここまで我の強い音+フレーズというのもまた珍しく、グロスマンらしいといえよう。この人、 この手のサウンドでもあんまりブルーノート使わないんだよね(全然使わないわけじゃないけど)。基本はグロスマンフレーズ。
まあ、時代のアダ花感プンプンの迷盤、珍盤の類ではあるが、グロスマンの変遷を知るために、フリークにとっては欠かせないアルバムだと言えよう。
この時期の重要アルバム
その他の活動として欠かせないのは、実はNYの日本人絡みのアルバムだ。
中村照夫: At Carnegie Hall
まず、前の日記にも出てきた中村照夫のパーマネントバンドであるRising Sun Bandのカーネギーホール公演(1979/6/15)への参加。これが”At Carnegie Hall”というライブアルバムになっている。一応グロスマンはレギュラーメンバーの様なのだが、ゲストとしてランディブレッカーとまだNYシーンにデ ビューしたばっかりのボブミンツァーが入っている。
カメレオンみたいなファンキーな曲とか、サンバと4ビートが交互に出てくるノットエチオピアみたいな曲とか、結構バラエティに富んだ選 曲。まあ、典型的なこの頃のジャズ/フュージョンですね。このレコード25年ぶりぐらいに聞いたのだが、当時の印象通りグロスマンの調子はいま一つかな。 わかりやすいグロスマンフレーズのオンパレードではあるのだが、なんか本調子ではない感じ。実は隣のボブミンツァーが素晴らしくて、負けているかもしれな い(笑)。
菊地雅章:Susto, One Way Traveler
次は、ちょっと時間が空くが、1980/11に録音された菊地雅章の”Susto”と”One Way Traveler”という2枚のアルバム。当時の菊池雅章は、当時活動停止中のマイルスをリアルタイムで模倣するような混沌とした音楽をやっており、どれもこれも怪しげなビートの上に怪しげなコードがそのうえでソリストがピーヒャラ吹くといった内容。残念ながら菊地雅章にはマイルスマジックはないので、ほとんどの部分が退屈だなあ、私には。そういえば、その後水戸で菊地雅章のバンド(なんとかブギーバン ド)見たけど何がなんだかさっぱりわからなかった(その模様がライブ盤になって評論家から激賞されて相当驚いたりしたものだ)。
話はそれたが、まあ、要はそういう雰囲気のアルバムなので、グロスマンもマイルスバンド当時の役割を期待されている感じで、なんとなく出てきて ピーヒャラ吹いて、という感じである。ただし、Sustoの"Gumbo"という、若干レゲエ風味でコード進行のある曲は、テナーを吹いてなかなかいいソロだ。この曲、当時ブリジストンのコマーシャルかなんかでテレビで流れてたよなあ、確か。 今になってみ ると、こんな曲でCM作るなんてなかなかの度胸だと思うが、まあそういう時代だったんだろう。
One way Travelerの日本盤解説を見ていたら菊地雅章のコメントがあって興味深いので引用してみる。曰く、
スティーブグロスマンは、世界中のテナーの中で 一番才能があると思う。前からコルトレーンの様に吹くのをやめろと言っているが、ちらっと凄いものが出てきても、コルトレーン・コンセプションに逃げ込ん でしまうあたりがやや不安だった
これはどういう意味なのだろうか。私の様な凡人に天才、菊地雅章の考えていることを推し量ることは不可能ではあ るのだが、その後のグロスマンの活動を考えると興味深い(おそらく菊地雅章の考えた方向とは真逆に行ってしまったというのが正解なんだろうが)。
Gil Evans Orchestra: Lunar Eclipse
最後に、この時期のグロスマンの音源としては最上級の一枚。1981年の7月にヨーロッパで録音されたGil Evans OrchestraのLunar Eclipseというライブアルバムだ。というわけで、81年の夏にはギルエバンスのバンドで欧州ツアーをしていたことがわかる。
81年というのはマイルスが数年にわたる引退生活から復活した年であり、ジャズ界は変に沸き立っていた。確か7月に行われたニューヨークで行われ たクールジャズフェスティバルで奇跡の復活を遂げたわけだが、そのフェスティバルにギルエバンスオーケストラも出ていたはずで、そこでは確かビルエバンス (ts)が入っていた(スイングジャーナルかなんかの記事で写真を見た)。おそらくその直後に行われた欧州ツアーでの録音が本作というわけだ。
グロスマンのソロが出てくるのは2曲目”Variation on the Misery” だけなのだが、これは本当に強烈。そもそも怪しげなアンサンブルで始まる怪しげな暗い曲なのであるが、グロスマンがソロを一音吹くと、音量がぐっと上がっ て、部屋の温度が嫌な感じで下がる(笑)。「荒野の素浪人」というか「ユダヤ系ゴルゴ13」というか、「薄暗く光る出刃包丁」というか、一匹狼のさすらい テナーマンの凄さをひたすら感じさせる音、フレーズ、構成のソロが聴ける。WRに入る前の若きオマーハキムとハイラムブロックがバックで大暴れているのも 含め、正に名演。盛り上がる割にものすごく暗いけど。
結論:「ハイブリッドテナー」のフュージョン不適応
と、とりあえず私が持っている範囲でこの時期の参加作を何作か取り上げてみた。
今回の結論だが、こうやって並べて聴いてみると、稀代の「ハイブリッドテナー」のフュージョン不適応が明らかになったといえるのではないだろうか (最後のGil Evansのような例外もあるが)。そもそもプレイがガサツというか、不器用な感じで精緻なバックのサウンドとはマッチしないし、短いコーラスでメリハリ の利いたソロ、とかもなかなかできない。かといって菊地雅章や引退前のマイルスの様な混沌としたビートの一発モノではワンパターンに陥ってしまってなかな かカラーが出せない。ジャムセッションではブレッカーだろうがボブバーグだろうが、あるいはジョージアダムスだろうがビリーハーパーだろうが軽く蹴散らし ていたはずのグロスマンだが、この路線には自ら疑問を感じていたとしてもおかしくはないだろう。
というわけで、81-84年あたり、グロスマンは表舞台から姿を消す。といってもNYでの活動は続けていたんだろうが、それは次回に書く。この時 期、私は大学生で、遅ればせながらグロスマンフリークとなって音源をあさっていたのだが、リアルな活動がまったく聞こえてこないため(一方悪いうわさも聞 こえていた)、ああ、この人は既に幻の存在で、実際にそのプレイを聴くことはできないのだろうなあと諦めていた覚えがある。
さて、当時、極端に情報が少ない中で妙に印象に残るエピソードがあるので紹介して今回を終えよう。確かスイングジャーナルか何かの記事だと思うの だが、81年の復活マイルスバンドに抜擢されたビルエバンスのインタビューの発言から。うろ覚えだが、こんな感じだったと思う。
「デイブ(リーブマ ン)に師事した僕は、一時期、本当にデイブそのままのスタイルになってしまっていた。でもあるときスティーブ(グロスマン)から『もっとロリンズを聴け』 といわれて他のプレイヤーも聴くようになり、プレイの幅を広げることができたんだ」。
1982年ぐらいのSwing Journal に載ったBill Evans (sax)のコメント
当時は「へ~」くらいしか思わなかった記事だが、今になって考えると、当時(81年ごろ)のグロスマンがテナーの新星にこのようなアドバイスをしていたというのは極めて暗示的といえる。
というわけで、次回はバッパーとしてシーンに復活してくる時期を検証してみる。最終回のつもり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
