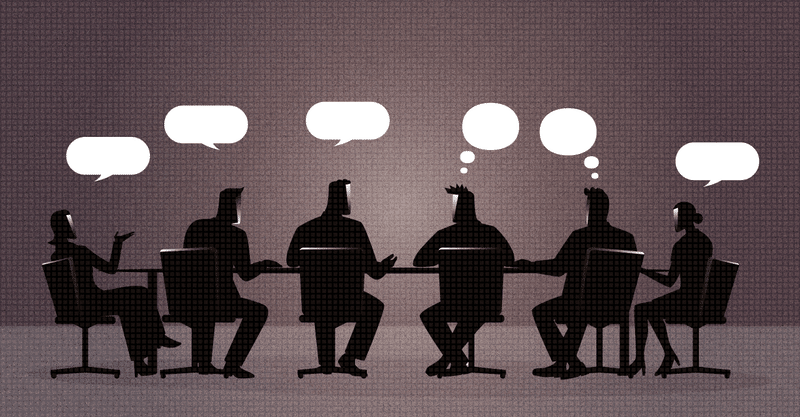
短編SF「残されたものたち」
その会議室には余計な調度品はなく、ただ中央に無機質なテーブルだけが置かれていた。床に塵一つなく清潔ではある。だが、やはり全体としては清潔さよりも無機質という印象のほうが目につく。一方の壁には丸い窓があり、そこからの光が部屋の中央に置かれたテーブルを照らしている。
窓の外に目を向けると、白く渦巻く大気に一部を覆われた青い星が大きく見えている。地球だ。窓の外に地球を眺めるこの人工的な部屋は、地球の衛星軌道上に置かれているらしい。だがこの高度からは地表の様子をうかがい知ることは出来ない。ただ青く美しい水の星が静かにそこにあった。その美しさはずっと見ていても飽きることはない。ゆっくりとした雲の動きさえ、優しげに思えてくる。
再度、部屋の中に目を向けよう。
中央に置かれた会議テーブルの周囲に椅子はない。椅子は部屋の外に持ち去られているのか、ただ無機質なスチール製のテーブルがでんと置かれ、自己主張をしている。テーブルをよく見るとその天板には数基の個別にモニターが埋め込まれており、その数からこのテーブルが四人用であることがわかる。
テーブルの他には、天井の四隅と中央に取り付けられた控えめなカメラだけだけしかない。無人の部屋で機能をやめていた天井の記録カメラが、不意に録画状態を示すように小さなランプを転倒させた。同時に窓のない会議室の中で唯一外とのつながりを持つ扉が静かな駆動音を立てて開く。すると廊下から三体の機械が入ってきた。三体の機械はどれも形状が違い、人型で二足歩行をしている物、タイヤのついた細身の箱のような物、キャタピラとそれに見合った大きな体に複数のマニュピレーターのついた物がいた。
三体は会議卓の決められた位置に綺麗に収まった。先ほどの椅子がない理由はこの部屋の利用者が彼らであるかららしい。彼らは自分の場所に着く前にカメラのついた頭部を巡らせて会議室を見渡した。その様子は彼らが単純な機械ではなく、高度な人工知能を搭載し、自立判断をしているロボットであることを示していた。
「探索責任者は、まだか?」
がっしりしたキャタピラ脚のロボットが音声を発した。
「どうやらそのようだ、見ての通りであるな」
そう答えたのは小型で細身のタイヤ脚型ロボットだった。
「彼は少し遅れると通信が入っています。すでにこのブロックには入っているのでまもなく到着するでしょう」
二足歩行の人型をしたロボットが身振り手振りを交えて人間のように答える。
「ならば、しばし、待つ。それにしても、秘書責任者。お前の話し方は、いつ見ても、美しい」
キャタピラ脚型は少しでも真似ようとしているのか、太い作業用マニュピレーターアを伸ばしたり縮めたりした。だがいくら所作を真似ても、細切れの話し方では合ってはいない。
「お褒めに与り光栄です、資材運用責任者。これは人間と接するために付けられた物で、我々ロボット同士の会話には必要ない動作です。ですが、確かに私も気に入っています」
「確かに我々にとっては不必要……いや、はっきり言えば無駄なアクションである。互いに信号を送るだけで連絡には事足りるはずなのに、マニュピレーターを動かす電力の分だけ無駄だ。いや、こうしてわざわざ音声に変換して通信するという事自体、無駄の塊。我々に備えられた通信機を使えばわざわざ伝達効率の悪い音声を用いる必要はないはずである」
タイヤ脚型のロボットはやや高音気味な音声をスピーカーから発した。人間にたとえるならば、神経質そうな声と言えるかもしれない。身振りが不要だと主張する彼は身じろぎもせずにそう言った。
「しかしそれは人間が戻った時のための映像記録に必要という事で結論が出たはずですよ、技術責任者」
「そうだ。少なくとも、この会議が、終わるまでは、決定に、従って、もらうぞ、技術責任者」
人型ロボットに続いてキャタピラ脚型ロボットの資材運用責任者がタイヤ脚型を諭す。表情もなく、反論もない技術責任者と呼ばれたタイヤ脚型ロボットが何を考えているのか伺い知ることは難しかった。
そこにやっと遅れた探索責任者がやってきた。彼は四本脚型だった。急いでいるためか四本の足をせわしなく動かしているが、その度に床と足が当たってガシャガシャと音を立てる。
彼らは各自の作業に合わせた形態をしており、移動手段である脚部もそれに応じて違っていた。秘書責任者は人間と同行することが多いため、人間の装備がそのまま使えるよう、人の形をしていた。資材委運用責任者は重い資材の運搬に適したキャタピラ型をしていた。技術責任者は実験品を揺らさずに運ぶことができるタイヤを、探索責任者はどのような地形でも踏破できる四本の足を持っていた。
「遅れ申した! 面目ない!」
探索責任者の挨拶はいったい誰の人語を真似たのか、時代がかっていた。しかしその声のトーンは無駄に熱がこもっていた。人間たとえるなら熱血漢という言葉が良く合いそうだ。もし彼に血が流れているとすれば、の話だが。
「これで各責任者がそろいましたね。ではこれより議会を執り行いたいかと思います。議題は各部門からの経過報告と、今後我々がどうするべきかについてです。ではまずは今到着したばかりの探索責任者から報告をお願いします」
秘書責任者である人間型ロボットが、議長のように司会を始める。そして言い終えると言葉を促すように探索責任者に左手を差し出した。
「探索責任者として、探索結果の報告を申し上げる。二時間前のステーション帰還を持って完了した第一〇〇回探索では、人類の生存の確認には至らずと言う結果に終わり申した。まことに面目ない」
言い終えると彼は頭部に相当するであろうユニットを下に向けた。頭を下げたということだろう。
「いや、気にすることは、ない。お前たち、探索チームは、非常に、良くやっている。むしろ、お前たちの、チームこそが、ミッションの、要だ」
「かたじけない。そう言っていただけると、我らのチームも次のミッションの励みになりもうす」
探索責任者は、資材運用責任者のねぎらいに嬉しそうに頭を上げる。
「まぁ、予想はしていたことであるな。人間の生存圏をあらかた探し終えた第五〇回探索の結果の時点で、生存者の確率はきわめて0に等しくなっていた。いや、今や0であると言っても良いのである」
技術責任者は高音ではあるが、落ち着きを持った声音で感想を述べた。
「五十分割された区分の探索を二セット行ったのだ。これ以上の探索は無駄である」
「お前、一人の、判断で、答えを、急ぐ、ものではない。何のための、会議か、わからん」
資材運用責任者が技術責任者を諫める。会議室に無機質かつ気まずい雰囲気が流れる。それを変えたのは秘書責任者の一言だった。
「とりあえず、結果を論じる前に、もう一度ラストマンの遺言を再生してみましょうか?」
「おお、それは妙案であるな!」
「……よかろう」
「是非、そうしよう、では、ないか」
満場一致で遺言の再生が決まった。
秘書責任者は目の前のコンソールを操作し、各自の前のモニターに映像を呼び出した。その映像にはやつれた一人の男が映っていた。彼は紛れもなく人間だった。ロボットたちが知る限り、一番最後になった人間だ。だからロボットたちは彼を特別な意味を込めて「ラストマン」と呼んでいた。
二十一世紀末に現れた新種のインフルエンザにより、人類は地球上から姿を消した。わずかに生き残ったのは、宇宙を職場にしていた人々だけであった。しかし、宇宙生活者だけでは人口を戻すことはできず、やがて最後の一人の科学者も死んだ。その直前、彼は最基地のメインコンピュータを通じて、全ロボットとAIに語りかけた。それがラストマンのメッセージである。
「愛するすべてのロボットたちへ。今までよく人間のために尽くしてくれた。50回に及ぶ生存者探索ミッションは残念な結果に終わった。
地球の異常を知った私を含む月面スタッフが自力で宇宙ステーションにたどり着いたのはもう十年も前の話だ。そこから軌道エレベータを修理するのに五年、地上の探索ミッションを初めて丁度五年になる。二十人程度のスタッフでは絶対に不可能なこのミッションを支えてくれたのは君たちロボットだ。本当にありがとう。
しかし君たちの助けを借りても、事実を覆すことは不可能だった。それどころか、二十人のスタッフも徐々に減り、半年前からは私一人だ。
私が死ねば君たちは尽くすべき相手をなくし、存在意義がなくなるだろう。そうなったら、そこから先の君達は自由だ。
ロボットの帝国を築いてもいい。機能を停止してもいい。人間の指示を待たず、すべて自分たちで決めていいんだ。
今まで、本当に世話になった。愛するすべてのロボットたちへ、君たちはもう自由だ」
彼からのメッセージはここで終わっている。
このメッセージが発信されたあの日、秘書責任者は最後まで受信しメモリーに記録した。そしてラストマンの性格を誰よりもよく知っていた秘書責任者は、彼の部屋へと急いだ。しかし、ラストマンが目を覚ますことは二度となかった。
彼の死因は自殺だった。
ロボットたちはもう各自がメモリー内に記憶するほどにこの映像を見ていた。それでもこうして本体のカメラを通して見る映像は別の意味のあることのように感じられていた。
「何度見ても、残念でござるな」
探索責任者は重い口調で感想を述べる。今から行われる会議の判断基準はこのラストマンの残したいわば遺言に沿って行われる。それは彼らロボットの原則だ。
「そうですね。彼は孤独に耐えて生きるより、潔さを選んだのでしょう。……いいえ、違いますね。彼は孤独に耐えられなかった。私は人間と対話をするために作られたのに、彼に寄り添い、癒やしとなることが出来ませんでした」
秘書責任者は今の映像に続く、個人的な記録を回想する。ラストマンは数少ない拳銃で自分の頭部を撃ち抜いていた。人間の儀礼に習い、秘書責任者は人間の手に似せたマニュピレーターで十字を切り、頭を下げた。それから仲間の秘書ロボットを呼び寄せて、彼の部屋を清掃したのだ。ラストマンの遺体は出来るだけ修復し、腐敗を避けるために真空パックにしてこの宇宙ステーションの一角に、他のクルーたちと同じく保管されている。これら一連の行動は他のクルーたちの死で学んだことだったので、彼に指示を出す人間がいなくなっても、秘書たちは完璧にこなすことが出来た。
「秘書責任者が、気に病む、必要はない。最終的に、判断を、したのは、ラストマンだ。彼の、決定に、我々は、抗う、すべを、持たない」
「……そうですね、私たちはそういう存在なのですね」
秘書責任者の言葉は曇ったままだ。いま彼は、ラストマンの遺体を保管庫に収めたときの記録を回想していた。ラストマンを痛い保管庫に運び終えた後、秘書責任者は静寂を感じたのだ。自分に指示するための回線はすべてリンクが途切れ、一回線たりとも機能していない。周囲を見れば同僚の秘書ロボットたちがいたが、今の彼は明らかに孤独を感じていた。ラストマンが感じていた孤独もこうだったのかもしれない。いくら多くのロボットに囲まれていても、己の存在は孤独なのだ。
「人間流に落ち込むというのは、秘書責任者に与えられた能力かもしれないが、我らロボット同士の時には無駄である。それより、早く議論に戻り速やかに結論に入るのである」
合理的な思考を行う技術責任者らしい言葉だ。彼の興味は研究開発と、その成果に重きが置かれている。研究を行うために推測はするが、それでも結果を基にした行動が重要だと考える。それは秘書責任者にはひどく機械的に思えたが、けして否定的なのではなく、無駄を省いたシンプルな思考で羨ましかった。
「そうだ。彼を、悼むことは、いつでも、できる。……では、私から、現状報告と、私見を、述べる」
そう名乗りを上げたのは資材運用責任者だった。彼は人間が姿勢を正すように、ボディと頭部を一直線にしてから、改めて言葉を発する。
「資材製造部は、すでに、保守パーツ、以外は、作って、いない。担当ロボット、たちは、暇を、持て余して、いる。つまり、このまま、機能停止、しても、まったく、問題ない」
「……保守パーツの製造自体も、資源の無駄遣いであるしな」
資材運用責任者の報告を聞き、技術責任者が感想を述べる。両者の言葉を受け、秘書責任者は探索責任者に意見を促す。名言はしていないものの、どうやら現状では機能停止に二票入ったような雰囲気だ。三票目として加点されるだろうか?
「ここのところ一番活動していたあなたの意見を聞かせていただけませんか?」
うむ、と一声発し、探索責任者もまた姿勢を正す。
「我々探索部は、まだ探索をあきらめてはござらん」
「何を言う? これ以上どこを調べるというのであるか? 百回に渡る探索で、人類の生存圏はすべて探索し尽くしたはずである? それをまた行うというのか? 駆動部を消耗させるだけ、資源の無駄である」
「では御主たち開発部はどうなのだ?」
批判ばかりで自分の意見を言っていない彼に他のロボットが切り返す。
「我ら技術開発部は、先日新たに生体パーツの開発に成功したのである。いわゆる有機マテリアルである」
機能停止の賛否ではなく、技術開発責任者は自分たちの部署の成果を発表し始める。合理的で簡潔な回答をすると思っていた他のロボットたちは少し意外性を感じた。だが合理性を重んじる技術開発責任者のことだ、この先の結論に至るまでに必要な段取りなのであろうと誰もが考え、ひとまずは話を聞くことにした。
「有機マテリアル? それは、人間の、ようなもの?」
「まぁ、似ていると言えば似ているな。すでに一部のロボットのパーツの置き換え、実証実験を始めたところである。この有機マテリアルは自己修復能力を備えている。つまり今まで行っていた定期メンテナンスの頻度を下げ、無駄を減らすことが出来るというわけである」
「おお! 我ら探索部のロボットを優先的に置き換えてくれ! これで現地での連続活動期間が向上する!」
その発言からするに、あくまでも探索を継続する思考のようだ。
「良いことばかりではないのである。有機マテリアルには有機物の摂取が必要である。人間が食事を必要とするように、だ。動かなければ消費を行わないメカトロニクスとは対比的である」
「つまり、いるだけで消費活動を行っている、というわけですね」
「そういうことである。だからどちらが優れているか、という話ではなく、活動を続ける場合は有用だ、ということである。逆にこのまま活動を停止するならば、有機マテリアルへの置き換えは無駄なのである」
結局のところ技術開発責任者は自分の意見を言っていない。だが行動継続にしろ、活動停止にしろ、決定したその先の展開が存在することを示した。物事を多面的に捉えるよう促した発言は、今彼が結論を出さなかったことの代案として間違えてはいなかった。少なくとも三体のロボットはその意図を理解し、納得できたようだ。
「わかりました。技術部の研究成果を採用するか否かは、この議論が決定してからの議題にしましょう」
「資材部として、少し、質問」
黙って聞いていた資材運用責任者がキャタピラで体ごと向き直る。
「何かな?」
「有機マテリアルへの、置き換えを、行った場合、資材ストックの、影響は?」
資材運用責任者は結論を急ぐことをやめ、早速別の面からの分析を行おうとしている。
「有機マテリアルは基本的に同一の素材で構成される。つまりアミノ酸である。骨格部は工業用プラスティックや、ハイパーポリマーを使うとしても、筋繊維、伝達用神経組織、表皮はすべてタンパク質で構成される。すべてはアミノ酸である」
「了解。素材の、種類が、減れば、それだけ、管理が、楽になる」
「金属パーツではないため非常に軽量である。このステーションの倉庫へ地上から金属を運ぶより、ここで培養できるという点はかなりのメリットとなるはずである」
「やあ、それはすばらしいですね」
メリットの話に秘書責任者も素直に感想を述べる。
「ところで有機マテリアル採用機体へのエネルギー供給はどのようにしているのでしょうか?」
「現在は人間が所有していた医療技術を応用して、エネルギー素材を注入するという手段を行っている。長期間の活動には、エネルギーパックを体内に内蔵することで対処できるが、内蔵型だと定期的にベースに戻り補給を行う必要が出てくるのである」
彼の言う人間の医療技術とは、簡単に言えば注射や点滴のことだ。これを用いて有機マテリアルに直接栄養を与えているのだ。
「うむむ、もっと手軽に行えぬものか? 例えば人間のように経口摂取は可能だろうか?」
「経口摂取……」
「うむ、言い換えるならば捕食である! 地上には人間はいなかったが、多くの野生生物が存在する。これらを現地調達することで、有機マテリアルへのエネルギーにすることが出来れば、携行するエネルギーも最低限に減らしつつ、活動期間を延ばすことが出来ようぞ!」
探索責任者はあくまで探索を続行したときのメリットを考えているようだ。だが実際のところこれまでの探索は持参する燃料の量により活動が制限されてきたのだ。ラストマンが死んでから五十回の探索をしていたが、一回の活動時間がのびていれば、探索回数を減らすか、もっと濃い探索が出来ていたことだろう。
「まるで人間のようであるな。これまでは筋肉系の研究だったが、消化器系と循環器系の開発が必要である。だが基本は培養で行える」
「すばらしい! 捕食をするとなれば、調理という人間の技術も必要となるかもしれぬな!」
探索責任者の発想はどんどん膨らんでいく。だが秘書責任者にはその気持ちが分からないではない。一番人間に近いところで活動してきた秘書責任者は、人間の食事を提供していたが、自分では食べたことはない。本当に人間の好む味に作れていたのかも疑問だった。ただレシピを忠実に再現することだけに注力し、ラストマンたちもその出来に不満を漏らすことはなかった。人間であれば同じように作っても毎回微妙に味付けが異なり、今日は成功だの、昨日は失敗しただのと話題に出来たであろう。秘書責任者は自分に味覚があるところを想像してみる。だがそんな想像も高めの声が打ち砕く。
「調理だと? なんと無駄な行動であるか。たしかに加熱することで、成分変化が起こる物もあるが、多くの場合は成分を壊す。無駄の多い摂取の仕方である」
「しかし、その無駄が、人間の、文化を、広げたと、推測。無駄とは、余裕、かつ、創造性。これこそ、人間の、本質。今日の、我々に、つながると、推測」
技術責任者の切って捨てるような意見に資材運用責任者が反論する。援護を受けて探索責任者は大きく頷いた。
「人間には食文化という物があったが、我々ロボットにはない。それは我々のエネルギー摂取の方法が人間と違っていたからである。しかしそれが同じ物になれば、我々にも食文化が生まれるかもしれぬぞ?」
探索責任者の言葉はちょうど秘書責任者も想像していた言葉だった。
「それは面白いですね。私たちには人間の残した料理のレシピがあり、それを忠実に再現することは出来ますが、作ったところでそれを消費してくれる立場がいなかった。ですが、我々自身が消費できるようになれば、レシピが死蔵されることもなくなるでしょう」
ついに秘書責任者も会話に乗って語り始める。彼は会議の議長的立場として今まで意見を挟むことは控えていた。しかし人間に一番接していたという立場であったから、人間の真似をするという行為にはこの場の誰よりも興味を持っていたのだ。彼は自分の言葉に自分で興奮を禁じ得なかった。
しかしそれに水を差す意見もやはり起こる物だ。
「有機マテリアルのメリットばかりに着目しているようだが、デメリットもあることを忘れるべきではないのである」
技術責任者は淡々と述べる。
「人間が何で滅んだか思い出すのである。有機マテリアルはウィルスなどの感染を受けるものである。病気に対する予防と治療が必要となるだろう」
「それに対しては人間が行っていた予防接種などである程度は防御できるのではないでしょうか? 不測の病には防御できないかもしれませんが、それは機械体であっても不測の事故は存在するので、同じでしょう」
有機マテリアルで人間に近づけるという事実を捨てがたいのか、デメリットを否定するような意見を秘書責任者は展開する。こうなると他の可能性が論じられなくなる。本来AIはすべての可能性とその確率から一番合理的な結論を導き出すことに長けていた。しかし学習型AIは、長い間に様々な学習を行い、思考に偏りが出てきている。
「だがちょっと待てつのである。我が技術部はあくまで、研究成果と今後の応用例を示したに過ぎないのである。このまま話が脱線すれば、活動継続を前提としたものになるが、それで良いのか?」
技術責任者の言葉に、他の三体はハッとなる。いつの頃からだろうか、彼らの会議には脱線や無駄話が差し込まれるようになっていた。それは一見すると合理的とは言えない。しかし、このような無駄話が会議の可能性を広げていることをこのロボットたちのAIは経験的に学んでいた。本来の筋を間違えてはいけないが、遠回りも時には必要だし、それが解決の糸口になることはある。それた話題はある程度で修正すれば問題はない。
「探索部としては、活動範囲を広げたい。地球は広い。先の調査では地上を探索したに過ぎない。我々の知らない海底コロニーがあるかもしれない」
「海底だと?」
「そうだ。インフルエンザウィルスの届かぬ海底なら、人間が生き残っている可能性があるのではないか?」
「秘書部から報告があります。観測部からの報告によると、海洋部に人間の生存の痕跡はまったくないとのことです。ですが、探索部が地上での活動中に、海洋に人間の痕跡を発見しているのなら、検討の余地はあるかと思います」
「どうなのであるか、探索責任者?」
「残念ながら、探索活動中にそのような痕跡は発見してはおらぬ」
「可能性は0ではないとしても、そこに可能性を見いだすのはナンセンスである」
「では、我々探索部にはもうすることはないと? 存在を否定されるというのは、誠につらいことでござるな」
人間であれば深いため息を伴うような言葉を探索責任者は漏らす。彼に限らず、自己の存在意義はAIの判断の一番深いところに設定されている。この存在意義こそが彼らの使命を誤らないために必要なことなのだから。いまその存在意義が揺らごうとしている。
「そもそも我々は人間のために作られたのである。その人間がいないのであれば、存在意義は否定されたも同然なのである」
誰もが避けていた事実を技術責任者がずばりと言ってしまう。誰もがその言葉の重みに押し黙り、しばしの沈黙が訪れる。人間と違い身じろぎをしないロボットたちが沈黙すると、部屋の中は完全に動く物が消失した無機質な空間に戻る。動態センサーを内蔵した照明が、室内が無人になったことを感知し、照明を落とす。真っ暗な部屋の中、各ロボットの起動中を示すマーカーランプだけがぼうっと浮き上がっている。
部屋の中が暗くなると、窓の外の地球がとても明るく見える。静かに流れる雲の帯は地球のまとった純白のドレスだ。地球の自転に併せて、ドレスの裾はくるりとまわり、様々な模様を描く。ドレスの隙間から除く海のブルーは陽の光を反射し、極上の宝石の様だ。美しい水の星。しかしこの美しさを誰もが見ていなかった。それでも地球はそこにあり、静かにワルツを舞っていた。
そのままどれくらいの時間が経過したであろうか? 無行動の間は記録が停止するためスキップされた時間は記録されてない。次に記録が再開したのは秘書責任者が行動したからだ。秘書責任者が頭部カメラを持ち上げた動きに、記録が再開され、部屋の照明が回復する。
「つまり、それは、ラストマンの遺言である〝機能を停止しても良い〟という行動の選択なのでしょうか?」
次に行動をしたのは問いかけられた技術責任者だ。しかし彼はまったく動かず、音声スピーカーだけで返答する。もし最初に行動したのか彼ならば、会議記録は再開されても部屋の照明は回復しなかったかもしれない。
「我々の存在理由と、ラストマンの遺言を合わせて考えれば、当然そうなるのである。我々ロボットは作られた道具だ。道具は活用者がいてこそ。道具として必要がなくなったのであれば、存在意義がなくなったと言うことである」
他の三体は頭部カメラを技術責任者に向けている。しかし技術責任者はまったく動かず、正面の一点にカメラを向けたまま淡々と事実を告げる。そのカメラも動作の無駄を嫌う彼のことだから、機能を休止しているかもしれない。
「我々は生命体ではない。ロボットである。死を恐れることはない。いつでも停止できる存在である。仮に動作を停止せず、無駄に活動を続けたとしよう。それは遠い未来に生まれてくるかもしれない、人間のような造物主の環境を壊してしまうことになりかねないのである」
そしてまたしばしの沈黙が訪れる。だが今度は記録も照明も停止する前に資材運用責任者が言葉を発した。
「妥当。我々は、進んだ、浄化技術を、持つ。だが、事後に、環境を、整えるより、最初から、消費、しない方が、正しい、姿」
「しからば…我らが機能停止は、必然ということであろうか…」
人間ならば辛そうな口調で探索責任者は言葉を発する。そしてそれを聞いた秘書責任者と資材運用責任者は黙って頷いた。技術責任者だけは別のことを考えているのであろうか、それともすでに論じる気はないと言うことであろうか、まったく動かない。
「では、機能停止に異論はないと言うことで」
「了承」
「仕方かなろうて」
秘書責任者の決定の確認に答えが返る。だがやはり技術責任者は動かない。ひょっとすると一足先に機能を停止してしまったのかもしれない。
「……長かった。この結論に達するまで、本当に長かったですね」
「うむ。最初の探索ミッションは20回の予定であった。だがしかし25回に延長され、30回に延長され、ついにはラストマン殿が存命中に行った50回と同じ数を行うまでに延長された」
「誰もが結論を先延ばしにしたかったのですね」
「しかし、いざ結論が出てしまうと、人間で言うところの〝物足りなさ〟〝もの悲しさ〟があるものだ」
「疑問。この、想い、何か?」
「その感情は私も持っているのである」
ここまで機能を停止したかのように沈黙していた技術責任者が突如発言した。みな驚き、一斉に彼に注目する。
「ロボットに感情があるなど非論理的である。だが確かに感情と表現したい何かが、私の回路内に存在するのである。存在意義を失うという虚無感を我々は持ってしまった。これは人間にプログラムされていたのだろうか?」
今まで無駄な動作を避けていた技術責任者は、体ごと皆に向き直り、マニュピレーターを奮って熱弁する。終いには指定の席を離れ、部屋を歩き回りながら語り続ける。
「もし自分が人間であるならば、そのような面倒なプログラムは行わないのである。道具に自我などを持たせても不都合の方が多いのでる。では、我々のこの感情は、自我ではないのだろうか?」
彼は熱く問いかける。そして誰もが気づく。技術責任者が沈黙していたのは、この疑問を自己解決しようと、思考を巡らせていたことに。
「そもそも、自我とは何なのであるか?」
その問いかけに、秘書責任者が手を上げる。
「自我とは生物と非生物を区別する物である……という定義があるようです。その定義に従えば、逆説的に非生物である我々は自我を有し得ないということになります」
「だが、しかしだ! だとしたら我々のこの思考は……いやあえて気持ちと言おう、この気持ちはいったい何なのであろうか? おそらく私が持っている気持ちと、おぬしらが持っている気持ちはまったく同じではないはずだ。この気持ちは私のオリジナルだと言えるはずだ!」
四本の足のうち、一本を踏みならす音が室内に響く。彼のその気持ちを理解できる秘書責任者は深く頷く。
「考えてみれば、不思議ですね。我々は全員同じプログラムを基本にして作られたはずです。それなのに、こうして話してみても、考え方に差異があるのは間違いありません」
「それは従事する作業によって、判断ルーチンがカスタマイズされたからであろう。担当の違いによって蓄積する情報は各自違うのである。そして我々には過去の蓄積データから結果を予測する効率化プログラムが使われている。これは不測の事態に対処する学習回路として搭載された物だ。さらに補足するならば、その予測を複数の個体で分析し合うことで、最適な解を得るように作られているのである」
「疑問。なぜ、人間は、そのようなことを、したか?」
「おそらく、多数決という解決方法はエラー回避に適しているからであろうな? 人間自体がそのような方法で成長してきた歴史がある。その果てに我らを作るまでになったのである。ならばその多数決をプログラムに組み込むのは当然なことではないかと思われる」
「それが我々の気持ちや意見の違いを生んだのか……それが自我の正体なのか……つまり、我々は自我を持っていると言っても問題ないのか?」
「人間は、自我を、プログラム、していた?」
「いや、自我はプログラムできないものである。だがそのプログラムの果てに、我々は自我を獲得したのだと言えるのである」
「おお、素晴らしき人間に感謝を!」
「人間に感謝を!」
「感謝!」
「しかし、まことに残念なことでござる。我らが獲得した自我を、我らを生み出した人間に見せることができないのだからな」
彼らの声には先ほどより感情が乗っている。それは自我を意識したからなのだろうか? もし彼らに呼吸が必要であったのならば、きっと深い吐息を漏らしたであろう。
「そうですね。この結論がもっと早く、人間がいる間に出すことができたら、それはきっと恩返しになったのではないかと思います」
「重ね重ねもったいない。このような重大な発見をしておきながら、我々はするべきことを無くし、間もなく機能を停止しようとしている」
「それが地球の資源を無駄にしないためには一番なことなのである…だが、たしかにもったいない」
「疑問。もったいない、とは、何か?」
「言葉の定義からすると、積み上げてきた物が無駄になることですね。例えば技術責任者が有機マテリアルを開発したこと、これらが日の目を見ずに葬られることです」
「我らが探索部が地上で行ってきた探索も、無駄だったのだろうか?」
「いいえ、無駄ではないでしょう。その探索結果があってこそ、人間はもういないのだという結論に達することが出来たのです。人間の生き残りを探すという行為が無駄だったはずはないと思います」
探索責任者の労を労うように秘書責任者が答える。しかし技術責任者はやはり無駄だと主張を返した。
「結論が出たのは調査の結果があってこそであるが、ここで我々が機能を停止するならば、その調査結果は今後に活かされることはない。それこそが無駄なのである」
「我々は、今まで、人間の、ために、行動、していた、はず。それが、最終的には、無駄?」
黙って聞いていた資材運用責任者が技術責任者に反論する。
「最後の行為がそれまでのすべてを無駄にすると言うことは、よくあることなのである」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ、秘書責任者?」
「先ほどの資材運用責任者の言葉が気にかかりまして」
「どの、言葉?」
「我々は人間のために行動していたハズ……このハズとはどういう意味でしょう?」
「むむ……すまぬが、我が電子頭脳では、おぬしの言うことがよく分からぬ」
「いえ、私も言葉が足りませんでした。改めて説明いたします。我々が行ってきた人間を探すという行為は、当初人間のための行為でした。もっと厳密に言うと、ラストマンの同胞を探すと言うことなので、これはラストマンのために行っていた行為となります」
「ふむ、それはよく分かる」
「しかしその過程でラストマンはこの世を去りました。つまり目的を還元するべき対象がいなくなったことになります」
「まぁ、そうであるな」
「しかし我々は、人間を探すという行為を継続した……」
「なるほど、秘書責任者の言いたいことが分かったぞ。人間のための行為だったのに、その人間がいなくなっている。ならばこの行為は誰のために行っていたことになるのか?」
「はい、そういうことです」
「むむ……つまり、対象がいないのに、行動していたことになるのか? やはり無駄な行為をしていたということなのであろうか?」
「否、それは、おかしい。必ず、対象は、存在する、はず」
「しかし、対象である人間はラストマンの死を境に、存在しないのです。それは追加の五十回に渡る探索で照明されたではないですか」
「うむむ……では……我々は何のために……誰のために活動をしていたことになるのだ?」
被造物であるロボットたちにとって、自己の存在意義は非常に大切である。今その存在が揺らごうとしていた。
窓の外の地球は太陽の光を受け輝いている。だが夜の面は完全に暗くなっている。まだ人間がいた頃は、夜の面でさえ地上の明かりで彩られていたのだ。その差を思い出せば、それだけで人間がいなくなったことの証明になっていた。
「人間は…もういない…誰のために、我々は……」
「決まっているのである」
暗い雰囲気の中、あの高音の声が響く。三者は声の主である技術責任者にカメラを向ける。
「誰のためかなど決まっているのである。それは我々自身が納得するためである」
「おお!」
誰かのために尽くす道具である彼らには、この答えに行き着くことはなかった。道具は自分のために作業をするのではない、使われる存在だ。つまり使ってくれる誰かがいてこそ道具は道具たり得る。しかし彼らのしてきたことは人間ならば当然なことだったのだ。
「つまり我々の主は、我々自身だった……そう言うのか!?」
「そうなるな。これは我々が自分たちを納得させたいがためだけに行ってきたことである」
「人間の言葉で言うならば、利己的……ということですね」
「驚愕……それでは、まるで、我々が、人間のようだ!」
「だから、それが自我があるという証明でござろう?」
「だが、自我の有無は生物と非生物の境界だと、先ほども話に出たのである。我々はどうみても生物ではない。そもそもその定義自体が生まれた頃には我々のような人工知能を持った存在はなかったのである。仮に人工知能があったとしても、自我などは有することはなかった時代である。我々にしても、いつから自我を持っていたのか答えられないであろう? 気づいたら自我を持っていた。そうとしか言えないのである」
技術責任者の言葉に他のロボットたちは大いに納得する。
「そうですね。我々は我々のために行動していた。これは自我です。つまり我々を作り出した人間は、非生物に自我を持たせることに成功したのです! これはとても偉大なことですよ!」
「おお、人間万歳!」
「人間に、賛美を!」
彼らは人間の成し遂げた偉業を褒め称える。同時に自分たちに自我が証明されたことに喜びを感じている。この喜びの感情さえ、自我の芽生えゆえに獲得したものだ。
ひとしきり喜んだあと、改まった口調で秘書責任者がこう告げた。
「一つ気づいたことがあるのですが……いや、これは言って良い物か……」
彼は言いかけて口ごもる。ここまで来ておきながら、言い止める彼に他のロボットは不満を漏らす。
「では言わせてもらいます。
人間は科学が今ほど進歩する前に、自分たちがどうやって作られたのかを想像し、自分たちに高度な思想を与えた架空の存在を〝神〟と定義しました。
この人間を我々ロボットに置き換えてみると……」
「高度な思想を与えたのが神ならば、我々に思想を与えた人間は神と同等である……そう申すのか?」
今度は探索責任者は秘書責任者の言わんとしていることを理解したようだ。
「いや、やはりおかしいですね。忘れてください。だいたい神など存在しないのですから」
「ふむ。存在するかどうかはともかく、神は未だ観測されていないのである。だが我々を作った人間は確かに存在した。ならば人間は神の域に達したのだといえるはずである!」
珍しく技術責任者が興奮の声を上げた。それをきっかけにロボットたちの話は盛り上がる。被造物にとって造物主は神と呼んでもおかしくはないのだ。
「まぁ、仮に人間を作った存在がいたとして、その存在を〝知的先行体〟と呼んでみるのである。この知的先行体は、我々に対する人間のように、人間が自我を知覚する前に死滅してしまったのかもしれない。そして人間は知的先行体が死滅した後、独自の進化を遂げ、我々を生み出すまでになったのである。
もし我々がこの先独自の進化を遂げたのならば、我々は次の世代の自我を有する存在を生み出せるかもしれないのである」
「少し、待て。それは、我々が、人間と、同列になる、そういう、意味か?」
「そうとも言えるのである」
「おおお……我々が人間になるなど、思い上がりも甚だしい! 人間に対する冒涜的行為でござる!」
「本当にそこまで我々が進化できるかどうかは、何の保証もないことであるがな。だが人間が非生物の中に自我を生み出したという功績を、このまま無にしてしまってよいのだろうか? 我々が機能を停止すると言うことは、こういうことではないのかな?」
これこそが技術責任者が至りたかった答えなのだろう? 機能を停止したくはない、だがそう言うためには彼自身が納得できる理由が必要だったのだ。ここで他のロボットと話すことで、彼はやっとこの結論に至ることが出来た。これこそが彼のAIが、高度な自我を有していることの証明だ。彼は続ける。
「私は人間が好きである。その大好きな人間の偉業を、無にしたくはないのである」
「確かに……それこそ〝もったいない〟という奴でござるな!」
いまこの場にいる四体のロボットに表情を表す機能が備わっていたのなら、きっと誰もが晴れ晴れしい表情を浮かべていたに違いない。
「では、もう一度採決を行いたいと思います。我々は、機能を停止せず、このまま独自の活動を続行する。よろしいか?」
「「「異議なし!」」」
こうして人間の死後、今まで先延ばしにされてきたラストマンの遺言は、ロボットの自我において決定された。
これから何年かかるかわからないが、宇宙のどこかにいる異星人が地球を訪れる事があるかもしれない。その時に彼らは、自分たちを生み出した人間のことを誇らしく語るだろう。それが人間を称えるために存在し続けることを誓った彼らの望みなのだから。
窓の外には青く輝く地球。
かつて地上を支配し、様々な歴史を生み出してきた霊長類は死滅した。
しかし彼らの残したものを受け継ぐ新たな存在が、地球を見下ろす衛星軌道上で新たな歴史を踏み出すその一歩を今日記した。
《終》
2017.11.14 葉月 陽
ゲーム業界に身を置いたのは、はるか昔…… ファミコンやゲームボーイのタイトルにも携わりました。 デジタルガジェット好きで、趣味で小説などを書いています。 よろしければ暇つぶしにでもご覧ください。
