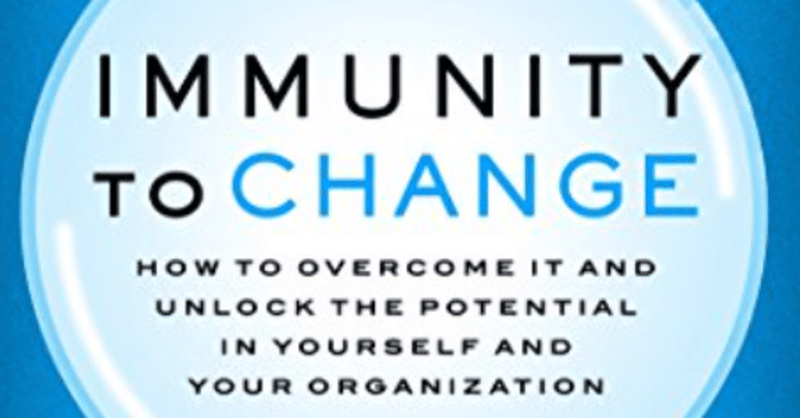
「課題図書」 Inner MBA 体験記 #2
得体の知れない Inner MBA の入学式は 9 月 19 日 (アメリカ時間) と決まった。日本はその時間は真夜中のなので、後で録画を観ればいいそうだ。
ただし、その10日ほど前に生徒用のポータルサイト (オンライン講義がアップされたり、生徒同士のチャットグループが作れたりと SNS 的な機能がある) がオープンし、事前学習のための課題図書を読むように、と告知された。
その名も「Immunity to Change」直訳すると、変革のための免疫?
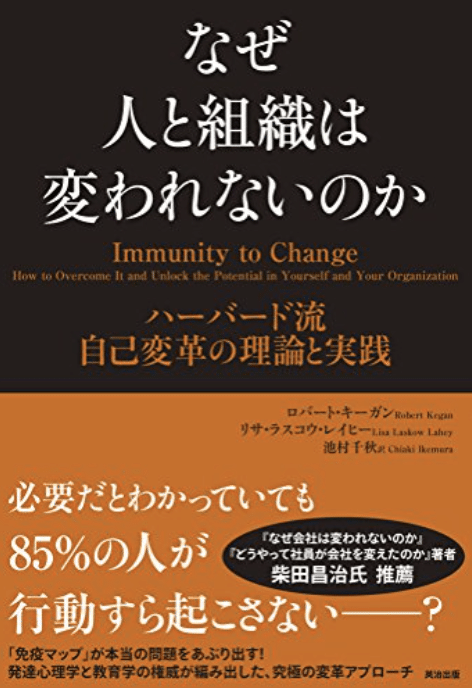
Amazon で見ると翻訳版も出ており、90 件以上のレビューがついている。名著とのこと。邦題は「なぜ人と組織は変われないのか ハーバード流自己変革の実践」とあり、思ったよりビジネス寄りな雰囲気を感じる。(いきなりマインドフルネス入門、とかじゃないのね、と思った)。
著者は教育学者のロバート・キーガンとInner MBAの講師の一人もである発達心理学者のリサ・レイヒーの二人だ。成人教育や発達心理学が専門とのこと。
しかし 400 ページ超... 英語で読み通すのはきついな... 英語学習のため、という当初の目標と早々に矛盾しながら、翻訳版を購入してみた。そしてその後、バーチャル入学式ギリギリまでかかって通読したところによると、大きく3部からなるこの本の主張は以下だった。
第1部: 大人になっても知性は伸びるよ!
これまでは20歳ごろまでで知性は頭打ちになると思われていたが、実はもっと大人になってからでも伸びていく。その知性には3つの段階があるという。
ステップ1.環境順応型「周りの価値観のなかで、言われたことをやります」
↓
ステップ2.自己主導型「自分の価値観と軸があるから、ブレずにやります」
↓
ステップ3.自己変容型「自分の価値観を客観的に見ることができ、必要に応じてものの見方自体を変容させていけます」
成功しているリーダーはステップ3にいる確率が高いとのこと。
じゃあどうやって知性を伸ばすか?
ずばり、免疫マップ(Immunity Map)というフレームワークがある!と本題に入る。それは、改善目標 | 阻害要因 | 裏の目標 | 固定観念 という4つを自己分析によってあぶり出すことである。
例えば、とある企業の新任マネージャーのケーススタディでは、
①改善目標: もっと部下に仕事を任せていきたい
②阻害要因: でもついつい自分でやってしまう、作業を抱え込んでしまう
③裏の目標: 自分が一番優秀だということを確認したい、自分こそが問題解決のヒーローでありたい。
④強力な固定観念: 現場で手を動かすことこそが真の仕事で、管理職ってのは本当の仕事じゃない(なぜそんな思い込みが?その理由は後述)。
だった。この免疫マップのポイントは①②の比較的わかりやすい課題と現象から、③④の隠されたインサイトを見つけること。
隠されたインサイトが阻害行動を生み出し、改善目標を邪魔する。これが変革を阻む人間の免疫システムであり、アクセルとブレーキを同時に踏むような人間心理の避けられない仕様なのだ、と。
第2部: 具体的にこんな事例があるよ!
そこで、この免疫マップ作成とそれを通した人材開発のワークショップについて様々な個人や組織の事例を紹介。いかに自己の免疫を把握し、それを克服するか?
取り上げられるのは製薬会社だったり森林管理局のような行政機関だったり、不動産会社のCEOだったり麻酔科の看護師だったり...。さらっと書いたが文章量はこのパートが一番多い(そして彼/彼女らの実際のマップがこれでもかと紹介されるのでとても目が疲れる)。
第3部: あなたが実践するときのコツを紹介するよ!
では、実際に免疫マップをあなたも作ってみよう。その時に気をつけるべきポイントは...というパート。
前述の新人マネージャの例で言うと、マップの4枠目(強力な固定観念)について、
「自分はブルーカラーである職人の家で育ち、そのことに誇りを持っている」
「だからホワイトカラーのマネージャという"あっちの世界"の人間になりたくない。それは本当の仕事ではないと思うから」
「だからどうしても自分の手を動かしたくて、部下に仕事を任せられない」
という潜在意識があることが浮き彫りになった。このように、自身の出自にまで根ざした変革を阻む自己免疫システムを知ることができるのがこのフレームワークのパワーだという。
つまり、場合によってかなりプライベートな部分までさらけ出すことになるので、ワークショップを行う際は、「片手間で参加しないこと」「ワークショップのリーダーとなる人間が率先してマップを書いて告白すること」「本業の人事評価には関係がないと約束すること」「できれば第三者からファシリテーターを入れること」など、いくつか気をつけるべきポイントが示された。
簡単に言えば、このマップ作りは心理的安全性が確保された場で行う、ということだ。いろいろデリケートな話に議論が及ぶと考えれば納得だ(言うは易し行うは難しなんだろうけれど)。
---
それにしても細かい字で400ページ...長い本だった。でも、Inner MBA を卒業する頃には原本を英語で再読してみよう(もちろん、きっと、たぶん、できれば...)。
次回、体験記 #3 「ソフトスキルほどハードなスキルはない」に続く!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
