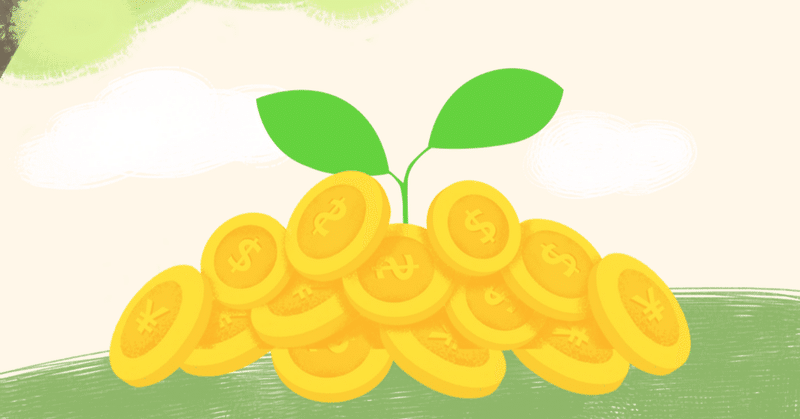
iDeCoに加入するなら、出口をちゃんと理解しておこうね!
おはようございます、ひらっちです。今日で4日連続投稿!やったー!! すぐに前言撤回する僕が言うのもなんですが、やっぱり習慣化が一番ですね。再び習慣化して毎日更新を続けられるといいなぁ~…といって明日から更新しない可能性も大ですが笑。何事も肩肘張らないのが良いかと(^^♪
<いつものように簡単な自己紹介です>
僕は、地方国立大学を卒業後、ブラック企業で営業マンを経験。その後、フリーランスのライターとして独立開業、さらに数年後、新規就農して農業をスタートさせ、2020年現在、好きな仕事を選びながら人生を謳歌する「ほぼセミリタイア生活」を実践しているアラフォーです。
このnoteでは、特に20・30代のビジネスパーソンの皆さんに、僕の経験に基づいた「人生を楽しく過ごすための技術」を提供し、少しでもたくさんの方に「幸せな毎日」を掴んで欲しいと考えています。どうかお付き合いください。
現在、『マイナビ農業』で不定期連載中! 農業にご興味のある方はぜひこちらもご覧ください!
■今日は久しぶりに「iDeCo」を取り上げてみました
あらためまして、ひらっちです。今日は「お金」「老後」をテーマに書いてみたいと思います。
「誰でも利用できる老後資産形成制度」として、だいぶ世間一般に広まってきたiDeCo(イデコ)。このnoteでも再三にわたって紹介してきているので「ひらっちさん、またなの?」「そんなの知っているよ!」という方も多いかな。でもその一方で「え?なにそれ?」という方もいると思うので、今日は「最近のiDeCo事情」について、おさらいがてら改めて解説してみます。
そもそもiDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の一つです。 公的年金と違って加入は任意。 加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てを自分で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができるという制度です。
「基礎から詳しく知りたいよ!」という方は、ぜひ厚生労働省のリンクを貼っておくのでじっくり読んでみてください。これを読めば基礎の部分はご理解いただけると思います。
このiDeCo、今年から制度が改正されました。ポイントは「延長」です。これまで60歳までしか加入できませんでしたが、2022年5月から加入年齢が65歳まで引き延ばされたんですよね。あとは、受け取り開始可能年齢も、選択の幅が60歳から75歳になるまでに拡大されています。このあたりを詳しく知りたい方は、下記のリンク先をご覧ください。
というわけで、引き続き注目を集めているiDeCo。なかなか伸び悩んでいた加入者も、最近はかなり増えてきているそうな。
色々と使い勝手が良くなるのは、国民としてはありがたい限りです。ただ、その裏には「老後の資金は自分たちで何とかしてね!」というメッセージが隠れていることはちゃんと肝に銘じておかないといけないですけどね。
■iDeCoに加入するなら、最低限の出口の知識は身に付けておこうね!
さて、このnoteでは、何度も「老後資金戦略」をテーマに取り上げてきました。気になる方は、ここにいくつかPickupしている過去記事をご覧いただければと思います。
過去の記事を読めば分かると思いますが、僕は基本的に、若い人たちのiDeCoへの加入を推奨していません。なぜか? 出口戦略が難しいからです。iDeCoの掛け金は所得控除となり、節税効果が見込める点が大きな魅力ですが、その一方で出口、つまり老後の受け取りの部分をうまく調整しなと、所得税が増えたり、社会保険料が大幅にアップしたりします。
退職金が多い大手企業のサラリーマンの方は、所得税の節税メリットは大きいものの、受け取り時に税金をゼロにするのは難しい。その一方で、退職金がほとんどないフリーランスの方は、そもそも所得控除の旨味が少なく、60歳まで資金が拘束されてしまうのが大きなネックです。要するに色々と使い勝手がよくない面があるんですよね。
もちろん、運用成績さえ良ければ、税金を気にしないでいいくらいの増額が見込めるわけだけど、大した成績を上げられず、しかも税金がしっかりとられるような事態になれば、そのショックは大きいです。
人間は、利益が出た時の嬉しさよりも、損失が出た時のショックの方がでかい生き物です。リスクが大嫌いな日本人は、この傾向が強いような気がします。予測のできない老後に余計な不安を残すくらいなら、「まずは積み立てNISAでコツコツやった方がいいんじゃね?」というのが僕の意見です。
そこで、ちょうどよい記事が、今日の日経新聞に掲載されていました。このnoteではお馴染み、日経新聞の田村さんのiDeCo関連の記事です。
田村さんの年金に関する解説は、相変わらずめちゃくちゃ役立ちますね! どういうもらい方をすれば、効率よく節税しながらiDeCoを受け取れるかがわかりやすくまとめられています。
マネーリテラシーに自信がない方には推奨しませんが、「それでもiDeCoを始めてみたい!」という方は、上記の新聞記事を読んで分かるくらいまでには、iDeCoに関する知識を深めておいた方がいいと思います。新聞記事はあくまで一つのケースでしかないので、これを元に自分の想定退職金などを当てはめ、ざっくり出口戦略を見据えておく。そのうえで加入するかどうかを判断してみるのがおすすめです。
■まとめ
いかがでしょうか? 皆さんは老後の戦略をきちんと立てていますか? このnoteは20代・30代をターゲットにしているという建前なので、正直、そのくらいの年代の方が「今から老後をなんとかしなければ」と焦るより、目の前の仕事に全力投球して、人的資本、いうなれば「稼ぐ力」を磨いた方がよっぽど将来のためになると思います。
だって、この世代はほぼ間違いなく、70歳、いや75歳くらいまで働き続けることになりますから。一生稼げるスキルを身に付けること。これが一番の老後対策になることは言うまでもありません。
そのうえで「へえー、iDeCoはこういう制度なんだね」とざっくり理解できる程度の知識を身に付けておくことが大事だと思います。このnoteでは今後もお金に関する情報をこまめに発信していく予定なので、「あれ?そういえば何かあったな?」と検索できる力くらいのマネーリテラシーを身に付けておいてもらえば、きっと今後の人生に役立つと思いますよ(^^♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
