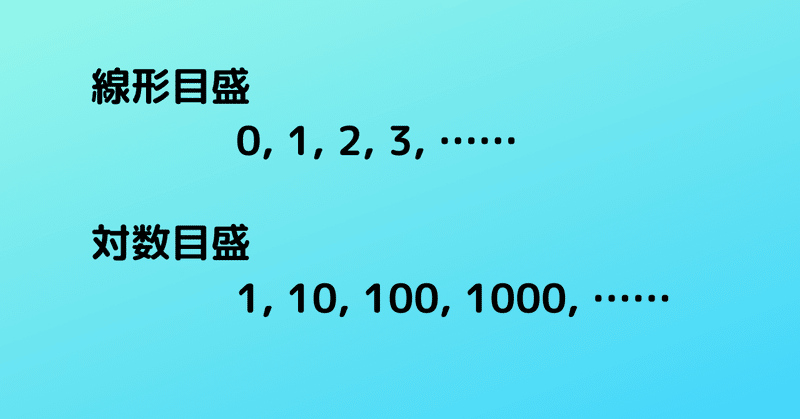
対数目盛で変化をとらえる
新型コロナウィルスも、5類への引き下げで、落ち着いてきた印象があります。コロナ禍の3年あまりは、毎日、新聞に感染者数推移グラフが掲載されていました。

このグラフを見ると、オミクロン株以降の感染者が、それ以前のピークよりも圧倒的に多いことが、一目瞭然でわかります。今、見直すと、第3波以前は、ピークがあったのかも、よくわからないレベルです。第1波は、学校が休校になり、自粛ムードで強い警戒感がありましたが、このグラフだけ見ると、ほとんどなかったに等しいことになります。第1波について、グラフから読み取れるようにするにはどうすれば良いでしょうか?
通常、グラフの縦軸は、等間隔でプロットされています。0人と2,000人の間隔と、20,000人と22,000人の間隔は同じです。ニュースで聞いた時の印象として、感染者が0人だったのが2,000人になった時のインパクトと、20,000人が22,000人になった時のインパクトは同じでしょうか?ほとんどの人は、前者の方のインパクトが大きいのではないでしょうか?
このような場合に有効な方法として、対数目盛があります。対数(常用対数)は、10を何回かけ合わせるか(何乗するか)で、大雑把に言うと、桁数(に1たしたもの)に相当します。10の場合、0が1つで1、100の場合は0が2つで2とします。10と100の間は少し面倒ですが、つじつまがあうように(?)計算されます。
感染者数のグラフ(図1)を、実際に、対数目盛で描き直してみました(図2)。

対数目盛だと、第1波~第8波のそれぞれのピークがわかります。どの時期が、第何波だったか、よくわからなくなりつつありますが、対数目盛では初期の波もわかりやすく、何番目のピークか、読み取れます。第1波の印象も実感に近くなるかと思います。
このように対数目盛が便利な場面は意外と多くあります。
あまり大きな数字だとピンとこず、10兆が100兆になっても、千が1万になったのと印象があまり変わらないことがあります。こういう場合、対数目盛だと同じ間隔になり、感覚に近づきます。(線形目盛で実際の変化量を認識すべきか、対数目盛で見た方が良いかは、目的次第です。)
製造業では製品の不良率を減らすことが重要です。10%の不良を5%に減らすのと、6%の不良を1%に減らす労力は異なります。不良率の推移グラフを見ていると、改善や悪化について、過大評価になる場合や、感度が低くなる場合があります。こういった場合も、不良率を対数目盛にすると見通しが良くなることがあります。不良率といった百分率(パーセント)の場合は、オメガ変換やロジット変換という方法もありますが、ざっくり傾向を見るだけであれば、Excelでも簡単に描ける対数目盛が便利です。
普通のものさし(線形といいます)だけではなく、対数のものさしをもっていると、多角的に物事をとらえられるようになります。大きな数値にまどわされず、初期の小さな変化に敏感になれます。単なる計算道具ではなく、視点を増やすために、数学を学び直してみてはいかがでしょうか?
対数については、以下の記事でも書いています。興味とお時間があれば、ご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
