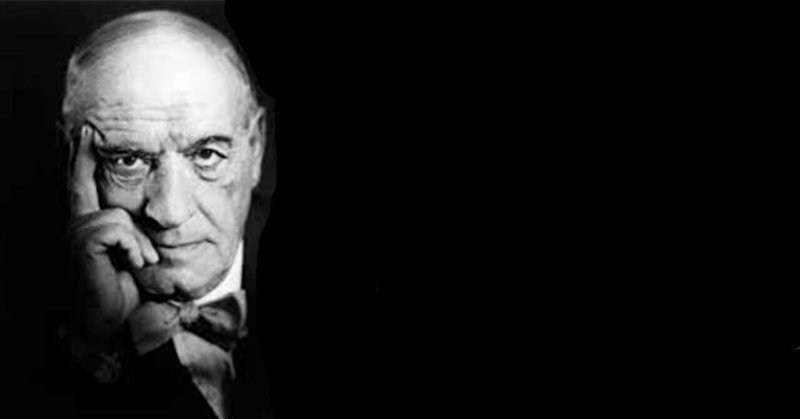
福田恆存を勝手に体系化する。1 オルテガのパースペクティヴィズムとの関係
孤独の遠近法
さて、どうして人間は孤独なのか――
結論を先にいえば、福田恆存における「孤独」とは、人間の存在論的条件に基礎づけられたものである。つまり、どんなに修行をつもうとも、あるいは愛にむすばれていようとも、人と人が直接むすびつくことは原理的にけっしてできないということを意味している。それがわれわれ人間にあたえられている仮借のない宿命なのだ、とかれは考えている。
人間とはなにか。生きるとはどういうことか。そういう問いにわれわれはどのように答えるだろうか。まず一般になされているのは、概論的方法である。人間とはホモサピエンスであり、生物学的に身体の機能を描写する。あるいは社会学的に人間の行動を分析する。構造主義的に人間の文化を解明する。また宗教的に人間の業を語る。こうした概論的方法に共通するのは、いずれも外部から人間をとらえる方法であるということだ。
しかし、人生において生起するさまざまな事象について真実を語ろうとすれば、われわれは内側から語るほかない。なぜなら、われわれが他者や社会についてする外側からの思考はあくまで推論であり、多様な前提に影響された抽象なのだ。ふだんわれわれが何とはなしに信じているさまざまな先入観を剥ぎとって、根源から自己の生活をみなおしてみれば、私が確実に知っていることは、私自身の体験することのほかにないはずだ。人間一般や社会一般についての言説は、どこまでいっても不確実な仮定でしかないのである。
したがって世界像には二種類あるということになる――内的な世界像と外的な世界像。真実のものと、仮定的なものの、二つだ。
人生とは、不可避に、内なる出来事にほかならない。であれば、少しでも明証性のある事実を語るというのはつまり、自分自身について語ることである。
「世界」とか「自然」「社会」といった数多の抽象的な観念を一度取り払って、無垢な目で、自分のおかれている根本的状況を点検してみてほしい。
そこに現れてくるのは、私をとりまく多数の事物と、それを眺める私、である。ハイデガーの用語でいえば、「世界内存在」ということになろうか。しかしそういう連想や予備知識も、意識から排除してもらいたい。
私をとりまく多数の事物と、それを眺める私――
これが、われわれに直接的にあたえられている根本的な状況であり、これこそが「私の内側」である。一つの視点とその視野。いいかえれば、「私」とは各人固有のパースペクティヴといえる。
現実的なものはすべて、この私固有のパースペクティヴの中にあたえられている。万物はパースペクティヴの中に現れ、その中で働いている。人はそこで生きようとし、事物について省察し、それらに働きかける。
私がハイデガーを遠ざけ、哲学を忌避したのは、かれらが現実的なものとはべつにいつも、「存在」というものを措定するからである。形而上学者は、事物の背後に「存在」というべつのものを見ており、それこそが事物そのものよりも第一義的な価値をもち、事物を事物たらしめる至高のものであると主張する。ハイデガーもまた、「世界内存在」のどこかに「存在」という真の最高価値を探究してやまない。しかしここでは、いったんそうした形而上学の偉大な業績から距離を置いてもらいたいのである。
おそらく福田恆存もそう考えていたであろう。文芸批評が哲学と完全に手を切ることはできないし、それどころか、哲学から養分を吸収することは有意義なことでもあるのだが、それでも文芸批評と哲学は注意深く峻別されなくてはならない。要するに、それぞれ持ち場がちがう。
福田恆存は、文学においても深く広い視野が必要ではあるが、文学の思考は実験室の密室ではなく、生活の領域においてなされるものだと、のべている。(「文学の効用」)
それを私流にいいなおせば、次のようなことになる。
厳密な哲学的思考においては、われわれが直観的に知覚するもの、他者や事物や自然といったわれわれ周囲にあってわれわれを支えているものを、明証性をもった実在とはみなさない。そういったものすべてを疑ってかかることをもとめられる。それゆえに哲学的思惟の本質は、自己の生活からの脱出であり、人生の中断なのだ。そしてそれは理論を構築するための中断であり、留保なのである。
ところが文学においては、行動がその本質をなす。思考もまた、行動の一形態として処理されていなければならない。いかなる意味においても、理論形成は文学の目的とはならない。
文学において起点となるのは、「存在」ではなく、「生きる」ということである。スタンダールのいうように、「書いた、生きた、愛した」それが文学だ。ここが、それ以上一歩も退くことのできぬ起点である。究極の事実は私に生きられた人生であり、その背後に回りこみ、その裏面に遡ることはけっしてできはしない。
対象が物体であれ、人間であれ、私たちは始終、さまざまな対象とぶつかりあつてゐる。そのぶつかりあひが、すなはち「生きること」なのであります。
「教養について」
人は、何かを感じ、何事かを思考し、表現し、そして行動する。それはことごとく各人固有の内なる出来事であり、ドラマである。そしてその舞台となるのは、かれ独自のパースペクティヴなのだ。
柄谷行人は久野収との対談のなかで、福田恆存の思考の射程距離の深さを評価しながら、それは案外、デカルト的なものだ、とのべていた。たしかに以上の考察から、懐疑主義的な独我論とみなされるきらいがないでもない。私を取り囲んでいるあらゆる事物は、私のパースペクティヴのうちに現象として現れる。その意識の事実を素材としてわれわれはわれわれを取り巻くすべての客体を構築しているといえる。この点だけとりあげれば、「すべては私の意識の中にあらわれるものであり、意識をはなれて対象の存在を証明することはできない」とするデカルト的省察と同断されることは否定できない。
この問題はのちに深くつっこんで論じられるべき課題の一つなので、とりあえず柄谷説をしりぞけるために、ここでは暫定的にデカルト的思考との大きな差異をひとつだけ提示しておくにとどめよう。
デカルトは、究極の実在として「思考」を見いだした。それはまさに近代の起点となる大変革だった。そこから確実にいえることは、思考がある以上、その思考をおこなう主体が存在するということである。だが、デカルトはここで、はたと立ち止まった。それでは自己の外にある現実に確実性をあたえるものとはなにか。それらはすべて思考の対象であり、意識のなかに表象される。確実な外部への通路はない。そうすると、つまるところ外部の現実はすべて主体の意識にのみこまれてしまう。それが近代以降の観念論のすがたであるとおもう。
福田恆存の思考が観念論でないのは、自我の定立に先行するものとして他者の存在を想定しているからである。かれのよくつかう表現でいえば、「人はそれぞれ歴史によってつきだされている」ということになる。自我意識とはいってみれば、「ただ、生きたい」という意欲のことである。(「白く塗りたる墓」)
つまり、「我思うゆえに、我あり」ではなく、まず自然があり、社会があり、歴史があり、他者がある。そして、言葉。たとえそれが意識の事実として現象するものであろうがなかろうが、自己のパースペクティブにあらわれ、知覚にあたえられる世界の存在が主体を覚醒させる。われわれは歴史の先端に位置し、社会の機能によって人となる。その作用は純粋理性によるアプリオリな演繹ではなく、不可避に経験的なものだ。
とはいえ、それはまた素朴実在論でも経験論でもないのである。なぜならば、そこでは普遍的な構造としての客体的世界があらかじめ前提されているわけではないからである。われわれにあたえられているのは物との共存であり、それらの現象するパースペクティヴのみである。
しかも福田恆存は現実の事物から帰納し複写しうるものだけを実在と考えているわけではない。「神」や「社会」とか「民族主義」、いまでいえば「LGBTQ」などそういうものも含め、人が生きる上において考慮にいれなければならないありとあらゆる観念もまた、すべて実在とみなすのである。
こうした基本的認識が、福田恆存の文学と批評の源泉となっている。
さて、ここまでで気づいた人も多くおられるだろう。それは、ニーチェやオルテガの遠近法主義との明白な方法論的類似である。あるいはそれを私の恣意的な牽強付会とみなす方もおられるであろうし、説明のためのいらざる便宜であるという批判をうけそうでもあるのだが、あにはからんや、福田恆存自身がそのことをとうにみとめている。おそらくかれは、一般に考えられている以上に、本質的なところで「哲学的」である。ただ意識的にその痕跡を注意ぶかく消していっているように私にはおもえる。哲学が直接的に引用されるのは、基本的には、ほとんど初期のテキスト、昭和二十五年までにかぎられる。
そういうわけで福田恆存の哲学的教養の全体を知るのは困難で、いかにしても憶測の域をでないのだが、おそらく世代的に考えて、東大ではカントで基礎的な哲学的思考の基礎を築いたであろう。文芸批評家はともすると同時代の新思潮につき合いすぎる傾向があるが、福田恆存の言説からうかがわれるのは、同時代の実存主義に対しても、そういう流行思想から一歩身をひいて、ギリシャ以来の西洋哲学史という歴史的背景のうちに、みずからの視点から位置づけようとする姿勢である。それを可能とするためには、かれの頭の良さという特異な要素を割り引いても、それ相当の広範な哲学的訓練で自己をじゅうぶんに涵養しておく必要がある。
それとともに忘れてはならないのは――むしろこちらのほうが重要なのだが、福田恆存にはキリスト教思想というもうひとつの軸があることだ。したがって教会史や聖書解釈とともに、専門哲学者以外にはあまり踏みこむことない、教父哲学やスコラ哲学をもかなり深く読みこんでいたと推測される。中世哲学の権威であるジルソンの書籍に言及してもいる。(「近代の宿命」「イギリス文学の可能性」)いまおもいだしたのだが、デューイを翻訳したという証言もあった。
前置きはそのくらいにして、福田恆存はオルテガからの直接の影響を否定しつつ、かれの哲学との「共通性は認め」て、次のようにのべている。
パスペクティヴィズムといふのは、わたくしたちが現実を認識するさいに、そこに眺められた世界はぜったいに全一なものではなく、つねにひとつの視点から一定のパスペクティヴ=遠近法においてしか把握できないといふ考へかたなのであります。ここにおいても、もちろん主体は世界を眺めわたしてをります。しかし、それはあくまでひとつの視点を守らされてゐるのですし、高みから眺めるのではなくて眺められた世界と同じ次元に立つてゐるのですから、他の視点から見れば、その視点に立つてゐる主体の守るパスペクティヴに抱合されてしまふわけです。すなはち、見る人間とはいひながら、それは絶対的な観照者ではなく、あくまで相対的で、他からは見られる人間であるにすぎません。
「文学の効用 Ⅱ」
簡にして要、てぎわのいい解説である。もっとも、これは解説というよりもかれ自身の基本的な認識論の表明でもあるのだから、てきわがいいのは当然の話だろう。ここで私があえて付け加えるとするならば、この「パスペクティヴ」は空間的な広がりだけではなく、時間にも適用されるということである。それはまた個人の記憶から歴史へと遡る時間的「パスペクティヴ」でもある。
これこそ私の勝手な感想であるが、かれらの「パスペクティヴィズム」は、アインシュタインの相対性理論にきわめて近接した世界観であるとおもう。たとえば、「見る人間とはいひながら、それは絶対的な観照者ではなく、あくまで相対的で、他からは見られる人間であるにすぎません」という部分は、アインシュタインの相対性理論がその名称によって誤解されているように、一見、相対主義ともとられそうであるが、これはいかなる意味においてもけっして相対主義などではない。観測の起点と対象との空間的・時間的関係――特定の視点と対象との関係性はあくまで絶対的な意義をもつ。それをみとめた上で、われわれの棲む世界というものが万人にとって普遍的唯一のもの――福田恆存の言葉でいえば「全一なもの」ではなく、複合的・多元的なものということである。
われわれ人間はそれぞれ、不可避に一つの視点をとらされる。のみならず人間は空間的存在であるから、物理的にその視点は他者をたがいに排除する単独のものならざるをえない。したがって、二つの視点は同時には絶対的に一致しない。とすれば、私とあなたがならんで富士山を眺めているにしても、見ている光景は違うということだ。
私たちは同じ場所から、あるいは同じ窓から、同じ山を見てゐるのではない。同じ窓といふものがあるにしても、その窓の右と左から見てゐるのである。いや、それだけではない。私たちはそれぞれ別の肉体の中から別々に外部をのぞいてゐるのである。
「批評家の手帖」
つまり、われわれがふだん感じている、だれもが共通の世界に生き、共通の時間を過ごしているという感覚は幻想にすぎないのである。いまそこにある客観的世界は推定され構築されたものだ。たとえそれがあるとしても、われわれはそれを直接認識することはできない。
その意味で、遠近法主義とは、ライプニッツのモナドロジーの発展形態といえなくもない。「モナド」とは、「単純な実体」を意味している。表象と欲求を含み、この世に唯一のものであり、部分に分割することもできない。くわえて、かの有名な定義が追加される――モナドには窓がない。そこから出たり、他者が侵入したりすることは不可能なのだ。
こうしたモナドの特徴は、各人固有のパースペクティヴのそれと一致する。パースペクティヴにも外部へと出入りする通路はない。事実上、人はそれぞれそこに閉じ込められている。私はあなたの世界の内側に入って行けないし、あなたも私の世界の内側に入って来ることはかなわない。愛とか信頼が自他の完全な一致と理解を意味するものならば、それは絵空事である。
私は私の視点に縛られている。それを他者に譲渡したり交換したりすることはできない。私の苦痛と苦悩は私だけのものであり、誰とも分かちあうことはできず、私だけがひとりその苦しみに堪えることをもとめられる。歓びや楽しみもまたおなじだ。
われわれは各自、自分だけの世界に生きている。にもかかわらず、そこには第一義的に他者が存在する。それは自己矛盾のようにみえる。しかし私のパースペクティヴにあらわれるのはかれらの身体だけだ。身体はただ存在するだけではなく、さまざまな表情、表現を示し、多様な応答をする。私はそこに、自分に似た内面性をもった他我が存在していることをただ憶測するだけだ。つまり、自分とおなじ孤独な存在者をそこに見出すのである。そしてかれもまた、自己のパースペクティブにべつの孤独があらわれたことを感じているのではないかと、私は想像する。多元的とは、互いに包みこむ相対論的な構造をさしている。
福田恆存が人間は徹底的に孤独だというとき、こうした人間の生の構造についての認識がその前提となっている。だから人と人のあいだに架ける橋はないのだ。孤独は人間にあたえられた基礎的な条件であって、何人たりともそれを拒否することはできない。だからこそかれは、ことあるごとにこういうのだ。
――絶望から出発せよ。
福田恆存さんや、そのほかの私が尊敬してやまない人たちについて書いています。とても万人うけする記事ではありませんが、精魂かたむけて書いております。
