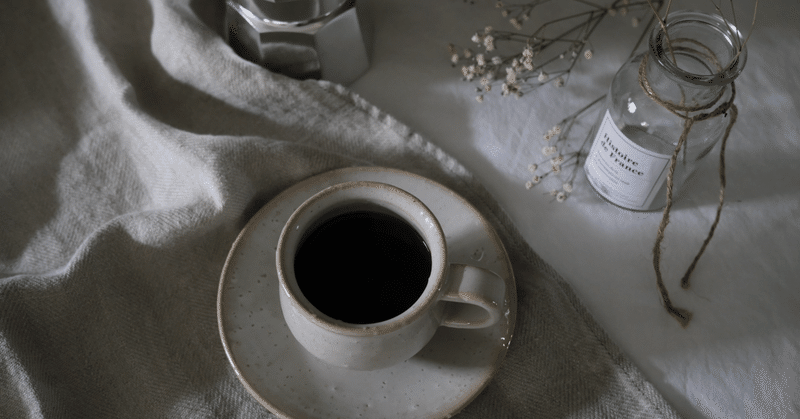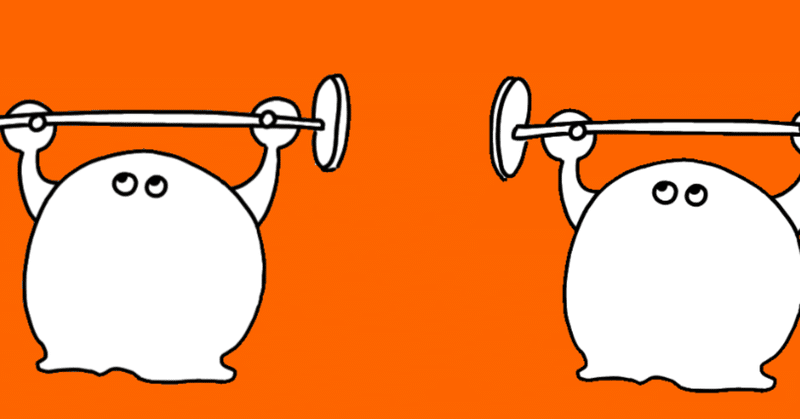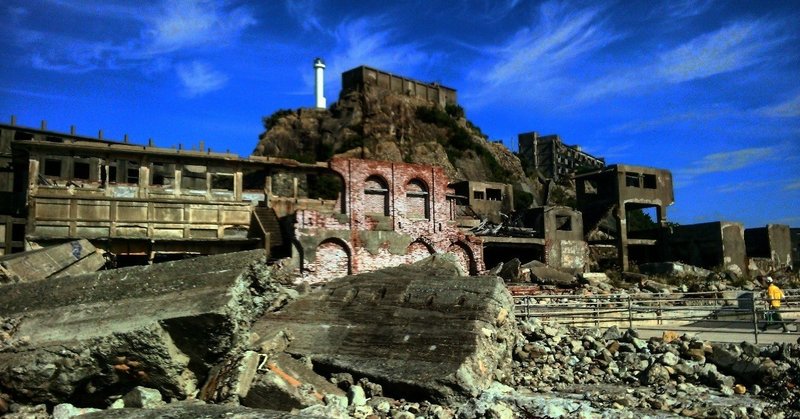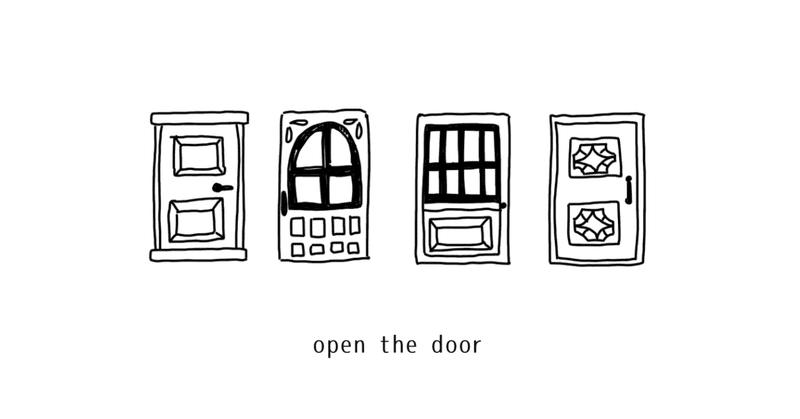#ソーシャルワーク
ナラティブアプローチへの傾倒と個人的価値観
10代から20代への移行時に生じた、経験至上主義から社会構成主義へという個人の価値の変化は、その後、現場に出たのち、ソーシャルワークの技法の一つであるナラティブアプローチへの傾倒を引き起こした。
オルタナティブストーリーに「人間の強さ」のようなものをみて、過去の自己のリカバリーのプロセスと重ね合わせたのだろう。自己のリカバリーのために他者のストーリーを摂取していることに気づくまでに、時間を要した
個人の問題を社会化するための技術的探索-マクロソーシャルワーク論文を補助線にして-
1.はじめに日本社会福祉士会から、マクロソーシャルワークについての書籍が刊行された。
援助技術としてのマクロソーシャルワークは、それが援助「技術」である以上、それは言語化し伝達可能なものであるという前提に立ち、上記を読む前のタイミングで、自身の経験から言語化した(N=1)ものを、書き記しておき、比較しながら読みたいと思い本稿を記した。
_____________________________
自身の傲慢さとどう向き合い付き合うか
起業する前は独立しているワーカーに対し、修士に行く前は研究者に対して漫然とした批判をしていた。当時の記録が他者の目に触れるところに残っているので言い訳はできない。漫然さが浅はかで恥ずかしい。
でも、自分の傲慢さに気づくことができなくなることを恐れるのならば、漫然で浅はかな批判を他者の目に触れるところに残しておくのもよいのかもしれないと思う。
考えていることのログを残し外部化することは未来の自分
”信頼”の機能についての雑感
信頼の機能ケアの受け手は、極論、ケアの提供者に生殺与奪の権を握られているという前提に立つとき、受け手が「この人は信頼できる」と思えるならば、「強引に口の中にスプーンを突っ込まれるかもしれない」と思わずに済む=不安や恐れが発生する頻度を下げられるため、「信頼」は恐怖や不安を縮減する機能として働く。
受け手が「この人は信頼できる」と思える=「強引に口の中にスプーンを突っ込まれるかもしれない」と思う不
自己覚知:経験至上主義への嫌悪について
「(私の経験は特殊だからあなたには私が言うことは)わからないと思います」という拒絶のジャブを向けられたとき、過去の自分をみているようでひどくイラつくのは、”経験至上主義”は”自らの行為を以て(自覚せずとも)社会に復讐すること”と相性が良いことを少しだけ知っているからであるように思う。
経験を外部化し相対化しようとつとめることは、経験至上主義から脱する術のひとつではあるけれども、その過程で自らの動
ソーシャルワーカーとして自己研鑽するための方法論/トレーニングについて
社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネージャー等の資格を取得後、多くの方は、自身のキャリアアップやスキルを磨くために色々な方法を試され、自己研鑽に励まれていると思います。
プロフェッショナルとして研鑽し、成長するための方法論について、私個人の経験(7年間)を振り返り、「ソーシャルワーカーとして自己研鑽するための方法論/トレーニングについて」と題してまとめました。
用意された研修を受講する以外にも
「失せろ!!!」と心の中で叫ばれているかもしれないと仮定できる想像力を.
ときどき想像する。
今日、数時間後、自分が、脳梗塞で倒れ、自分の人生において様々な力点をおいている言語運用する機能に重度の障害が残ったとして、そんな自分の目の前に病院のソーシャルワーカーが現れた、としたら、と。
白衣を着た清潔感のある男性が病室に入ってくる。胸元にあるネームプレートに少し手を触れながら、
「ソーシャルワーカーの●●と申します。横山さんが望む今後の生活について、一緒に考えて、お
”劣化するソーシャルワーク”に抗うために
少し遅くなりましたが、2020年もよろしくお願いします。
年始に、自職業の置かれているマクロな環境について考える時間を持ちたいと思い書いた,ソーシャルワーカーと自認している仲間に向けてのエントリになります。約7割が先行研究等の紹介ですが、よろしければお目通しください。
1.劣化するソーシャルワーク
ソーシャルワークの社会的使命とは何か. 国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)によるソーシャル
インテーク面接において大切な3つのキホン
前回「アセスメントとはなにか?-初心者でもわかるアセスメント-」と題し、アセスメントの概念的な捉え方についてポイントを絞ってお伝えをしました。
アセスメントにおいて、必要となるのはクライアントに関する”情報”です。
(”情報”については、別エントリで記しました)
そして、クライアントに関する情報を得る方法の1つは、クライアントを前にしておこなう面接です。
本エントリでは、【話を聴くために
コロナ禍でソーシャルワーカーができることを考える
自分や大切な人たちの生活を守ることに精一杯だったこと。
日々明らかになるさまざまな事実に対して、自分にできないことばかりに目が行き罪悪感や葛藤を感じていたこと。
今の生活様式に、実は、少しホッとしていること。
でも、何かしなければ、と急き立てられたような気持ちになったこと。
掻き立てられるように動き、少し疲れたこと。
わたしは、3月の下旬から、そんなことが顔を出しては引っ込む時間を行き来して過ご
アセスメントとはなにか?-初心者でもわかるアセスメント-
先日、「すべてはアセスメントからはじまる。-アセスメントの範囲を広げよ-」というエントリを記したが、そもそも「アセスメントとは何か」ということについて詳しく言及をしていなかったことに気づいた。
専門職にとっては聞きなれた言葉であるが、本エントリでは、「アセスメントとはなにか?-初心者でもわかるアセスメント」と題し、アセスメントについて、その輪郭を浮かび上がらせてみることを試みてみたい。
===