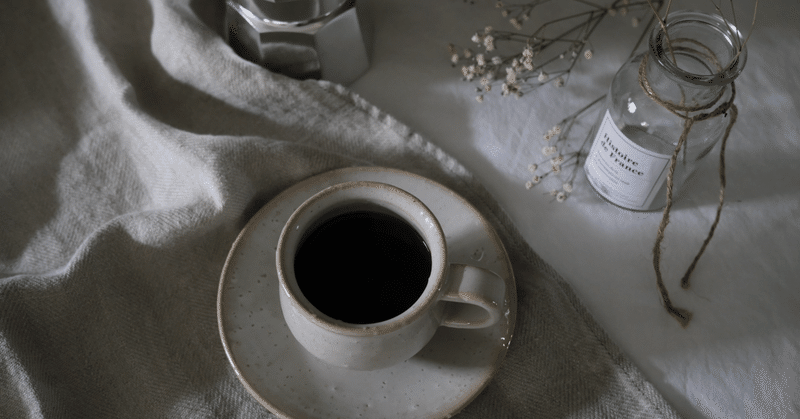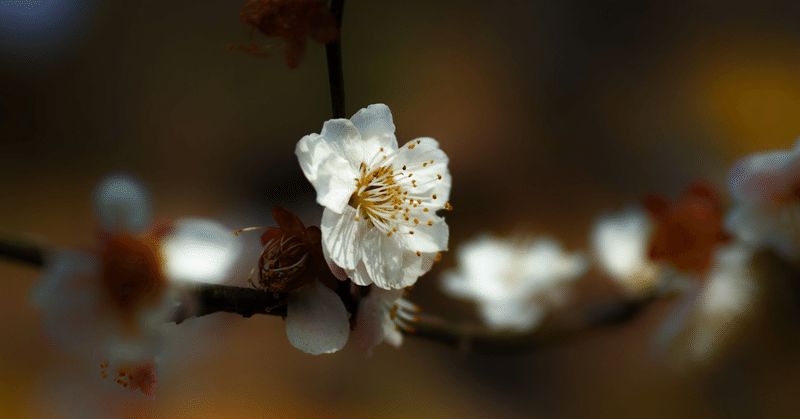#自己覚知
ナラティブアプローチへの傾倒と個人的価値観
10代から20代への移行時に生じた、経験至上主義から社会構成主義へという個人の価値の変化は、その後、現場に出たのち、ソーシャルワークの技法の一つであるナラティブアプローチへの傾倒を引き起こした。
オルタナティブストーリーに「人間の強さ」のようなものをみて、過去の自己のリカバリーのプロセスと重ね合わせたのだろう。自己のリカバリーのために他者のストーリーを摂取していることに気づくまでに、時間を要した
大学時代のバイザーからの言葉
大学の時の実習のバイザーに、「あなたがこの先この職業を選んだとしても、常にすぐ傍の道には別の選択肢があることを忘れないでね」と言われて、当時は?だったのだけれども、
今となっては、自己納得強度のある物語は自身の歩みをエンパワメントしてくれるけれど、常に仮組みにしておかないと、その物語に首を絞められるよ、ということをSVerは伝えたかったのかもしれない。それほどに当時の自分に危うさをみたのだろうな
ソーシャルワークの価値と倫理について考える-価値葛藤を補助線にして-
先般、価値と倫理について、実践における価値葛藤を材料にして言語化する機会を得たので、こちらでも書き残しておきたいと思います。
__________________________________________________
ソーシャルワークの価値と倫理、と言えば、人それぞれ、実践で出会った・得た・書籍等で読んだテキストなどに関連付いて想起されるのではないでしょうか。
私が、いつも思い出す
クライアントに対し自身が「期待するストーリー」を当て込んだ経験から学んだこと
過去、中途障害のクライアントの方から「あなたは言葉少なで、まるでわたしが話す言葉を期待しているみたいね。あなたからはわたしと同じにおいがするのよ。ね、あなた、昔、大変なおもいをされたのでしょう」と言われ、ギクリとしたことがありました。
「まるでわたしが話す言葉を期待しているみたいね」
この一言は、「わたしは、自身の想像力不足(もしくは怠慢)を埋めるために、自身の想像力の範囲内で調達できる安易な
自身の傲慢さとどう向き合い付き合うか
起業する前は独立しているワーカーに対し、修士に行く前は研究者に対して漫然とした批判をしていた。当時の記録が他者の目に触れるところに残っているので言い訳はできない。漫然さが浅はかで恥ずかしい。
でも、自分の傲慢さに気づくことができなくなることを恐れるのならば、漫然で浅はかな批判を他者の目に触れるところに残しておくのもよいのかもしれないと思う。
考えていることのログを残し外部化することは未来の自分
”信頼”の機能についての雑感
信頼の機能ケアの受け手は、極論、ケアの提供者に生殺与奪の権を握られているという前提に立つとき、受け手が「この人は信頼できる」と思えるならば、「強引に口の中にスプーンを突っ込まれるかもしれない」と思わずに済む=不安や恐れが発生する頻度を下げられるため、「信頼」は恐怖や不安を縮減する機能として働く。
受け手が「この人は信頼できる」と思える=「強引に口の中にスプーンを突っ込まれるかもしれない」と思う不
自己覚知:経験至上主義への嫌悪について
「(私の経験は特殊だからあなたには私が言うことは)わからないと思います」という拒絶のジャブを向けられたとき、過去の自分をみているようでひどくイラつくのは、”経験至上主義”は”自らの行為を以て(自覚せずとも)社会に復讐すること”と相性が良いことを少しだけ知っているからであるように思う。
経験を外部化し相対化しようとつとめることは、経験至上主義から脱する術のひとつではあるけれども、その過程で自らの動
ソーシャルワーカーズ・ハイ-助手席からハンドルを握ることを止めるために-
現場3年目の頃だろうか。
とある状態に「ソーシャルワーカーズ・ハイ」と名前をつけた。
俗に言う「困難ケース」と呼ばれるケースに出会ったとき、助手席にいたはずの自分(ソーシャルワーカー)が、運転席にいるクライアントのハンドルを奪い、握っている場面を揶揄して使っていた言葉だ。
出典は、「走るうちに苦しさが消え、高揚感がわき上がってくる」という”ランナーズハイ”をもじった。
___________
自己覚知を助ける"ストレングスファインダー"から見る私の5つの資質
前回のエントリで自己覚知について書きました。自らの内的感情と向き合うだけではなく、他者にそのプロセスを助けてもらう方法もあると記しました。今日は参考までに、ストレングスファインダーを紹介します。
ストレングスファインダー®は「人は自分の弱みを改善するよりも、自分の強みに意識を向けそれを活かすことで最大の能力を発揮する」という故ドン・クリフトンの考え方に基づいて開発されました。ストレングスファイン
なぜ、ソーシャルワーカーに自己覚知が必要なのか?
対人援助職につかれている、つきたいと思っている方でしたら必ず耳にしたことがあるだろう「自己覚知」という言葉。
この言葉自体に明確な定義は無く、簡単に言えば、「自己覚知」→「自分を知ること」→「職業的な自分をコントロールするために、自分の依って立つ価値観について知っておくこと」とでも表現しておけばおおかた間違いではないかと思います。
さて、では自分を知るためには・・・
自分がどんなときに感情