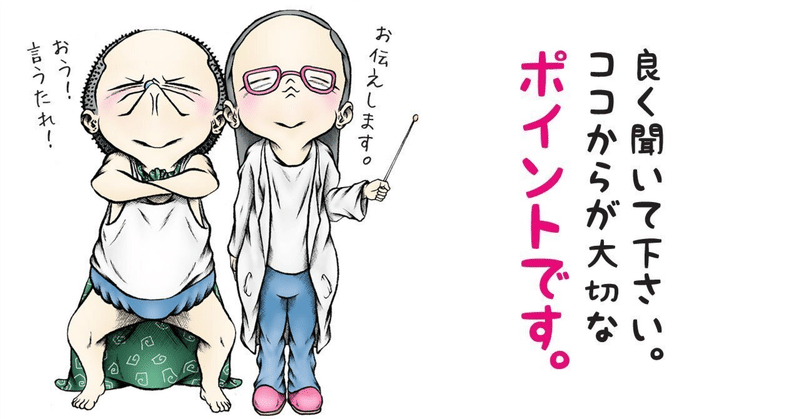
洋上風力ラウンド3以降の公募選考事務局が質すべき輸送・建設計画
以前の記事で、洋上風力の公募選考事務局には迅速性を評価できるほどの技術的な目利き能力に問題があることを指摘しました。その理由は、公募の選考事務局に風力発電の実務経験者がいない(利益相反が起きるので入れない)ためでしょう。
このまま実現性・妥当性のない迅速性評価、つまり、根拠なき早いもん勝ちがまかり通れば、風力行政の信頼は失墜し、アンチ再エネ世論が巻き起こりかねません。そんな惨状を憂い、今回の記事では、そんな選考事務局に勝手に入れ知恵させていただきます。

選考事務局が見るべき輸送・建設計画のウソ・ホント
ラウンド3以降、洋上風力の公募の選考事務局に、各事業者の輸送・建設計画のウソを見抜けるようになっていただくために、入札資料の輸送・建設計画のウソ・ホントの見分け方を解説します。
1.EPC(ゼネコン)により異なる建設機材
洋上風力発電所の建設では、どんな建設機材を使うことができるのかによって、建設工程が大きく変わります。中でもどんなSEP船・HLV船を使えるのかが鍵になります。SEP船とは、Self-Elevation Vesselの略で、下図のように、海底に脚を着けて船体を持ち上げることで波の影響を受けずにクレーンを使える特殊な作業船のことです。

HLV船は、Heavy Lifting Vesselの略で、下図のように、モノパイルを持ち上げるクレーンとそれを打ち込むハンマーを有した杭打ちのための特殊な作業船のことです。
風車の基礎据付用のHLV船を持っているゼネコンはまだ日本にありません。このような状況から、現在はSEP船を持っているゼネコンと話を詰めることが大事です。とはいえ、ゼネコンによって持っているSEP船の大きさが異なります。大きいSEP船を持っているほど、大きい風車の工事ができます。では、日本のゼネコンが持っているSEP船の大きさを見ていきましょう。
日本のSEP船
最大揚重能力2,500tのSEP船です。出力15MWの風車を想定すると、TP(トランジションピース)なしのモノパイル基礎(風車基礎で最も重いタイプ)でも吊れる大きさです。基礎や風車本体の工事に長く各地で活躍しそうです。
揚重能力1600tのSEP船です。15MW級の風車の場合、TP分離型のモノパイル基礎なら吊れそうな大きさです。基礎や風車本体の工事に各地で活躍しそうです。
揚重能力1250tのSEP船です。15MW級の風車の場合、ジャケット基礎(風車基礎で最も軽いタイプ)なら吊れるかどうかギリギリかもしれませんが、風車本体の工事には活躍しそうです。
以上から、ゼネコンによって持っているSEP船の大きさがこんなにも違うということがおわかりいただけたかと思います。それによって、読者の皆さんは、次のことにお気づきではないでしょうか。
建設機材による風車や基礎の制約
どのゼネコンが建設するかによって使えるSEP船が決まり、SEP船によって工事可能な風車や基礎のタイプが決まってしまうということは、ゼネコンやSEP船が風車や基礎タイプの選定の制約になるのではないか?
その通りです。真面目な発電事業者にとっては当たり前のことですが、いい加減な発電事業者はそんなことも知らないで、洋上風力発電という国家事業に入札しているのです。
しかも、ラウンド2の選考事務局は、そういう事業者を迅速性があると評価しました。国が金を払って選考事務局にツッコみを頼んでいるにもかかわらず、発電事業者がボケて、さらに選考事務局もボケるというのが、洋上風力行政の笑うに笑えない実態です。

ラウンド3以降の選考事務局は、同じミスを繰り返さないために、建設計画の実現性・妥当性を評価するにあたって、以下の3点を厳しくチェックいただきたいです。
建設は、どのゼネコンが担当するのか?
どのような建設機材(特にSEP船)が使われるのか?
ゼネコンもSEP船も未定の事業者は、どんなシナリオを想定しているのか?
1点目と2点目は前述したので、ここからは、まだ触れていない3点目について解説します。
ゼネコンもSEP船も未定時のシナリオ
これまでの説明をお読みいただければ、ゼネコンを決めずに建設計画どころか風車と基礎タイプの選定すらできないことがおわかりいただけたかと思います。ここからは、選考事務局の立場で、ゼネコンもSEP船も決めていないくせに、建設検討したかのようなウソをつく発電事業者への詰め将棋について考えていきましょう。
まず、その建設計画がSEP船未定でも実行可能な条件を整理しましょう。
基礎の工事:その発電事業者が選んだ基礎のタイプを据え付けられるだけのSEP船またはHLV船を確保する具体的な計画が示されていること
風車本体の工事:その発電事業者が選んだ風車機種を据え付けられるだけのSEP船を確保する具体的な計画が示されていること
上記を考えるときに参考になるのが、秋田洋上風力発電所です。
この発電所の建設工事のゼネコンは鹿島建設でした。当時、鹿島建設はSEP船を持っていませんでした。そこで、発電事業者の幹事会社である丸紅が商船三井とともに出資していた英国Seejacks社に依頼し、ZaratanというSEP船を日本船籍に変更してもらうことで、日本で使えるようにしました。
Zaratanは、揚重能力800tのSEP船です。一方、同発電所に使われた風車は、出力4.2MWの風車で、基礎タイプはTP分離型モノパイルでした。このぐらいの風車と基礎ならば、このSEP船でも工事できそうなのですが、実際には一部のモノパイル基礎の工事には起重機船が使われました。おそらく水深が深い場所でのモノパイルが意外に大きくなったのでしょう。
秋田洋上風力発電所の事例から、国内にSEP船がない場合、海外のSEP船を船籍変更して日本で使うという手があることがわかります。さらに、そのSEP船の大きさ(揚重能力)が基礎の大きさ(重さ)に対してギリギリの場合には、起重機船のようなバックアップ手段も考慮すべきだとわかります。
これを踏まえて、選考事務局には、ゼネコンもSEP船も未定の事業者に対して、次の詰め将棋を期待します。
ラウンド3以降の選考事務局が発電事業者にすべき詰め将棋
ゼネコンもSEP船も決まっていないなら、海外のSEP船を船籍変更して日本で使うことを検討しているか?どのSEP船なのか?
この事業者が選んだ風車と基礎のタイプは、そのSEP船で吊れるのか?(上記の日本のSEP船リストを目安に)
そのSEP船で基礎を吊れなかった場合、起重機船を使うか、海外のHLV船を船籍変更して日本で使うかを検討しているか?どの起重機船またはHLV船なのか?
起重機船の場合は、凪でしか使えない。有義波高0.5m以下の時期に基礎の建設工事を予定しているか?
いい加減な発電事業者なら、以上4手で詰むはずです。もしこの詰め将棋がラウンド2でなされていれば、村上胎内沖と西海江島沖の結果は変わっていたかもしれません。

2.輸送・建設スケジュールと基地港湾の関係
洋上風力の公募の選考事務局が見るべきもう一つのポイントが、各海域の輸送・建設スケジュールとと基地港湾の関係です。洋上風力ラウンド2から加わった「迅速性(早期運転開始)評価」の影響で、各海域の工事に使用される基地港湾の使用予定が極度に過密になってきたためです。
東北地方におけるR1(ラウンド1)とR2(ラウンド2)の各海域の事業者のスケジュールから、基地港湾の使用予定をプロットしたのが、下表です。

2027年の秋田港の使用予定をご覧ください。同時期にR2八峰沖とR2潟上沖の基礎工事が予定されています。SEP船が着岸できるのは飯島埠頭1箇所に限られますから、現状では2海域分の基礎工事の同時利用は至難の業です。
これを可能にするには、秋田港が大幅に拡張されてSEP船が着岸できる埠頭がもう1箇所必要です。そんなことは発電事業者もわかっているであろうに、なぜこんなカオスが起きているのでしょうか?

その理由は、R1三種沖、R2八峰沖、R2潟上沖の3海域で、基礎工事が2027年に予定されているためです。なぜ能代港を使うR1三種沖が関係するかというと、R2八峰沖の最寄りの基地港湾である能代港を、R1三種沖のグループが先に押さえていることから、R2八峰沖のグループが諦めて、秋田港の使用申請を出したためです。
このカオスを解決するには、経済産業省と国土交通省が、予め先行海域の輸送・建設スケジュールと基地港湾の使用予定を上記のように一目でわかるようにしておき、青森港と酒田港を2027年の秋ぐらいまで、秋田港のバックアップにとっておく必要があるように思います。
しかし、現実には迅速性評価のために、ラウンド3では2027年から青森港や酒田港を使うグループが選ばれるでしょう。そうなると、R2八峰沖とR2潟上沖は共倒れするリスクが高まります。
以前の記事で解説した通り、R2の他のグループは元の計画からして迅速性に根拠がありません。R2八峰沖とR2潟上沖が共倒れしたら、ラウンド2で迅速性(早期運転開始)を達成する海域は一つも残らなくなるのです。
このような惨状を避けるべく、ラウンド3以降、選考事務局には入札資料に示された輸送・建設スケジュールに対して、以下の詰め将棋を期待します。
ラウンド3以降の選考事務局が発電事業者にすべき詰め将棋
以前のラウンドの事業者と基地港湾がかぶっていないか?
北陸地方以北の日本海側の海域で、11月下旬から3月上旬に洋上工事が計画されていないか?
基礎工事と風車工事が同一年内に予定されていないか?
1点目の「以前のラウンドの事業者と基地港湾がかぶっていないか」については、ラウンド3については問題ないでしょう。
2点目の「北陸地方以北の日本海側の海域で、11月下旬から3月上旬に洋上工事が計画されていないか?」については、もし計画されていたら、前述のゼネコン・SEP船未定時の詰め将棋で詰めることができます。
3点目の「基礎工事と風車工事が同一年内に予定されていないか?」について、もし予定されていたら、そのグループに対する詰め将棋は、以下の通りです。
1.基礎工事と風車工事の基地港湾は別なのか?
R2八峰沖のように基礎工事と風車工事に別の基地港湾を確保しているならば、基礎の搬出入と風車タワーのプレアッセンブリ(事前組み立て)の同時並行も可能です。そうでなければ、次の一手へ。

2.基地港湾が同じなら、どこで風車タワーをプレアッセンブリするのか?
プレアッセンブリした風車タワーは岸壁に近くないと、SEP船が吊れません。しかし、SEP船が接岸可能な岸壁が一つしかない基地港湾で、岸壁近くでタワーをプレアッセンブリしてしまうと、基礎の搬出入ができません。
この問題を解決するには、SEP船が接岸可能な岸壁の近くでタワーをプレアッセンブリし、起重機船が接岸可能な岸壁の近くに基礎部材を置くという手も考えられなくはありません。しかし、日本の基地港湾は概して広くないので、その計画を地図に落とし込むことはできないでしょう。仮にできたとしても、前述のゼネコン・SEP船未定時の詰め将棋で、起重機船が稼働可能な時期に計画しているのかを見極める必要があります。
そこまでの思慮もなく、この質問に未定と答えるようなら、その輸送・建設計画はウソと言えます。しかし、苦し紛れに、プレアッセンブリするかどうかも未定と逃げるかもしれません。その場合は、次の一手へ。
3.プレアッセンブリなしなら、風車工事に何日見込んでいるのか?
プレアッセンブリなしということは、陸上風車と同じくタワーを1セクションずつ現場で施工することになります。SEP船の大きさ(揚重能力)にもよりますが、1本3~5日かかるでしょう。これに風車の本数とその時期の稼働可能日数の比率を掛け算すれば、プレアッセンブリなしの風車工事日数になります。(稼働可能日数の計算方法は、前回の記事を参照)
選考事務局は、回答を逃げまくる発電事業者に対して、「プレアッセンブリなしの風車工事日数で運転開始時期を再提出せよ」と詰めるべきです。ちなみに、建設機材で最もコストが高いのが日当たり傭船費千万円単位のSEP船ですから、「プレアッセンブリなしの投資計画も再提出せよ」と詰めることもできます。これで根拠なき迅速性は潰せるはずです。

この詰め将棋は、本来ラウンド2において、潟上沖のグループに対してもすべきところでした。選考事務局には、この記事を参考にして、同じミスを繰り返さないように期待します。
まとめ
今回は、「洋上風力公募選考事務局が質すべき輸送・建設計画」と題して解説しました。今回の記事もそうですが、このnoteでは、国からお金をもらって働いている選考事務局が本来持つべき知見を、誰からもお金をもらっていない風力業界の中の人が、誰に頼まれたわけでもなく、丸一日かけて執筆し、無償提供しています。
それは、選考事務局の目利き能力が低いままでは、洋上風力の公募選考の公平性・妥当性が崩れ、アンチ再エネ世論に火が点くことを心配しているからです。洋上風力は、日本のエネルギー自給率を高めるのに必要な施策です。選考事務局の皆さんには、その一翼を担っているというプライドを持って勉強していただきたいものです。
経済産業省・国土交通省の洋上風力行政の関係者に届くよう、読者の皆さんにも、この記事の拡散をよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
