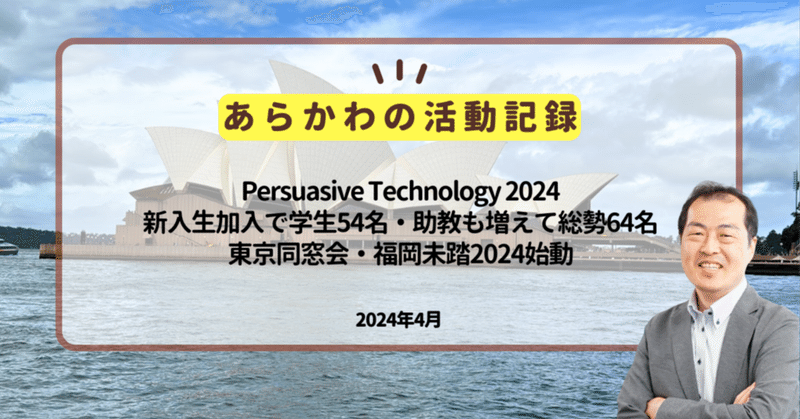
2024年4月の記録
4月は、早々にオーストラリア出張があり、その後も毎週東京に出張していたため、あっという間に過ぎ去りました。ま、いつも通りですが(笑)新年度ということこで新しい学生も加わり、九州大学での6年目がスタートしました。研究グループの学生は54名、スタッフを合わせると64名という過去最大の大きさになりました。
研究関連
Persuasive Technology 2024での発表
オーストラリア・ウーロンゴンで開催されたPersuasive Technology 2024に参加し、Poster/Demo発表を行いました。傘下のワークショップBCSS2024にもPCメンバーとして参加し、関連する研究者と交流を深めました。

デジタルウェルビーイングに向けた情報選択行動支援研究会研究会
科研費・基盤研究Aに関連する研究討論を行う研究会を九州大学・大橋キャンパスで開催しました。東京大学・鳥海先生、NAIST・諏訪先生、津田塾大学・鈴木先生、九州大学・峯先生に参加いただき、2日間、みっちりとディスカッションを行いました。発表+質疑で、一人約60分と、発表毎に白熱し、深い議論が行われる場は大変貴重です。

東京大学塚田研究室に弟子入り
PerCom2024@BiarritzのワークショップPerViehcleの招待講演者としていらしていた塚田先生と久しぶりに話したら、こちらの研究室で困っているシミュレーションソフトウェアをフルに活用されていたので、学生たちを連れて東大を訪問し、3日間滞在させてもらい、ソフトウェアの使い方を伝授してもらいました。同時に、双方の研究について紹介しあったりできてとても楽しい時間となりました。

研究室関連
19名の学生が新加入!総勢53名に
2024年は、荒川・峯・福嶋による人間情報システム研究グループに、博士1名(台湾から)、修士1年生10名、学部4年生8名、合わせて19名が新規加入しました。
Huang Jianyu助教加入
3月に博士の学位を取得したHuangを助教として迎え入れました。研究室に中国人が増えてきたこともありますが、社会人経験もあり、論文執筆能力が際立っている彼にチームを率いてもらいたいと思ってます。
新入生歓迎会
早速ですが新入生歓迎会を開催しました。今年のM1も、研究室内部からのそのまま進学が6名であるのに対して、外部(他研究室や他大学)から10名も加入しており、みんなの仲を深めるためにもこうした交流は大切にしていきたいところです。

東京同窓会
2019年に九州大学に研究室を立ち上げて、5年経過しました。途中から峯研とも合体し、現在では九州大学・大学院システム情報科学研究院でも最大の研究グループになり、この4年で51名の卒業生を輩出しています。今回、ちょうど東京で時間があったので、卒業生たちに集まろうと声をかけたら20名くらいが集まってくれました。みんな元気に社会人を頑張っていて、それでいて学生のままっという感じで、楽しいひと時でした。無事に博士を取得された石川さんにもお会いし、記念品の贈呈もできました。

講義
ICT社会基盤デザイン特論2024
デザイン思考を学びながら、ICT技術で社会問題の解決に取り組む講義、ICT社会基盤デザイン特論ですが、2024年は、デジタルIDウォレット、をテーマにしています。例年通り、山口大学の坂口講師、富士通の川高講師にサポートいただきながら、富士通やトヨタコニックアルファから特別講師をお招きして、最先端のICT技術の1つであるデジタルIDウォレットが世界をどう変えていくかについてこれから3ヶ月間考えていきます。

環境ヘルスサイエンス@慶應
毎年恒例となっている島津先生の環境ヘルスサイエンスという講義に、今年もご招待いただきました。1年生から修士学生まで100名近くの学生の前で、AIやIoTの話、行動変容やSaMDの話をさせてもらいました。偶然にも川島先生にも会えて、良き滞在となりました。

その他
福岡未踏
今年も、経産省・AKATSUKIプロジェクトに採択され、福岡県下の未踏的人材を発掘・育成するプロジェクトを実施することになりました。今年から、補助率が2/3となっており、1/3は地域で集める必要があり、営業に追われていますが、次の世代の若手クリエータのために運営陣一同頑張りたいと思います。
MBL研究会運営委員会
情報処理学会・モバイルコンピューティングと新社会システム研究会(MBL研究会)の運営委員会に参加しました。コロナ禍でオンライン化が進んだ結果、コロナ終焉後もオンラインのままとなっていましたが、やはり対面で会って話すことが重要であると再認識させられました。2回目の幹事2年目、ICMU2025の担当をメインとしながらも、研究会全体を盛り上げていければと思ってます。

研究室訪問多数
修士、博士ともに大学院の出願時期となり、ありがたいことに、今年も多くの学生から問い合わせがあってます。オンラインでの説明、研究室訪問、いつでも対応してますので、興味がある人は気軽にお問い合わせください。以下のnoteも参考にどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
