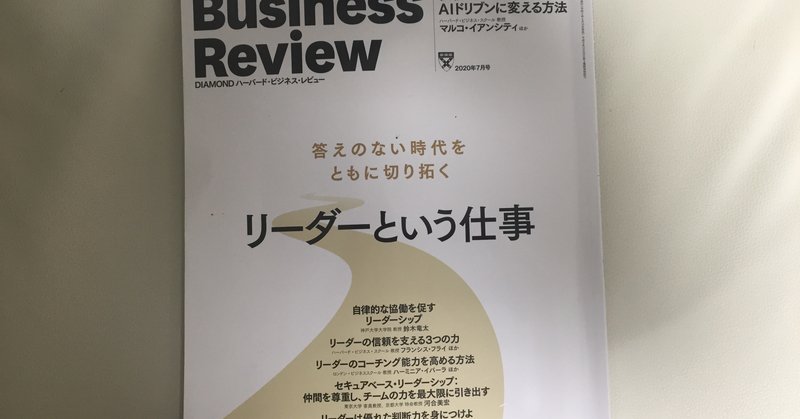
【読書録】Harvard Business Review(2020年7月号)リーダーという仕事
ハーバードビジネスレビューを定期購読するようになって久しいが、昨今様々な本が積読状態になっており、割り込んでくるため笑、本書の読書が不十分な状態が続いていた。そんな折に、ビジネススクールの同窓の方が本書の読書会を毎月開催していることを知り、上記の状況を打破すべく、まずは「参加予定」を思い切って押下。自分に軽いプレッシャーをかけ笑、読書会の日に間に合うように指定された記事を読んで参加した。
読書会では、新しく獲得した視点や知見、改めて認識を深めた点、違和感などを各自持ち寄り意見交換していく。やはり自分一人で読んで完結するのとは違い、感じたことや考えたことを自分の言葉で語ることで考えがクリスタライズされ、そこに皆さんからの新しい意見を加えてもらい、そしてそこに自分の感じたことを加えて・・・と自分の見解・仮説を進化できる様は楽しい。これからも都合をつけて参加したい。せっかくの楽しい気持ちをぐっと腹の中で消化し、自分の血肉とするため、本文では、その意見交換の一端を交え、自分の考えや思いを徒然なるままに語ってみたい。
■討議模様・読後感 さて、今回の特集は、「リーダーという仕事」だ。指定対象記事は下記の3つである。リーダーシップに関する知見もどんどんアップデートされていて、実際私が働いていても、リーダーシップは変容してきているように思う。下記の3つの記事を題材に、そんなところも考えていきたい。
1. リーダーの信頼を支える3つの力
2. セキュアベース・リーダーシップ: 仲間を尊重し、チームの力を最大限に引き出す
3. ソニーは、誰のために、何のために存在するのか
1. リーダーの信頼を支える3つの力
まず、表題の3つの力とは、オーセンティシティ、共感、ロジックのことであり、リーダーはこのトライアングルで信頼を構築することが肝要と述べている。共感やロジックについては、当たり前のように聞く言葉であるが、「オーセンティシティ」はなかなか定着していない言葉ではないだろうか。近年俄かに聞かれるようになったワードのように感じるが、日本語の辞書的な意味では、「信頼がおけること、確実性、信憑性、真正性」とされており、本書では「噓偽りのない本心で接してくれていること」という概念として説明されている。「共感」は、自分のことや自分の成功を気にかけてくれているということであり、「ロジック」は、思考と判断が理に適っているということ、といったところは敢えて言及不要であろうか。信頼が損なわれているときは、この3つのドライバーのいずれかが欠けており、どのドライバーが揺らいでいるかを突き止める必要があると主張されている。
印象に残ったのは、下記2点の議論だ。
一つは共感について。共感ができないチーム、間柄は脆いということ。Face to Faceの会議で相手が話しているのに、相槌を打たなかったり、相手の目を見なかったり、あれおかしいなと思ったら議事を取っているのではなく、内職をしていることに気づきイラついたという経験は「あるある」ではないだろうか。また、スマホばかり気にして議論に没入できていないこともあるといった自戒を込めたご意見もあった。図らずもコロナ対策でリモートワークが当たり前になった昨今、共感できる関係を築くのは一工夫いるかもしれない。名前を読んであげる、相手の意見のどんな意見をどう受け止めたのか、どう有益だったのかをさりげなく伝える、そんな言語化能力も必要かもしれない。
もう一つは、オーセンティシティについて。本書でも、多様性が高くてもインクルージョンを実現するするために積極的に働きかけなければ、多様性の低い同質のチームに遅れを取ることすらあると耳の痛い話が述べられている。然し、多様性に富むメンバー同士がそれぞれ独自の視点や経験を惜しみなく差し出せば、チームでアクセスできる知見が広がり、つけいる隙のない優位性が得られるとされている。そしてその視点や経験を惜しみなく差し出すには、オーセンティシティをもってさらけ出す各々の勇気とその勇気を当たり前のように受け入れるリーダーの度量が必要だとも述べられている。翻って、日本企業でも、ダイバーシティが提唱されて久しいが、これがまだ成果としてポジティブに語られることが少ないのは、ダイバーシティを活かす仕組みやメンタリティが不十分だからだという議論を行った。中途採用、外国籍社員の採用等を行っても、彼らが入社した会社の制度に汲汲としてアジャストすることを余儀なくされ、本音を言えず、ユニークな価値を発揮できず、結果としてすぐに辞めてしまうという悲しい出来事を目のあたりにした方も少なくないのではないか。ダイバーシティ以上にインクルージョンの方が難しいと意見して頂いたがその通りだろう。そして、その状況の打破に「オーセンティシティ」があるのだ。言うが易しだが、かつてのリーダーが明確なビジョンを打ち出すことが求められてきたが、これだけ環境変化が激しい時代では、メンバーのアイディアを活用しながら、先導し、微修正することがより大事になってきている。メンバーのアイディアを活用できる環境を率先して創っていくことがリーダーには不可避になってきた。現状での私の総括はそんなところだ。
2. セキュアベース・リーダーシップ:仲間を尊重し、チームの力を最大限に引き出す
こちらの記事は、国際機関をゼロから立ち上げ、20年に渡り牽引してきた日本人の筆者が自身の失敗談とその失敗を教訓としてどのように事業運営に活かしていったかの歴史が述べられている。
文化の違い、思想の違い、人種の違い、雇用形態の違いなどを超えてリーダーシップには万国に共通する原則があり、3つに集約されるという。
① 個人として情熱を持ち、組織として理念を持つ。
② 仲間を尊重し、その最高の力を発揮する後押しをする
③ 自分を修めてこそ、人を治め組織が発展する
筆者は①について、自負をもって推進し、目標を達成してきたが360度評価を行ったときに、その結果が目を覆うものであり、取締役会に当たる執行委員会でもリーダーとしての資質に問題ありと厳しく追及を受けたのこと。振り返ってみると、自分が目標達成のみに集中し、仲間をその手段として見ていなかったことに気付いたというのだ。この点については、痛いほど分かると過去の経験を話してくださる方もいた。
筆者はそれから②を推進したという。メンバーとの積極的な対話を行い、相手のことを思って率直に、誠意をもって良い点と改善点を両方伝える。改善すべき点を伝えるのにためらうべきでないとされている。このポイントは私たちの間で特に議論になったところだ。フィードバックは受け手が聞く気持ちがなければ意味がなく、特に厳しいフィードバックを受けたとき、そこにどれだけ向き合えるかが肝要である。人によってその厳しさを受け入れる度量も違えば、同じ人でもコンディションによって変わってくるときもあろだろう。ここがフィードバックの難しいところである。例えば、スタートアップのエンジニアの世界では、ポジティブなフィードバック仕合うことに慣れていて、文化として定着しているため、フィードバック文化が上手いこと根付いていると教えてくれる方もいた。やはり、大事なのは、メンバーとの1 on 1を通じて、受け手がどういうフィードバックを受けたいか、フィードバックを与える側は、その人にどうなって欲しくてそのために、XXの意図や目的でフィードバックをしたいんだということを伝え合い、目線合わせが肝要なのだろうということを私たちは話しながらクロージングしていった。自分が手に届く範囲のメンバーを一人一人に合わせたフィードバックを行うことがリーダーとしては問われる資質だということなのだろう。③は言わずもがな。努力をしないリーダーにメンバーがついていこうとは思わないだろう。
3. ソニーは、誰のために、何のために存在するのか
こちらはソニー代表執行役会長兼社長CEOの吉田さんのインタビュー記事。私も個人的にソニーのファンで、かつてはWALKMAN、VAIO、X-PERIAとソニー製品を好んで買ったものだ。インタビューでは、カリスマ型からパーパス型のリーダーシップへとそのスタイルを変容させ、更なる成長を目指しているという。
ただ、こちらの記事、”Something New”がなく、今更感を感じてしまったという印象を受けたというのは少し辛辣だろうか。パーパスも最近よく聞かれる言葉だが、企業理念とさほど変わらないように思うし、新しい概念ではない。ただ、概念そのものは大事だとは私も思っており、未来永劫、自分たちを取り巻く環境がどう変わろうと、自分たちの存在意義は不変であり、その組織の足腰・土台に相当するものである。環境変化が激しい時代だからこそ、一喜一憂するのではなく、自分たちの存在意義を果たそうではないかという思想は大事だろう。かつて盛田昭夫、井深有という創業者カリスマがいた時代から大きく変わり、事業領域は広がり、社員はグローバルで11万人を有するというのだから、よりこういう明文化されたもので認識を共有することは決して否定されるものではない。但し、新しい概念を提唱する際、気を付けなければいけないのは、「キーワードのオンパレード感」である。新しいキーワードが出てきては消え、何も変わらなかったという苦い経験をした方も少なくないだろう。キーワード同士がシンプルに構造が分かるようになっており、従業員の記憶に残るレベルの情報量であり、そしてそれを徹底的に従業員に浸透させるという努力が必要である。これらができていないと、従業員の間に「またか」の諦めムードが漂ってしまうのだ。そういう「あるある」をどうやって克服したのか等の生々しいインタビュー記事になっておらず、綺麗な会話に終始してしまっているのが、この記事にイマイチ物足りなさを感じてしまうのは、私がひねくれているからであろうか。
少し視点を変えて、この激変の時代の中、自分たちの普遍的な価値・存在意義を示したパーパスが更に重要になってくるというのが誤っていないという前提に立った際、これから企業経営で重要になってくるのが「パーパスに共鳴する人材をいかに獲得できるか」が重要味を帯びてくるだろう。タレントマネジメントでも理論と実践の往来で日々進化している領域であり、パーパスとセットでこのトレンドの行方をWATCHし、使いこなせるようになっていかねばならないだろう。
■最後に(まとめ)
本書以外の記事にも目を通したが、コーチングをスキルとして身に着けているリーダーも増えているといった趣旨のことが語られており、方向を明確に示して、強烈なリーダーシップで力強く組織を率いるという型より、メンバーの能力を発揮できるように環境を構築し、メンバーの意見を度量をもって受け入れ、時には伴走者にもなるという新しいリーダー像が臆することなくほぼ全ての記事で語られているように思う。誤解を恐れず言うならば「裏方のリーダーシップ」ともいえ、「謙虚さに満ちたリーダーシップ」とも言えるだろうか。
そんなリーダー像は、今、私が意識してスキルアップを図っているファシリテーションとも符合するものがある。ファシリテーションが何故重要になってきているかというと、この環境変化が激しい中で、自分一人で解を持ち得ないという謙虚な自己認識が起点としてあり、そのためにメンバーの意見・能力を存分に発揮しない手はないという認識に基づいていると私は理解している。そして、置かれている状況やメンバーのコンディションを把握することで、適切なゴール設定を行い、メンバーの心理的安全性を担保しながらいつの間にかメンバーは巻き込まれ、発散と収束を経てゴールを実現していくファシリテーションの手法は現代のリーダーシップそのものではないかという思いを持つに至る。
私自身、これといった尖ったものをもっていないことを自覚している中、昨今の新しいリーダー像、つまり謙虚に自己を捉え、時には裏方であり、ファシリテーターになり得るというリーダーシップスタイルの勃興は私自身にはチャンスだと思っており、何とかモノにしたいという思いを持つに至った。
また、本読書会が長く継続されていることも、各参加者のリーダーシップあってこそなのだろうという想像も巡らせた。会の全体運営、記事の選定、討議のファシリテーション、自身の見解の共有等、各々がリーダーシップを発揮され、運営されている。素晴らしいことである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
