
広い木陰を作るモモタマナ(クヮーディーサー)
駐車場にこの木が植えられていたら、ありがたい。枝を大きく横に広げて傘のような姿(樹形)になり、ちょうどいい木陰を作ってくれるからだ。テカテカした大きな葉が枝先に集まり、その中心にモモのタネの形に似た実がなる。
筆者は19歳で初めて沖縄を訪れた時、印象に残った樹形の木トップ3が、コバノナンヨウスギ、ガジュマル、そしてこのモモタマナだった。枝を水平面に低く長く伸ばすので、緑陰樹(木陰を作る木)に最適な面白い樹形だなぁ、と思ったものだ。
漢字で書くと「桃玉菜」(または桃玉名)。「モモ」は実の形がモモのタネに似ているから、「タマナ」は大きな葉が集まる様子がキャベツ(和名は玉菜)に似ているため、という説が有力だ。コバテイシ(枯葉手樹)の別名もあるが、こちらの由来はよく分からない。沖縄では「クヮーディーサー」の方言名もよく使われるが、この語源を沖縄の人に聞いても、みな知らないと言う。
秋に熟す果実は、味もモモに似ている。果肉は薄くて、中身の大半は大きなタネなのだが、かじるとほんのり甘いモモの風味がある。その果実を求めて、日没後にオオコウモリがよく集まって騒いでいる。だから、果期のモモタマナの木の下には、オオコウモリがかじってガサガサになった実がほぼ必ず落ちている。
筆者が沖縄移住後に知ったのは、沖縄ではモモタマナは「お墓の木」のイメージが強く、庭木には好まれないこと。本来は海岸に生える木で、流線型の果実は、海水に浮いて遠くへ流されるための形なのだが、昔ながらの集落を歩くと、確かにお墓の前によく植えられている。シーミー(清明祭)の木陰にもぴったりなのだろう。
そんなモモタマナは、拙宅の庭に生えている。海岸から持ち帰って捨てたタネが発芽し、5年で5m近い高さになった。間もなく車を覆うちょうどいい木陰ができるが、タイワンキドクガという毒蛾の毛虫がよく発生することと、アリが葉の蜜腺をなめに木によく登り、葉を通じて家にも入ってくることが難点だ。
ところで、東南アジアを旅していても、町中や海岸でときどきモモタマナを見かける。その姿は、同じ木と思えないほど背が高くて、縦長の樹形をしており、驚いた。あの低く横に広がる樹形は、台風が多い沖縄ならではの姿だったのだ。
【樹形】識名園の駐車場に植えられたモモタマナ。横に伸びる枝が、広い木陰を作ってくれる。
【葉】モモタマナは太平洋諸島〜インドに分布する半落葉高木。日本では沖縄の海岸に生え、奄美ではごく稀。葉は先が広い形で、長さ20〜35㎝と大型。
【モモタマナの実と紅葉】モモタマナの果実。葉は秋〜冬に赤く紅葉することも多い。

* * *
沖縄の木の見分け方や特徴を詳しく知りたい方は、奄美〜八重山の自生樹木全種を収録した著書『琉球の樹木』(文一総合出版)や、草花も含め1000種掲載した著書『沖縄の身近な植物図鑑』(ボーダーインク)もぜひご覧ください。
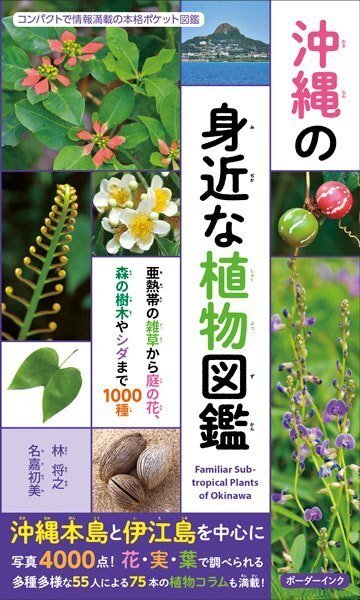
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
