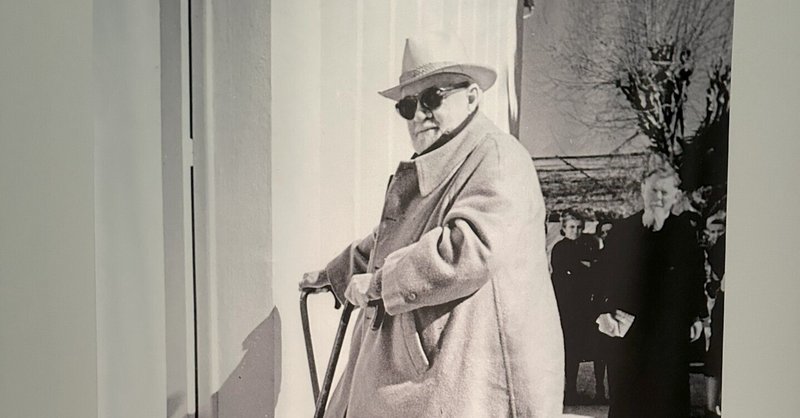
ドラクロワを模写していたというミステリー。『マティス 自由なフォルム』
国立新美術館でのマティス展。昨年、東京都美術館で回顧展があったので、またですか?という感じではある。昨年の展覧会のレビューは以下。
大きな違いは、昨年はポンピドゥー・センター、今回はニース市マティス美術館の協力ということ。後者は、切り紙絵のコレクションが充実しているそうで、それに関連した展示が多かった印象がある。日本初公開の大作《花と果実》が話題だ。

みんな大好き《ジャズ》も再登場。《ジャズ》のオリジナルは、1947年に270部限定で刷られたというので、昨年とは別のシリアルなのだろう。回顧展として、今回もツボを押さえたラインナップとなっていたし、ほどよい密度で疲れず、楽しめた。
キャリアの初期にコローの影響を受けていたのを実感できたのは、昨年の回顧展の収穫だったが、今回はセザンヌの大胆な画面構成術からの影響が、静物画の《ハーモニウムのある静物》から確かに窺えた。
キャプションによると、国立美術学校在学中、師のモローから勧められ、ルーヴルでドラクロワの模写に励んでいたという。その事実には少し驚かされた。濃密な色彩表現で真に迫るドラマ性を露にしたドラクロワと、習作期以後、多少の振れ幅はあったとはいえ、基本的には明快さやプリミティズムを志向したマティスとは、相容れないようにも思える。ドラクロワの影響をあからさまに示す作品が展示されていたわけでもない。
しかし、ドラクロワは、モロッコなど北アフリカ旅行をきっかけに色彩感覚を拡張し、《アルジェの女たち》に象徴されるようにオリエンタリズムを創作の糧とした。マティスもまた、非西洋への関心を終始持ち続けた人ではある。今回も、北インド産と思われるタペストリーやトルコまたはシリア産と推定される火鉢など、絵画内にもモチーフとして登場する彼の私物が展示されていた。
さらにマティスは1930~33年、ニューヨークに断続的に滞在した際、アフロアメリカンの演劇や音楽(ジャズだろうか?)に積極的に触れたという。後年の《クレオールの踊り子》は、マティスのオリエンタリズムが高度に純化された傑作だろう。本作は、どことなく、ジャズの帝王マイルス・デイヴィスが手掛けた絵画、なかでも『Star People』のジャケット等にも近い感じがする。


しかしながら、ドラクロワの影響を顕著に見出すのはなかなか難しく、言ってみればミステリーのようでもある。いやむしろ、ドラクロワを模写したことで、ドラクロワの偉大さを痛感し、その影から逃れるべきというアーティストとしての本能が働いたとしても不思議はない。先達に学ぶことは、吸収するだけでなく、断ち切るところまでがセットなのかもしれない。そうでなければ、アートは先を切り拓くことができないからだ。そんなことも考えさせられた。
展示の最後は、彼が監修したヴァンスのロザリオ礼拝堂である。昨年は現地映像の放映だったが、今回は内部空間を原寸大で再現していた。1日の光の移り変わりも3分に凝縮して再現しているという。すごいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
