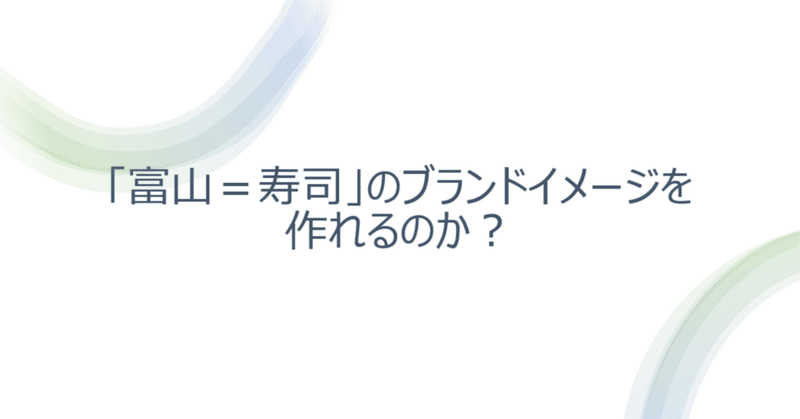
しあわせる富山 参加レポート
はじめに
10/14~15の2日間で「しあわせる。富山」というカンファレンスに参加してきました。
富山に関する様々テーマでトークセッションが開かれるのですが、富山県のブランド戦略のセッションが非常に興味深い内容でした。
本記事では、セッションの内容を独自の考察を踏まえて振り返りつつ、体験レポートという形で残しておきたいと思います。
セッションは
・ブランディング戦略PT座長:高木新平さん(モデレータ)
・ガストロノミープロデューサー:柏原光太郎さん(食のプロ)
・株式会社ウオ― 代表取締役:中川めぐみさん(魚のプロ)
の3名による公開ディスカッションという形で進められました。
3名のバックグラウンドの詳細は以下を確認ください。

「寿司と言えば、富山」地方ブランドは本当に作れるのか?
前提として、今富山県は「富山=寿司」となるようなブランド戦略を打ち出し、多くの施策を実施検討中です。
県外の人に「富山県といえばなんだと思う?」と質問したときに「あぁ、寿司が有名だよね」と多くの人が答える状態を目指すということですね。
富山県出身の私からすると、これは応援したくなる動きです。というのも
「富山県...どこだっけ?」「富山県ねぇ、何があるんだっけ?」「富山県で何すればいいかな?」
と言われた経験は星の数ほどあり、そういわれる度に忸怩たる思いをしてきたのです。
そんな富山県がこれから「富山=寿司」というブランドを作ることが本当にできるのだろうか?
セッションはこの質問をオーディエンスに問いかけるところから始まりました。反応としては「できない」が5割、「できる」が5割といった感じで、オーディエンスには富山好きな人たちが多いにもかかわらず懐疑的な様子です。
それもそのはず、寿司で有名な都道府県と言えば、北海道やお隣の石川県、もっというと東京の江戸前寿司が本場というのは多くの人の共通認識ですよね。私もその気持ちはわかります。
確かに富山県の寿司だっておいしいですが、ただおいしいだけではこの壁を突破することはできないでしょう。
ではいったい富山県の寿司の特徴って何でしょうか?
富山の寿司文化は「呑み寿司」にあり
地方のブランド戦略には2つの観点が重要と、柏原さんは語ります。
曰く、
・ローカルを徹底的に掘ること
・俯瞰的に見ること
実際に柏原さんは、富山県のブランド戦略を聞いたのち、富山県の寿司巡りツアーを通してこの2つを実施したようです。
知人からの情報を頼りに数日の間でかなりの数の寿司屋さんを巡り、ます寿司の食べ比べなどもやったとのこと。(うらやましい)
そこで柏原さんが見つけた富山の寿司文化は「呑み寿司」だったようです。はて、呑みってお酒?ん?あんまり紐づかないぞというのが最初に抱いた感想でした。
それもそのはずで、自分の場合は高校卒業後に富山県を出ているので、酒と寿司はあまり近く結びつくものではありませんでした。
しかし、富山県の街並みを見ると確かに、昔ながらの雰囲気を醸し出し、深夜までやっている寿司屋さんは存在します。(セッションを聞いた日の夜に町並みを少し歩いたのでこれはほんとです。)
特に富山駅周辺は市街地ということもあり、メインストリートから裏路地に至るまで多くの寿司屋さんがあります。
郊外の方に視点を移しても、やはり駅前には寿司居酒屋が必ず1店舗はあるような気がします。
(たまーに地元に帰ると寿司をつまみに酒をかっくらう、なんてことをやっていました。)
この雰囲気は他県にはあまり無いのかもしれません。
石川県ではどちらかというと雅な高級寿司という感じがしますし、北海道はとにかく大きいホタテやウニやカニなどを豪快に楽しむイメージがあります。江戸前寿司は、冷凍技術や流通経路が整備されていない時代に発展したもので酢や塩での締め方、つまり技術の方に特徴があります。
一方で富山県は、とれたて新鮮(方言でいうと「きときと」)な寿司が居酒屋で出てきて、それがまぁうまいわけです。
ついでにいうと、北アルプスの恩恵を受けて育った米とそこから作られたお酒も一級品です。
気取らずふらっと入ったお店でハイレベルな寿司とお酒を楽しめることこそが富山独自の寿司文化(=呑み寿司文化)なのかもしれません。こういう視点ってやはり内部からは見えづらいものなので、俯瞰って大事ですね。
新鮮さにプラスして
前述の通り、富山県の寿司の売りの一つに「新鮮さ」があります。それ実現しているのが「大陸棚」と呼ばれる富山湾独特の環境です。
以下の図の通り、少し沖に出ると一気に水深が深くなる特殊な構造をしているのです。
(余談ですが小学生の頃、「海で遊ぶときはちょっと遠くまでいくとマジで急に深くなるから死ぬほど気をつけろ」、と学校の先生によく脅されたのを思い出しました。)

より定量的にそのすごさがわかる話が、中川さんからも出ていました。
あるとき千葉にのどぐろを釣りに行き、その時は船で片道3時間、往復6時間という道のりだったそうです。
同じことを富山県でするとなんと片道15分!(驚愕の93% OFF)と言われて超びっくり。なんだったら千葉の時よりも大量でさらにびっくりなんてことがあったらしいです。
現代人にとって時間の価値は言わずもがなですが、魚の鮮度にとってもこの近場で大量に多種多様な魚が獲れるという環境は大きなアドバンテージとなりますね。
もちろんこれは一つの例を切り取っただけですが、こうして数値でみると富山の持つ「新鮮さ」の解像度がよりあがります。
一方で、そんな新鮮さがあるが故にもっと伸ばせる技術もあると柏原さんと中川さんは語ります。
江戸前寿司は酢や塩での締め方、熟成のさせ方、タレへの漬け込ませ方など加工の技術が際立っています。
(このように魚のおいしさを引き出すことを「仕込み」「仕事」とも言うようです。)
これは、前述の通り現代ほど冷凍技術や流通網が発展しない時代背景があり生まれたものです。
そのため新鮮な魚が常に手に入る富山県では加工品の需要は小さく、結果的にその点が良くも悪くも差になっているようです。
これは食のシーンだけではなく、漁の場面でも言えると中川さんは続けます。
神経締めという技術を皆さんは知っているでしょうか?
私も初めて知ったのですが、獲った魚の鮮度を保つために、特殊な器具で神経系を破壊する作業のことのようです。
職人の練度によってその質は変わってくるらしく、どうも東北地方などではこういった活け締めの技術は進んでいるようです。
これらの職人芸が富山の新鮮な富山の漁場にプラスオンされたら、鬼に金棒ですよね。
ちなみに、新鮮な魚を加工するという具体例を私は知っています。
富山県朝日町に愛馬商店という魚の加工品を扱っているお店があります。
ここで扱う商品は新鮮な魚をあえて漬けたり、干物にしているのですがこれがもう絶品なのです。
(ホタルイカの沖漬けは特にお気に入り)
ご興味ある方はぜひリンクからチェックしてみてください。(念のため言いますがステマじゃないです。)

人を呼び込む、そのためには…
寿司文化をより発展させ・外に発信するためにも職人・料理人を呼び込む必要があると高木さんが語ります。
もっというと、そのポテンシャルが既に富山にはあるらしいのです。
というのも、料理人にとっては、新鮮な素材を扱えるということはそれだけでかなり魅力的に映り、それを目的に移住するような例もあるのだとか。
(私の身近に料理人はあまりいないのですが、これ本当ですかね? もし料理人の方いれば教えてください。)
「最近はSNSの発展もあって、あっという間に情報が共有され特に魅せ方の部分はすぐに真似されちゃう。だからこそ、真似できない素材そのものの価値を活かすということはこれまで以上に重宝されるようになるのでは?」(多少意訳あり)と話されていたのが印象的でした。
柏原さんがこの意見に同調して別の例を教えてくれました。
「とあるフレンチの料理人が日本の地方でフレンチのお店を出してもあまり流行らかなった。食材もフランスから取り寄せた本格的なフレンチだったのに。でも、あるとき現地の食材を活かした料理を創作・提供するとこれが当たり、今でも大人気になっている。」
それだけ現地の食材を使ってやり切るということは大事だしそこに人々は魅力を感じるよね、と高木さんが言うと会場も納得感に包まれたようでした。
自分の経験を振り返ってみても旅行に行く際には現地の食文化に触れたいですし、地元ならではの体験を求めていることは多いです。
これはこの記事を読んでいる皆さんも同じではないでしょうか?
さらに話は進み、人を呼び込むためには何が大事かという議論になります。
この問いに対して中川さんは「言語化・見える化」と「受け入れ力」という2つのキーワードを出します。
言語化・見える化
言語化は別のセッションでもキーワードにあがったのですが、いいものを伝えるときには必ず必要なステップのようですね。これは私自身も賛成です。
SNSもあり写真や動画が各メディアを席巻していますが、「刺さる言葉」というのはいつの時代も存在しますし、そういうものは心の中に長く強く残ると思います。
また、言語化するうえで必ず対象のモノ・コトを深く考えるステップが入るはずです。このプロセスがより深い自身に繋がり、結果的に多くの人を巻き込む一大ムーブメントをにつながるのではないでしょうか?
見える化に関しては、柏原さんからまたもや興味深い話が出ました。
スペインのサン・セバスチャンという街ではオムレツのレシピをオープンソースにすることで店のレベルを上げたという例あるようです。
(オープンソースとはIT業界で使われる言葉ですが、要はレシピを公開し誰でも使えるようにした、ということです。)
通常であれば、レシピはその店の営業秘密ですがこれをあえて公開することで、その町のどの店に入っても一定品質の料理が提供されるようになったそうです。
さらに面白いのは、このように各店舗でレベルが並んでくると、どの店もその中で1等賞をとりたくなり、それぞれ改良を重ねていく正の循環が起きたということです。
私の本職はエンジニアなので断言できますが、オープンソースの発想なくして今日のようなIT業界の急速な発展はあり得なかったでしょう。
もちろんそれだけが原因ではないですが、「見える化」はそれだけの可能性、強い力があると私は思います。
情報交換という意味では日本の料理業界や漁師業界でも活発に行われていると、高木さんと小川さんが言及されていました。
「ねえねえ、今日の魚は締め方をちょっと変えてみたんだ。なんだと思う?正解はねー、血抜きのときに取るエラの本数を変えてみたでした☆彡」
みたいな会話が漁師さん同士でされているんだそうです。
(漁師の人ってそんなかわいい感じだったのか...)
口調はともかく、こういった互いに教えあうという雰囲気・土壌は本当に大事ですよね。
受け入れ力
受け入れ力に関してはどうでしょうか。
セッションの中では「変態を受け入れる勇気」というワードが出て、これが非常に印象的でした。世の中どうしても変わり者は排斥される傾向があると思いますが、「新しいブランドイメージ」を作るといった大いなる目的のためには、変わり種を受け入れる勇気・マインドが大事なんだと自分は解釈しました。
話はより具体的になって、「寿司の学校とかいいと思うんですよねー」と高木さんは語ります。
「海外では寿司職人は超人気で高年収な職業になっている。稼げる可能性があると感じることが大事で、もし富山で寿司を学んで海外に出て活躍するという流れが起きれば、『富山ドリーム』みたいなものが起きて全国各地から人が流れてくるかもしれない。」
話を聞いていて、自分はあながち夢物語ではないと思いましたし、何より面白い発想で聞き入ってしまいました。「富山=寿司」というブランドイメージは何も消費の観点だけではないのです。
これから一番伸びる富山県
セッションの最後にはオーディエンスに対してもう一度「『富山=寿司』というブランドを作ることができるのだろうか?」という質問がされました。
最初はきれいに半分に分かれていた意見も最後はほぼ全員が「できる!」と思い力強く手を挙げていました。この記事を読んだ皆様はどう思いますでしょうか?
富山県はふるさと納税額が最下位だったり、スタートアップの数も数年前まで全国最下位だったりと改善すべき点が多くある県です。しかし、それは伸びしろであり、今、この状況を変えようと知事をはじめとして多くの人が活動しています。少なくとも私はその兆しをこの2日間で肌で感じることができました。
今後も自分たちでできることを模索してチャレンジしていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
