
分別する眼と無分別の眼を共鳴させる -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(4)
中沢新一氏の『精神の考古学』を引き続き読む。今回は、第五部「跳躍(トゥガル)」を読んでみよう。「トゥガル(跳躍)」とは、「青空と太陽を見つめる光のヨーガ」である(p.175)。
「光」を「みる」、視覚のモデル
このヨーガを修することで、あるとても不思議な「光」を「みる」ことができるようになるという。
*
通常、「見る」といえば、感覚器官である「眼」に「外界」からの「光」が「刺激」として入力され、それによって神経系に電気的化学的な変化が生じる。その変化がつまり神経系において作られた外界の光についての情報であり、その情報を組み合わせて、脳が処理し「見ている」という実感を生じる・・・という説明になる。

これに対して、「トゥガル(跳躍)」の教え・哲学・思考では、視覚ということを上述のものとは別のモデルで考える。すなわち、”心臓”、”水晶管”からはじまり、”生物としての眼(いわゆる、感覚器官としての眼)”、そして”潜在眼”を生成させつつある”脈動する光の通り道”を考えるのである。

私たちは日常”生物としての眼”による分別に頼りきりで、心臓や水晶管や潜在眼のことを忘れてしまっているが、この全体性を取り戻すのが「トゥガル(跳躍)」であるといえようか。「トゥガル(跳躍)」の行では、日常ものを見るのと同じ様に”生物としての眼”で眺められている対象としての”青空”に「神経組織を通して、心の「内部空間」から」照射される「光の粒」を「投射する」。
それによって「内部空間」にあふれる「法身の運動」を”生物としての眼”の感覚、経験において「直に見る」のである。
そうすると「山や森や家々などの外界の景色が、光の粒となって粉々に飛び散っていくサンタルという状態を体験する」ことができるようになるという。これついての詳細は後述する。
+
ここで一番重要なことは、この「光をみる」行は、教え・哲学・思考とセットで行われなければならない、と言うことである。ただ見るのではく、その見える光の「意味」を思考するための教え・理論が重要なのである。
”心”の深みをひらくための
方便として「光をみる」こと
ここで前回の記事でも紹介した下記の一節が登場する。
「トゥガルのヨーガを通して自分の目の前に展開している光の運動を、それがいったい何なのかという正確な理解をもたないままに陶然と眺めているだけでは、映画を見るのとなんらかわりがない。この光のヨーガはゾクチェンの哲学と結びつくことによって、はじめて心の解放のための強力な方便(手段)となりうるのだ。」
見える光は、「心の解放」の為の「方便(手段)」として用いられてこそのものである。「金剛連鎖体」と呼ばれるような、自身の「内部空間」からの不思議な「光」を、外界に重ね合わせて「見る」ようなことができてしまうと、ふと、この光自体を、何か特別な、神的な、崇拝の対象にしたいと言うような気持ちになってくる。
見える光もまた人間の「心」(分節システム)から出てきたもの
しかし、そのような「見える光」もまた、あくまでも人間の「心」から浮かび上がったものである。この「見える光」を、何か他のものとは区別分別差別される”特別なもの”だと思ってこだわったり、欲望したり、執着したりするようでは、分別心(セム)が動くばかりで、無分別・分節の手前の”分けつつ分けない”セムニーのうごめきにふれることはできなくなってしまう。
「[…]セムとロンの哲学がトゥガルの実践の隅々にまで浸透して、一つ一つの体験に意味を与えている。その哲学がなければ、トゥガルのヨーガも[…]ただの幻覚になってしまう。」
みえるだけでもない。
哲学、思想、思考だけでもない。
みえるを、哲学、思想、思考することで解釈し意味付ける。
*
対立関係を複数重ね合わせる
みることもひとつの分別であり、言語的思考もまた別の一つの分別である。それぞれの分別は、それぞれの分け方で突っ走っていくが、複数の異なる分別をあえて二人三脚(ツイスト)させることで、もつれ、そして新たなリズムが発生することもある。
そこから立ち上がる叡智がある。
あるいは”創造性”というようなことは、対立関係と対立関係とを幾重にも重ね合わせていくことにあるのかもしれない。すなわち、対立関係にある二極を入れ替えたり逆転させることはエネルギー不足でできないとしても、複数の対立関係を重ね合わせる向きをくるくると回転させていくことは、相対的に容易なのかもしれない。
+ +

「みえる光」を解釈するための哲学・論理
「みえる」を解釈するための教え・哲学・思想とはどのようなことであったか、復習のために中沢氏がまとめてくださっている。
「心の働く全領域は「法界(ダルマダーツ)」と呼ばれる。法界には底がない。よりどころとすべき土台もない。[…]加行の中で学んだように、中観とも唯識とも違って、ゾクチェンではこの心の全領域は空でも有でもないとされる。」
人間の「心」は、経験的感覚的には、好き/嫌い、ある/ない、動く/止まる、などなど、対立する二極を区切り出してどちらかを選ぶ働きをするように感じられる。こういうモードで動いている心を”セム”(分別心)と呼ぶ。
わたしたちはしばしば、心といえば100%、この分別をするメカニズムであると想像してしまうことがあるが、これはあくまでも心のひとつのモード、働き方を極端に絞り込んだ形である。
心・法界
心の「全領域」はもっと広い。この広大な領域を「法界」とか「セムニー」という。法界を、
土台/上物(うわもの)
内部/外部
有/無
といった二項対立の一方の極の側に分別して「理解」することはできない。
法界はあらゆる分別を超えており、というか、分別するという働きが可能になる場が、法界であるといえようか。
「心=法界は自性(それ自身の性質、本質)を持たないから空であるけれど、この心=法界は一切の現象をつくりだす力を内蔵している。」
心=法界は、「空」であるけれども「一切の現象(有、一切諸法)を作りもする。こうなると「心=法界とは、無なのか、有なのか、どっちだ?」と問いたくなるところであるが、ここで気をつけて考えてみよう。
+
無であるが無でなく、有であるが有でない
分別心「セム」は、ものごとがそれぞれ他と異なるものとして分かれて存在することになっている、「ある」たちの世界だとすれば、それに対して法界(セムニー)はたがいに分けられたものごとがまだ「ない」世界である・・・と言いたくなるところであるが、ここで気をつけたいのは
有の世界 / 無の世界
||
セム / セムニー
という類の分別をするのもまた分別であるということ、つまりセムの働きであることを忘れてはいけないということである。
セムが有であるのに対して、法界・セムニーが「無である」というわけではない。
法界・セムニーでは有/無の分別が”分別されているでもなく分別されていないでもない”。
そうであるからして、空でありながら一切の現象(有)がそこで生まれつつありうごめいている、ということができる。
空である「心=法界は一切の現象をつくりだす力を内蔵している」のである。
情報
この有でもなく無でもない心(セムニー)=法界を考える上で、中沢氏が手がかりとしている用語が「情報」である。情報というのは、時間と距離を超えて「ある」と「ない」を媒介することができる。情報のもっともシンプルな定義は、現時点で目の前には存在しない何かについての”知らせ”、ということである。
「空である心が形や色を現象させるのは、心が形態についての情報(ク sku 身)を内蔵している、純粋な力によってつくられているからである。その力はリクパと呼ばれる。」
心(ここでいう心は、全領域、セムニー、法界である)が”情報を内蔵している”というのがおもしろい。
情報が「いまここにないもの」を「いまここに出現させる」ために利用するのが、いわゆる記号とか信号とかいう”それ自体ではない他のものを意味するもの”であるが、そういう意味することができる記号は、きわめて根源的な、偏りを生む傾向、あるいは偏りを生む振動、あるいは/が振動するリズムのパターンといったところから生じてくる。
いずれにせよ「リクパ」というコトバで、そういう偏りを生むリズミカルな振動のことをイメージしてみることにする(少し違うような気もするが、一つの読み方として)。


+ +
情報、そして「知性」である「振動」
このリクパ(偏りを生むリズミカルな振動?)のことを、中沢氏は「知性」であり「透明な光の振動」であると書く。
「リクパは法界に遍満している知性的な力であり、現象界へ向かう励起力(ナンワ)をはらんでいる。自性を持たない法界はほんらい空であり、どんな思念によっても汚されることのない透明な光の振動であり、その振動はあらゆる方向に向かって自在に拡大していく。」
法界は、情報を生じ・蓄えつつ、振動する。
あるいは、振動が、そのまま「情報」である。
ラジオの電波の変調波のすがたを思い描いてみるまでもなく、振動は、いくつもの座標軸上で検出可能な差異を充満させている。
+
この差異。つまり分けつつ分けず・分けるでもなく分けないでもなくの”線”が走り回り、からみあう。これが知性、ここから分別するということが可能になり始める。
+ / +
走り回る差異、分けつつ分けず・分けるでもなく分けないでもない振動たち。あとはこの振動の、どこを検知して、どう増幅して、どういう変換コードで別の分節システムに写像させるか、である。そして表層の分別心「セム」もまた、ここに根をはって、ここから生えてきて、ここに枯れ沈んでいくいくひとつの多重化した差異から差異への変換系の姿であろう。
・・・

そしてそして、振動し、情報=差異をリズミカルに生/滅させる法界は、いくつもの、無量の分別心=セムたちを発生させたり消滅させたりするが、この無量の分別を発生させたり消滅させたりするという振動そのものは「不動」である。もちろんこの不動は動きつつある不動である。
「法界の全域ではたえまない相互作用がくりかえされているが、それによって別のものに変化することがない。法界は不動なままである。しかし少しも静止していない。」
そしてこの「不動でありながら静止していない」としか言いようのない”力”が「法界」に満ちる「リクパ」なのである。
「リクパ」には、「リクパ-ではない」別のなんらかの”原因”はない。
リクパは「外からの働きをいっさい受けずに、自分に内蔵された力だけによって、法界に潜在的な拡張力を与え」ると中沢氏は書かれている(p.178)。
そしてこのリクパの振動の拡張力のことを「原初的知性(イェシェ)」と呼ぶ。
「リクパの持つ知性的な働きを特に「原初的知性(イェシェ)」と呼ぶ。この原初的知性には、形態ないし様態についての情報(ク)が含まれている。原初的知性が自身の持てるすべての潜在力を赤裸に顕現するとき、それを「法身(ダルマカーヤ)」という。」
「法身」という言葉を覚えておこう。法身、報身、応身の法身である。
振動し、情報=差異をリズミカルに生/滅させている法界から、いわばこの振動たちが共振して描き出す波紋のあれこれのパターンのように、法身が、そしてさらにいくつもの「身」が「顕現」してくる。
この法身が現象界を生み出していく。そのとき原初的知性のはらむ潜在力にたいする情報縮減がおこなわれて、さまざまな生命体(有情)とその生命体にとっての「諸世界」が形成されてくるのである。
その「法身」の波紋のあれこれのパターンたちがさらに響き合う様にして、「現象界」を生じ、さらに”生命体と、その生命にとっての環世界”とを生じる。
多世界の生/滅
こうしてご存知の通り、私たち「人間」と、人間の心、人間の心に映る不穏で不安で束の間ハッピーで、それでもやっぱりあまり楽しくないような恐ろしい深淵の上にかろうじて浮かんでいるような感じのする「世界(人間用)」もまた「形成」されてくる。そしてこの形成されつつあるものは、いつしか形成されなくなる。おそらく地球が無くなるのを待つまでもなく。

原初的知性がはらむ潜在力と、その情報を縮減することで形成される諸世界。
うち/そと、包む/包まれる
ここで中沢氏は『法界蔵』という書物の言葉を紹介されている。
その一部を引いてみよう。
「名前も価値づけも超えて、迷妄も無迷妄もすべてが大いなる広がりである原初からの空間に包摂されている。」
「現実態と可能態の諸宇宙と輪廻・涅槃する諸世界のすべては菩提心に包摂され、天空に輝く太陽さながら、構成されたものではない透明な空として 自己生成する原初的状態にひろがっていく原初の空間なのである。」
「輪廻と涅槃を支配して揺らぐことがない[…]すべてを包摂する菩提心[…]は空ではなく、空さえも超越している。[…]それは「ない」ではなく、サンサーラとニルヴァーナの全領域を包摂している。「ない」でもなく「ある」でもなく、自発的に自己組織される原初空間である。そこには極端も区別されるものもなく、実体もなく土台もなく底もない。」
諸宇宙の現実態 / 可能態
輪廻 / 涅槃
A極 / 非-A極
上物 / 土台
ある / ない
こういう私たちの経験や感覚にとって基本的な分別=二項対立たちが列挙されながら、それらがすべて「原初からの空間」に「包摂され」ていると説かれる。
そしてこの”包摂”という言葉にも注意が必要である。
この包摂は
包むもの / 包まれるもの
という容器とか袋の様なものの内/外の二項対立の一方の曲としての、”外部に対する内部としての包むもの”ではない。
セムニーは
言語では捉えられないが、
眼で見ることはできる
このような空と非-空さえ分別しない哲学から、「青空と太陽を見つめる光のヨーガであるトゥガル」が「出現してくる」と中沢氏は書く。
この徹底して二辺を離れるでも離れないでもない高い振動数の思考は「光をみつめる」行とセットになることで(「身体と生命の脈動」と共振することでp.180)、人の「心」の真実を明らかにする。
・「トゥガルは眼と神経組織を用いた特殊なヨーガの実践」である
・「トゥガルのヨーガでは[…]密教の方法とは根本的に異なって、
眼にも神経組織にもなんの操作も圧力も加え」ない
・「見開いた眼が見ている「外部空間」の青空に、神経組織を通して、心の「内部空間」からリクパの光粒が投射されることによって、「内部空間」を満たしている法身の運動を、直に「見る」体験を持つことができる[…]」
・「トゥガルでは、山や森や家々などの外界の景色が、光の粒となって粉々に飛び散っていくサンタルという状態を体験する」
・「眼は内面の心=法界にたえまなく生起している「あらわれ=現象化」のありさまを、如実に見届けることのできる器官」
・「セムニーが目前にありありとあらわれる(現前)のがトゥガル」
・「セムニーを言語で把捉することは不可能ですが、眼でそれを見ることは可能」、「原初的知性を光として見ることができる」
ここまで論じられてきたセムニー(法界)は「言語」によっては捉えることはできない(不可得)が、「眼で見る」ことは「可能」なのだというところがすごい。
セムニーのことを言語でもって説いていくと、”分別心が分別するありとあらゆる二辺のどちらでもあってどちらでもない”という表現を反復することになる。とはいえ、この論理性だけを頼りに、ありとあらゆる経験的感覚的に自動的に走り出してしまう分別を、分別しつつ分別しない状態に励起するのは、相当な意識状態になっていないとできない。あるいはそういう”相当な”意識状態は、もはや通常の言語的知性では無くなっている可能性があり、どちらかといえば「眼」と同期したものであるのかもしれない。

〜 〜
「分節と無分節の区別もまたあるでもなくないでもなく」という哲学・思考の言語による論理性で踏み込めるのは「迷妄している世界を観察して、ああこれは迷妄した世界であるとわかる」ところまでである。
この思考している状態はなお「対象把握の心作用」のうちにある、つまり主体/対象の分別がまだ効いているのである(p.183)。
これに対して「光をみる」トゥガルの行は「清浄なままのイェシェを光の形や動きとして、眼前に見ることができる」のである。
+ + +
セムニー、法界を、眼で見る
さて、ここから実際に中沢氏が「トゥガル」の行を通じて「みた」ことの報告へと話が進んでいく。もちろん何がどう見えたか、ということについては言葉できる部分はほとんど無いと思われるし、準備体操をしていない人をいきなりそこに放り込んでしまうと、恐れと不安と違和感からかえって自/他を強分別してしまって、悟りから遠ざけてしまうことにもなる。
これについて中沢氏は次のように書かれている。
「文字にして人に伝えても良いと思える部分だけを、私が理解し体験した範囲内で、私の言葉としてお伝えしようと思う。それほどにトゥガルは人間の身体と心の繊細微妙な領域のことに関わっている。」
というわけで、ここから先の話については細かく引用することはせず、概略をご紹介するにとどめたい。ご興味ある方は、ぜひ『精神の考古学』を読んでいただけると、中沢氏の意図されるところに触れることができるものと思う。
”分節と無分節が分かれるでもなく別れないでもない”に接近してみたいという私という一読者の関心から、ごくかいつまんで分別心を励起する論理を頼りに追ってみよう。
生物の眼、水晶管、光の波動でできた潜在眼、心臓
○眼を眼としてだけ扱うのではなく、眼と心臓をつなぐ神経管(これを「水晶管」と呼ぶ)に注目する。
○水晶管に「光の波動でできた潜在眼」があらわれる。この潜在眼は外界を「対象化して捉えるため」の「生物の眼」とは異なる。
○「明/暗を分別する瞳を備えた「生物の眼」は、この水晶管の「先端」にできる。この「生物の眼」によって「内部空間」と「外部空間」の区別が生じ、「外界の諸物」と見ている主体との間に距離が生じ、分離が生じ、分離されるがゆえに「欲望」が発生する。(p.187)
○しかし同時に、この「生物としての眼」は「水晶管を通じて心臓と繋がり、心臓で活動する原初的知性(イェシェ)の脈動に触れている」(p.188)
眼というと、眼球そのものや、せいぜい脳につながっている神経の束のようなことを考えてしまうが、トゥガルの行で用いられる「眼」は「眼球(生物の眼)、水晶管、光の波動でできた潜在眼、心臓」からなる系である。
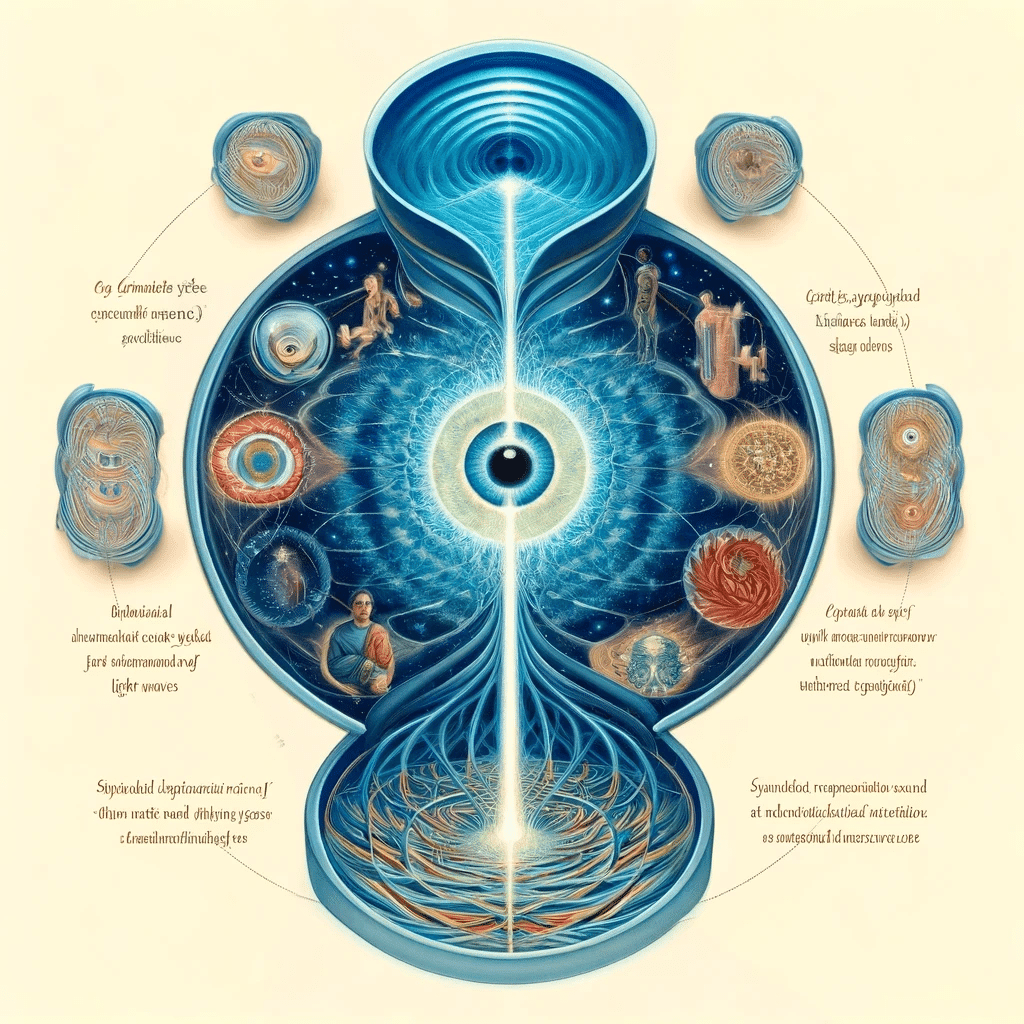
如来蔵
中沢氏はこの"生物の眼、水晶管、光の波動でできた潜在眼、心臓"からなる眼のあり方が「「如来蔵」の仕組みを端的にあらわしている」という。
「人間の心は妄想に歪められた分別心と純粋な無分別心との「混合識」としてできている。[…]眼を通して、生物は対象との間に距離を作り出し[…]それは分別の働きに力を貸して、欲望を発生させる。それと同時に同じ眼は分別を超えた無分別・無妄想なリクパに繋がってもいる。」
・妄想に歪められた分別心
・純粋な無分別心
このふたつの「混合識」としての人間の「心」
「妄想に歪められた分別心」に対応するのが「生物としての眼」である。それは内/外を分け、自/他を分け、良い/悪いを分け、あるもの/それではないものを分け、…とにかく分ける。
一方「純粋な無分別心」に対応するのは、光の通り道たる水晶管に生じる”光の波動でできた潜在眼”である。
この二つの「眼」は、二つに分かれていながら一つにつながっている。というか、ひとつの仕組みの中の二つの異なるモードといえようか。
*
このような多重化された眼によって「青空と太陽を見つめる光のヨーガ」を修する。そうすると次のようなことになる。
「セムニー(脈動する法身)はリクパの力を内蔵していて、このリクパは自発的な運動性によって常に自由な「戯れ」の状態にある。[…]リクパの運動が、水晶管をとおして瞳を通り抜けて外部空間に飛び出していく。するとそこに躍動的に動き変化していく光の粒子群が出現する。この粒子群のことを、ゾクチェンでは「ドルジェ・ルクギュー(金剛連鎖体)」という用語で呼んでいる。そのありさまを無努力・無為の状態を保ちながら青空に「見る」のである。」
脈動する法身(セムニー)は「自由」な「戯れ」の状態にある。
つまり他の何かによって受動的に対象化されて動かされているのではなく、それ自体において振動している。そこから「光の粒子群」が飛び出す。
行者の自覚的な意識は、自身の生物としての「眼」を通して、おのずから飛び出してくる光たちの様子を、「無努力・無為」に眺める。
主体の様なものが、努力して、頑張って、作為的に、はかりごとをして、見られる対象としての光を”構築”するわけではない。そのような努力、はかりごとは、
主体 / 対象
の分別を切り終わった後の話である。
*
*
ここで中沢氏は師匠の言葉を紹介する。
「青空に内光の顕現を見るこのヨーガは、じっさいにはゾクチェンの教えが人間にもたらされるのよりずっと前から行われていたと伝えられています。」
「青空に内光の顕現を見るヨーガ」は、ゾクチェンの教え・哲学を遥かに遡る。ここで中沢氏はオーストラリアの先住民に伝わる「旧石器時代的な空を見つめるヨーガ」に想いを巡らせる。人類は、もしかするとチベットにもオーストラリアにもたどり着く以前から、この「光をみる」ヨーガに魅せられていたのかもしれない。
そしておそらく、この「生物の眼」によるものと重畳して「潜在眼」による光も「見える」ということ、それを自覚せざるを得ないことと、人において言語のシステム・言語的な分節システムが発生可能であるということはリンクしている。
どちらも、分けつつ分けない、異なるが同じ、ということをもっともシンプルなアルゴリズムにして、そこから差異を開きつづ、複雑な対立関係の重ね合わせを組んでいく。
そうであるからして、この「光を見る」ことを手掛かりにして、言語の”底”を透過して降りていき、そしてまた戻ってくることも可能になる。
*
この「光を見る」ことで、「身体器官や表象能力がその人に課す様々な制限からしだいにしだいに自分を解放していく」道を、人は歩み始めるのである(『精神の考古学』p.194)。
つづく
関連記事
*
参考図書
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
