
中沢新一著『構造の奥』を読む・・・構造主義と仏教/二元論の超克/二辺を離れる
(本記事は無料で全文立ち読みできます)
中沢新一氏の2024年の新著『構造の奥 レヴィ=ストロース論』を読む。
ところで。
しばらく前からちょうど同じ中沢氏の『精神の考古学』を読んでいる途中であった。
さらにこの2年ほど取り組んでいるレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を深層意味論で読むのも途中である。
あれこれ途中でありますが、ぜんぶ同じところに向かって、というか、向かっているわけではなくすでに着いているというか、最初から居るというか。
ようは同じ話なのであります。
すでに「ここ」に「すべて」が「ある」のであるけれども、妄分別で切り刻まれた「心」では、ここ-にある-すべてを”分かる”ことはできない。
分かるを、分けるを、妄分別モードのそれではなくて、別のもっと励起された、あるいは沈潜したモードでもって実行すること。そういう叡智を「いいなあ」と思っている。
+ + +
すなわち
Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-
という具合に言葉を並べるために、ひとつひとつのΔについて、
Δ / Δ
|| ||
Δ / Δ
という四項関係が必要であり、この四項関係を分けつつ結びつけるために、一例として描くと下記のように”β”で表記した別の四項関係が四つに分かれたり図の中央に収縮したりを繰り返す脈動が必要である。

そしてこのようなかっちりと固まったかにみえる構造体を描くのも誤解を招くもので、これは脈動する規則正しい振幅が重なり合って描かれる波紋のようなものなのである。
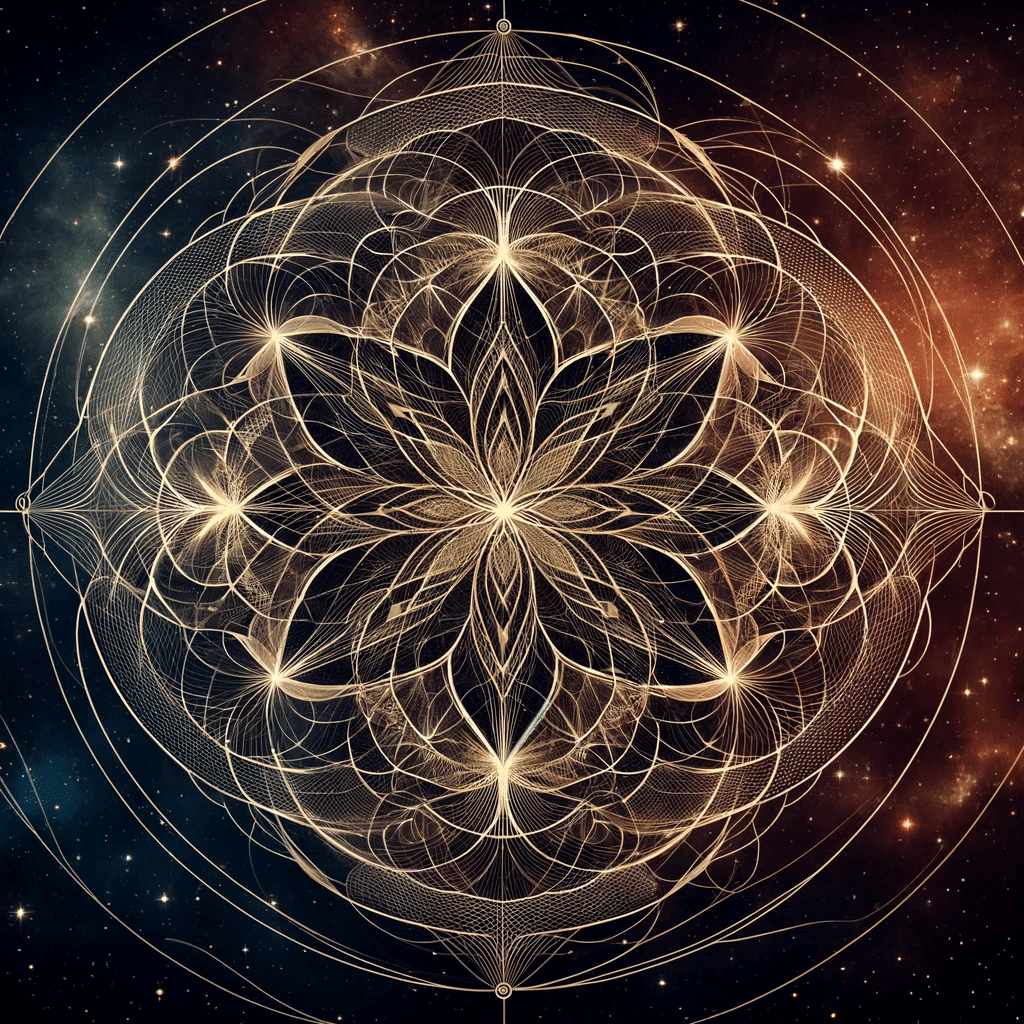
というようなことをなんとなく考えつつ、あちこち読んでいるのである。
ふと油断すると、ふっと心に浮かんでは、分けのわからない(笑)ことを分別し、選ばせようと仕向けてくるこの言葉という名の死者たちの声の無量の残響たちを共振させて、歌わせるようなことができればよいなと思うのであります。
*
*
さて『構造の奥』である。
構造には、その「奥」がある。
ある、というか、その「奥」について語り得る、というこの本のタイトルからしてなんともホッとする。「ある」なんていうのも妄分別である分けだけれども、「妄分別だからダメ!」と分別するのではなく、果敢にそのまま「これはこれでよし」と遊ばせておく。
二元論の超克
『構造の奥』の冒頭から、中沢氏によるレヴィ=ストロース「論」の核心が明らかにされる。
「構造分析が、欧米系の人類学の世界に二元論的な象徴分析として好意的に迎えられていた頃、レヴィ=ストロースはそれに対する破壊的な論文「双分組織は実在するか?」を書いた。この論文は書き方が難解であったため、その破壊性に気づく人はあまりいなかったが、二元論の超克として彼の構造主義をとらえていた私には、極めて重要な意味を持つ論文であった。」
レヴィ=ストロース氏の「構造主義」とは、「二元論の超克」の試みである、というのが中沢氏の読みである。
ここがポイントである。
レヴィ=ストロース氏が「構造」を論じるところを一見しただけでは(あまりにも一見にすぎるが)、例えば親族構造であれば
男 / 女
とか、
夫の兄弟 / 妻の姉妹
とか、
神話の分析であれば
月 / 太陽
獲物 / 狩猟者
とか、あれこれの二項対立が次から次に登場する。
こういうのが並んでくると、なにやらレヴィ=ストロースという人は、二項対立、二元的ペアをこの世界を構成する最小単位とみなし、その目録を作っているのだというように読めなくもない。そこで世界は根源的な二つの項、それ自体として端的に存在する第一項と第二項とが出会い、遭遇し、結合し、関わるところに発生するなにか、というようにとらえられているように見える。レヴィ=ストロース氏の構造分析が「二元論的な象徴分析として好意的に迎えられ」るというのもそういう感じである。
◇
しかし!
構造主義は「二元論」ではない。
構造主義は「二元論」を「超克」する。
超克というのはつまり、二元論の二元・二極を離れて、その二極が二極であるのはそもそもどうしてだろう、といったところから考え始める。
レヴィ=ストロース氏は、有名な『構造人類学』に収められた論文「双分組織は実在するか?」で、二元論の二極は所与の静的な実体(しばしばなにか究極の原因物のように誤解される)ではなくて、動的な関係を表現するための方便なんじゃないか、というようなことを書いている。要するに二元論だけで分かり尽くすことはできないよ、というのである。
このことに中沢氏は注目する。
難解すぎて破壊性に気づかれない
それにしても、破壊的なのに難解すぎて、その破壊性がバレないという中沢氏による「双分組織は実在するか?」評はおもしろい。
このこと自体が二元性の「超克」のひとつの表現のようにも思われる。
「こっちが真理だ!」、「こっちこそ正しい」、「向こうは間違いだ!」「間違いを黙らせろ!」と、正解/不正解をズバリと二つに分けて、一方に高い価値を、他方に低い価値を付与しようというのは、いかにもな二元論なのである。そういうことをしないし、読み手にもさせない。できないようにしておく。
その時「難解」であること、つまり”分かりにくい”、”分けーにくい”ということが役にたつ。二つに分けようにもどこがどうなっているのかよくわからないという、分けようにも分けようがないどちらか不可得な状態に、思考する心を励起する、いや、深く潜航させる、決まらなさに耐え続けることを強いるのである。そしてそれは叡智を研ぎ澄ますというか柔らかくしていく上で的確極まりない方法なのである。
*
大急ぎで二項をどこからか持ってきて、対立させて、片方を選んで、「ヨシ!」とやる。これが人類の分別「心」がどうしてもやりがちなアタマのツカイカタのパターンである。
ここで、二項対立を「切り分けるな」、片方を「選ぶな」と言ったのでも、二項対立を超克したことにはならない。
なぜなら、このような禁止、タブーの設定はそれ自体が
禁止じられた行い / 禁じられていない行い
をはっきりと分けて、「禁じられていない行い」の方だけを自分の領分として選び続けましょう、とする点でまだ典型的な「二元論」である。
* *
対立する二極はたがいに相手を巻き込みつつある
そういうのに対して二元論を超克する思考は、二項対立を切り分けるような切り分けないような、片方を選ぶような選ばないような、というところにじっくりと止まる。そして「この項はどこから来たのだろう?どうしてあるのだろう?そもそもあるのだろうか?」と思い始める。
「構造主義は経験主義とも機械的決定論とも異なって、人間の精神と自然に内包された知性との間に働いている「エンタングルメント(巻き込み)」の過程を、正確に取り出そうとする科学である。」
(人間の)精神 / 自然
この二項対立からなる二元論は、現代を生きる私たちの集合的無意識、阿頼耶識の底に深く刻みつけられた二極であるが、この精神と自然は、もともと別々の二つのことではない、と構造主義なら考える。
「人間の精神」と「自然に内包された知性」とは相即相入、二つでありながら一つ、一つでありながら二つにからみあっている。
このように考える点が、構造主義の近代に対する新しさであり、今日に至っても、いや、21世紀の今日であるからこそ、輝くところなのである。
中沢氏は次のように書く。
「[…]民族学は[…]先住民の世界に、神話的思考をつうじて、人間と自然を再統合しようとする豊かな知的実践が、人知れずおこなわれていたことを熟知している。構造主義はその非二元論的な知的実践の意味を明示しうる、いまのところほとんど唯一の人間科学なのである。」
あるいはここで「人間の精神(心)」の概念からして、自然と二項対立関係をなす一方の極としてではなく、自然と分かれつつつながった事柄として考え直される余地が開く。同じく中沢氏が『精神の考古学』で「セム」と「セムニー」という二つの用語で区別する、二つの「心」のあり方である。
『構造の奥』には四つの章が立てられている。
第一章 構造主義の仏教的起源
第二章 リュシアン・セバーク小伝
第三章 構造の奥
第四章 仮面の道の彼方へ
まず「構造主義の仏教的起源」という章題に目が釘付けになるので、ここから読んでみよう。
構造主義と仏教をつなぐ、というか”そもそもひとつ”ということを可能にするのが「二元論の超克」、「二辺を離れる」である。
* *
『構造の奥』20ページ、「構造主義の仏教的起源」の幕を開くのは、レヴィ=ストロース氏が『悲しき熱帯』の最後の方に記したチッタゴンの仏教寺院で受けた心象に関するテキストである。
『悲しき熱帯』で、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。
「私は実際、私が耳を傾けた師たちから、私が読んだ哲人たちから、私が訪れた社会から、西洋が自慢の種にしているあの科学からさえ、継ぎ合わせてみれば木の下での聖賢釈尊の瞑想に他ならない教えの断片以外の何を学んだというのか?」
哲学も、西洋の科学も、釈尊が瞑想したことに比べれば、その「断片」のようなものである。ここだけでレヴィ=ストロース氏が仏教というか釈迦の教えをいかにリスペクトしていたかがわかる。
中沢氏かここから、「構造主義」と「仏教」の思考の深い、そして明らかなつながりを解き明かしていく。
「仏教は人間の精神的現実の中に[…]高い次元での解放を実現しようとしてきた。人間の精神にたえまなく発生してくる煩悩は、それを拡張された精神である「空」からとらえるとき、水に描いた絵のように跡形もなく消滅していくと、仏教は教えた。煩悩は空と本性は同一であるが、空の表面効果として煩悩は生まれ、心を縛っていく。心に生まれているものを、外的な物質的条件の変化によって消すことはできない。心に生まれるものは、心自身によってしか消滅させることはできないからである。」
ここで中沢氏は、レヴィ=ストロースがルソーに傾倒していたことに注目する。レヴィ=ストロースはルソーを読みながら「苦悩する存在」としての人間、「同じ苦悩する同胞にたいする「憐れみ」」といったことにフォーカスしていく様子を中沢氏は捉えていく。
中沢氏はこの「苦悩する存在としての人間」「同じ苦悩する同胞への憐れみ」は、仏教における無明による妄念に苛まれる人間の心と、慈悲の教えに通じるものと読み解いていく。
「人生苦のおおもとは老いと死にある。老いも死も自然現象であるから、動物はそのことで苦悩しない。しかし人間は「私」という自我の意識を持つために、それが衰弱し消滅していくことを恐れる。仏陀はこの老死への恐れが、生への執着を生み、その執着が有(存在)の世界にたいする執着を生んでいくと説く。」
執着が執着を連鎖的に生み、いわゆる「十二支縁起」によって固められる輪廻(サンサーラ)の現世が出来上がる。
1)老死への恐れが、
2)生への執着を生み、
3)有)への執着を生じ、
4)「外部の事物を自己の内部に取り込もうとする欲望「取」が生じ、
5)外的対象に対する「愛(渇愛)」が生じ、
6)外界の刺激にたいする好き嫌いの感情「受」)が生じ、
7)感覚「触」が生じ、
8)強化学習された感覚器官「六処」が生じ、
9)この感覚情報を統合した名色が生じ、
10)これがさらに寄り集まって「識」(認識作用)ができる。
11)そして認識作用に基づいて行為「行」が生じ、
12)ここに無明すなわち妄想分別で固まった心が出来上がる。
この12)無明が、1)老死の分別へとフィードバックして、生死の分別をさらに際立たせ、そして2)生の区別をさらに強化し、恐れをさらに強め、という具合にぐるぐると回っていく。
無明は分別する心による。
生/死を分けて、生/滅を分けて、「生」の方だけを選び取ろうと望みつつもそのようなことができるはずもなく、そうして苦悩する。
* *
ここでもうお分かりのように、苦悩は分別心、「分けること」「/」によって生じている。
生 / 死
有 / 無
欲しい / 欲しくない
過度に欲する / 欲しない
好き / 嫌い
感覚できる / 感覚できない
↑
左辺に執着
そしてこの「生」「有」「欲しい」「好き」「感覚できる」で目覚めた意識をいっぱいに満たしつづけていられるように、分節システム=識 〜 分別心を固めて自動化していく。と、これが無明。妄念、妄想分別である。
分別するでもなくしないでもなく
分けるということの扱い、特に生/死を分別するようなときに、わたしたちの「心」は一体全体、なにをしてしまっているのかを深く見抜くことで、人は人のままこの苦悩を離れることができる。

◇
ここに二辺を離れる、二元論を超える、ということが出てくる。
「仏陀は「縁起」の理法を説いた。孤立した事物というものはなく、あらゆるものが相依相関しあいながらつながりあっていて、世界は全体運動をしている。個物は一つ一つが自律しているが、縁起によってつながっているのであるから、個物に「これ」とか「あれ」とかいう実体はない。実体と思えるものは幻影である。「私」というものさえ実体を持たない。「私」がないのだから「対象」もない。もともとないものに人間は執着して、苦しんでいるのである。」
人が執着する「あれ」「これ」。
「あれ」は「あれ-ではないものーではないもの」としてなんとなく切り分けられている影であり、「これ」も「これーではないものーではないのの」としてなんとなく切り分けられている影である。
「私」もまた、それ自体として固有の所与の本質に依って存在する「実体」ではない。「私」もまた、「私ーではないことーではないこと」をあれこれ切り分けて束にした何かである。
もちろん、実体は「ない」が、影のようななにかとしては「ある」。
あるか?ないか?
ある / ない
のどちらを選ぶか?!
という話ではない。ありとあらゆる項、二項対立の他方に対する一方としての項は、「「有り」かつ「無い」」(中沢新一『構造の奥』p.37)、「どちらのものとも決めかねる」(中沢新一『構造の奥』p.43)というのが、ことばによって言えるもっとも適当なことである。
この分けるけれども分けない、分けるような分けないような、分かれているでもなく分かれていないでもない、という状態にコトバを励起していくことが、”二項対立を分けて片方を選ぶ”式の「二元論」の思考を超える道である。
*
中沢氏は「二元論の超克」こそ「仏教と構造主義の共通した主題」であると書く。ここ!『構造の奥』第一章のもっとも重要な覚えておきたいところである。
「レヴィ=ストロースの構造主義は、主体と客体、精神と身体のような二元対立によって思考する傾向の強い西欧の伝統を否定して、二元論からの脱却を重要な主題としてきた。」
レヴィ=ストロース氏が研究の対象とした先住民社会こそ、二元論的な思考によらず、「非二元論的思考によって、現実に対処してきた」人類の思考の実践例であるという。
「私たちの社会では、生と死が分離される傾向にある。二つは別のものと考えられているのである。ところが新石器的な社会では、生と死とは分離されない。生と死は弁証法的に結びつき、二つの共存と混交の中から、現実の世界は作られている、と考えられている。」
生/死だけではない。
真/偽、美/醜、内/外、男/女などの経験的で感覚的に対立する二極は、いずれの場合も「相互に相手を「呑み込みあっている」」(中沢新一『構造の奥』p.43)
・「「有り」かつ「無い」」
・「どちらのものとも決めかねる」
・相互に相手を「呑み込みあっている」二項対立
ここでも二項対立はあり、他方ではないものとしての一方の極として、ありとあらゆる項が存在している。しかし、二つに分かれているということが、まったく同時に、二つに分かれていないということでもある、という関係になっている。分かれていないからこそ分けるのであり、分けようとするからこそ分かれていないことがあきらかになってくる。
分かれていること / 分かれていないこと
分節 / 未分節
二(多)であること / 一であること
この分別もまた、分別なのである。
ということを知って、神話の思考は、分けたり繋いだり、繋いだり分けたり、過度に分離した二項があれば、それぞれを別のところで過度に結合させたり、といったことをしては、分かれているでもなく分かれていないでもない、を実演する。
「仏教では通常の悟性がとらえている「分別」の世界と、縁起によって動いていく全体知性である「無分別」のとらえる「法界」とを、分けて考える。分別と無分別は別のものではなく、もともと一体のもので、無分別の知性がロゴスによって頽落すると分別に変貌する。」
無分別と分別さえ、「分かれているでもなく分かれていないでもない」という、徹底した非二元論を重視するのが仏教である。
「人間の心においては、この分別する二元論的知性と無分別の非二元論的知が協働して働いている。合理的思考が要求される場面では分別知のほうが優勢に働くが、夢や無意識や瞑想においては、非二元論的な縁起の知性のほうが優勢を取り戻すことになる。」
夢、無意識、瞑想、そして神話もまた、二元論と非二二元論の間を自在に往来する。
「二元論では、世界に二分割を導入する極端な概念(生/死、善/悪、恒常/無常、存在/非在など)が立てられ、それをもとにして思考が進められる。仏教はその考えを否定して、二元論的分割によらない「中道」によってのみ、現実を観察する真実の方法が得られると説く。」
中道。
つまり経験的感覚的に対立する二極のどちらか不可得、どちらでもあってどちらでもないようなことを、確固とした実体であるかのように見える二項対立の間に挟んでいく。
神話の論理は、この不可得な項(両義的媒介項)もまた、それ自体として確かに存在する実体ではなくて、別の不可得な項との対立関係の中で、他方ではないものとして分節される限りでそのポジションを得ているのだと教える。
こうして神話の語りは、最小構成で二項対立関係の対立関係の対立関係である八項関係が、八極を描くように広がったり、中央一点に収縮したりする脈動のようなことを浮かび上がらせていく。
「構造主義はこのような非二元論でつくられた文化を研究してきた。そのなかで西欧的な二元論の思考が、人類の普遍ではなく、むしろ非二元論のダイナミズムを失った変形ないし硬直化であることを、さまざまな領域で明らかにしてきた。」
二元論、たとえば
主体 / 客体
意識 / 対象
人間 / 自然
精神 / 物
といったことがまず二つに分かれている、と置いて、そこからこの両極のあいだにどういう関係を考えることができるのか、と問うのが「西欧的な二元論の思考」の基軸である。
現代産業資本主義の社会で生まれ育った私たちは、こういう二元論を”当たり前”だと思って生きるように強いられている分けであるが、こういう二元論は「人類の普遍」ではない。
「むしろ」である。むしろ、非二元論こそが、人類の心の底で動いている「思考」の根というか種というか芽である。この種、根、芽が、深く根ざしているのが「構造の奥」の、「空」であり、「心(無分別心と分別心のどちらでもあってどちらでもないような心)」、原初の「情報」が格納されたところである。
そこでいわば動きながら育ってきた分別心が、いつしかその動きを止めて、ことによると枯れ果てて「硬直化」してしまったところに、画然と固まった分別たる二元論が確立される。
しかしこの硬直化した二元論もまた、あくまでも、もっと深いところから育ち、生えてきたものだということを知ること。
それを知ることができるのが神話の論理によって動く神話的思考である。
そして中沢氏は次のように書く。
「仏教とは神話的思考の夢であり、その到達点である。」
構造主義と仏教のつながりは、レヴィ=ストロース氏という個人の中で二つの理論がくっつけられた、ということではない。構造主義も仏教も、どちらも古からの人間の「心」の奥の底を、研ぎ澄まされた意識でもって観察したところに見えてくるダイナミックな”構造”なのである。
*
この章の最後に、中沢氏はおもしろいことを書かれている。レヴィ=ストロース氏による神話分析は「人類学の現場で」行われた「無我の行」である、という。
私も、学生の頃に読んで衝撃を受けたレヴィ=ストロース氏の著書『神話と意味』から、中沢氏は次の一節を引用する。
「「私が」どうするとか「私を」こうするとかいうことはありません。私たちの各自が、ものごとの起こる交叉点のようなものです。交叉点とはまったく受身の性質のもので、何かがそこに起こるだけです。」
神話の分析は、「私」をこの「交叉点」にするということに他ならない。
分析者、分析する主体、分析する自我。
「分析してやるオレ様が!」みたいなもの。
そういう操作主体にして構成主体のような「我」は、”分析結果”の”創造者”のようなものは、神話を分析することに関しては登場しようがない。
神話は、いわばおのずから、強いて言うなら神話自身で勝手に変換を引き起こしていく。ある二項対立が別の二項対立を呼び、対立する二極のどちらでもあってどちらでもない両義的媒介項が治らざるを得ないポジションを区切りだし、その媒介項のポジションと対立関係をなすポジションを同時に区切り出すとともに、そこにまた別の何らかの二項対立関係を呼び込む。
というようなことを繰り返していく。
神話を分析すること、すなわち神話の語りから対立関係の対立関係の対立関係を解いていく動き自体が、神話論理として記述される構造の”すぐ奥”の脈動と、まったく異なることのない動き、互いに共鳴しあうひとつの動きなのである。
それこそが、二項対立が分かれつつつながる、分かれているような分かれていないような、どちらに転ぶかわからない、可能な分別についての情報だけを含んだ「空」にして「心」ということであり、そこには「我」と「我の対象」の二項対立もまたない、まだない、分けよう思えば分けられるが、まだ分かれていない。
そうであるからして、実は、私がここしばらく取り組んでいる、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を深層意味論で読んでみる、という試みも、ここでいう「無我の行」に他ならないのであり、だからこそ、いくらでも、いつまでも、飽きることなく続けられるのである。
*
ちなみに、私が『神話と意味』でたいへんな衝撃を受けたのは、それまで「意味の意味とはどういうことか??」という問いに捉えられて他のことが考えられなくなっていた私のところへ「意味とは言葉の置き換えである」という一節をもたらしてくれたことである。
「意味とは言葉の置き換えである」。この一文で、いろいろなことを動かすことができるようになったように思う。
*
関連記事
参考文献
ここから先は
¥ 510
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
