
「三枚のお札」と「かぐや姫」は同じ話?! -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(58_『神話論理3 食卓作法の起源』-9)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第58回目です。
これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
まさかそんな
「三枚のお札」と「かぐや姫」は"同じ話"である。
まさか、そんなはずないだろう!
またいい加減なことを書いている!
と憤慨される向きもあるだろうが、ところがまさか、神話論理という観点からすれば、この二つは「同じ」なのである。
もちろん、かぐや姫や実は小僧さんだったとか、山姥の正体は竹取翁だったとかいう話ではない。物語に登場する「小僧」「かぐや姫」「竹取翁」「山姥」といった”項”は、いわば関数に対する変数である。変数をいろいろと変化させたとして、その変数と変数の関係を規定する関数は同じということがある。
神話にはレヴィ=ストロース氏が「神話論理」と呼んだ論理があるように見える。すなわち神話は、二項対立関係の対立関係の対立関係を図1のように編むべく、諸項が分離しつつ結合する/結合しつつ分離するように動く動きを言葉の線形配列の上で演じさせる。
どういうことか?
レヴィ=ストロース氏の『神話論理3 食卓作法の起源』、98ページに掲載されたM391 「テンべ 転がる頭」という神話を手がかりに、考えてみよう。
この神話は日本昔話「三枚のお札」を思わせる物語である。

Δ1とΔ2の対立関係と、Δ3とΔ4の対立関係を対立させて、”Δ1はΔ3である”、Δ2はΔ4である”などと言う=置き換えることを可能にするために、β1とβ2、β3とβ4の四項関係を過度に分離したり過度に結合したり、また過度に分離したりする動きを作り出し、この動きが動き回る余白に、Δ1からΔ4が析出できる場所を開く。

山姥を呼びに行くことにした、かぐや姫
(AI生成 新作昔話:「餅に挟むもの獲ってくるわ」)
三枚のお札の物語を展開させる二項対立は、(1)小僧さんと山姥の対立と(喰われる/喰う)、三枚のお札の呪力によって小僧さんと山姥の間の過度に縮まった距離がまた大きく分離されるという(2)小僧と山姥のあいだの分離と結合の対立あるいは、近い距離と遠い距離の対立である。
「山姥と小僧さんが対立していました。」
といったのでは、これはただの世の中によくあるトラブルである。つまり図1で言えば、出来合いのΔ項を二つだけを意識の表層に立ち上らせて、あとはどっちだどっちだとやっていればよい話である。
一方、
「山姥と小僧さんの間の距離が最大値と最小値の間で振幅を描いています」
とくると、ここに神話論理が出てくる。
すなわち、β項を分離しつつ結合し結合しつつ分離し、その振幅のはざまにΔ項が収まる余地を開く動きが動き出すのである。

生/死、すなわち
生/非ー生 すなわち
非ー非ー生/非ー生
としての不老不死の概念を生成するかぐや姫
嘘をつく分離された項:「まあだだよ」
というわけで、M391 「テンべ 転がる頭」である。
昔々、狩人たちが森で大量の動物を狩って、野営した。
獲物が多すぎて、燻製をつくる台が倒れ、
獲物の頭や皮や内臓が地面に散乱した。
翌日、皆が狩に出ている間、一人の若者が残って燻製造りに励んでいた。
そこに突然、一人の見知らぬ男が現れて、獲物を調べ、
ハンモックの数を数えてから立ち去って行った。
*
若者は、仲間たちが戻ってくると、この不審な男のことを話したが、誰も気に留めようとしなかった。
*
*
夜になり、若者は改めて、隣に寝ていた父親にその話をした。
父親は不安を覚え、ハンモックを取り外し、森の中に移動して寝た。
親子が森で眠りにつくと、仲間たちの野営地の方から、夜行性の動物の鳴き声や人間のうめき声、そして骨が折れる音が聞こえてきた。動物たちの守護精霊とその眷属が、無礼を働いた人間の狩人たちを喰っていたのである。
(後半につづく)
ここだけではまだ三枚のお札感はないが、重要なところなのでよく読もう。
まず冒頭、「獲物が獲れすぎる」という話がくる。
ここだけ読むと、「ふーん、ラッキーやねえ」という感じであるが、ここは神話である。
この「獲物が獲れすぎる」は、要するに人間/動物、あるいは狩猟者/獲物、という経験的に適度に分離されつつも適度に結合された両極のあいだのバランスが失調し、過度に結合してしまっているということなのである。
神話論理とは?
神話では、下の図に示すように、Δ1/Δ2(例えば、人間/動物)、Δ3/Δ4(例えば、狩猟者/獲物)という経験的で感覚的な二項対立関係を分節するために(つまり対立関係がもともと「ない」ところから、対立関係を区切り出すために)、そして二項対立関係を二つ重ね合わせて「Δ1はΔ3である」式の置き換え=意味するということを可能にするために、β1〜β4の四つの項をΔ1〜Δ4の間に挟み込むようにして、Δの二項対立関係の対立関係を付かず離れず(分離しつつ結合し結合しつつ分離する)という中間状態に置く。このβ1〜β4をそれが分けつつ繋ぐΔ二項に対する「両義的媒介項」と呼ぶ。

どこに何番のΔを配置するか、どこに何番のβを配置するかが、実はしれっと時々変わっている。
これは理論が揺らいでいるわけではなくて(そう見えると思うけど)
そもそもこの関係自体が揺らいで動いて定まらないからである。
何かの項をどこかにおいたつもりになっても、あっという間に動きに飲み込まれて、姿を消してしまったかと思えば、不意に思いもよらないところに浮かび上がる。
いまこの神話で「獲物が獲れすぎる」ということは、経験的にははっきりと分離されつつも完全に分離されてはいない(獲物を捕えるのは簡単なことではないが、全く獲れないわけではない)という付かず離れずの関係で対立する二極が、おどろくほどピッタリと一つにくっついてしまっている状態である。
そこで例えばこの「獲物を獲れすぎる狩人」は、Δ3を人間、Δ4を動物と置くならば、β3の位置に移動あるいは置き換わっており、また「狩猟者に簡単に捉えられてしまう獲物たち」もまた、β3の位置に移動してしまっている、ということになる。経験的に対立する二Δ項が過度に結合して区別がつかないほど一つになってしまったもの。それがこの場合のβ3両義的媒介項である。
八項関係は、所与の項の二次的集合体ではない
ここで、β項もまた、個々の項が単独で単立することはできない。
β項もまた二項対立関係にある相手方との間に、β3=β3ではないものーではないものという関係をつくっている。
この神話の場合、β3獲物を獲れすぎる人間と人間に獲られすぎる獲物(仮)と対立するのは何かといえば、β-3燻製をつくる台から落ちて地面に散乱した頭や皮や内臓である。
β3獲物が燻製にされた「食べられるもの=正統派の料理」であるのに対し、β-3は「食べられないもの=砂や泥で汚れた可食部ではないもの」である。
・・・
いや、β3は”獲物”であると同時に”獲物を獲れすぎる人間”でもあるだろう、と、人間が「食べられるもの=正統派の料理」とはいかなることか、思われると思うが、この答えはすぐに出る。動物たちが、夜には人間を食べにくるのである。
経験的事実の客観的報告か、とおもったら
”獲物が獲れすぎて、燻製台が壊れて、獲物の「頭や皮や内臓」が地面に散乱した”、という、このわずかほんの一行の経験的事実の客観的報告のような一節こそ、神話論理がβ四項を一点から四方へ、四方から一点へと拡張したり収縮したりを繰り返す脈動を通じて、その振動の干渉波のパターンのようなものとしてΔ四項関係を分節している動きの一端を、はやくも浮かび上がらせている。
実におもしろい。

ちなみに、β-3と書いたものは、上の図では、β2に収まるのか、それとも他の位置に収まるのか?
この質問にすぐに答える必要はない。
どこにおいても結局はなんとかなる場合が多いのである。
すっきり収まるのはどこか、一通り八項全部がそろってからじっくり考えて当てはめれば良い。
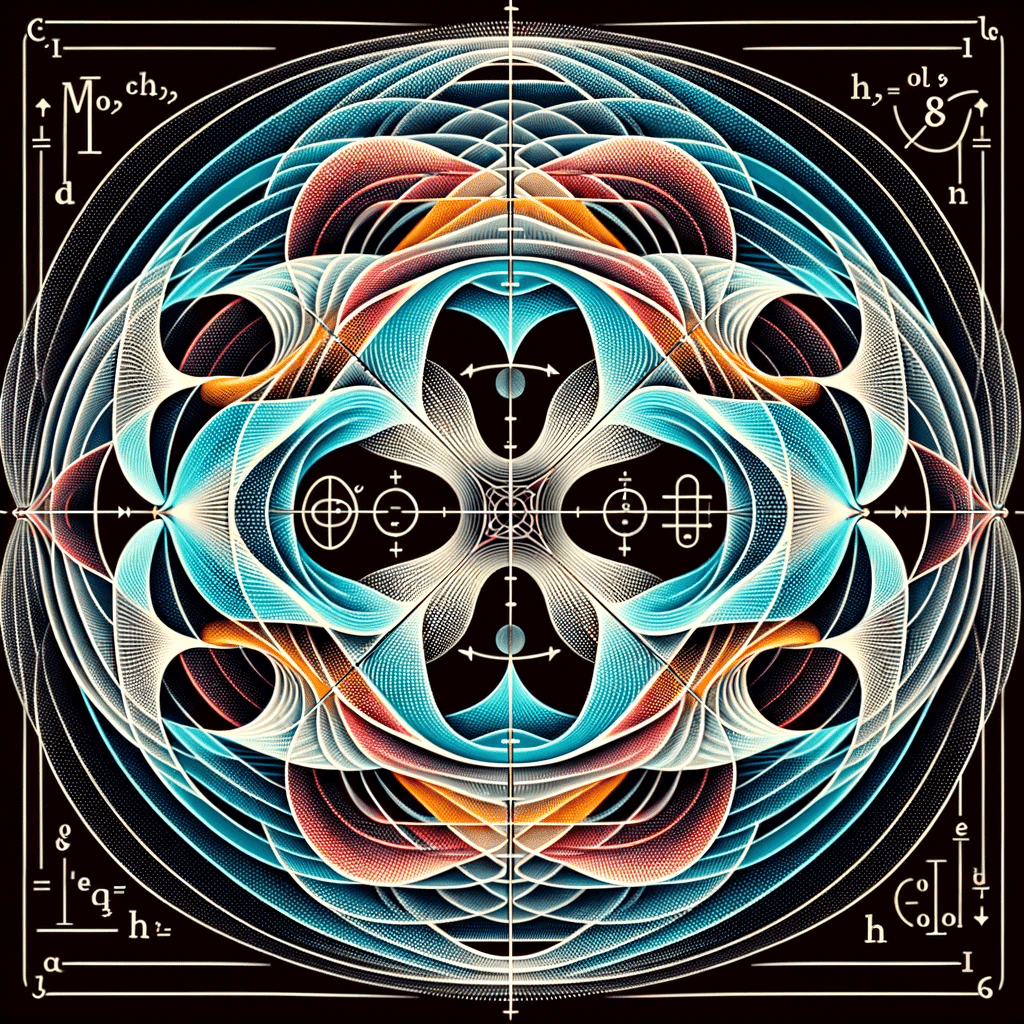
脈動状態にあるβ四項は、あらかじめ固定された所与の四項がかっちりと箱詰めして並べられたようなものではなく、浮かび上がったり沈んだり、見えなくなったり見えるようになったり、あちらに出たかと思えばこちらに出たりと、湧き立つ温泉の源泉にうかぶ泥の泡のようなものだ。
もっと言って仕舞えば、β四項は四即一一即四の関係にあるともいえるが、あまり大きくまとめてしまうと振幅を描く脈動の精妙な姿を眺めるモチベーションが下がってしまうので、程々にしておこう。
*
いずれにせよ、どの項をどこに置きましょうか、というのはΔ四項関係による意味分節が定まった後の話である。
この神話では、すぐに新たな項、β項が出現する。「獲物を調べ、ハンモックの数を数えてから立ち去って行った、一人の見知らぬ男、不審な男」である。すぐにわかるように、これは動物を獲りすぎた狩猟者=人間たちに反撃すべく偵察に訪れた、動物の守護精霊の斥候である。
おもしろいのは、この動物の守護精霊の斥候が「一人の男」つまり人間の姿をしているということである。動物なのに人間に変身している。
これは
Δ1人間/Δ2動物
という経験的二項対立の両極をショートした、中間的で両義的な媒介者である。この人間に変身した動物(の守護精霊)は、Δ1とΔ2の中間、β1の位置に収まるであろう。
そしてこの動物の守護精霊たちは、夜になると、人間の狩猟者たちが獲物である動物たちに対して行ったことと同じことを、逆にしてやり返す。
人間と動物、どちらが狩猟者でどちらが獲物か、区別ができないようになる。この経験的区別が未分節な状態から、神話は、また安定的にかっちりと分節された二項対立関係の対立関係としての”意味のある(定常的に意味分節できる)世界”を切り結ばないといけない。
そこで登場するのが、動物たちの襲撃をかわすことに成功した一組の親子である。

(AI生成)
β項は、不可分のΔ二項で置き換え得る
+ +
親子というのは、同じ一つの家族でありながら、別々の二人の人間である。
同じ一なのか、別々の二なのか?
親子、兄弟、あるいは夫婦というのは、この一だか二だか、どちらか不可得、という位置にあり、これすなわち、二人一つでβ項なのである。
+++
このβ親子は、次なるβ項に出会う。
「頭」である。
夜が明けて、父と子が野営地に戻ると、
一人の仲間の切断された頭が生きていた。
頭は、親子に向かって、自分も一緒に村に連れて帰って欲しいと懇願した。
父親は息子を先に歩かせて、自分は頭を蔓の先に縛り付けて、引きずって歩いた。息子、父、父に引かれた頭、という順番である。
*
父親は、頭を置いていきたいと考えた。
しかし頭はどうしてもついていくという。
そこで父親は一計を案じた。
父親は、「突然が痛くなった」というと
頭から離れた場所へ移動し、糞を出した。
そして父親は糞に対し、
「頭がやってきて”まだか”と尋ねたら、
”まだ腹痛が治らない”と返事をするように」と命じた。
そして自分は、糞から少し離れた場所に落とし穴を掘って、その中に隠れた。
(次の引用へつづく)
頭が転がって喋ったり、糞がしゃべったり、「食卓作法」とはかけ離れた「食事に不向きはお話」ばかりで恐縮である。
が、ここはあくまでもβ脈動の美しいマンダラ状の波紋をみたいのであって、あまり個々の「項」それ自体が「生首である」とか「糞である」とか「何かである」ということにこだわる必要はない。

そもそも「何かがなにかであるとか、ないとか」と言えるようになるのは、定常的なΔ四項関係の分節が定まった”あと”の話なのである。
今われわれがいるところはその手前というか裏側である。
+
転がる頭、喋る生首、そして「喋る糞」というのは、経験的には一つにつながっているはずのものが二つに分離してしまったという、過度な分離をあらわす項である。
さてこの頭、自分の首から下の身体とは過度に分離しながら、同族である親子とは過度に結合しようとする。
そしてその結合のための手段が、この場合は「言葉」なのである。
首は言葉によって懇願し、いやがる親子が渋々自分を運ぶように強要する。
* *
この、過度に結合しようとしてくる「頭」から分離するために、父親がとった奇策が「糞に嘘を言わせる」である。糞というのも出てくるまでは父親の一部、父親とひとつだったものである。このあたりはジャック・ラカンの『精神分析の四基本概念』を思い出してしまうところであるが、つまり糞と父親は一でありながら二であり、ニでありながら元々は一、という関係にある。
「頭」は人体の”上”に露出しており通常は外れないものであるのに対し、「糞」は人体の”下に隠されており外れる(出る)のは通常のことである。
上 / 下
隠れていない / 隠れている
通常分離しない / 通常分離する
という三つの二項対立関係に関して、頭/糞は、みごとにはっきり、綺麗に対立している。とても美しい。

文字通りの意味と、嘘
そして「頭」が、「懇願」という、結合することを要求する文字通りの言葉を発し続けるのに対して、「糞」は「まあだだよ」と嘘をつく。
つまり本当は分離しようとしている(実はもう分離してしまっている)父親と「頭」の間が、まだつながっているかのように(父親がまだそこにいるかのように)嘘をつき、その嘘によって父親と頭を分離しようとする。
結合を表明する文字通りの言葉 / 分離を隠す嘘の言葉
ここも見事に真逆になっている。
ここに
嘘をいう / 本当のことをいう
喋ることができるもの / 喋ることができないもの
この二つの二項対立に関して、対立する両極の過度な分離から過度な結合への急展開を繰り返す振幅が描かれている。
+
ここでさらにおもしろいことに、父親は「糞」をそのまま地上に転がしておいて喋らせ、自分自身は通常であれば糞を埋めるような土中の「穴」の中に入り込んで沈黙する。通常あり得るように分離した父親と糞であったが、しかしその分離後のポジションは通常とはあべこべになっている。
このくだりからふと、大江健三郎氏の『万延元年のフットボール』の冒頭を思い出す。
さて、つづきである。
繰り返そう。
個々の項が「何であるか」はとりあえず気にせず。
対立する両極が、過度な分離から過度な結合へと、急展開する。
その分離から結合へ結合から分離への振幅に注目して読んでみよう。
頭は「まだか」と呼ぶ。
それに対して糞が「まだだよ」と答える。
あまりにも時間が過ぎ、
不審に思った頭が様子をみにくると、糞が喋っている。
頭は「ふつう糞便は喋らないものだ」と文句を言いながらごろごろ転がっていたが、誤って、父親が隠れている落とし穴に落ちてしまった。
すかさず、父親は、頭を穴の中に残し、自分は外に飛び出して、
そして落とし穴を埋め、頭を閉じ込めた。
父親は急いで村へ逃げ帰った。
*
夜になると、森から、頭の遠吠えが聞こえた。
そして怒り狂った頭は、ついに穴から逃げ出し、
猛禽に変身し空を飛んで、村を襲い、最初に見つけた村人を喰らった。
ひとりの魔術師が矢でその怪鳥を射ることに成功した。
矢は猛禽の片目から入り、反対の目から貫通し、出て行った。
(終わり)
まず、冒頭の父親が仕組んだ通り、「糞」が嘘をつく。
そして「頭」は騙される。
しかしすぐに不審に思い、様子を見に転がってくる。
つまり分離されていたところがまた結合する。そうして頭は、「まだだよ」と喋っているのが父親ではなく「糞」であることに気づく。
そうして頭は「糞便は喋らないものだ」という。
”切り落とされた頭も「喋らないものだ」”とおもうが、自分のことは棚に上げておけばよいのであろう。
丁寧に見ると、
頭:身体と結合していれば喋ることができるが、分離されたら喋れない。
糞:身体と結合していても分離していても、どちらにしても喋れない。
という関係がある。
頭は
身体と分離 / 身体と結合
||
喋れない / 喋れる
という具合の四項関係に収まっているが、
糞は
身体と分離 / 身体と結合
||
喋れない / ・・・喋れる
という具合で、頭が切り結んでいる四項関係を半分ずらした関係にある。
*
ここで頭はゴロゴロ転がりながら、父親が掘って中に隠れている「穴」に落ちる。ここで頭と父親は一瞬、ひとつ同じ穴で過度に結合できたのだが、足腰丈夫で穴から飛び出せる父親は、重力の制約のなかで転がるだけの頭から、すかさず分離する。
過度な結合から、過度な分離へ。見事なβ脈動である。
**
頭が穴の中でもがいているうちに、父親は穴に頭を埋めてしまうと、村へ逃げ帰る。
頭/父親の過度な結合は、無事分離したのである。
と思ったのも束の間。
頭は「遠吠え」という古代からの遠隔コミュニケーション術を用いて父親の耳に声を響かせる、つまり音声、空気振動によって首の口と父親の耳が結合する。
過度な結合から、うまく分離したかと思えばすぐに結合する。
結合から分離へ、分離から結合へ、急展開するわけである。
結合といえば、土中の首は、空中の猛禽に変身する。そうして村人襲い食べてしまうという形で、人間の世界、人間が生きる世界と過度に結合する。
+ + +
最後の分離・分離の確定
過度に結合するとなると、神話なら、このあとすぐに、過度な分離が生じるはずである。案の定この猛禽は、呪術師の矢によって速やかに退治される。
「矢は猛禽の片目から入り、反対の目から貫通し、出て行った」
というくだりに注目しよう。
目は、右と左にひとつづつ、別々に二つある。
この別々の二つの目を、一つの矢を通して、一つにつなぐ。
二が、一に、なったまま、つまり二即一一即二のβ振動状態、両義的な第三項の位置に区切り出されたまま、この頭=猛禽は、Δ四項の分節システムである経験的で感覚的な「この世」から消える。
β項は、Δ二項対立に覆い尽くされたこの現世に対しては「第三項」として排除されるのである。
++++
この神話では、”両目を貫かれた猛禽に変身した転がって喋る頭”が退治されたことで、人間/動物、狩猟者/獲物 の経験的な定常的な付かず離れずの対立関係が回復されたとみてよいだろう。
Δ1人間/Δ2動物
|| ||
Δ3狩猟者/Δ4獲物
この安定的な四項関係、Δ四項関係を分節するために、
β1:”過度に結合した人間と動物”
→人間に変身した動物、人間を食べる動物
β2:動物でもなく獲物でもないが獲物である人間
β3:β3獲物を獲れすぎる人間と人間に獲られすぎる獲物
β4:狩猟者でもなく人間でもないが、狩猟者であり人間である
→猛禽に変身した人間の頭
この四つのβ項が、くっついたり離れたり、離れたりくっついたり、その間の距離を伸び縮みさせて振幅を描いてきたのである。

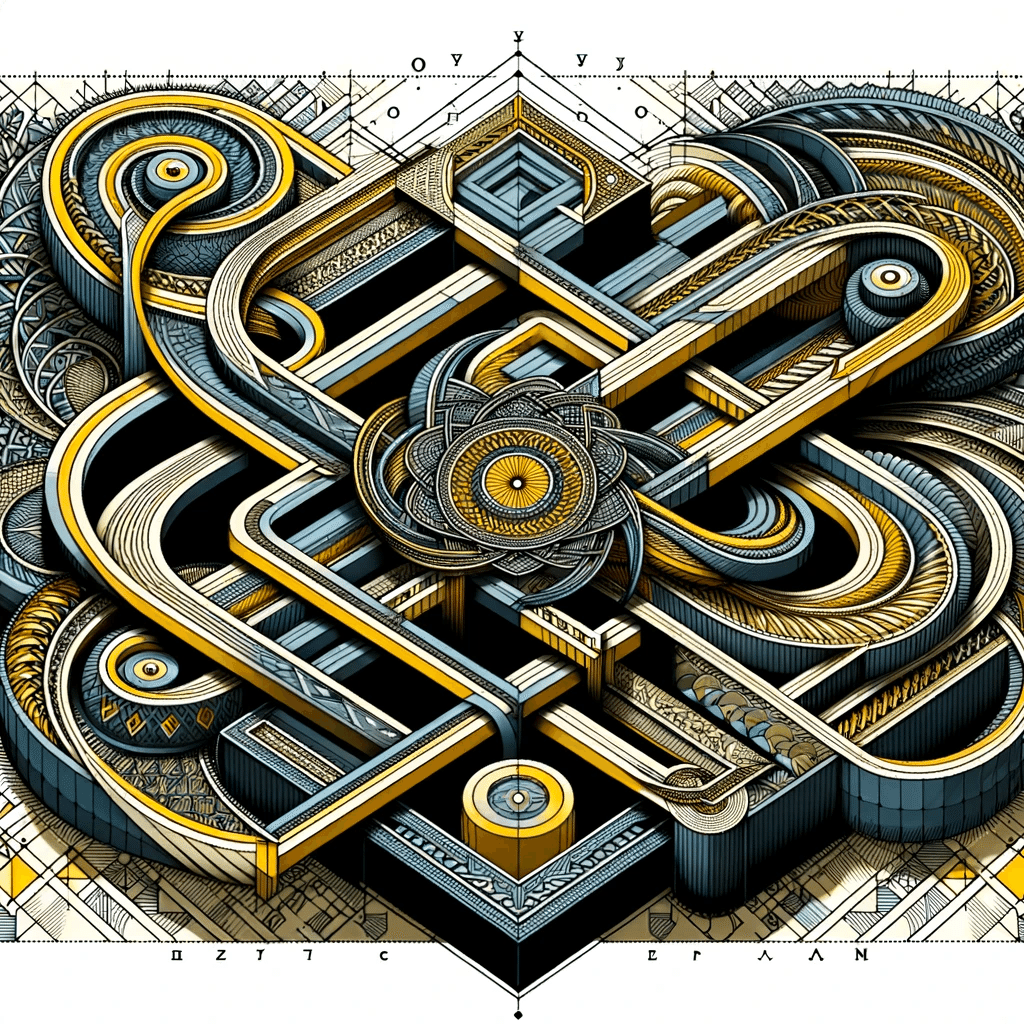
項に注目すると全く別の話だが
レヴィ=ストロース氏は、この神話に続けて、よく似た別の神話を紹介している。M255「ムンドゥルク 夏の太陽と冬の太陽の起源」という神話である。
こちらのM255神話には、「糞」は登場しないし、「頭」たちも転がらないし、二種類の太陽の起源という話は、M391の転がる頭にはまったく出てこなかった話である。
二つの神話は、登場する「項」に注目すれば、まったく別の話に見えるが、しかしやっていること、未分節と分節を分節して、定常的な四項関係を区切り出す、という操作はまったく同じである。
M255「ムンドゥルク 夏の太陽と冬の太陽の起源」を見てみよう。
ふたつの頭が棒杭の先に突き刺され、
ひとりの少年がそれを見張るよう命じられた。
少年にはシャーマンの資質があり、首たちが動いて話すのがみえた。
少年は長老に向かって「頭たちがもう直ぐ天に登りそうだ」と叫んで伝えたが、村人たちは少年が嘘をついていると思い、耳を傾けなかった。
戦士たちは、頭を赤く塗り、羽飾りをつけた。
* *
昼になると、頭たちはそれぞれ妻をつれて昇天しはじめた。
一組目の頭とその妻の夫婦は、素早く高く、上がって行った。
二組目の頭とその妻は、妻が妊娠しており、ゆっくりと登って行った。
戦士たちは頭を矢で射て落とそうとしたが、届かなかった。
見張り役だった少年の放った矢が、二番目の頭の両目にあたった。
二人の頭たちは、太陽を父とし月を母胎としてすごし、
太陽の二人の息子に変身した。
一人目の頭は、明るく、日明が良い美男の太陽になった。
二人目の頭は、雲がかかって薄暗い時の醜い太陽になった。
まず、この神話は「明るい美男の夏の太陽」と「薄暗い冬の醜い太陽」、つまり夏と冬、対立する季節における、対立する二つの太陽のあり方の起源を語るものである。
最終的に、Δ二項としてΔ1明るい美男の夏の太陽と、Δ2薄暗い冬の醜い太陽の二項対立関係を切り結ぶために、Δ3とΔ4、そしてβ1〜β4の四つのβ項を配置していくようになっているはずである。

というわけで見てみよう。まず頭が「二つ」ある。
二つセットになったものは、たいがい両義的媒介項の位置におさまることができる。この二つセットの頭をβ1と置こう。
いきなりβ1の位置に放り込んで大丈夫かと思われるかもしれないが、この二つの頭が最終的に二種類の太陽Δ1とΔ2に変身することはわかっているので、”Δ1でもありΔ2でもある”β1の位置に置くとちょうどよいだろう。
*
次に登場するβ項目は「見張りの少年(シャーマンの資質あり)」である。この見張りの少年は、β二つの頭が喋ることを聞き取れたり、後の方では矢を放って、片方の頭の両目を射抜くことができたりすると言う点で、二つの太陽と分離されながらもつながり、つながりながらも分離する関係にある。そこでこの「見張りの少年」を先ほどの二つの頭β1と対立するβ3の位置に置いてみよう。
この二つの頭は互いに会話することができるが、どうやら、見張りの少年以外の村人や部族の戦士たちは、首が喋っていることがわからないらしい。そうして少年の首の言うことを耳にしたという報告を「嘘」と決めつける。
ここに、
喋る / 喋らない
という経験的な対立二極を短絡させた「喋らないはずなのに喋る」という両義的媒介項が出てくる。この「喋らないはずなのに喋る」はβ二つの頭のことである。またこれと同じことを「聞こえないはずなのに聞こえる」と言い換えても良い。この聞こえないはずなのに聞こえるのはβ見張りの少年である。この「β喋らないはずなのに喋る(聞こえないはずなのに聞こえる)」は、β1二つの頭、β3見張りの少年のどちらともつながっており、β2かβの位置に置くことができる。
この「β喋らないはずなのに喋る(聞こえないはずなのに聞こえる)」の真逆の位置に区切り出されるのは「β喋ってるのに聞かれない(聞こえているのに聞かない)」である。これは村の長老たち、他の村人たちがやっていることである。すなわち、頭の言うことを報告した少年を嘘つきと決めつけることである。
*****
さて、ここで四つのβ項が揃い、たがいに結びつきつつ分離し、分離しつつ結びつく脈動をみせている。ここからΔ1明るい美男の夏の太陽と、Δ2薄暗い冬の醜い太陽と、あと二つ、経験的に対立する何かが区切り出されるはずである。
まず二つの頭が昇天する。
この昇天する動き、つまり地上から離れる動きによって、天/地の区別が切り広げられる。
天/地
ここでΔ3とΔ4の位置に収めるものとして、この天/地あるいは、天界/地界、言い換えると明/暗を選べそうである。
昇天する途中の頭は、まだβ項であるから「一」に見えてしまっては具合がわるく、あくまでも「二」振動して、振幅の両極を浮かび上がらせるように、だぶって見えないといけない。そこで二つの頭は、それぞれ「妻」をもつことになる。
二つの頭はそれぞれ「妻」との二項関係に入ったことで、二つの頭同士のあいだを異なるものとして分離することができるようになる。
すなわち、
素早く高く / ゆっくり(そしておそらく低く)
|| ||
矢があたらない / 矢があたる
|| ||
第一の頭夫婦 / 第二の頭夫婦
という、うまい具合の四項関係が生まれ始める。
ここで、β見張りの少年が放った矢が、ゆっくりの頭の「両目」に当たると言う話は、先ほどの神話で猛禽に変身した頭の両目が矢で貫かれるのと同じである。
* *
”両目を貫く矢”がベータ振動をΔ点に
両目は二である。
この二を一本の矢で「一つ」にする。
二を一にする。
これはすなわち、両極を区切り出す振幅を反復的に描いていた振動するβ項目を、一点に固定することである。こうして昇天した頭の夫婦はβ項のポジションから、Δ項のポジションへと移ることができる。
この移行のプロセスを、”頭が突然太陽になった”とまとめても、神話としてはなんとかなりそうな気もするが、この神話では省略しないで詳しく語る。
すなわち、「太陽を父とし月を母胎とし」て「太陽の二人の息子に変身した」というのである。それが夏の明る太陽と、冬の薄暗い太陽である。
ちょっとまてよと、夏と冬の太陽が対立する二としてあるとして、その父親である「太陽」は、いつの季節のどれなのだ、と。
この父なる太陽を実物の太陽のどこかの季節のものと同定する必要はない。というかできない。なにせこの父親である太陽は月と結婚するのである。つまりどちらも神話的に過度に結合したり分離たりするβ的な父とβ的な母であり、Δ夏冬の太陽の手前、あるいは裏側の、超感覚的世界で振幅を描いているβ太陽とβ月である。
+++++
今日の科学的な自然史からすると、まったくの夢物語のように思われるかもしれないが、神話では太陽や月の起源神話、太陽や月が未だないところからあるようになる経緯を語る場合がある。
ということで、ようやく「月」つまり、かぐや姫に接近してきたわけであるが、1万字を超えてきたので一旦休憩しましょう。
ご精読ありがとうございました。
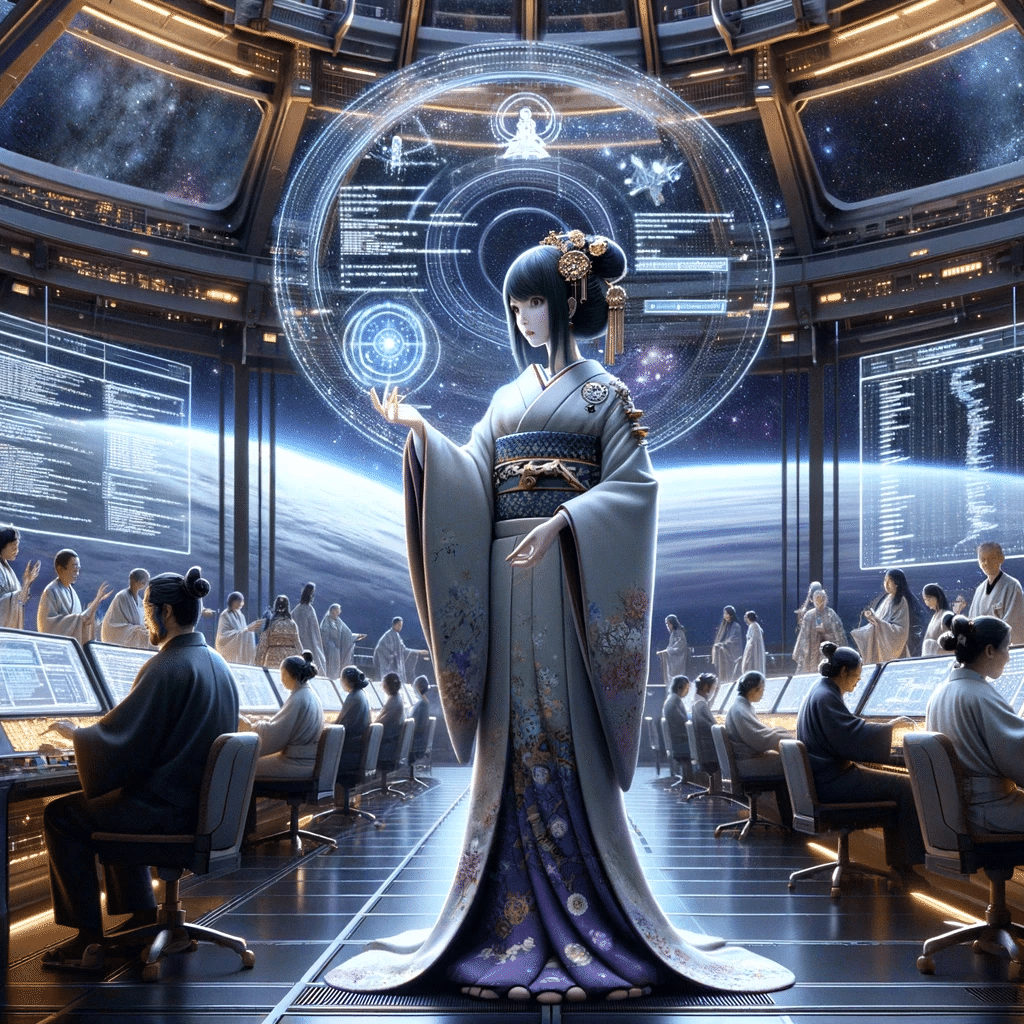
と開発者(翁)たちの不安を煽るかぐや姫
(言わずと知れたAI生成)
つづく
>つづきはこちら
関連記事
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
