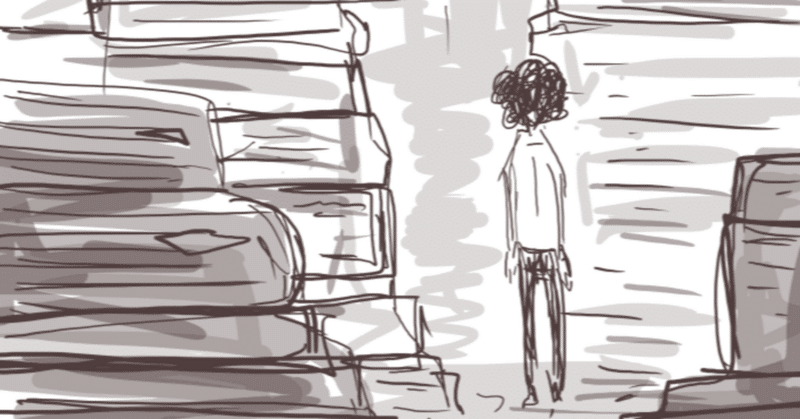
「高校3年間を通して「羅生門」しか読まなくていいのか…灘中学の国語科教師が懸念する"文学離れのマズさ"」という記事を読んで考えた。文学、ことに小説を読むということは、どういう意味を持つのか。国語の学校教育で、どの程度の位置づけであるべきか。
昨日、ヤフーニュースを見ていたら、元記事はプレジデント・オンラインだが、こういう見出しの記事があった。
「高校3年間を通して「羅生門」しか読まなくていいのか…灘中学の国語科教師が懸念する"文学離れのマズさ"」
灘中学・高校李の井上志音先生に、教育情報サイト「リセマム」編集長加藤紀子氏がインタビューした記事。
論旨に完全同意なわけではない。のだが、昨日から、この記事に触発されて、「文学、ことに小説を読むことの意味。それを国語教育の中で扱うことの意味」について、いろいろと考えている。そのことについてつらつらと書いていきたい。例によって書きながら考えていく。まだ考えははっきりはしていない。
元の記事から、私を触発した部分をまず引用してみようかな。
まずは問題意識
【井上】高校の話になりますが、2022年4月から始まった高校の新学習指導要領では、「現代の国語」で評論文を、「言語文化」で小説と詩歌、古文、漢文のすべてを扱うことになりました。しかし授業はそれぞれ週に2回ずつです。入試対策としては古文と漢文は譲れません。すると、いつ文学をやるのか、という問題が浮上します。
【加藤】古文や漢文の読み方のルールを教えるだけでも大変ですよね。
【井上】それだけで手一杯です。高2と高3の選択科目に「論理国語」と「文学国語」「国語表現」「古典探究」の4つの科目があります。多くの学校ではこれらの中から2つほど選びますが、大学入試の出題順を考えたら、日本の場合は当然、評論を読まなければなりません。もし選択科目で「論理国語」と「古典探究」を選んだ場合、高1の「言語文化」の中で、文学と言えば『羅生門』を1年間のどこかで読むのが精一杯で、高2と高3では文学は何も読まないまま卒業してしまうということが起こります。
その上で、問題のありかの核はこのあたり
【加藤】学校での文学離れは、今後どのような問題を生じさせると思われますか。
【井上】個人の体験や具体的な経験をないがしろにする風潮に拍車をかけるのではないかと危惧しています。ある人にしかわからない体験など、客観性がないのだからどうでもいい、という風潮が生まれてくるのではないかと。
個人の体験への軽視、なんでもかんでも「エピデンスは??それはあなたの感想ですよね」というひろゆき語法への懸念、ということが語られる。その点は賛成だが、ここからこの記事、ちょっと変な方にスライスしていって、最後の方はあまり賛成できなくなる。
ここから先、文学は個人が自由に読んでいい、個人の自由な感じ方が尊重されることは文学を読むことの中で培われる、ということをめぐって井上先生と加藤氏の対話が展開されていく。のだが、そこには私はすこし賛成できないのである。
「個人の体験」を通して社会、世界のありようを想像力と創造力を駆使して、言語表現で虚構としての作品世界を作るのが小説である。そこまでは井上先生や加藤氏と私の考えは共通していると思う。
しかし私はここでいう「個人体験」の個人とは、読み手の自由の話ではなく、語る作者と、何よりも小説の登場人物の「個人の視点」から世界や社会を見る、体験するという小説そのものの特性のことと考えるのである。
「個人の感じ方は自由」(人文系学問)vs「エビデンス・客観的データで語れないものは価値がない」(自然科学系学問と、そのふりをする経済学など一部の社会科学)、という対立の中に小説や文学を置いてしまうことになると思うのだな。この対談の後半部分から引用。
【加藤】子どもが「あなたはどう思ったの?」と聞かれて、自分が思ったことを答えたときに、「そういう見方もあるよね」と言われると自信や自己肯定感につながるのは、国語の授業ならではですよね。アートなども同じです。そのように、自分がどう感じたかを認めてもらえる授業って、一部の子どもたちにとってはすごく大切な居場所だと思うのですが、いかがですか。
【井上】それは大きいですね。一方で、その裏返しで、「もしも自分の感じ方がほかの人に共感されなかったらどうしよう」という恐怖心や不安感も子どもたちにはあるのかもしれません。日本ではどちらかというと、「みんなと違ってもいい」ではなくて、「みんなと一緒がいい」という感覚が根強くあります。違うことを思っていたとしても、一緒に染めてしまうようなところがありますから。
【井上】いま「文学は人生を豊かにするために読むんだよ」と言っても、「豊か」の概念がよくわからない、と言われてしまうような気がします。子どもからすると、自分はいま十分満ち足りていて幸せなんだよ、という感覚なのでしょう。 文学の価値は読んですぐにわかるものではなくて、もしかしたら10年後、あるいは20年後に、それも役に立ったのかどうかも気づかないうちに生き方に影響を与えているようなものです。文学の価値とはそのようなものだと思います。
こんな風に論を進めては、文学の価値は、絵画や音楽などの芸術と同様に「あったほうが人生は豊かだが、なくても困らない、好き嫌いの問題で、少なくとも学校教育では小説は、音楽や美術と同様の、選択的扱いで十分」という、ここ最近行われたカリキュラム変更による現在の指導要領を結果として肯定してしまうと思うのである。
だからね、そうではないのだなあ、と感じているのである、小説を読むという体験の意味というのは。僕はもっとはっきりと、小説を読むことの人間にとっての根本的意味というのが、あるはずと考えているのである。
ここからは、「えー小説なんて、人によって感じ方の違うものだし、テストにだって正解なんて数学やなんかみたいに一つに決まらないはずだし、そんなものでテストをするの変じゃーん。小説なんて、そもそも好きな人が楽しみで読むもんで、マンガとかアニメとかと同じようなことが言葉だけで書かれているっていうだけじゃーん。学校の授業でやったり、受験問題で出てくること自体、変じゃーん。出題者とたまたま同じ感想を持った人が有利って変じゃん。そんなの学校の国語でやる必要ないじゃん。やるならもっと論理的で実用的な文章の読み方書き方をきちんとならったほうが、おとなになっての社会生活でも仕事のプレゼンとかレポートとか書くのにも役に立つじゃーん。」という中学生から高校生くらいの若者に語るつもりで書いていこうかなと思うのである。
(こう書くとアニメや漫画を軽く見てるの、と取られそうだが、僕は、アニメとマンガとあとテレビドラマは文学の一ジャンルで小説と隣り合った分野だと思っている。言語だけか、絵や動画や実際の人物が動くという表現技法が著しく異なるが。国語は「言葉で」という限定がある科目なので小説を扱っているのである。ここから後で書いていく小説の役割、存在意義をマンガやアニメにテレビドラマが同じように担っている(私にとってそのように機能している)と感じている。ので、小説感想文をまとめている私の「読書家note」に、ときどきテレビドラマ感想文やアニメ映画感想文が混入しているのである。)
話は元に戻って。
小説を国語の授業で学ぶことに、どういう意味があるのかしら、についての解説を長くなりそうだが試みてみる。それは実は中学生、高校生だけじゃなくて、大人も、老人にとっても意味があることのはずなんだよな。
まず、人間というのは、わけもわからないまま、たまたま、この世界、社会に投げ込まれて生まれてくるわけだよ。偶然。この21世紀前半の日本に、君たち、僕たちが生きているのは、まったくの偶然で、もしかしたら戦国時代真っただ中に生まれたかもしれないし、狩猟採集生活をしていたアメリカ大陸の原住民として生まれていたかもしれないし、キリスト教が生まれた頃のイスラエルに生まれていたかもしれない。でもそうじゃなくて、現代の日本に生まれたわけだ。
中学生・高校生になると、漠然と今の日本がどういう社会で、どういう社会の仕組みになっているかとか、少なくとも今、いきなり隣村同士で殺し合いが起きたりするような社会でも、全員が強制的に奴隷労働させられたりする社会ではないし、何か言っただけで秘密警察に連行されて行方不明になっちゃうような社会じゃないっていうことは分かる。そして、世界で一番豊かな国ではないけれど、世界には日本よりずっと貧しくて飢えて死んだりする人がたくさんいるような国もって、日本はそこまであからさまに飢えと疫病で人がばたばた死ぬ、というような国、社会でないこともわかっている。もちろんいろいろとより隠された形で貧困とか苦しさはある社会だ、ということが漠然とわかってきている。
それから、現代の日本には、スマホや自動車やインターネットやといった技術とサービスがあって、いろんなことをわりとすぐ調べたり知ったりできたり、友達と、現実に合わなくてもいろいろ情報交換できたりするということも分かっていて、なんかそういうことを実現する科学技術が昔と比べると発達していることも分かっている。それは大昔と比較するだけじゃなく、君たちのご両親ややおじいさんおばあさんの生きてきた時代と比べてもかなり科学技術が発達した時代なのは漠然と分かっている。
ここで、国語以外の科目について、その学ぶ意味というのを遠回りだけれど、考えていく。
自分が今生きている日本の現代が、どういう時代と社会なのかは、ニュースやテレビのバラエティとかYouTube動画でときどき見る「他の国」との比較で、なんとなくわかる。「同じ今の時代の、他の国との比較」だね。
それから、今の時代を過去と比較することでもわかる。テレビドラマや映画や歴史解説YouTube動画なんかで見る、戦国時代とか幕末とか、この前あったらしい戦争の時代とかと較べると分かる。昭和の時代のドラマなんかでも分かる。
今の他の国との比較でわかる、というのを「学校の科目」としてまとめたのが「地理」で、昔との比較で考えられるようにまとめたのが「歴史」と、ざっくり分けられる。外国の歴史は「地理と歴史」合わせて考えないとわからなくなるよね。
そして、その結果として今の社会がどういう仕組みになっているのかをまとめた科目が「公民とか、現代社会」とかいうやつだ。政治や経済についてのニュース、意味はよくわからないけれどいろいろややこしい仕組みになっているらしいことは、分かる。
「社会」という科目はそうやって、今の自分が生きている時代と社会を、いくつかの角度から知ることが出来るように作られているわけだ。
で、その時代の今の暮らしを作っている、いろんな科学技術や、例えば医療や、それから食べ物を作ったり捕獲したりする農業や漁業や、様々な移動手段、自動車や飛行機が動く仕組みや、通信やインターネットやカーナビや、天気予報だって結構当たるし、地震がおきると揺れる直前に警報が鳴ったりする。そういういろんなものを動かすには、たいていなんか電気が使われている。それ以外にもガソリンやガスや、なんかエネルギーのもとを掘り出したり使えるように加工したりするらしい。そういうものを、どうやって生み出したり使えるようにしているか。
こういうことがどうやって可能になっていったのか。大昔はそういうものは全然無かったということはなんとなく知っているわけで。何か科学技術とかいうものが昔から現代にかけてどんどん進んできたらしいことは知っている。
自然の、物事の仕組みをどんどん深く理解して、それを人間のために使えるようにすること。「どんどん深く正確に知る事」のほうを科学といい、人間が使えるようにすることを「技術」という、とおおまかに分けることができる。「科学」は、モノや宇宙の根源的成り立ちを研究する物理学、物理学で見つかったモノのおおもと、原子とそれからなる分子という形をとった物質が、いろいろな形や性質を持つことを研究するのが「化学」、それが命をもった生物になってどういう性質や仕組みを持つかを知る「生物」、僕らの地球や、地球、人間と関わりのある天体の動きを研究する「地学」。理科というのは、今の生活を形作る「科学技術」についての知識を、今、分けたように学びやすいように分類したものだ。
数学は、科学を研究するおおもとになっているし、社会の中の、お金など経済活動に関しても、それは日常のお買い物の段階から、働いて、給料をもらったり税金を払ったり、お金をためたり増やしたり、そういう社会生活にも必要なのは分かる。数学がなければ科学技術はまったく発展しなかっただろうし、社会生活も成り立たないから、数学が大事なことは、好き嫌いはあるだろうけれど、みんな「ある程度は必要だし大事」なことは分かっていると思う。
ところでね。みんな、いまのところ、社会も理科も数学も、「ちゃんと分かっているわけじゃない」よね。分かっていることより、知らないことがたくさんある。すでに小学中学で習った範囲だけでも、全部分かったり覚えたりしているわけではないし、今まで習っていることより、まだ習っていないこと、知らないことの方がずっとずっと多いだろうな、ということは、みんな漠然とだけれど、分かっていると思う。
実は、それはみんながまだ中学生だから、高校生だから、ではないんだな。大人だって、老人だって、どんな人間だって、神様じゃないんだから、程度の差はあれ、知っていること分かっていることより、分からないこと、知らないことの方がずっと多いのだよね。だって、科学も技術もどんどん進歩するし、どこの国でも新しい歴史はどんどん生まれているし、社会の仕組みもどんどん変わっていくし。毎日忙しく日常の生活と家族のことと自分の仕事をこなすのに精いっぱいで、学校を卒業して大人になって生きている人たちだって、知っていることより知らないことの方がずっと多くて、よく分からなくて、それでも毎日、なんとか生きているんだよ。
どんなに偉い人もお勉強ができた人も、みんな「知らないこと、分からないことだらけのまま、この世界、社会の中に、偶然、投げ込まれた中で、もがきながら、毎日を生きていて、そうして、ときどきいいことがあって幸せな気分になり、嫌なこと悲しいことがあって、不幸な気持ちになって、そうやっているうちに、歳をとったり病気になったり、事故や災害や戦争に巻き込まれたりして、死に方はいろいろだけれど、結局、この世界について、自分の人生について、わからないことがたくさんだったなあ、というまま、死んでいくというのは、変わらないのだよね。そういう点では、人間は生まれて、もがいて一生懸命生きて、死んでいくという点では変わらないのだけれど、人間てそういうものだと教えてくれる学校の科目ってあるかなあ。
でもまた一方で、これまでの人類の歴史上、だれ一人として同じ人生を生きた人はいない。生まれた場所も時代も、同じ時代だって都会か田舎か、豊かなお金持ちの家か貧しい家か、優しい家族か怖い家族か、いや、家族がいるかいないか、も一人一人全員違う境遇に生まれて、それぞれ、生まれ持ったからだや性格も全然違って、全部の人がそれぞれ違う人生を生きてきたのだよね、これまでの人類の歴史の中で。そういうことを教えてくれる科目も、あるかなあ。
それが、国語の中の文学、文学の中でも特に「小説」というのは、そういうことが書かれているものなのだな。「人生はそういうものだ」という結論ではなくて、いろんな個人が、そういうことを書かずにいられない、それが人間の営みの中で、なぜか大きな分野として世界中にあって、日本にもあって。そういうものの代表的なのを、いくつか読んでみようか。そういう勉強をするのが、国語の中の、文学的文章、特に小説、というのを読むということなんだな。
ところでちょっと話はそれるけれど、人生で起きたことを、全部そのまんま覚えていて思い出そうとしたら、生きていた時間と同じだけ時間がかかっちゃうから、不可能でしょう。
だからね、人間の脳っていうのは、起きたことのうち、忘れないでずっと覚えていた方がいいことを、「物語のような形」にして記憶する。という仕組みを持っているのだな。何でもかんでもとりあえず覚えておく「短期記憶」から、ずっと蓄積しておく「長期記憶」にするときに、「物語的なエピソードの記憶」にする。そして、忘れないようにときどき思い出したり、人に話したりする。そのときに、言葉で物語るよね。長期記憶は、言葉で語られることで、どんどんはっきりしてくるんだけれど、実は自分に都合のいい嘘が混じってくるのが、人間らしい所なんだな。
大事なことを記憶するために物語にする。それを言葉で何度も語り直す。それに自然に嘘が混じってくる。これは、人間だけに固有の、とても大切な働きなんだな。神話とか昔話というのも、そうやって形作られてきた。文学というのは、そういう、人間固有の、記憶を蓄積し、語るという脳の仕組みそのものを反映した、いちばん根源的で人間的な活動なんだな。
その最新バージョンというのが、「小説」という文学の形なんだな。小説は、基本的にフィクション、「嘘」なんだよね。ある登場人物が、大切なことがよくわからないまま、一生懸命、ある時代の、ある場所のある社会の中で生きている。そこで経験することを、その個人である、よくわからないけれど生きている主人公の立場から描く。書き方として、主人公が語っている形を取る「一人称小説」、「私は、僕は」として書かれるものと、作者が外から登場人物を観察して「彼女は、彼は、エミリーは、一郎は」っていうふうに語るパターンがあるけれど、どちらにしても、「ある社会、時代を生きる、個人の視点、体験から」書かれるのが小説なんだな。複数の視点をいったりきたりする小説もあるけれど、やはり「複数の個人」の体験から語るわけだ。
そして、歴史小説みたいに、一見、事実だけを書いているように見えても、小説は「作者の、たいていは意図的だったり、時には無意識についちゃう嘘、虚構」でもって作られていくものなんだな。個人的な嘘になんて、何の意味があるの?それも全部が意図してじゃなくて、作者も無意識な場合もあるのに、そんなもの、読んだり、試験問題にして問うことに何の意味があるの?「作者の意図」なんて作者にもわかんないかもじゃんね。たしかにそうだよね。個人的な嘘の話。それが小説だからね。
ところがね。結局、すべての人間は「よくわからないまま人生を生きていかなければならない存在」なわけだ。昔の人も、今の人も。すごくお勉強のできる人も、そうでない人も。なんだかよく分からない、なんだかむかつく。でも生きていかなきゃいけない。
いろんな時代の、いろんな社会の、いろんな境遇の人が、それぞれの分からなさを抱えながら、どんなふうに生きたのか。それぞれひどい社会だったり、ひどい家族だったり、戦争だったり、災害だったり、いろんなことが起きるなかで、人は生きていくわけだ。あるいは、毎日毎日同じことしか起きないつまらない人生で、友達もいなくて孤独で、何も面白いことがなくても生きていかなければいけない。そんなことを描いた小説もある。
そのこと自体を、元の小説というもの自体を読むことに、意味があるのだな。国語の中で、文学、小説を読んでみる、ということには。なんでこんなどこの誰だかわからんおっさんかおばさんかの、どうでもいい戯言を読んで、ああだこうだ言い合うのだ?それは、つまり、そういうものを書いて読むということが、人間の生きてきた、生きている避けようのない現実を映し出す、数少ない(唯一とは言わない、優れたアニメや漫画やテレビドラマや演劇や映画には、そういう働きはある。)と、脳の仕組みとを反映した(言語だけで、というのがけっこう人間にとっては本質的なのである)、どうしても書かれずにはいられない、そしてある程度の人には読むことに意味がある、そういう重要な言語表現のジャンルだからなんだな。
他の科目との比較に戻るね。
人間は、社会や理科や数学や外国語を勉強して、この社会、世界、時代についてできるだけ正確に理解して、自分の人生とこの社会や世界が少しでも良くなるように生きて行けるようにしよう、それが学校で習う他の科目が教えてくれることなわけだ。全部完璧にはできないから、それらの中で、わりと分かるもの、得意な科目、楽しい科目をだんだん深く学んで、その方向で職業に就くことで、自分も有利に大人になっていけそうだし、周囲や世の中、大きく言うとこの世界にとっても、「それぞれが得意なところでがんばって進化進歩していく」のはいいことだ。
だから、社会理科数学外国語を学校で勉強することが「具体的に役に立つ」のは誰にでも分かる。
こういうすべての教科の教科書も、それにまつわる資料や参考書も、日本で学ぶときには日本語で書かれている、外国語ですら、日本語で解説し、日本語との間で相互に訳していくことになるから、国語の勉強はこれらの科目すべての基礎になることは、誰も反論しないよね。だけれどそれらは基本的に論理的かつ実用的な文章を正確に読む、という能力養成に意味がある。
そうではない文学的文章、特に小説というのは、そういう実用性の反対側に、その必要性があるというのは、さっきまでの説明でなんとなく、わかってきたと思う。
人は、分からないこといっぱいのまんま、生きていかなければいけない。この社会、この国、この世界、この時代、何がどうなっているのかはっきりしないまま、分からないことがたくさんあるまま、生きていかなければいけない。その中で、幸せなことも、不幸なことも、避けようもなく起きる。そういうことをいろんな人が「個人」として生きていく。個人的体験として、それを書いていく。それぞれの内面に起きたことは、他人のことは全部は分からないし、自分のことだって実は分からないし、ちゃんと覚えてはいない。記憶だって自分に都合よくいろいろと変更されたり、取捨選択されちゃったりしている。だから、そういうこと全体を書くには「科学的に正確に」書くことなんて不可能で、書く人の想像力でおぎなって書かれた「虚構」になる。フィクション、小説という形になるのだな。
そういう、人間というものの限界と特性、そうやっていきていくしかないらしいということを、小説というものを読むことで、人間は学んでいくのだな。神話とか昔話、というのもそういう役割をずっともってきたわけだけれど。小説というのは、より今の時代に近いところで、「ああ、自分と似ているところがあるなあ」と感じられる形で書かれている、ここまあ200年くらいの間に成立した文学の形なんだな。起源をさかのぼって考えれば、日本の平安時代とか、西欧の中世とかに小説らしきものはあるけれど。
学生生徒全員にとって意味がある、とは言わない。言語だけ表現に馴染まない人もいる(マンガやアニメやテレビドラマなら理解できるし楽しめるという人はいると思う)し、どうしたわけかフィクションに意味を見出さない人が一定割合存在することも事実だ。
しかし、小説が救いになる人間も一定割合いる。言葉だけで書かれていることで、より直接、脳に直接語りかけられているように感じるタイプの人が、何割かいるのである。
また他の実用教科との関係で考えると、歴史や地理や現代社会や理科各科目の勉強それ自体だと、自分に関係があると思えない、というか端的に「つまんねー」と思ってしまう学生が一定割合いる。
でもそういう人たちも「小説を通じて歴史に興味を持つ」「小説を通じて現代社会の問題に興味を持つ」「小説を通じて、どこか外国に興味を持つ」「小説を通じて医学とか、天体とか、原子力とか」科学の様々な分野に興味を持つ、という入口、橋渡しになることがあるのである。
理科社会の教科書の客観的正確な叙述には全然、興味がわかないけれど、小説を通じてだと興味が湧くという人はいる。司馬遼太郎にはまって歴史を学ぼうとして「司馬遼太郎のはフィクションだぞ、バーカ」と先輩に怒られる人がたくさん出てきても、そのうち何割かが「やっぱり歴史より文学が好き」に戻り、一割でも歴史学の方に方向修正したら、それでいいのである。
人間はいろいろ分からないまま、人生を、この世界を生きていく。そのこと自体を受け入れながら、生きていく。
他の人は、他の国の人は、過去の人は、未来の人は、どうやって生きていたのだろう。小説を読んで、ウソと分かっていても、そのことを知る。自分もそうやって生きていくのだということを意識する。文学というのは、特に小説というのは、そういう体験をするということなのだよな。
それに意味があるのは、中学生・高校生とかいう若い年齢だけではないのだよな。もう、あとは死ぬだけという私のような年齢になっても、いろんな国の、いろんな時代の、いろんな境遇の「あとは死ぬだけ」年齢の人たちが、どんなことを思ってどう生きたのかという小説を読むのは、なかなかに意味深いことなのである。
※その上で、冒頭紹介した記事の「小説の感じ方は個人の自由」に完全同意というわけにいかないのは、小説の読解と理解には、普通の人が「どう読もうと自由じゃーん、感じ方は人それぞれ違うじゃーん」と言うよりは、かなり厳密に正確に読むことが可能で、ちゃんと読めば正解範囲はこの範囲には限定できるよ、ということはあるというのが僕の考えなのだな。書かれた時代、社会、背景の理解という側面と、文章読解の、小説やその作者の独特のクセみたいなものをきちんと加味していけば、正解範囲を狭めて厳密に読めるのである。ということは蛇足ながら、書いておく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
