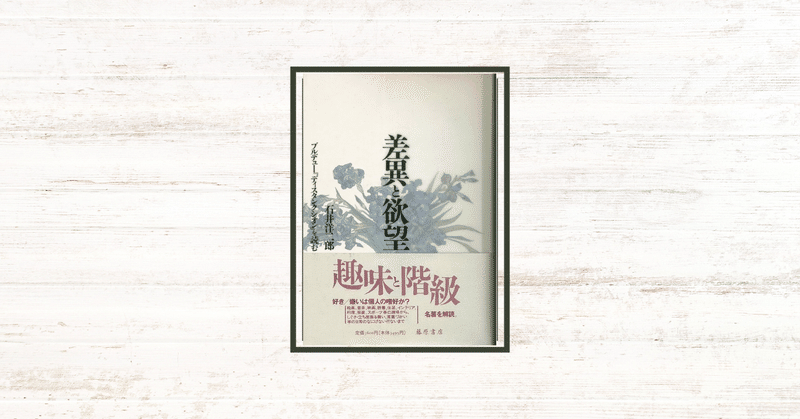
【読書記録②】『差異と欲望』(石井洋二郎著)
どんな本?
テーマ
階層と趣味
主張
私たちの趣味やその他諸々の好みは、出身階層によって規定されている
アプローチ
『ディスタンクシオン』の内容を日本社会との関係も交えつつ、解説する
事前目的
『〈責任〉の生成』という本に出てきた「ハビトゥス」を正しく理解する(事前知識がこれしかないのでこの程度)
感想メモ
前回読んだ『階層化日本と教育危機』の参考文献の1つである『ディスタンクシオン』(P. ブルデュー)の解説書。私たちは自分の趣味や好みを純粋で、完全に内発的なものとして捉えがちであるが、実際には階層の影響を大きく受けている。友人や恋人として誰を選ぶのかということも、出身階層によって、ハビトゥスの予定調和によって決まる。
『階層化日本と教育危機』(苅谷剛彦)では、教育における「階層」的な視点の欠如が問題視されていた。実際、本書では戦後日本についてこのように書かれている。
敗戦とそれに続く民主化路線を経験してきた日本は、したがって、半ば意識的に社会の階層化を回避してきたと言える。
中間層が増えたとは言え、「差異」は確実にある。しかし、それを露見させまいとする意識は、『友だち地獄』(土井隆義)で見た「優しい関係」に通ずるものを感じた。一方で、友人関係の実態は大きく異なっているように思う。「優しい関係」もハビトゥスによる予定調和も、同質な存在を求めるという点では共通している。しかし、「優しい関係」では、ほんの少しの「差異」の表出も回避しようとする。階層社会であれば、ハビトゥスによる予定調和が働くはず。そのため、人間関係の自由化が進んでも、それほど「選ばれない不安」は感じないのではないだろうか。中間層が大部分を占め、かつ、階層意識の希薄な日本だからこその「優しい関係」なのかもしれない。
次回予告
次に読む本は、多分『スティグマの社会学』。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
