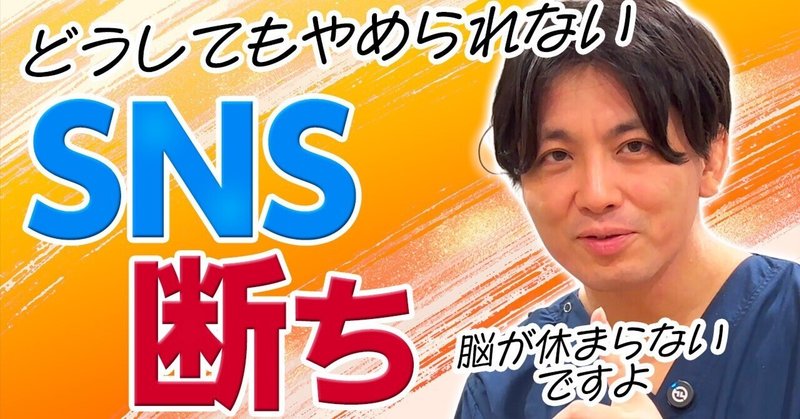
SNS断ち – 依存によって起きる弊害 精神科医目線で語ります
本日は「SNS断ち」というテーマでお話しします。
質問をいただいているので、早速答えていこうかなと思います。
■SNSをやめたくてもやめられない人たち
こういう人いません?ということですけれども、結構います。
具体的にはそれだけを主訴に来ることは少ないですが、例えば転職準備や片付け、やらなければいけないことがあるのにできない人、片付け、あとは学校の課題など、やめられない人というのがいますし。
あとはひきこもりの人たち、不登校の子たちも多いです。
SNSをやめたくてもやめられない人たちの中で似ているのは、実は心気症というか、身体の症状ばかり考え続けてる人たちもやめたいのにやめられないということです。
結構似ていますけど、同じようなカテゴリーというか、脳内では違いますが、臨床上の病前性格というか、そういうのは似ているなと思います。
■なぜやめられない?
やめたいのにやめられないのはなぜかというと、例えば、やめようというのは意志の力ですよね。
だから意志の力が弱っているとき、つまりうつ状態のとき、うつ病や適応障害などのうつの状態のとき、ADHD、依存症的になっているときはやはりやめにくいです。
いわゆるSNSだけの単独の依存症、スマホ依存というのはちょっと少ないのかなとは思いますけど、ギャンブル依存やアルコール依存に比べたらね。
でもやはりうつやADHDの合併として、こういう依存性が際立つというパターンは多いだろうなと思います。
そもそもSNSをやめられないのはなぜかということですけど、SNS依存というのは何かというと、医学的には「行為依存」の仲間と言ったりするんです。
依存症というのは「行為依存」と「物質依存」があって、物質依存というのはアルコール依存、覚醒剤依存、大麻や違法薬物、ベンゾジアゼピン依存、カフェイン依存もありますけど、ニコチン依存とか、そういうのは物質依存です。
行為依存は、ギャンブル依存、買い物依存、美容整形、万引き、盗撮、自傷行為、摂食傷害も仲間です。
結局なぜやってしまうかというと、承認欲求が満たされるとか、不安を煽ったり、見ないとダメだよ損するよ、SNSが持ってるUI、やりやすい、光が来る、チカチカする、何かを押すと次の情報が来る、時々Hな情報が流れる、買い物の情報が流れる等々、やめにくいように作られてるんですよ。
いいね!を押されると快感物質がブワーッと出るし、他人の楽しそうな写真を見るとムカムカムカッと怒りが湧いてくるし、それはパチンコ台の大当たりがなかなか出なかったときのイライラ感にも似てるし、そういうことですよね。
いいね!を押されるときはパチンコが当たるときですね、ウワーと出てるみたいな。
SNS依存というのはありますよね。
こういうのを行為依存と言ったりします。
具体的にどんなタイプがなりやすいかということですけど、さっき言った通りです。
うつ、ADHD、依存症っぽい人たち。
こういう人たちはどういう人が多いのかというと、依存症になりやすい人たちの中では、人との交流が苦手、愛情不足、愛着障害、そういうのもあったりします。
人に依存できないから、何か他のものに依存してしまう。
倒錯的に何かに依存してしまい、結果的にその虜になってしまうというのも結構あったりします。
■依存によって起きる弊害
依存してしまうとどんな弊害が起きるかというと、結局脳が休まらないんですよ、活動しちゃうから。
休まらないので、脳内が整理されないんです。
記憶の定着や脳内の整理、課題の整理が行われないです。
脳の整理や記憶の定着というのは、僕らが紙に書いて整理するだけじゃなくて、脳みそを使わなかったら、寝てたりしたら勝手にやってくれるんです。
人間はよくできていて、無意識にやってくれるというか、オートで整理してくれるんです。
自分で頑張って整理しようとか紙に書いて悩み事を整理しようとしなくても、基本的には放っておいたら整理してくれるんですけど、SNSなど他のことをしてると、やはり整理されないという感じはあります。
論文で証明できているのかと言われたら、該当する論文はすぐパッと出てこないんですけど、臨床上よくわかります。
臨床上明らかなんですよ。
SNSをずっとやっている人はやはり落ち着かないし、1週間、2週間経っても自分の内面との内的会話が進んでいないから、課題が整理されてなくて、せっかくカウンセリングしても、宿題がちゃんとできてないというか、カウンセリングで出た宿題や結論、疑問がきちんと活かされてないんです、診察と診察の合間のときに。
だからわかります。
こういうのが障害かなと思います。
■SNS断ちのデメリット
メリットは何かと言うと、単純で脳が休まるし、記憶が整理される、課題が整理されるし、うつが良くなったり、気持ちが楽になります。
翌日の仕事も学校の勉強もスムーズに効率的にやれるようになります。
SNS断ちのデメリットは何かというと、全くないです。
友達が減るかも、情報についていけないかも、と言うかもしれないですけど、SNSの頻度が減って困ったと言った人は、僕が診察してる中で一人も会ったことありません。
この10何年間の間に一人も会ったことないです。
だから基本的には全然OK、Yahoo!ニュースを見なくて全然OKですね。
ニュースを見なくなって良かったという人はいても、見なくなったから世の中についていけなくなったんです、だから仕事でミスが増えました、と言った人は一人も会ったことがありません。
なのでSNS断ちをしてのデメリットは全くないですね。
実際ゴールデンウィーク期間中から始めるというのもありですし、実際にSNS断ちに成功した人もいます。
その結果、うつが良くなったとかあります。
うつなど、病気の人だから、今はあなた病気ですよ、と。
ちょっと厳しく聞こえるかもしれないですけど、今は病気なので、今は休みの期間だから、お酒を飲まないようにSNSは控えましょう、と言います。
グググという感じですけど、やはりSNSをしていたら落ち着かないし、仕事の情報が入ってきたら辛いので、アレかなと思います。
あとはデメリットで脳が休まらない、整理されない。
■妬み→自己肯定感の低下
あと妬みの話です。
僕らは妬みというのがある。
だけど妬みというのは感知されないんです。
直接妬みや嫉妬というのは感知されず、自己肯定感の低下という形で僕らは感じられるんです、自分はダメなんだ、と。
でも実際自分がダメなんじゃなくて、妬んでるんだよね。
ダメなんじゃなくて、あの人に比べたらダメなんだ、あの人は持ってるけど私は持ってない、あの人に比べて自分は運がなかったとか。
これなんだよね。
本当に今のあなたってダメなやつなの、と言うと、そうじゃない。
私はバカなんです、という早稲田の学生がいますけど、何でと言ったら、いや周りがみんな東大で医者で、と言ったって、いやあなただって十分エリートでしょ、と。
いや、私はダメなんですって言って。
でもあなた、別にダメじゃないじゃないですか。
いや周りに比べたら、とね。
だいたいそうですね。
本当の意味で、ダメなんだ、みたいなことを言う人は本当にいないですよ。
逆にできない脳は自信過剰というか、本当にダメだったら自信過剰というか、あんまりダメと思わないんですよね。
ダメと思わないからこそ妬みが出てくるんですけど、今度は。
ここら辺はややこしいですね。
でもSNSとはそういうことなので、妬みを煽って、妬まれたら嬉しくなるという、こういう人間の欲望を刺激するもので、良くないですよね。
SNSにすごくハマってる人を見ていて、ちょっと痛々しいというか、ちょっと苦しい、承認欲求が見え隠れしてしまうから嫌な感じです。
じゃあ益田のYouTubeは何なんだ、という感じがしますけど、まぁそうなんでしょうね。
益田も他の人から見たら承認欲求が高いな、ナルシストだな、キモいなとか見えるんでしょうけど、恥ずかしいけどそれ込みでこういうYouTuberという仕事ですから、まぁいいのかなとは思ってますけど。
はい。
■本日の宿題
今日の宿題は、SNSと妬みというテーマで今回感じたことを書いていただけるといいかなと思います。
そしてそれを断ってみることで気持ちが楽になるということを実感してもらえたらなと思います。
そしてその実感をコメント欄で書いてもらうといいかなと思います。
妬みますよ、妬み。
この今の感じている感情は、原形は妬みなんですよ。
一回加工されてますから、もう一回言いますけど。
自分が何か感じた時の焦りや怒り、色々なものがあると思いますけど、それは加工された後の姿であって、その源泉は妬みなんだということです。
ここに気付くか、気付いても受け入れられるか、これがめちゃくちゃ大事ですから。
▼オンライン自助会/家族会の入会方法はこちらhttps://www.notion.so/db1a847cd9da46759f3ee14c00d80995
▼iPhone(Safari)からのメンバーシップ登録方法https://youtu.be/_49prDk9fQw?si=BMjBO1CyXlhq7BaI
▼iPhone(Google Chrome)からのメンバーシップ登録方法https://youtu.be/38zE3uwcPgg?si=XE2GJ8hWI-ATjjGe
▼オンライン自助会/家族会の公式LINE登録はこちらから
https://lin.ee/XegaAAT
ID:@321iwhpp
よくわからないこと、聞きたいことなどが
あれば、こちらにお問合せください。
運営スタッフより、返信いたします。
onlineselfhelpsociety@gmail.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
