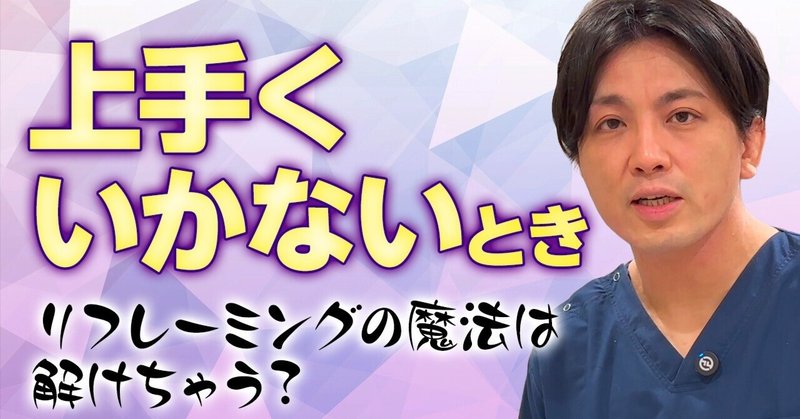
上手くいかない時のリフレーミング術 主観2.0
本日は「リフレーミング」についてお話しします。
リフレーミングはわかりますか?別の視点から物事を見ると、ネガティブなものもポジティブに見えるというやつです。
よく例えがあるんですけど、コップの中に水がありますよ、と。これを多いと思うのか少ないと思うのかはあなた次第ですよ、というやつです。
この量のコップの水を少ないと思うんじゃなくて、これしかないと思うのではなくて、こんなにもあると思った方が生きやすいですよ、というのが典型的なリフレーミングの説明となります。
リフレーミングの天才というのを僕は何人か知ってるんですけど、そのうちの一人は、以前対談をさせてもらった佐渡島さんです。
漫画編集者の佐渡島さんです。『ドラゴン桜』や『宇宙兄弟』の編集をしていた佐渡島さんですけど、天才ですよね。
文学の天才、リフレーミングの天才で、色々なことに何でもかんでもリフレーミングできちゃうんです。ネガティブなものもポジティブに変えられるということですけど。
人類が到達できる、日本語圏で到達できるリフレーミングの最高峰は佐渡島さんだと思います。それがリフレーミングなんです。
対談動画を見てもらったらわかります。あんな感じです。当たり前ですけど、僕よりも言語能力が高くて、言語の扱いに長けていて、本当に日本人の、日本語圏の中の最高峰なのかなとは思います。
■リフレーミングの効果
じゃあ精神科臨床でリフレーミングだけやるかというと、あまりそういうことはないんです。
患者さんに「こういう見方があるんじゃないの?」と僕らが伝えて、それでもっと喋りが上手かったりしたらね、僕みたいな三流ドクターじゃなくて、もっと喋りがうまい良い先生だったら、患者さんの心を本当に変えちゃうんです。
ある種の洗脳に近いというか、上手いんですよ。
そうすると診察室の中で本当にリラックスできて、「ああ、先生に話してよかった」「先生に教わってうまく物事を切り替えて見られるようになった」となるんです。
その効果はどれぐらい持つのかというと、現実は変わるわけないですから、この量の水に対して少ないと思っていたのが多く見えたときに、でも解けちゃうんですそんなもの、どこかのタイミングで。
魔法は解けちゃうわけです。
次の診察まで保つかもしれないし、わからないですけど。
でもそういうもんですね。
リフレーミングをすることで、その場をしのぐとか、患者さんを褒めたり、つなぐ診療というのもあるわけです。
今苦しいからつなぐ、その人の世界の見え方をどうにかして説得してつなぐ、というやり方もありますけど、あまり良いやり方ではないです。
ただ緊急事態を防ぐためには良いんですけど、中長期的に考えるとあまり良いやり方じゃないなと思います。
■主観→客観
結局、多いのか少ないのかわかんないですけど、そういう主観的なものの見方をしてるわけです。
だけどこれを主観的じゃなくて、客観的に捉える必要があるんです。
そうじゃないな、と。150ccだな、と。
150ccはコーヒーでちびちび飲むには充分な量だけど、喉が渇いたときに150ccの水だったらやはり足りないわけです。
お風呂だったらより足りないし、全然お風呂の水にも使えないですからね。
これを経て、でも客観的だとやはり判断がつかないので、これを理解した上で次の世界に移るというのが治療的だし、主観2.0と言ったりします。
だから一見「これってリフレーミングなんじゃないの?」と思われそうですけど、そうじゃないんだよね。
そこには質的な変換が起きる。
主観的なものの平行移動ではなくて、今まで見えてたものと、一回客観的な事実を理解することによって人格の成長が行われますから、同じ「水は多いな」と思うのと、主観2.0の「水は結構あるな」と思えることは全然意味が違うんです。
それはしっかり客観的な状況を吟味してるかどうかということになってます。
だから認知行動療法でも精神分析でも物事を明確化していき、それを患者さんと共有することで、患者さんは次のステージにいけるということになってるんです。
ただ自分の欠点や客観的な事実を受け入れられないんですよ、人間というのは。
だからここに抵抗というものもあるし。
もっと大人の意見をしろと言っても、これもできないですよね。
抵抗にあうんですよ。
一回こっち側に行けると思ったら、またこっち側に戻ってしまうということあるわけです。
人間はこう行かなければいけないのに、人は変わりたいと思ってるにもかかわらず、変われない。
それはなぜかというと、抵抗にあうから。こういう風に変化したいけど、なかなかうまくいかない。この抵抗があるから。
抵抗というのはどういう形なのかというと、否認、否定してしまう、合理化、酸っぱいブドウのように感じてしまう、色々な防衛機制がありますけど、様々な理由をつけて元の場所に戻ろうとする。
だけど精神科医療は抵抗を解釈して、あなたはこういう抵抗を感じてるんじゃないですか、と。
あなたは妬みがあって、自分の弱さを受け入れられないんじゃないですか、とそういうことを突きつける。
突きつけるというとあれですけど、それを一緒に共有して、でも良いんだよ、と。
弱くても良い、私も弱いし、あなたも弱い、と。
弱くても良いんだよ、と。
今日変わらなくても良いんだよ、明日変わらなくても良いんだよ、5年後さえ変わってなくたって良いんだよ、と。
でも、変わっていけるんだよ、ということだよね。
それを共有できるということが治療上とても重要ということになります。
これがリフレーミングのあり方です。本当の臨床的なリフレーミングのあり方とは、こういうことになるのかなと思います。
精神分析、認知行動療法、何でも良いんですけど、同じようなことを言ってますけど、使ってるタームは違います。
益田裕介はタームを合わせた方が良いなという形で、わかりやすいように主観2.0という言い方をしています。
パソコンのバージョンが変わるみたいな感じです。2.0に移りましょう、と。
2.0で終わりかと思ったら、そうじゃないんですよ。
2.0の次は3.0、4.0と続きますから。
そういう意味も込めて主観2.0という言葉を使っています。
もうちょっとだけ行きますか。
■質問:マイナスにとらえすぎてしまう人
じゃあ物事をマイナスに考えすぎてしまう人にどういうアドバイスをしたら良いですか、と。どうやったら良いですか、ということなんですけど。
これは、僕は、アドバイスが良いのかというと、ちょっとわからないです。
短期的には良いと思うんですね。
短期的にはポジティブにさせる、励ます、というのは良いんだけれども、先ほど言った通り、こういう見方があるよ、と言って説得していく。説得の技法は色々ある。
詐欺師のやり方、色々な商売のテクニックとしてあると思います。
ミラーリングと言って同じような行動を取ったり、信頼感があるように有名人の名前を出すとか、色々なやり方で相手を説得する説得の技法というのがあるので、そういうものを使ってアドバイスしていくというのはもちろんアリですし、YouTuberでもそういう人たちがいっぱいいますけど、説得の技法を使うことで視聴回数を伸ばしているなというのもいますけど、僕らはやはりあまりしないですね。
見え透いているしね。じゃなくて、やはり大事なのは聞くことなんです。
ネガティブはネガティブなりの理由があるし、ネガティブだからこそ自分を守っているところもあるので、僕らがやるべきこと、精神科医がやってることは何かというと、聞くこと、傾聴することなんです。
アドバイスより傾聴、1に傾聴、2に傾聴、3、4がなくて5に傾聴。
本当に必要なアドバイスはありますよ。
薬を飲みなさいとか、今すぐ休職をしなさいとか。
僕らは本当にやって欲しいことはきちんとアドバイスしますけど、そうでない限りはできるだけ傾聴の時間をとっている。
病気説明などやらなければいけないことはやりますし、明らかに間違った科学知識の話をしてる場合は訂正することがありますけど、基本はそういうことをせずに傾聴します。
そうでない限りは、主観的な出来事の間は、僕がここで否定しなかったらトラブルが起きるということ以外は基本的に傾聴ということです。
ただ聞くこと。聞いていれば受け入れられていると思いますから。
弱くても大丈夫なんだ、と。
そうしたら客観的なものを受け入れるんです。
結局、世の中の人は、よく思いますけど、みんな賢いというか、馬鹿じゃないというか、みんなわかってるんだよね。
益田がわざわざ言わなくてもわかってるんだよね。
正論なんか聞きたくないんですよ。
正論なんか言われたくない、わかってるんだから。
だからここなんだよね。
問題はここの抵抗なので、じゃあどうやって抵抗を取ってあげるか、抵抗を取る補助は何なのかというと、愛情ですね。
あるがままのあなたを許す、愛する、そして愛されることによって自分を愛せるようになるということなので、本当に何か宗教っぽいですけど、でも本当にそうなんだよね。
聞くということが最大の愛情ですからね。
距離を取ってしっかり聞く、対価を求めず聞くということが最大の愛情なので、そういうことをします。
わからない人もいますね。
もちろん発達障害があるとか、一部の人たちは聞くことが最大の愛なんだということがわからないタイプの人もいるので、その場合はこの限りじゃないですけどね。
■質問いろいろ
Q:ポジティブすぎる弊害もありますか?
もちろんあります。
Q:はっきりとした診断を言えることはありますか?
精神科医という仕事は、患者さんとの向き合い方も大変そうですが、ということですね。
はっきりとした診断を言えることありますか、と。
言えないときもあります、ということです。
Q:心の病における完治はありますか?
完治はあると僕は思います。
治癒というのが起きると思います。
よく僕が「治癒」という言葉を使うと、いや精神科の病気は再発が多いだろう、寛解しかないだろう、と言ったりしますけど、そういう意味で僕は治癒という言葉を使ってるんじゃないんです。
もちろん統合失調症とか双極の人は再発が多いんですけど、治癒というのはそこじゃないんだよね。
どちらかというと、僕らの心、僕らの知識や経験から成り立っている人格と呼ばれるものが成長していくこと、その中で治癒を感じることというのがあるんだよね。
だから薬で抑えられているとか、今たまたま社会的な問題がないとか、家族とかの問題がなくて症状が寛解してるというのと、治癒というのはやはりイメージが違うんです。
人格的な成長や飛躍が起きてるときを僕は治癒だと思っていて、そこに立ち会える感動というものを僕らは求めているし、それを感じると病みつきになってしまうので臨床をやめられないんです。
完治という言い方はわからないですけど、心の病というか、心の病をきっかけに人間の人格が成長していく、成熟していく、治癒に至るという、この感動や奇跡というのはあります。
Q:日々様々な患者さんの心のケアをする中で大切していることは何ですか?
色々ありますけど、僕も医者の最初の頃と違って、だんだん中堅に入ってきて、YouTubeを見られるようになってきた中で、やはりお手本でありたいという思いが強くなってきたというか、お手本をやっている先生たちと出会うことが増えたんです。
そういう人たちの次を僕らの世代がやるということを考えながらやってると思います。
色々な人と会える機会も増えてきたし、そういう中で自分の中で心の病を持っている人たちにとって、どんな精神科医がいてくれたら日本や社会に対して絶望しないんだろうとイメージしながら、僕はYouTube上のキャラクター益田裕介を演じているし、それを臨床で落としているし、そしてバレちゃうので、自分自身をそういう役割としてなじませるようにしてるんです。
苦しんでいる人たちがいる中で、この人がいることで社会の見方、世界の見方が変わる。すごく腐りきった世界のように見えてるかもしれないけど、でもいるんだと思ってくれたら良いなと思っているんです。
こんな人いるんだ、と。
そしてそれは僕だけじゃないので、絶対。
僕の仲間もいるわけだし、教えてくれた先生たちもいっぱいいるので。後輩たちもいっぱいいますから。そういう精神科医をやっているということです。それが精神科臨床だなと思っています。
ということで今回は、うまくいかない時のリフレーミング、ということで、主観2.0というお話をしました。
■本日の宿題
本日の宿題は、主観2.0を味わった人、益田が言っていたのはこれだと感じたことがある人は、その体験を書いてもらうと良いなと思います。
あと他の人が変わった瞬間、自分の子ども、自分の部下、自分の親、誰でも良いんですけど、それが変わった瞬間に立ち会えたこと、経験がある人たちを書いてもらうと面白いかなと思います。
▼オンライン自助会/家族会の入会方法はこちらhttps://www.notion.so/db1a847cd9da46759f3ee14c00d80995
▼iPhone(Safari)からのメンバーシップ登録方法https://youtu.be/_49prDk9fQw?si=BMjBO1CyXlhq7BaI
▼iPhone(Google Chrome)からのメンバーシップ登録方法https://youtu.be/38zE3uwcPgg?si=XE2GJ8hWI-ATjjGe
▼オンライン自助会/家族会の公式LINE登録はこちらから
https://lin.ee/XegaAAT
ID:@321iwhpp
よくわからないこと、聞きたいことなどが
あれば、こちらにお問合せください。
運営スタッフより、返信いたします。
onlineselfhelpsociety@gmail.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
