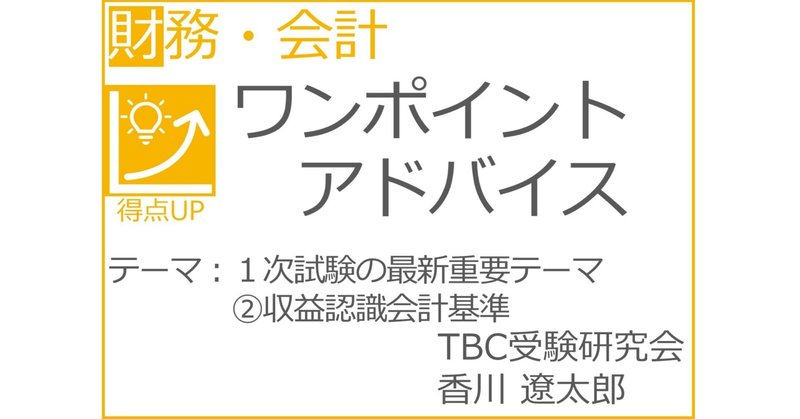
1次試験の最新重要テーマ ②収益認識に関する会計基準
皆さん、こんにちは!
TBC受験研究会講師の香川遼太郎です。
大変お待たせいたしました!
一昨日から順次YouTubeに「財務・会計」の講義動画がアップされています。
無料とは思えないほどのボリュームとなっておりますので、講義動画と早稲田出版の書籍を活用して、一次試験は「高コスパ」で突破しましょう!
さて、それでは今回も1次試験の最新重要テーマについて、ご紹介させていただきます。
今回は、令和5年度でいよいよ初めて出題された「収益認識に関する会計基準(以下、収益認識会計基準)」についてです。

「収益認識会計基準」とは?
「収益認識会計基準」は2021年4月から原則適用開始となった新しい会計基準です。中小企業については任意適用の段階ですが、中小企業診断士試験においては、令和5年度で初めて出題されたことから、今後も継続的に出題されることが予想されます。
「収益認識会計基準」をざっくり説明すると、収益の認識の方法を従来の「実現主義」から「顧客への支配の移転」に変えましょうというものです。
従来の「実現主義」というのは、割と曖昧な部分も多く、企業によって基準が異なっていました。また、国際的なスタンダードとも少しかけ離れていたため、新しい会計基準が作られました。
新しい勘定科目が必要になった
「収益認識会計基準」の適用により、従来の勘定科目だけでは表現できない取引が出てきたため、新しい勘定科目が必要となりました。
令和5年度1次試験第2問では、この新しい勘定科目を使った仕訳を問う問題が出題されましたね。それが「契約資産」です。初見の方は結構面食らったのではないでしょうか?
なぜ「契約資産」が必要になった?
「契約資産」は「売掛金」と近い概念です。
どちらも「企業が将来対価を受け取る権利」であることは共通なのですが、「売掛金」は法的な請求権があるものを指すのに対し、「契約資産」は法的な請求権がないものを指します。
ではなぜわざわざ「契約資産」という勘定科目を使う必要が出てきたのでしょうか?
従来の「実現主義」というのは、「収益が実現したことをもって認識する」という考え方です。
この「実現」というのは何をもって「実現」したとみなすのかというと「売掛金などの貨幣性資産を受け取ったこと」になります。
つまり、法的な請求権を伴う売掛金を受け取って初めて、収益(売上)を計上できるわけで、「法的な請求権がない状態」というのはあり得ませんでした。
ところが、「収益認識会計基準」では、「履行義務を充足」することで収益を認識することになりました。
履行義務さえ充足すれば、法的請求権がまだ発生していなくても、収益として計上しなければいけなくなったのです。
このとき、「売上」の相手勘定として「売掛金」は使えません。
そこで、「履行義務は果たして、将来お金を払ってもらえる権利はあるけれど、法的請求権はまだない状態」を表す勘定科目として、「契約資産」というものができました。
いかがだったでしょうか?
少し小難しい話になってしまいましたが、講義動画では、この辺りの内容を具体例を交えながら説明していますので、気になった方は動画の方もチェックしてみてください!
(第4章の内容になるので、動画が上がるまでもう少しかかるかもしれませんが…)
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
