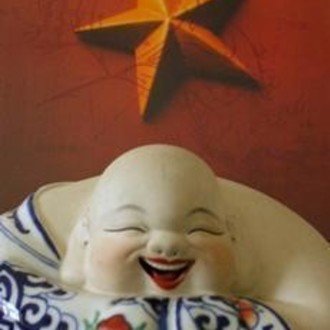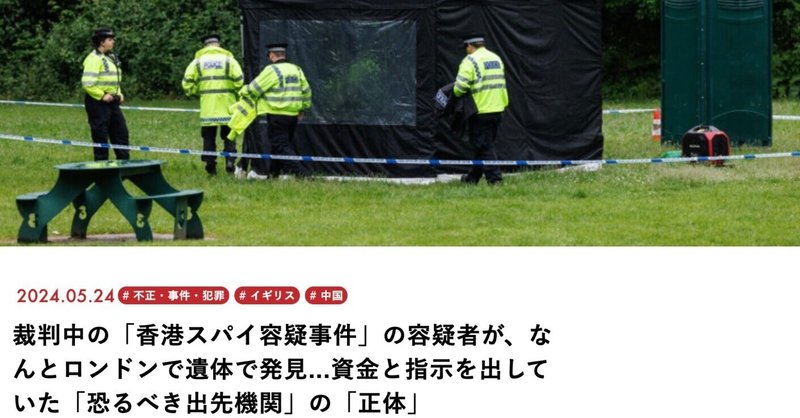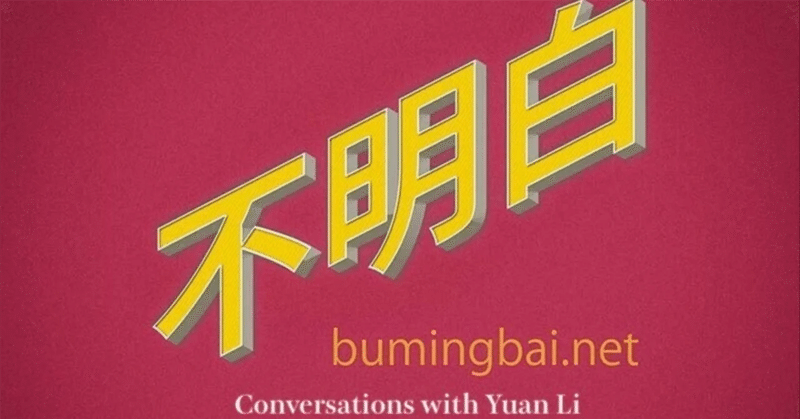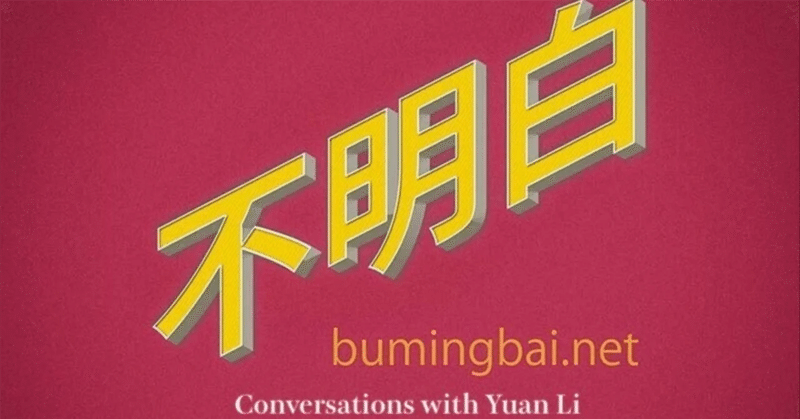記事一覧
【ぶんぶくちゃいな】世界最大級! 中国人ビットコインマネロン事件のミステリー
「中国NewsClip:『香港スパイ』事件の英国人被告、遺体で発見 死因不明」でお伝えした通り、5月13日に英国で起訴されたいわゆる「香港スパイ」事件は、19日に被告の一人であるマシュー・トリケット元英海軍兵士が遺体で見つかるという予想外の事態に発展した。
当初、ロンドン警察は同被告の死について広範な情報提供を呼びかけていたが、予定通り現地時間の24日に開かれた予備審問で、事件を担当したリバーサ
240529 【ダイヤモンド・オンライン寄稿】「私はあなたの母親じゃないわ」中国有名IT企業のやり手広報ウーマン、動画で職場ルールについて語り炎上
5月初めに中国のネットを騒がせた事件について書きました。
直後に原稿を書いたのですが、いろいろありましてちょっと配信が遅れたにもかかわらず、日本のメディアの関心をまったく惹かなかったようで記事が出てないですよね。こういうの、民心を知る意味で大事な情報だと思うんですが、たぶん各駐在記者さんたちがこの事件のカギとなっている、民心における百度の位置に気づいていないんでしょうね。で、彼らの目にはただの「
240524 【現代ビジネス】寄稿:裁判中の「香港スパイ容疑事件」の容疑者が、なんとロンドンで遺体で発見...資金と指示を出していた「恐るべき出先機関」の「正体」
「ぶんぶくちゃいなノオト」でも書いた香港スパイ事件の後続ニュースです。
というか、スパイ事件のあらましもそうなんですが、わずか1週間でちょっと予想もしていなかった展開になってしまいました。謎が謎を呼ぶ不気味な事件になりつつあります。政府直下の経済貿易代表部の名前が上がっている分、大変に厄介な話でもあり、今後の進展が注目されます。
なお、この記事の公開日24日にロンドンで開かれた裁判では、トリケ
【ぶんぶくちゃいな】前代未聞! 香港スパイ事件
とうとう、香港でも中国国内並みにVPN(Virtual Private Network)を利用しなければ、「自由なインターネット」を楽しむことができなくなってきた。
「週刊中国ニュースクリップ(2024/5/12-18)」でも取り上げたが、5月15日、YouTubeが2019年の反政府デモの「テーマソング」と呼ばれてきた「願栄光帰香港」(香港に栄光あれ)を使った動画32本への香港からのアクセスを
【ぶんぶくちゃいな・期間限定無料全文公開】Netflix版『三体』の文革シーンはリアルか、陰謀か?――わたしの文革体験(後編)
前回に続き、ポッドキャスト「不明白播客」から高さんの文化大革命(文革)を巡る当事者の回想録後編をお届けする。まだの方は前編からどうぞ。
「高さん」は今回の内容でも明らかにされるが、今年78歳の女性だが、身の危険を考慮して匿名にされている。前回の内容では、ちょうど清華大学に入学した年に文化大革命が発動されて駆り出され、結局大学生活を実際に学ぶ機会を与えられないまま、終わることを余儀なくされた世代で
【ぶんぶくちゃいな】ポッドキャスト「不明白播客」:Netflix版『三体』の文革シーンはリアルか、陰謀か?――わたしの文革体験(前編)
3月21日、世界的な人気を博している人気中国人SF作家の劉慈欣作品『三体』の実写版の放送が、Netflixで始まった。中国を舞台に中国人社会を中心にして展開する原作と比べると、さまざまな人種が登場するNetflixらしいそのドラマ版は、多くの原作ファンたちの度肝を抜いた。
Netflixは中国では配信されていないものの、Netflix自体は、中国語で「奈飛」とか「網飛」などと呼ばれてその存在は知
240425 【ダイヤモンド・オンライン】寄稿:「香港に5億ドル投じる…」謎だらけの「ドバイ王子」、AI顔認証で100%マッチした“驚きの人物”とは?
メルマガや「ぶんぶく」ではすでにご紹介した「ドバイ王子」に関する話を、掲載文字数の関係もありちょっぴりかいつまんで書きました。でもこの話題、本当は書きたいこと、もっともっとびっくりさせられる話がたくさんあって、もったいなさすぎです。
まぁ、とにかく読んでみてください。香港人もびっくりの「ドバイ王子」話です。これで5月に延期された王子のオフィスオープニングがもし、何事もなかったように開催されれば、
【ぶんぶくちゃいな】「歌う王族」香港政府を魅了する中東王子
3月末から4月初めの週にかけて、香港と中国はそれぞれ、前者がイースター連休(3月29日から4月1日)、後者は清明節連休(4月4日から6日)と連休続き。メディアもそれに合わせて休日配信体制に入ってしまい、ニュースチェックの感覚がちょっと狂ってしまった。
おかげで大変なニュースをうっかり見落としてしまっていた。
そのニュースとは、イースター休み明けの4月2日、香港株式取引所では3月末までに2023
240326 【現代ビジネス】寄稿:“ソフトパワー戦争”でも「中国の苦しい立場」が浮き彫りに...東南アジアをかき回した「テイラー・スウィフト争奪戦」
日頃から英語(系)メディアを読んでいる方はさんざん目にしたはずの話題なんですが、日本語メディアにほとんど真剣に取り上げられている様子がなかったので、書きました。たぶん、日本のマスメディアには、記事中の香港議員たちと同じように薄ら笑いして「エンタメ話題」程度としか思われていなかったんだろうな……
実は、テイラー・スウィフトのシンガポール公演がアジアに与えた衝撃はすごかったんですよ。もちろん、その動
【ぶんぶくちゃいな】国家安全条例施行、国際金融都市・香港はいったいどこへ行く?
2024年3月23日、香港の憲法と呼ばれる「香港基本法」第23条に基づき制定された、「国家安全維持条例」(以下、国安条例)が施行された。
同23条の条文にはもともとこう書かれていた(翻訳は筆者)。
今回制定された国安条例とは、この条文で触れられている行為を禁止することを目的に制定された香港独自の法令で、2020年6月に中国人民代表大会で可決された「香港国家安全維持法」(以下、国家安全法)とは別
『時代の行動者たち』書評続々
昨年12月に白水社から刊行した『時代の行動者たち 香港デモ2019』ですが、このところ続々と新聞各紙でご紹介いただいています。
●日経新聞 2024年3月9日朝刊
「多層的な運動 担い手の証言」 評者:国分良成・前防衛大学校長
●毎日新聞 2024年3月9日朝刊
今週の本棚 評者:米村耕一・毎日新聞外信部デスク
●しんぶん「赤旗」 2024年3月10日朝刊
「デジタル時代の社会運動を研
【ぶんぶくちゃいな】「Hong Kong is over」がもたらした激震
「Hong Kong is over.」(香港は終わった)と書かれた記事が香港で大激論を巻き起こしている。
記事を書いたのはスティーブン・ローチ氏、元モルガン・スタンレーのアジア地区主席アナリストで、現在は米エール大学の教授を務めている。2007年から12年まで香港を拠点としてアジアの経済分析を担当し、中国に対してどちらかというと楽観的、好意的な論を展開する中国経済専門家としてその名前を知られて