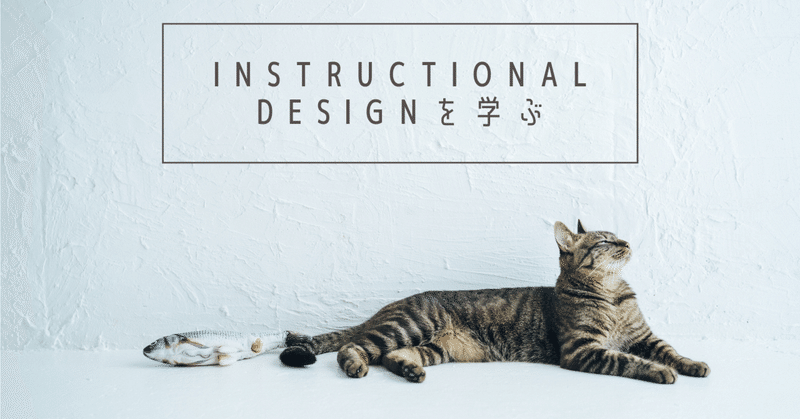
学習意欲デザインプロセス ID学 vol.11
やっぱり1日6時間を週5日教えるのってきつくないですか、まったく。シラバスや教材その他の環境によると思うけど、JLPT対策の新完全マスターシリーズを中心に語彙、文法、読解、聴解をプロジェクターなし、プリンターなし、既存の副教材なし、何にもなしでやるのって、本当にきついんですけど。ということで、なかなか進まないわけですよ、本読みが(言い訳ではないと信じたい)。やりっぱなしになっていた学習意欲デザインの試作についてまとめます。
J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
学習意欲の問題を見つける(分析)
まずは現状または予測を分析する4つのステップ。
①科目の情報
②学習者の情報
③学習者の分析
④教材の分析
どんな動機付け対策が有効か、現状の動機づけ対策に過不足がないかなど、動機付けに関する問題点を明らかにすることが目的。どう教えるかとか、どうしたらわかりやすいかとか、どうやったらアクティブになるかとかは、ここでは関係ないことに注意。ちょっとは関係あるだろうけど、しっかり分けて考えないと分析している間に迷子になる気がする。
科目の情報
科目名、目的、教える内容などについて書き込んでいく。他の科目との関連性や授業で使用できるハード面の情報、インストラクターなどソフト面の情報も洗い出す。さらに、期間や頻度、新規か既存か、今後継続されるのか、1回限りかなども確認する。これは(1)科目の目的に合った動機付け方策を設計する(2)動機付けデザインにかけられる時間と労力を見積もる(3)実現可能性を担保する、ためのステップである(と理解した)。
実際やってみた感想ですけど、これやるべきですね、動機付け方策云々に関わらず。これをやってからの教材選択やカリキュラム作成であるべき。しかも、教師自身にやはり経験や知識が必要。スリランカに来て初めて本格的にJLPT対策をやりはじめて約3か月、たぶん以前は書けなかったであろう「教える内容」の文言がちらほら出てきた。3か月の学生の観察から、むくむくと出てきたものだと思う、たぶん。それでもまだ、読解や聴解では具体的なそれらしい文言が見えるけど、語彙や文法は「教科書の語彙をすべて理解語彙にする」とか「知識を練習問題で応用できる、理由をもって正答できる」みたいな、結局は「教科書を丸覚え」的なことしか書けず… しかし、JLPT対策でほかに何を教えるんだろうか。「わからない語彙や文法を自力またはピアと協力して理解することができる」とか?(というか、そうさせる以外どうやって授業すればいいかわからない)
「教える内容」を書くつもりが、Can-doになっちゃったけど、ここのビジョンが教師にクリアに見えていると、繰り返すけど動機付け方策云々の前に、非常に楽だと思う。
学習者の情報
いわゆるレディネスだけど、クラスとしての性質も分析する。比較的均質か、上位集団・下位集団にわかれるか、まったく不均質か。また、クラスの学生同士が知り合いか、どの程度知っているのかなども確認する。これは内発的動機、とくにデシの所属感にも関係しそうである。学習者の学ぶということ全般に対する意欲や態度、そして、この科目に対する意欲や態度も予測する。さらに、学習者が慣れている教授法を書き込む。
このクラスを担当して2か月ほどだったので、予測ではなく現実を書き込んだわけだけど、それでわかったことは、教師として学習者に非常に恵まれているということだった。動機付け方策なんていらないんじゃない?という疑問まで生まれる始末である(動機付けはやりすぎると逆に動機を削ぐ恐れがある)。とりあえず、試作なので先に進む。
学習者の分析
学習者の情報をもとにARCSで分析を行う。
注意 学習者が科目に対して抱く好奇心や注意
関連性 学習者が科目に対してもつ道具的動機
自信 科目のレベルの適切性
満足感 学習者が科目から得るであろう結果への態度
本には各項目に対する説明やモデル分析が載っているが、いまいち「答え」がわからない。たとえば、注意は科目(教材と書いてある)に対する好奇心や注意とされているが、教師や教室などは含まれないんだろうか。外国語学習ではじめてネイティブ教師が担当するとなったら、好奇心(不安感)は強くならないだろうか。関連性は内発的動機の予測は必要ないんだろうか。現在のクラスはどう見ても所属感が強く、これが内発的動機に移行するのではと思うんだけど、それは書くべきか、書かざるべきか。などいろいろな疑問を抱えながら学習者分析を行い、vol.4でやってみた分析に比べて、かなり記述が厚くなり、また逆U字曲線上のプロットも変わった(そもそもクラスが違うけど)。

◆ 結果をみての所感
関連性
・道具的動機が強くなりすぎないよう何らかのケアが必要
自信
・漢字、読解、聴解にそれぞれ苦手意識をもつ学生が多く、レベル調整やステップ設定が必要
満足感
・NATテストおよびJLPTの結果に左右される可能性が高いため、テスト結果が満足感につながるようにテスト前の工夫が必要(達成可能な目標を明文化するなど)
・個人的なフィードバックなどがあれば尚よし
教材の分析
学習者分析をもとにARCSで分析を行う。11章には動機付け方策チェックリスト(p. 297)があって、それを使ってもよいと書いてある。また、ARCSそれぞれについて良い点、悪い点を書き出すワークシートも載っている。とくに、動機付け方策として足りない部分や過剰な部分を記録することで、それらをデザインによって改善できるという流れ。
チェックリストもワークシートもちらっと見たけど、ここまでくると結構本当に大変。ということで試作はここで断念。おしまい(え?)。
ARCSと簡単にいうけれど

大学院の講義でARCSについてレポートを書いたけど、背景にこんなに理論があるとは知らなかった。それを知っているのと知らないでいるのでは、ARCSを構成する層の厚みがかわってくる気がした。厚くなったからいいのかといえば、よくわかんないけど、とにかく考える幅と深さは出たような気はして、いまのところはそれでいいか(そろそろ次の書籍を読みたくなっている)。ステップ5へつづく。
