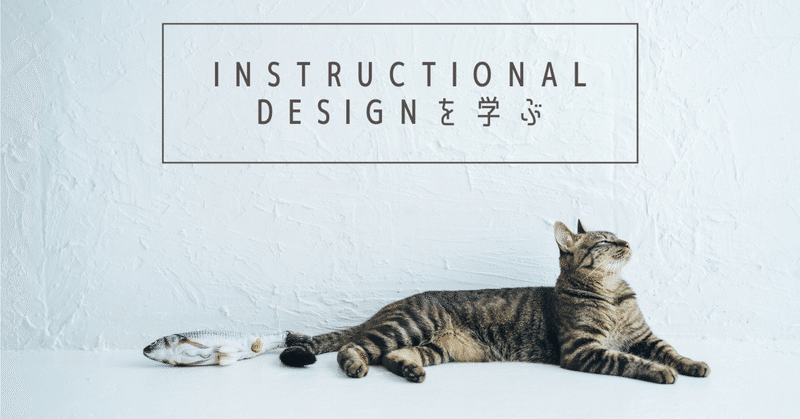
動機づけの目標と方策 ID学 vol.12
ようやく本題に辿り着いた感がある第9章「動機づけの目的と方策を練る」。どう考えても動機づけの目標じゃないかと思うのだけれど…
ずっとこの章で足踏みしていたのは、この章が大切でこの章をしっかり理解するためにここまで読んできたのだと思っていたからである(まさに期待が高すぎて動機づけが削がれる事例)。
これら動機づけ目標(motivational learning objective)を、授業の目的に関連してあなたが学習者に経験してほしい態度や感情といった情意的な学習目標(Affective leargning objective)と混同させてはいけない。
ここで引っかかって、前に進めなかった。動機づけ目標と情意的な学習目標の違いは何か。ここを読んだだけでは、わたしにはまったくわからない。「科目の学習目標を達成したかどうか」「学習が進んでいるかどうか」とは違うというのはわかる。あくまでも動機づけの目標だから。でも、「情意的」ってそういうことじゃない気がする。
J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
動機づけの目標と情意的学習目標
インターネットで調べても答えが見つからないので、最後の手段、ChatGPT-3.5に聞いてみる。ちなみに、Google Bardにも聞いてみた。
1. Affective Learning Objectives:
Affective learning objectives target the emotional and attitudinal aspects of learning. They are concerned with shaping the learner's feelings, values, beliefs, and motivations. The primary focus is on developing positive attitudes, fostering empathy, and nurturing social and emotional growth in learners. Affective learning objectives aim to influence the learner's affective domain and cultivate desirable emotional and attitudinal attributes.
2. Motivational Learning Objectives:
Motivational learning objectives, on the other hand, concentrate on the factors that drive and sustain a learner's motivation to engage in the learning process. They aim to enhance intrinsic motivation, self-efficacy, and the desire to learn. Motivational learning objectives emphasize developing skills such as goal-setting, self-regulation, and cultivating a growth mindset. The primary focus is on enhancing the learner's motivation, self-directedness, and perseverance in their learning journey.
To summarize, affective learning objectives focus on shaping the learner's emotions, attitudes, and values, while motivational learning objectives concentrate on enhancing the learner's motivation, self-efficacy, and goal-directed behaviors. While both types of objectives are crucial in education, affective learning objectives primarily target emotional and attitudinal growth, while motivational learning objectives primarily target enhancing intrinsic motivation and self-directed learning skills.
Google Bardちゃんは、このような表を作ってくれました。

どちらも言っていることはほぼ同じで、言及している側面が違うということらしい。ALO(Affective Learning Objective)は学習者の科目に対する感情や態度を対象にし、MLO(Motivational Learning Objective)は科目に対する動機を対象にしている。
そりゃ、そうでしょうね。
Bardちゃんの表を見ると、ALOはより学習者の内面を重視し、MLOは学習者が動機づけされたことで起こる行為に着目している感じはある。ChatGPTもMLOで "enhancing the learner's motivation, self-directedness, and perseverance in their learning journey." として、学習者の自己コントロールや目的指向性、学習(動機)維持の何らかの行為を示唆している(気がする)。
ということで、わたしの理解は以下のようになりました。

MLOをALOが包括しているということで、要するに動機づけの目標ではMLOだけを注意深く選択して、その他の目標は除外しましょうということかなというところで、深追いをやめました。
本にも次のように書いてある。
この文脈における目標とは動機づけプロジェクトの目標である。(中略)つまり、あなたの授業の受講生が授業への意欲を好転した際の変化を示すものである。
動機づけの目標を記述する
目標を設定する上で大切なこと
・これまで作ったワークシート(科目の情報・学習者の情報・学習者分析)を参照すること
・設定できる目標には2種類あること
(1)既存の授業に内在する問題を解消するための目標
(2)動機付けを持続させるための目標
・観察可能な(目標達成の)評価方法を設定すること
ワークシートの例を見ると、「注意をひきつけられ続けたと話す」とか「自信を示し続ける」とか「熱意を表す」などの言葉がある。なんとなくわたしのMLOの理解とは違う気が… 動機づけに直接関連した項目ではあるけれども、自信とか熱意って感情だし、ALOじゃないの?ということで混乱。
でもここで大切なのは学習意欲デザインを進めることであって、ALOとMLOの違いを明確にすることではないので、まあいいか。これらの目標は主にアンケートで評価されている。
動機づけ方策をリストアップする
動機づけ方策リストを作成する上で大切なこと
・その方策の効果が永遠に続かないと理解すること
・視野を広げ、どんなアイデアも除外せずにリストに載せること
・動機づけ方策にかける時間や労力が、実際の運用に見合うものかどうか精査すること(動機づけはインストラクショナルデザインの1部であり、動機づけ方策が、ほかの教授方策より優先されることがあってはいけない)
ワークシートはARCSの4項目を縦に、実施時期(科目開始期・実施中・終了期・終始)を横にとった表形式になっていて、そこに作成済みの教材分析のや11章の動機付け方策チェックリスト(p.297)、その他専門書などを参考に視野を広げて方策をリストアップしていく。
動機づけ方策を選んでデザインする
思いつく限りリストアップした方策リストから必要なものを選ぶ。ここで素敵なのは、方策リストではARCSに分かれていたワークシートが、ここでは分かれていないこと。これは動機づけ方策の統合について考えてほしいということだそうで、ワケもなく「素敵」と思ったという感想を書き留めておく(ただし、方策の文末に(A)などのARCSいずれの分類かを書けという指示はある)。
ここで学習意欲のデザインにおける主要原理。
すでに学習意欲のある学習者を動機づけしようとするべからず!
もし学習者がすでに高く動機づけられている場合、効果的なインストラクショナルデザインや学習意欲の持続に焦点をあてること。過度の「動機づけ強化策」はむしろ学習の進捗を妨げ、学習者をイライラさせることになるだろう。
今のクラス、まさにコレだと思う。うすうす気がついていたけど、早く言ってよ。
学習意欲デザインとは
デザインプロセスの章に入ってから、ワークシートの例がピンとこないの連続で(しかも明確にどことは言わず「陥りやすい間違いもあるから注意!」などとあって、どれが間違いなのかわからないわたしは疑心暗鬼に陥る)、実は理論以上に読みにくかった。でもそれは、今の動機づけされたクラスに当てはめて考えるからで、動機づけに問題を抱えるクラスであれば、もう少し理解しやすかったのかもしれない。要するに、動機づけに関する問題点を炙り出し、その問題点を元に動機付け目標を設定、方策を選択、ということなのだろう。そして、それは学びの場それぞれに異なるため、例にある「企業内研修」や「小学校教育」が自分の環境と全く違う場合、あまり参考にはならないということなのかもしれない。また、動機づけがすでにあるクラスであれば、動機づけ維持に焦点をあて、おそらくRCSについて注意深くデザインを維持するとともに、Aについて適度に新奇性を注入していくということになる(のかしら)。
