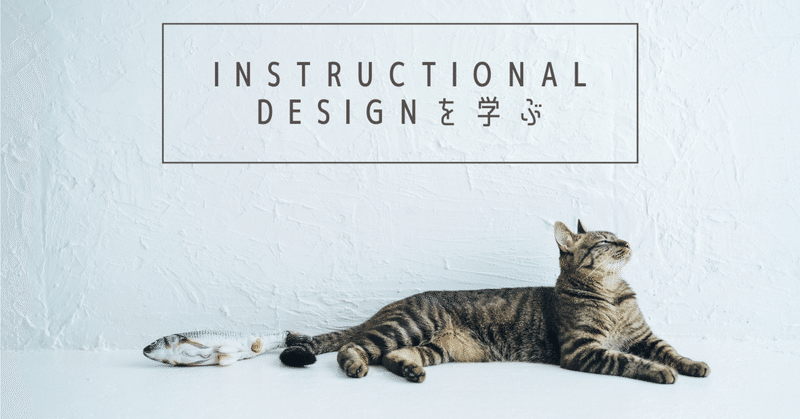
動機づけ方略チェックリスト ID学 vol.13
J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
いよいよ読了に近づいてきた。vol.12までで動機づけのデザインプロセスは終わり、あとは実際の教授デザインに組み込んでいくワークシートと、教材を開発または選択する際のチェックリスト、デザインの評価と改善をおこなうためのチェックリストが載っている。それはもう、とんでもなく必要になって切羽詰まらなければやらないであろうワークシートで、できるだけこまめに、利用できる機会を虎視眈々と狙うのみである。
それについて読み飛ばして、ここで何をしたいかというと、なんとなく失敗に終わった感のあるJLPT対策コースへの『読む力ー中級ー』(くろしお出版)の導入について、11章にある学習意欲デザイン便利ツールの1つである「動機づけ方策チェックリスト」を利用した猛省であります。終わってみての直感的な感想は以下の通り。
・テキストのレベルがちょっと高かった(初中級でよかったかも)
・問題数が多すぎて、教師もうんざりする
・メタ認知能力への着目は素敵だが、学生が理解していない
・使う時期が悪かった(JLPT直前に使うのは得策ではなかった)
動機づけ方策チェックリスト
ARCSの4要素それぞれがもつ下位3要素の合計12要素にわたって、チェック項目が73もある(数え間違いじゃなければ)。純粋に教材だけに注目するのか、教材の授業での提供の仕方(足りないものを補ったり、多すぎるものを削ったり)も考慮に入れるのかわからないけど、今回は失敗の原因と次回への活かし方を考えたいので、授業での提供の仕方までを評価対象とする。
チェックリストの使い方は、それぞれのチェック項目に対して①満足②不足③余分の3スケールで評価する。休日にやることではないが、とにかくこの本とオサラバしたいのでやってしまおう!
*ただし、各項目3スケール評価をしていると日が暮れるので(もう暮れかけている)だいたいのところをまとめるにとどめ、かつ、担当クラスにあてはめたチェックで、一般的な評価ではありません。
注意(Attention)
A1 知覚的喚起(具体性)
導入の話題が具体的か、一般的な原理や抽象概念を具体的な例や比喩を使って提示しているか、整理されたリストやフローチャート、図などで視覚的にわかりやすく提示されているかなど。
各課にブレインストーミングのページがついているので、それをCanvaで絵や写真を利用しながら(できるだけおしゃれな感じで)学生に提示し、いくつかの質問に対してグループで話した後、全体でシェアする時間を設けた。
読解スキル(メタ・コンテンツ把握能力や認知スキル)は説明が抽象的で学生の興味をひくのに失敗した。実はわたしも読解スキルの評価表(読解タスクと身に付くスキルの関係)が見にくいと思っている。
全体的に白黒で字が多く(読解なんだから当然だが)ときどき図やフローチャート、表などがある。
A2 探究心の喚起(好奇心の喚起)
探究心を刺激する問題(新しい知識を身につければ解決できるものや、これまでの経験と矛盾するものなど)や、ミステリーを演出する視覚的要素などが使われているか。
授業の冒頭で、読むことで答えがわかる質問を提示したりはしているけど、読解文の種類によって魅力的なときもあれば、そうでないときも、提示できないときもある。トピック自体はおもしろいものが多いとは思った(けど、学生がどう思うかは人それぞれ)。
A3 変化性
レイアウトや素材、文章表現、構成要素の順番の変化など。
エッセイや説明文など、読解文の種類は変わる。そのほかは変わらない。わたしの授業の流れも変わらない。
関連性(Relevance)
R1 目的指向性
教材の現在の価値(直接的な利点や内発的満足度を高める記述など)、将来的な価値(将来の目的達成や興味がある領域の学びに役立つか)が明らかか。
将来の目的をJLPTとすると、教師は役立つと思って採用したのだが、目的に向かってリニア的発想の学生にとっては役立つとは思えないといったところか。明らかかといわれれば、JLPTへの言及もないわけだし、明らかではない。現在の価値に関しては、読解そのものを必要と感じないようだし(今回に限らず「この読解は日本の生活に役に立つのか」と何回も聞かれている)内容が工学系になれば内発的価値が生まれるのかもしれないが、不運にもそういうものは少なく、かつ、そういうものは語彙が難しい。
R2 動機との一致
人間味のある表現が使われているか、達成への努力や成果を示す事例や達成に伴う感情を伝える事例、達成や成功までの道のりや感情をイメージするよう学生に促しているか(←ここまで意味がよくわからない)。多様な学習スタイル(グループワークや競争など)を含んでいるか、成功モデルを提示しているかなど。
学習スタイルは冒頭のブレインストーミング以外はほぼ個人作業で、学習スタイルの多様性は乏しい。成功モデルは提示していない(だってないんだもん)。
R3 親しみやすさ
既存スキルや知識、経験との関連が示されているか、積み上げるものになっているか、学習者が課題を選択できるかなど。
できない!
自信(Confidence)
C1 学習要求
学習の成功が観察可能な行動として明示されているか、学習者自身が学習目的や目標を書き記すための手段があるか。
各課に読解スキルの評価表があり、読解タスクの理解度(正誤)をチェックすることで、スキルが身についたかどうかが確認できる。ただし、前述したように見にくい。
C2 肯定的な結果
難易度が適切か、易しい課題から難しい課題へと段階を踏んでいるか、ひっかけ問題や難解な練習が含まれていないか、自己評価の手段があるか、フィードバックがあるかなど。
課にもよるが、比較的難易度が高かったかもしれない。読解以前に知らない語彙だらけという課もあった。ひっかけ問題や難解な問題はなく、理解を進めるための素直な問題がほとんどだが、なんせ問題数が多い。準備するわたしもうんざり。自己評価の手段としては前述したように読解スキル評価表がある。フィードバックは答えチェックぐらい。
C3 自己責任
学習者に選択権はあるか。
教材の流れは選択できない、ペースも選択できない、練習方法も選択できない、学習環境も選択できない、授業の改善案などを書き残す機会もない、ないない尽くしである。
満足感(Satisfaction)
S1 内発的な強化
新しく獲得したスキルや知識を実際に使う機会があるか、成功や努力に対する肯定的なコメントや称賛があるか、習得した学習者が未習得の学習者を助ける機会があるかなど。
うーーーーん、試験で実践できるという建前だが。肯定的なコメント、賞賛、協働いずれもなかったな….
S2 外発的な報酬
単調なドリルなどでゲームなどを用いて報酬を与えているか、報酬などによって内発的興味を強化しているか、公の場で称賛したり、修了証のような成功に対する報酬を準備しているかなど、オペラント条件付けに近い領域。
まったくない。
S3 公平さ
テストなどの最終評価の内容や難易度は教材と一致しているか。
最終評価はしていないので、ない。
動機づけ方策チェックの結果
注意(Attention)
教材だけでは学習者の注意を喚起・維持するには不足だといえる。導入部分では視覚的な副教材等をもちいて、問題提起をすることが必要だろう。これはやった。しかし、この教材の肝である読解スキルの説明や仕掛けを完全にサボったところが、まず敗因の一つといえる。読解スキルを視覚的にわかりやすく説明すべきだったし、それをJLPTと関連づけるべきだった。ただし、準備不足ではあったがやろうとした自分はいて、本当の敗因は、それを学生が求めているかどうかを見誤った点かもしれない。教材単体では【注意】の項目に不足があるが、適切に授業をデザインすれば、十分魅力的な教材だと思う。
関連性(Relevance)
そもそもJLPT対策向けの教材ではないわけなので、基本的に関連性は不足している。試験対策以外では読解に必要性を感じていない学生が多いので、さらに関連性は乏しい。JLPTと関連づける工夫が必要。学習スタイルの多様性や選択権など、JLPT対策の読解授業という設定との相性もあって、まったく足りていない。授業のデザインでフォローできる部分ではあるが、それを考えるなら、採用する時期を間違ったの一言に尽きる。
自信(Confidence)
教材自体は、成功を可視化し(読解スキル評価表)自分に何が足りないのか、逆に何が得意なのかチェックできるシステムなのである。しかし、なんせ見にくいし、抽象的でわかりにくい。ここに教師はかなり注力する必要がある。選択権も含め、授業デザインを考える。ここを工夫すれば、読解タスクの多さにうんざりして集中力を切らすといった事態も避けられるかもしれない。難易度に関しては、検討不足だった(一時帰国したときにパッと買っちゃったもので)。また、語彙の難易度などを考慮して、順番を変えてもよかった。
満足感(Satisfaction)
いずれも足りていない印象。この教材を経て、読解問題の正答率が上がるなどの体験をしなければ、満足感は得られないかもしれない。
チェックしてみると、失敗するべくして失敗したのだということがわかる。総括すれば、結局のところはじめに書いた「終わってみての直感的な感想」に行き着くのだが、それが具体化し、動機づけ方策をリストアップするための参考になることもわかった。
5か月かけて、学習意欲のデザインについて読み、学んできました。ARCSの土台となる理論について読みかじったことで、目の前で起こっている現象を分析する姿勢が出てきたかなと思う。しかし、11章で紹介されていた簡略版じゃなくて、フルバーションでデザインしようとすると時間も労力もものすごくかかりそうだと思ったし、チームでやったほうが独りよがりにならなくて効果的な気がした。手分けもできるし。そもそも、バリバリに授業数こなす教師がやるものじゃない気が… かといって、簡略版でデザインする自信もない。しかし、とにかく読んでよかった、自分の厚みが増した気がした。できるだけ間をあけずに次の本を読もう、そうしよう。
