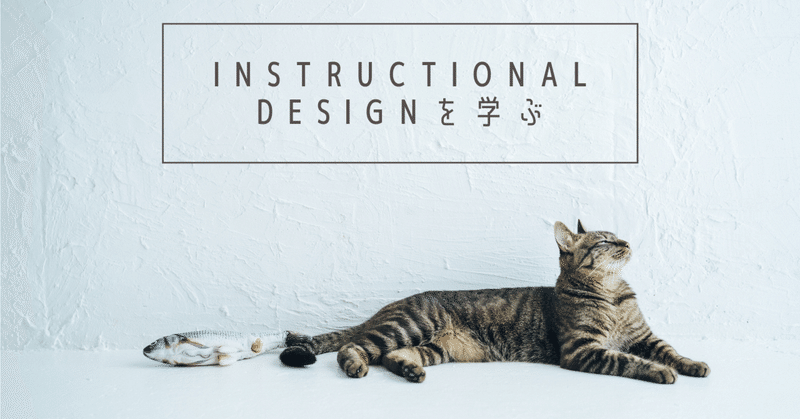
Satisfaction(満足感) ID学 vol.10
ARCSモデルのS(満足感)まで辿りついた。いまスリランカの世界遺産の町【Galle】のホテルでこれを書いている。いそがしくてぜんぜん勉強できなかったから、スリランカのお正月休みにこれをアウトプットできたのはよかった。ホテルも居心地いいし、楽天ゴールデンイーグルスが連敗をとめたし、鈴木大地選手が一軍スタメン出場(祝)だし!よかったよかった。

J. M. ケラー(著)・鈴木克明(監訳)『学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザインー』(北大路書房)
外発的強化と内発的動機
外発的強化の関わる理論
・古典的条件付け
・オペラント条件付け
・トークン強化システム
パブロフの犬に代表される古典的条件付けからイメージされるように、雑にいえば報酬や罰を通して学習をコントロールする方略の下敷きになる考え方、ですので外発的動機を刺激することで学習を促す。
ここでのポイントは、この外発的強化と内発的動機の関係性だと思う。書いたか書いてないか忘れたけど、すでに内発的動機をもっている学習者に対して外発的動機付けを行うと(達成したらご褒美とか)動機が弱まることが研究で実証されている。したがって、ヤミクモにご褒美を与えることは危険である。すでに内発的動機がある場合、動機を損なうことなく外発的強化を行うには、その強化が学習者のタスクに対して内因性をもたなければならない。つまり、学習者の努力や達成そのものに関連性のある強化、例えば、肯定的なフィードバックなどであれば有効だという。
じゃ、達成したらアイスクリームといった外発的強化は避けるべきかといえば、そうでもない。Deciの有機的統合理論を思い出してほしいんだけれども、外発的動機を内面化させることは可能である。要するに、はじめはアイスクリームに惹かれていた学習者も、学習を進める過程でなんらかの感情を経験し、より内発的な動機をもつようになって、アイスクリームのことは忘れるという現象も起きうるのである。したがって、内発的動機のまったくない状態においては外発的強化が有効だということになる。
満足感の相対性
満足感とは、学習の結果そのものによって決まるものではない。満足感とは、学習者が事前にもっていた期待感や、他者が得た結果や報酬との比較によって相対的に定まるものである。
たしかに。受講前の期待が大きく、結果がその期待を下回ったと感じたら、満足感は低くなる、というか不満である。結果が期待感を上回り満足感に浸っていたのに、ほかの学生がそれ以上の結果や報酬を得ていて、がっかりすることもある。このあたりにも、満足感を引き出すヒントがありそう。
その他の理論
・認知的不協和理論
・バランス理論
・公平理論
だいたいこうやって箇条書きにするときは、あまり興味がないか、よく理解できないかのどちらかでありまして、この3つの理論は各々は比較的理解できたと思うのだけれど、これらをどう消化していいかよくわからない。認知的不協和理論の研究はへーと思ったけど、Youtubeビデオがあるところをみるとかなり有名らしい。
退屈きわまりない実験に参加した後、つぎの参加者に「おもしろかった」と嘘をつかされて報酬を受け取るというものなんだけど、20ドルという比較的高い報酬を受け取った参加者は、実験後のインタビューで「実験はおもしろくなかった」と回答した(これ普通)。一方、1ドルしかもらわなかった参加者は「実験はおもしろかった」と回答した(おもしろくないんだってば)。これは、20ドルの参加者は嘘をつく行為と報酬が釣り合い変化を起こす必要を感じなかったが、1ドルの参加者は安すぎて嘘をつく行為に認知的矛盾を感じ、その不協和状態を脱するために意見を修正した(実験はおもしろかった)とされている。つまり、不協和状態を協和状態にもどすために行動が起こるという理論である。これが満足感とどうつながるのか、いまいちわからない。
バランス理論にしても(わたしにとっては)同じようなもので、公平理論は自己と他者の比較によって公平不公平を感じるといったところから、満足感へとつながるのはなんとなくわかるけれども、といったところ。
満足感を高めるための方略
内発的な強化
・獲得したスキルを使用する機会を与える
・努力や達成に対する肯定的なコメントやフィードバック
・タスクを達成した学生が未達成の学生を助ける機会を与える
・タスクに関連する新しい情報や応用的な情報を提供する
・さらに継続して学習するために何をやるかについて問いかける
外発的な強化
・トークン強化システムのような楽しいゲーム的な要素を盛り込む
・学習者が予期も制御もできないような報酬を与える(と内発的におもしろいタスクになるらしい)
・タスクに取り組んでいる最中や達成後に、各学習者に(教師の?)個人的な注目を与える
・新しいスキルを習得しようとしてるときは強化を頻繁に用いる
・タスクに精通してきたら強化は断続的にする(減らす)
・脅威や監視を避ける
・達成後に象徴的な報酬(証明書など)を与える
公平な待遇
・目標や学習内容、練習問題、テスト問題を一致させる
シラバスから評価(基準)まで一貫させるということですね。
内発的な強化と公平性についてはそうだろうねと思うものだったので、興味をひいたのは外発的な強化の方略かな。報酬のタイプや与えるタイミングなど、あまり考えたことなかった。
ARCSモデル
ここまで読んできて、ARCSモデルについて以前よりだいぶ深まったはず。少なくても、vol.4でやってみた学習者分析におけるARCSそれぞれの項目がかなりざっくりで、若干方向性も違うような、曖昧な印象を受けた。そもそも、学習者分析とかいって、授業分析に意識がいっている気配もある。
現時点での簡易メモ(わたし的まとめ)
【Attendance(注意)】
・好奇心をひき起こす刺激には知覚的なものと知的なものがある
・しかし、いずれにしろ好奇心は減退する
・ということだから、クイズ(知的不快感の設定)もいいが
・ルーティンにすると好奇心を刺激できなくなる可能性がある
・かもしれないなと今危惧している
【Relation(関連性)】
・人は目的への最短ルートで達成まで継続するものである
・学習者がその最短ルートをどう設定しているか
・について、教師の都合で考えないことが大切(自戒)
・学習者の将来への展望や態度も大きく影響
・道具的動機と内発的動機の混在とレビンの場の理論
・ということで人って複雑
・デシの自己決定理論や有機的統合理論はおもしろい
・外発的動機は内面化できるし
・人とのつながりや学習スタイルの一致も内発的動機を高めうる
【Confidence(自信)】
・自分で学習をコントロールして結果を出したという感覚が大事
・特性としては統制の所在が内的だとよし
・課題に対して自己効力感が高いとよし
・しかし、だからといって安心できない(教師自ら損わないこと)
・ゴール指向性を高めるためのTARGETもチェックの価値あり
【Satisfaction(満足感)】
・満足感とは相対的である
・内発的動機の維持と外発的強化のタイプやタイミング
全体として、やはり学習者自身が自ら学ぶためにどう環境を設定するかが何より大切だと感じた。また、学習者分析やコーチングの重要性を認識した。
