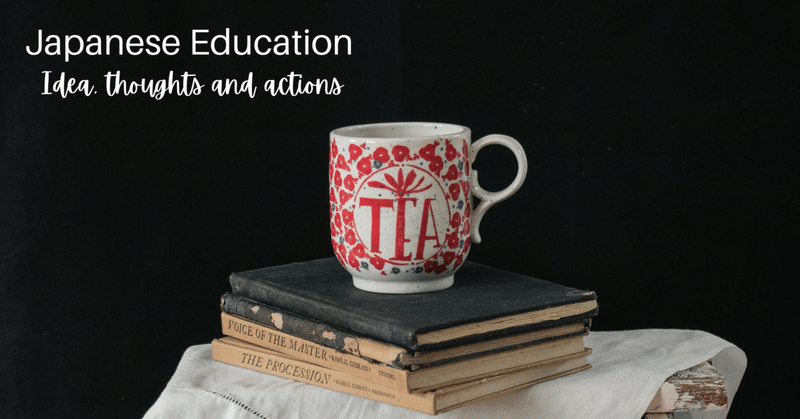
文章理解モデルから読解の授業についてちょっと考えてみた
スリランカでJLPTのN2を目指す学生を教えているけど、みんな読解が恐ろしくできない。つい先日は「読解大っ嫌い」とまでいわれる始末。思い返せばモンゴルでも「文の意味はわかるけど、何をいっているのかわからない」と禅問答のようなことを述べる学生もいたっけ。
ARCSモデルを勉強するかたわら、こんな本を読んでみた(決してARCSモデルの本に飽きて投げ出しているわけではない)。
小林明子ほか『日本語教育に役立つ心理学入門』(くろしお出版)
どこかで嘆いた通り、ARCSモデルを紐解くと心理学の理論が延々と続くため、「心理学入門」を読めば少しは理解が深まるのではと思ったからである。結果、ARCSモデルをひいひいと読み込んだおかげで、この本に書かれていることはほとんど知ってるという本末転倒な現象が起きて、本を選ぶって難しいわんと思った次第です。
とはいいつつも、やはりいろいろ確認できたり、考えたりはするもので、とくに第4章「文の理解」、さらにとくにVan Dijk & Kintschの文章理解モデルはおもしろい。はじめの修士論文のテーマが「読解」周辺(ボツになった)だったので、この理論を引用した論文も何本か読んでいて興味はあったが、今回改めて読んでみて、読解嫌いの学生と自分の読解授業に思いを馳せたわけである。
文章理解モデル
くわしくはVan Dijk & Kintsch(1983)を読んでいただくとして、このモデルでは文章の理解が以下の3つの段階で説明されている。
①表層形式
②テキストベース
③状況モデル
「表層形式」は語彙や文法などを含め書かれていることが理解できる段階、「テキストベース」は書かれていることから命題が取り出せる段階、「状況モデル」は命題と自分の既知知識や経験、スキーマが結びついてより深い理解に進んだ段階である(と理解している)。ちなみにこのモデルの説明は「日本語教育に役立つ心理学入門」で非常にわかりやすく書かれていた。
テキストベースから状況モデル
はじめにこの理論を読んですぐ思う浮かべたのが「文の意味はわかるけど、何をいっているのかわからない」という禅問答である。なるほど、学生は文中に知らない語彙はないし、知らない文法もないし(表層形式)、したがって文の意味もわかる(テキストベース)のだが、それを自分の既知知識や経験と結びつけることができないのだろう。すなわち、テキストベースから状況モデルへの移行に何らかの問題があるのだろうと納得したわけである。以来、わたしはスキーマの活性化やピア・リーディングなどの活動に力を入れてきた。
表層形式からテキストベース
今回、ひさしぶりにこの文章理解モデルに触れて、研究テーマを探しているわたしは(修士論文のテーマとは決別しそうになっている、少なくても次の学会発表の査読に落ちたら決別する)日本語教育と文章理解モデルについての論文をさくっと検索してみた。
櫻井直子(2019)「第二言語としての日本語の読解ー低次レベル処理に焦点を当ててー」『日本大学大学院総合社会情報研究科紀要』26,273-284
未熟な読解者は表層形式からテキストベースへの移行(低次レベルの処理)にワーキングメモリの容量を大きく割くため、状況モデルまで至らない(高次レベルの処理)という。したがって、低次レベルの自動化を促すことが必要と書いてあった。
なるほど、捉えた現象は同じである。語彙や文法がわかって、文の意味はわかる(テキストベース)。だからわたしは状況モデルへの移行を手助けする授業をと思っていたが、この論文は、だからテキストベースの作成を自動化できるよう指導を工夫すべきだという。
ワーキングメモリの容量ということを考えると、なるほどですね、と納得。
授業のマイナーチェンジ
いま教えているN2クラスでは、あまりにも読解ができないため、ひたすら練習問題という戦略を捨てて、この教科書を使っている。
奥田純子(監修)・竹田悦子ほか(編著)『読む力ー中級』くろしお出版
すでに3課まで終わったが、これまでは認知タスクに力を入れていた。しかし、実は言語タスクこそしっかりやるべきなのではと考えてみた。言語タスクによりテキストベースがきちんと作成されれば、学生の本来の読解力で状況モデルへの処理ができるのではないか、認知タスクは放っておいてもできるのではないかと考えたわけである。放っておいてもはいいすぎだけど、そこは学生の認知能力を信じるべきではないかと思っている。ということで、明日は授業だ。
