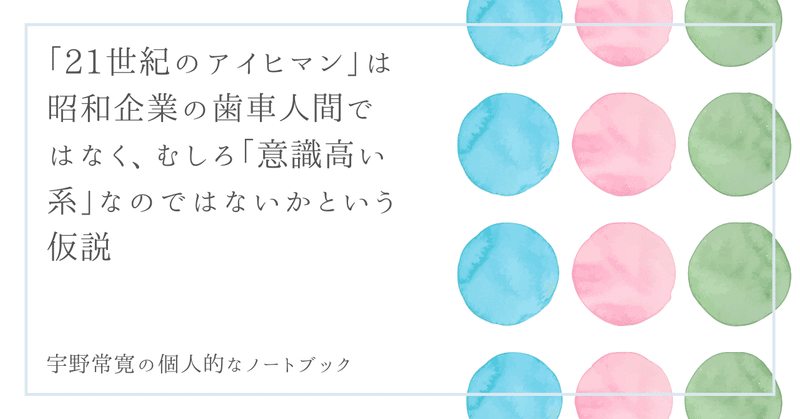
「21世紀のアイヒマン」は昭和企業の歯車人間ではなく、むしろ「意識高い系」なのではないかという仮説
さて、連休中に今更だけれど『〈悪の凡庸さ〉を問い直す』を読み、考えこんでしまった。これは昨年『ナチスは良いこともしたのか』で話題を呼んだ田野大輔と小野寺拓也の編で、ハンナ・アーレントの『エルサレムのアイヒマン』に登場する〈悪の凡庸さ〉という概念について議論したものだ。
今日の日本において、〈悪の凡庸さ〉という概念はアーレントの意図から半ば離れたかたちで定着しつつある。それはつまり、「難しいことや負荷の高いことは考えたくない」人間たちが、組織や共同体の命令や場の「空気」に流されて、何も考えずに「悪」に加担するという意味で用いられている。しかし、この傾向は人間を考えさせない組織やメディアなど環境こそが問題であるという理解を促進し、結果的にナチスのイデオロギーに内在する「悪」を軽視させる効果をもたらしてしまう。これが問題ではないかーーというのが、おそらくは本書の出版が企画された動機だろう。
さて、僕が本書を通じて考えたのはこうした意図(基本的にその問題意識は「正しい」と考える)はやや別のことで、アイヒマンの現代性のようなものだ。要するに、今や「俗語」となった「悪の凡庸さ」とは、アイヒマン本人がどうであったかという事実とは無関係に、組織の歯車として機能し、思考停止した人間が無自覚に悪に加担するケースのことを指す。しかし本書が指摘するように、実際のアイヒマンは出世欲と承認欲求に溢れた人物であり、決して言われたことをただ機械的にこなす人物ではない。むしろ、意欲的かつ創造的に「業務」に勤しんでいたことが記録されている。
つまりアイヒマンは現代日本のイメージで言うとお役所やJTC、つまりJapanese Traditional Company(伝統的な日本企業)の写真にありがちな「歯車」のような思考停止者ではなく、むしろ彼らを批判する「意識の高い」系のビジネスマンに近い人物であった、ということだ。
そしてここがポイントなのだが、アーレントは『エルサレムのアイヒマン』においても(今風に言い換えれば)むしろアイヒマンのこの「意識の高さ」こそが彼の「思考停止」を生んだ指摘している。(ちなみにアーレントの用いる「思考停止」とは、「考えなくなる」ことではなく「他者の声に耳を傾けなくなる」ことだ。)
アーレントのこの問題意識は少なくとも『全体主義の起源』の時点では存在したものと思われる。たとえばアーレントは全体主義の前身である帝国主義について、その推進力となったメンタリティについて取り上げている。それはいわば「ゲームのためにゲームを愛する」態度だという。
ここから先は

u-note(宇野常寛の個人的なノートブック)
宇野常寛がこっそりはじめたひとりマガジン。社会時評と文化批評、あと個人的に日々のことを綴ったエッセイを書いていきます。いま書いている本の草…
僕と僕のメディア「PLANETS」は読者のみなさんの直接的なサポートで支えられています。このノートもそのうちの一つです。面白かったなと思ってくれた分だけサポートしてもらえるとより長く、続けられるしそれ以上にちゃんと読者に届いているんだなと思えて、なんというかやる気がでます。
