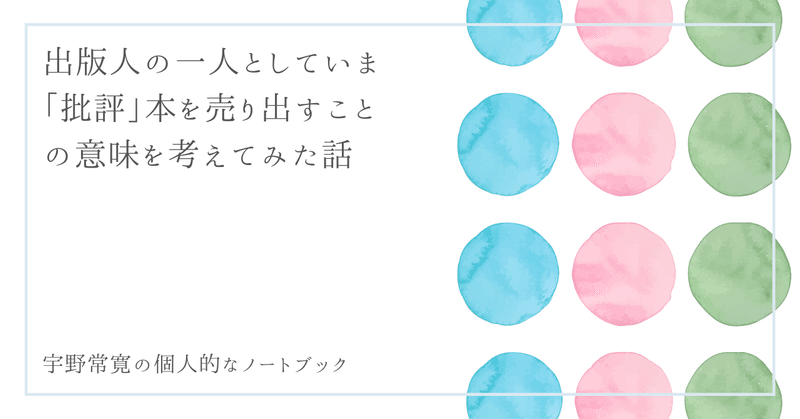
出版人の一人としていま「批評」本を売り出すことの意味を考えてみた話
今日は少し「出版業者」として考えていることを書いてみたい。
今日、三宅香帆さんの新著『娘が母を殺すには?』がPLANETSから、つまり僕のところから発売になった。
三宅さんは、前著の『なぜ働いていると本が読めないのか』が10万部超のベストセラーになっている。版元としては、新刊を出す著者の直前の(それも分野の全く違う)本がベストセラー化するというのはほとんど棚からぼた餅のような展開で、ああ、やっぱり僕の日頃の行いが神にフェアに評価されたのだな……と思うのだけど、その一方でこうも思うのだ。
「働いていると本が読めない」という焦燥を抱えた人がこれだけいるのなら、もっと普段から(全般的に)本が売れてもいいのではないか」と。
結論から述べてしまえば、いま人類が抱えている欲望は「本を読むこと」ではなく、かつて本というものが少なくともその一部を支えていて、そして今は「本」という記号が象徴している「何か」のことに他ならない。それはまあ、ものすごく卑しい表現をしてしまえば「知的な生活」というものかもしれない。
誰もが本当は気づいているはずだ。「働いていると本が読めない」のではない。いや実際に働いていると忙しくて仕事の資料以外、あまり読めないのだけどそれは現象面でしかない。僕たちは知的なものに憧れて、この種の教養論を思わず手に取るのだけれど、では、明日から心を入れかえて『知恵の七柱』を毎朝1時間開いて最後まで読み通そうとはまず、しないのだ。
ここから先は

u-note(宇野常寛の個人的なノートブック)
宇野常寛がこっそりはじめたひとりマガジン。社会時評と文化批評、あと個人的に日々のことを綴ったエッセイを書いていきます。いま書いている本の草…
僕と僕のメディア「PLANETS」は読者のみなさんの直接的なサポートで支えられています。このノートもそのうちの一つです。面白かったなと思ってくれた分だけサポートしてもらえるとより長く、続けられるしそれ以上にちゃんと読者に届いているんだなと思えて、なんというかやる気がでます。
