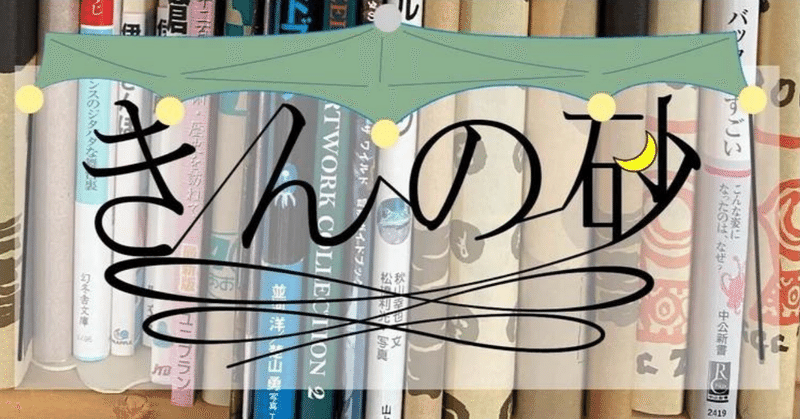
きんの砂〜4.刻の雪(2)
大きな窓の外を自転車の親子連れが通り過ぎていった。
亞伽砂はじっと、目の前の人物を見る。
「言いがかりはよせよ」
夕食時のファミリーレストラン。
向かいの席で彼は鼻を鳴らした。
「俺があのチンケな店に行ったなんて、どこに証拠があるんだ。さっさと新しい男連れ込みやがって」
呟きにも近い最後の言葉は聞き捨てならない。が、亞伽砂は怒りの感情を表に出すまいと辛抱強く言葉を押し出した。
「見に来たんだ」
新しい男というのはきっと得馬の事を指しているのだろう。店に顔を出さずとも、遠くから見たに違いない。コソコソ隠れて様子を見るなんて、ますますもって小さい男だ。
「通っただけだ」
横を向き決して亞伽砂の方を見ようとせず、机の下で貧乏ゆすりをしている。こんなに怪しくてよく自分は潔癖だといえたものだ。
「気づいてないんだ。あの店、防犯カメラがあるんだよ」
孝春の顔色がサッと変わった。
「おじいちゃんも用心して付けてたみたいでね、何なら公宣に動画送ってもらおうか」
バッグからスマートフォンを出す亞伽砂の手を、何か恐ろしいものを見るような目つきで見る。
「わ、わかった」
ロックを解除し電話をしようとした手が止まった。そして、「悪かったよ」
とあっさり認めた。
「悔しくて、ちょっと困らせるつもりでやったんだ」
おおかたそんなことだろうと思った。2ヶ月と少し前のあの夜、不審者を見つけた得馬が見たという赤のSUV車は孝春の車だ。流行りの車なので亞伽砂は別の人間の可能性も考慮し、すぐに連絡を入れなかった。というのは半分で、前日にあったことを考えるとすぐに彼と話をするのが嫌だったのだ。みんなの前ではなんともないような振りをしていたが、いつまたこの男が自分の前に現れるのかと思うと恐ろしくもあった。
なのにいまになってまたこいつの顔を見なければならないとは。顔を見ずに電話で問いただすという方法も考えたが、言葉だけではしらを切られるのが関の山だ。亞伽砂でなくても交渉役は自分でもできると公宣が立候補してくれたが、弟では正面からでも軽く遇らわれてしまうのが目に見えている。それよりもっともらしく防犯カメラの存在をちらつかせてやる方が効果があると提案してくれたのは得馬だ。彼が店に忍び込む実際の映像はもちろんないが、得馬と公宣がつけてくれた防犯カメラの写真と、ネットに転がる似たような場所の映像を用意してきた。万が一しらを切り通すようならもっともらしく見せればいいと。
結果、ありがたいことに本当にちらつかせただけでまんまと騙されたくれたわけだ。彼も馬鹿ではないので自分のしたことが立派な器物破損と不法侵入だと自覚しているし、そんな証拠を持って警察に駆け込まれれば社会的な制裁を受けることを知っている。
だがしかし、そうして亞伽砂が手に入れた本の行方は心が折れるものだった。
「中古本販売チェーン」
店に戻る途中の電話の向こうからも、得馬の心が折れる音が聞こえた。おそらく店の電話をスピーカーにして聞いているはずの公宣の心も、いまごろポッキリ折れているだろう。
孝春の出した店名は全国チェーンの中古本販売店で買い取りもしてくれる。腹立ちまぎれに手にしたものの使い道のない本達を、帰りがけに売り払ったのだ。どれも古い本だし作者のサインの入ったような特別な本ではないのですでに廃棄処分になっている可能性が高いが、車で外出しているついでに件の店舗に寄ってみると連絡を入れ、亞伽砂は電話を切った。
キンノコ堂に残された男2人は、店主が想像した通り心が折れて呆然とした面持ちで静かになってしまった電話の子機を見つめていた。
「無理だよ、あんな黄ばんだ本店頭に置くわけがない」
溜め息混じりに掴んだ子機を公宣がガチャリと置く。ああいった店が扱うのは古書として価値のあるものではなく、大量消費の末に捨てられたものだ。店頭に置かれる判断基準は希少性や蒐集家の好みではなく、傷や日焼けが少なくかつ話題性があるかないか。人々が書店で最初に手に取る基準に近い価値が求められる。公宣が嘆くように専用のヤスリで落ちないほどの濃い黄ばみやシワだらけの本は古紙として処理場に回されてしまのだ。
「得馬さん、何やってるの」
行き着いた場所が中古本販売店ではどん詰まりだと嘆く公宣をよそに、得馬がパソコンに向かい何かを始めた。
「無駄だと思うけど、一かばちかやって見ようと思って」
老店主が判別用に撮影しておいた行方不明本の写真を呼び出しキャプションをつけ貼り付けた先は、古書組合の専用掲示板だ。古書店同士の情報交換用の場所で、店舗を持つ組合員しか入れない。
「おじいさんは几帳面だったんだね。写真があって助かったよ」
探す本は何ということのないジュブナイル小説だったが、本の内側に持ち主のメッセージが記されていた。預かり品を写真で残すというのは、きっと増え続ける預かり本の判別に文字だけでは追いつかなくなった果ての策として、老店主なりに考えたものだろう。現にこうして役に立っていてくれる。
誰か興味を引いてくれるといいのだが。
週末、キンノコ堂のメンバーは神保町の一角にいた。
表通りから一本入った路地にあり、両隣も似たような古本を扱っている中の「みやた書房」という古書店だった。大きさはキンノコ堂くらいだが、扱う書籍の量はその何倍もあった。6階建てのビルの3階まで店として使っているのだが、天井から床まで、見えるところ全てが古色騒然とした古本で溢れている。同じように本だらけといっても、キンノコ堂は一般書店に近いほどの書籍しか店頭に置いていない。少なくとも書架と天井の隙間を本の塊が埋めてはいない。
「そうですか、お孫さんなんですか」
ビン底メガネに白髪混じりの店主について、狭い店内を歩く。神保町には得馬は時々通っていたが、本とは無縁の生活を送ってきたという公宣には別世界に見えるようだ。本にではなく、本に占領されている世界といった方がいいか。
足元にもある本を避けながら歩く亞伽砂もそれは同じだ。こんなに入り組んで本に視界を遮られ、万引きなどに合わないだろうかと別な心配もしてしまう。
時々人が入ってくるが、探す対象が決まっているのかお目当ての書架を少し眺めただけで出て行ってしまう。また店主の方も、そういった人の動きを把握しているのか確かめようともしない。
「しばらく活動されてなかったようだったので、どうしたのかとみんなで話したりしてたんですよ」
「みやた書房」の店主にも、キンノコ堂は知られていた。聞けば彼だけでなく、この界隈では有名だったとか。
「市場にも、時々顔を出してましたからね。目は確かでしたよ」
元恋人に持ち出した本の行き場所を聞いた時には、すっかり再生紙工場の溶鉱炉の中かと覚悟しながらも、念のために訪ねた中古本販売店で運よく亞伽砂はその時に応対した店長と話すことができた。確かに高春の持ち込んだキンノコ堂の本は痛みが激しく店では処分行きとして分類していたらしい。だがその中に既に絶版となっている珍しい本があることに気がついた店長は、他の本と一緒に中古本の市場に出品したのだ。
「比較的新しい本を扱ううちみたいな会社は、著作権を無視しているなんて言われるけど、求められれば答えるのが社会というものだからね。でもね、全く文化を消費の道具としているわけでもないんだよ」
全国に直営店を展開するその会社では、店頭で売る基準に満たないもののまだニーズがありそうな本は一度古書が集まる市場に出品させているという。
2ヶ月以上も前だというのに、自分も読書が趣味だという店長は言い訳がましく亞伽砂に語った。他の客が持ち込んだ商品なので店長に咎はないのだが、本好きとして本を処分するときには何らかの罪悪感を覚えずにはいられないらしい。
そして「みやた書房」の店主が買った本の中に、例の本らしきものが混ざっていたのだ。
「それにしても全くの偶然でしたよ。この本を手に入れたのは」
店の奥にある裏口から出た場所は、軽ワゴン車が収まるガレージだった。
「月に一度ほど、ガレージセールを開くんですよ」
「店で売らないんですか」
本の山に被せられたビニールを取る店主に、公宣が聞いた。
「需要がないんですよ」
いくつかの山を見て、その中の一つを取り出す。
「じゃあ、買わなきゃいいのに」
呟いた途端、公宣の脇腹に亞伽砂の肘が入った。
全国に古書が集まるこの街では、毎日何らかのジャンルの古書市場が開かれている。俗に交換会と呼ばれるこれらの市場でいらないものを出品し、代わりに競りで必要な品を買うのだ。
「一山いくらって、八百屋でもあるでしょ。一冊じゃ競りに出す基準に満たないから、目玉商品を入れて。抱き合わせ販売みたいにね」
亞伽砂と公宣の様子に目を細めながら、店主は見つけた山の紐を解いて本を出した。
「たまたま欲しい本がその本と同じ塊の中にあってね」
得馬が古書組合の掲示板に写真入りのメッセージを投稿して数日後、公宣のスマートフォンに「みやた書房」の店主からのメールが店のPCから自動転送されてきた。
「まとめる前にいちおう、本の状態は見るようにしてるから。写真を見たときにもしかしたらって思ったんだ」
渡された本を得馬は開いた。探している本にはメッセージ以外にも特徴があって、背表紙の裏側に小さな紙のポケットがあり、そのポケットに小学校のゴム印が押してあるのだ。プリントしてきた写真と見比べてると、どちらの条件も満たした、探している本そのものであると判明した。
「これはおいくらですか」
「値段はないよ。それは有名人のサインでもないし、読書カードのポケットがついたような代物は売れないよ」
苦笑いする店主に礼をいい、彼らは店を後にした。
店のリストに記された依頼主の住所は長野県だったが、メールとのやり取りで現在は都内在住であることが判明した。
不明になった本について、依頼主とは公宣が細かく連絡を取り合っていた。今日の神保町行きも伝えており、可能ならば同日中にも会いたいとの申し出ももらっていた。
早速公宣が駅前で依頼主に電話し、午後から会うこととなった。
河とも海ともつかぬ広くゆったりした水の流れの向こうに、見上げるほどの高さのある高層ビルが乱立していた。
まだ寒い海風にコートの襟を立て、亞伽砂は近未来的な風景を眺めていた。隣では公宣が何やら得馬にあれやこれやときいてる。
東京へは年に数回遊びに来るが、豊洲のこの辺りはあまり歩かない。いつもは渋谷のあたりを彷徨く公宣も見慣れない景色と、久々に得馬からたっぷりと仕事の話が聞けて大興奮しているようだ。
視線の先で低く輝く太陽光に目を瞬かせた亞伽砂の耳に、公宣の手に握られたスマートフォンの呼び出し音が飛び込んできた。
すぐに電話口に出た公宣が、あたりをキョロキョロと見回す。すると、少し離れたところから同じような風に歩いてくる年配の男性が見えた。
「塚本さんですか」
公宣の耳からスマートフォンが外れた時には、向こうも彼らのことに気づいていた。
「そうです。初めましてといった方がいいのかな」
携帯電話をジャケットにしまい込んだ男性は改めて3人を見た。
「まさか本当に預かっていてくれるとは、そして返してくれるとは思いませんでしたよ」
軽く挨拶を交わした後、塚本は亞伽砂から件の本を受け取った。
厚紙を使用した表紙に保護フィルムが貼られた、懐かしい本だ。開くとかつて教師として在籍した学校の図書室の名前と、自分が書いたメッセージがある。
これを関東の古書店に持って行ったのは、20年も前になるだろうか。
当時長野の公立小学校に教師として勤務していた塚本は定年が近くなり、退職を迎えようとしていた。もともと地の人間ではないので、退職したら子供のいる東京で暮らそうと考えていた。そんな時、かつての教え子がひょっこりと家に訪ねてきたのだ。高校を卒業し、春からは念願だった海洋学部のある神奈川の大学に進学することが決まっていた。
その学生が塚本の前に一冊の本を出した。かつてその生徒が小学校を卒業するときに無期限で貸し出した本だ。
「俺、もう大丈夫だから」
彼は本を返しにきたのだ。無期限で貸し出したといっても、実は校舎の建て替えで図書室も本の入れ替えがあり、処分するはずだった本だ。
「確かに、もう大丈夫そうだな」
この本が帰る場所はもうない。そう思いながら塚本は本を受け取った。夢を叶えるために少年は行く。小学生向けのジュブナイル小説などお守りにしなくても、これからは実力をつけていけばいいのだ。
そうしてかつての教え子が帰った後、塚本は本の処分を考えてみた。このまま東京へ引っ越すタイミングで捨ててもいい。だがこの本には、まだ仕事があるのではないか? ふとそんな風に考えたのだ。その仕事を完遂するために、自分の手元に戻ってきたのだと。
そしていつか新聞の片隅で見た変わった広告の事を思い出し、思い切って電話をしてみた。
「そうですか、あの店主は向こう側に行かれましたか」
老店主の近況を聞いた塚本は目を細めた。
20年前も自分より少し上くらいの年齢に見えたので、どうかするとすでに他界しているかもしれないとは思っていたが。彼の孫が店を継いだのであれば、あの小さいが居心地のいい店に預けられている本達も、安心しているだろう。
「実は連絡をいただくまで忘れていましてね」
東京に引っ越してからも色々あり、老店主には預かりの契約期間が過ぎたら処分しても構わないと伝えておいたせいですでに存在自体忘れ去っていた本だ。
それをこうしてまた引き合わせてくれるとは。
本当にまだこの本にはひと仕事残っているかもしれない。
「こういってはなんですが、もう一つ依頼を受けていただけませんか」
亞伽砂は息が止まった。
本を持ち主に返す。
キンノコ堂の店主としての仕事はここまでだ。
そう伝えて断ればいい。あの店は閉めるのだから新たな依頼は受けない。
だが、それでいいのだろうか。
祖父ならば、どうしていただろう。
自分を見つめる得馬と公宣ならどうするのか。
「話を聞いてから判断する、では駄目でしょうか」
とはいうものの、聞いてしまったら最後だと、頭の中のもう1人の自分が呆れているのを亞伽砂は感じていた。
※※※※※
薄暗がりの中で、飛騨映美は黙々と手を動かしていた。蓋が取られたままの衣装ケースや埃の溜まる段ボール箱に周りの物を入れて行く。最初に何が何処に入っていたのかは不明だが、夫は気にしなくていいといっていた。とにかく自分が探し物のために広げて散らかした荷物を、蔵の床が見える程度にまで片付けてくれればいいと言われていた。
夫の実家は農家だ。代々続く本家らしいが、いまは広い屋敷に年老いた両親が暮らしている。その両親も父親の方は近年病気がちで、年始から入院していた。そんなこともあり夫の実家には2、3回しか来たことがないが、母家の裏に古い蔵があるのを初めて知った。
「映美さん」
入り口の方から声がした。
「そろそろ行かないと、帰りの電車に間に合わないよ」
夫の母親だ。用事がありどうしても午後には東京に行かなければならないと伝えてあったので、呼びに来てくれたのだ。
「泊まりがけで後片付けに来てくれなくても、康徳が帰ってきた時にやらせたのに」
義理の母親は小柄だ。それなのに、どこにそんな元気があるのかと思うほどよく動き回る。
「いえ、康徳さんは忙しいので。私にできる事があれば」
映美の手には丸められた古い画用紙が握られていた。紙の裏に書かれた小学生の頃の息子の文字が見える。
正月に帰ってきても何も手伝わせないでいた嫁を、自分の片づけに1人で横した息子の変わり様に母親は驚いていた。2人の結婚は乗り気かそうでないか以前に、受けるか受けないかというものだったので、田舎者の息子とお嬢様育ちの嫁の間で何かあったのだろう。
互いを認め合うような何かが。
「それは持っていくのかい」
映美はさっきまで詰めていた衣装ケースの蓋を閉めた。
「はい。明るいところでゆっくり見ようと思って」
彼女が手にしていたのは、小学校高学年の図工で描いた康徳の絵だ。もしかしたら一枚だけではないかもしれない。
思えば、その頃から息子は将来の夢を決めていた。
人の声が遠くなりやがて入口が締められた蔵の中を、天窓から差し込むか細い光が一筋の道のように照らしていた。朧げにあたりを照らしだす光の中で、舞い上がっていた埃がゆっくりと落ちていく。
元のように、箱や衣装ケースの上に雪のように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
