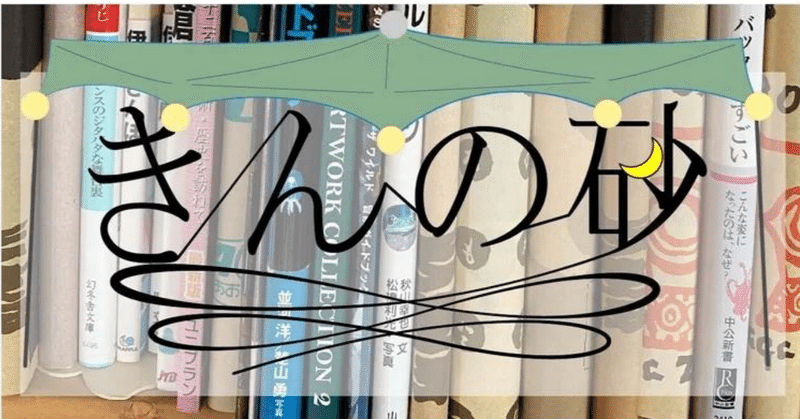
きんの砂〜4.刻の雪(1)
暗闇に、大きなネズミが動いていた。否、格子窓から差し込む光に露わになるのは人の体だ。大きな背中を揺らし、湿った土蔵の床を舐めるように隅から隅まで目を凝らす。
「康徳や、研究所から電話だよ」
入り口から伸びる光の帯の中に母親の小さな影が立つ。頭に付いた埃を払い、飛騨康徳は受け取ったスマートフォンを耳に押し付けた。家に帰るとリビングのテーブルの上に置きっぱなしにしてしまうのだが、実家に帰ってもつい同じことをしてしまう。
母・タカは泥棒にでも荒らされたような土蔵の中を見回し溜め息を漏らした。息子が何を探しているのか知らないが、昨日から家中ひっくり返してもまだ見つからないらしい。
「悪いな、今度映美を連れてくるから。その時に片付けてもらう」
研究所から許可された自由時間は終わってしまったのだろう。スマートフォンを胸に仕舞い、来た時と同じように何も持たず母家の前の庭に止めた車へと走っていく息子を見送ったタカは、散らかされた土蔵をそのままに鍵を締めた。仕事ばかり夢中になる息子に、教授の薦める見合いで物にした上品な嫁にこんな汚い土蔵掃除に来いなどと、言える度胸があるはずが無い。こんな田舎では見ない綺麗な顔立ちで素直ないい嫁だが、数えるほどしか見たことのない嫁についてはそれ以上は思い出せなかった。
何を探していたんだか。
昔からあの子はそうだった。不安になると懐かしいものを出してきて気が済むまで触れている。小学生くらいの時までは幼稚園の時に使っていたタオルや枕。大柄で、中学生かと見紛うばかりの体に小人専用の様な小さいタオルや枕を宛てて眠るのだ。中学生になると小学生時代の絵日記になった。時々夜中に起き出してきてはページの隅に書かれた先生のコメントなどを読み耽る。高校生になり思春期を迎えるとそんな行動も無くなった。時々、勉強も睡眠も忘れて読書に没頭することはあったが、それは数少ない彼の趣味だった。
大学ではどうであったのか。元々無口である上に寮生活について帰省しても特に話すことはないのか、こちらからも聞いた事はない。それでも昔の勉強部屋は土蔵を荒らしたことはなかったから、落ち着いていたに違いない。
大学附属の海洋学研究所に技術研究員として仕事を持ち世帯を持ち、立派な大人になってもまだ不安を掻き立てることがあるのか。
母家に戻ったタカは所狭しと居間に掛けられたり棚に置かれた息子の写真を見た。彼の心に巣食う不安という蜘蛛は母親である彼女にも取り払うことはできない。何に怯え何を必要としているのか。
妻であるあの娘には息子が理解できているのだろうか。
写真の中で笑う若い2人を見つめた。
新婚旅行で訪れた南の島でスキューバダイビングをした時のものだ。
夫の書斎の入り口に立ち、部屋の惨状を眺めていた飛騨映美は本棚に飾られた懐かしい写真を手に取った。
この旅行のために、友人に付き合ってもらってスキューバダイビングのスクールに通い、免許を取得した。スクールの講師が居ない場での潜水が初めてだった映美に、夫は優しく寄り添ってくれた。彼とは見合いで結ばれたが、お互いに愛し合っていると感じていた。
だが、いまはどうだろう。
カーテンの隙間を縫って差し込む光が胞衣のように広がる夕方のこの時間、こうして夫の書斎を眺めるのが好きだ。もともと納戸として設えられたサービスルームは夫の大きな体で書斎とするには窮屈に思えるがきっと、その狭い感じが心地いいに違いない。元来からして掃除が苦手らしいがこの部屋だけはいつもきちんと片付けられている。ただここ1ヶ月ほどは何かを探し続けて本棚や奥の箱を引っ張り出している。普段は何も言わない妻の入室もきつく禁じていた。
散らかり放題の部屋の真ん中で、そこだけポッカリと床が見える場所に映美は体を埋め、横になる。頭はプリントされた海洋学の資料の上にあった。書籍、手紙、写真、ビデオテープ。すぐ手元に古代の海洋生物の化石があった。箱に入ったままだが、角取れて丸くなっている。見合いをして最初の康徳の誕生日に映美が送ったものだ。
「何をしている」
怒気を含んだ夫の声に、弾かれたように彼女は頭を上げた。部屋の入り口に夫の康徳が立っている。
まだ帰宅には早すぎる。
「お帰りなさい。出発が近いし、片付けようと思って」
驚いたのも手伝って映美の声は震えていた。彼が自分に向けて怒りを露わにしたのは初めてだ。
「片付けなんかいい」
夫は探し物あるとかで一昨日から信州の実家に帰っていた。研究所の船での出発は明後日だから、帰宅は今夜になると気いていたのに。
「でもこのままじゃ歩くのもやっとだし、あなたも資料の整理が」
おずおずと立ち上がる映美に向かって康雄が歩いてきた。大事な資料も本も容赦なく踏みつけて。
「煩い!」
あっという間の出来事だった。彼が素早くてをあげたかと思うと、燃える様な痛みが映美の頬を打った。
「俺の仕事に構うな」
足を蹌踉させ座り込む妻の姿など、彼の目には見えていなかった。
「お前はただ、待っていればいいんだ」
思わずついた映美の手のひらに、額縁の角が当たる。部屋に入ったときに手にし、足元に置いたスキューバダイビングの写真だ。仲良く笑羽2人の笑顔の上に、赤い血が滴る。
口の中を切ったのだ。
違う。見えていないのではない。
見てはいけないのだ。
教授に紹介されて結婚した美しい妻。有名女子大出身で、才色兼備で、誰もが羨む妻。山に囲まれた土地で育ち海に憧れたむさ苦しい田舎男には似つかわしくない妻。
俺には重荷でしかない妻。
夫の狼狽ぶりは見なくとも感じ取ることができた。「妻を」ではなく「教授の紹介した妻」に手をあげてしまった。
その証拠に康徳の動きは止まった。
困っているのだ。その気もないのに預かってしまった女の扱いに。
だが映美の方は、夫に叩かれたことによって、初めて怒鳴られたことによってこれまで溜め込んできたものが爆発した。
「黙って、られるか」
素早く立ち上がると予想もつかない早さで、箸しか持ったことのないような華奢で骨張った拳が康徳の顎に食い込んだ。
見事なまでのアッパーストレートを食らわした彼女は、くっきりとした二重の大きな目を吊り上げて夫を下から睨みつけた。
「見縊るな! 伊達にしたくて主婦をしているんじゃない」
顎を抑えた康徳は妻の前腕筋を見て、そのようで、と心の中で納得した。家事で使うには立派すぎる筋肉がついている。ついでにいえば出会った時は色白だったはずの肌の色も少しだけ日焼けしている。
「何が心配なの? 不安なの? 言ってくれなきゃわからない」
「べ、別に心配も不安もない。お前は黙って」「黙ってたら潰れてしまう」
映美の声は叫びに近かった。
「ジャックの事故は、残念だったわ」
はっとして康徳は顔を上げた。半年前、フィリピン海溝沖で起きた潜水艇の事故の話は、したことがなかったはずだ。事故を起こした潜水艇の操縦士、ジャック・ミラーは業界でも最多の潜水時間を誇るベテランで同じ研究テーマでチームを組んだこともあった。潜水艇の整備は主に助手や専門の整備士がやるが、操縦士は潜る前に必ず自分の目で安全を確認する。康徳が整備した潜水艇に乗り込むときもジャックはその仕事に満足し誉めてくれたが、出発前には必ず自分で全てのチェックをしていた。それなのに事故は起きてしまった。通信が途切れた後引き上げられた厚さ20cmのチタン球核は見事にひしゃげていた。高水圧による破壊は一瞬だったに違いない。ついこの間、ジャックがはめていた腕時計が国際便で研究室に送られてきた。いつか形見に送ると話していた通り、ジャックの妻が康徳にと送って寄越したのだ。
「だからあなたが不安になるのもわかる」
「わかる? お前に何がわかるというんだ」
映美にジャックの話をしたことは一度もない。もちろん彼の事故についても。
「だってあなた、潜るんでしょ。初めて潜水艇で」
康徳の顔が引き攣るのがはっきりとわかった。
3ヶ月後の日本海溝の潜水調査で、康徳は初めての潜水艇に乗り込む。海洋学砂としてだけでなく技術者としても腕を磨いてきたのはそのためだ。500気圧の静水圧がかかる海底は超低温で無光層なベントス(底生生物)の世界。
恐怖を覚えないはずがない。
「お前、どうしてそれを」
「私はお前じゃない」
手に持っていたフォトフレームを康徳の胸元に叩きつけ、映美は部屋から走り出た。
背中でマンションのドアが閉まる音がする。
康徳は拳を握りしめた。これまで比較的浅い海で副操縦士としての訓練を積んできたが、次の航海からは操縦士としての訓練を始める。
映美が話したのはもちろん内部的な話で研究所の外ではもちろん、家でも細かい仕事の話をしたことはない。どうして知っているのかと散らかったままの書斎に目を走らせると、机の上のパソコンが目に入った。家で資料整理をすることもある康徳は研究所のネットワークに入る権限を持っている。
机の前に進むと、キーボードを裏返した。ネットワークに入るためのパスワードが貼られている。彼女はこれを利用して康徳のスケジュールを見ていたのだ。それだけじゃない。研究所の資料も、ジャックの事故に関する調査書も。
盗人のような妻の行動に再び怒りが込み上げてくる。もし研究の内容や内部文書が外部に漏れたら退所どころでは済まされない。
遠くからピーピーとなる電子音が聞こえてきた。
怒りが込み上げてきたもののこの事態をどう対処すればいいのか考える康徳の耳に、しつこく音はまとわりついてくる。
くそ、頭が回らないい。
キーボードを乱暴に机に戻すと、音を頼りにキッチンに向かった。
音は鍋が吹きこぼれたコンロから鳴っていた。立ち消え防止ブザーだ。
コンロにある鍋の蓋を開けてみると、康徳の好きな魚介のブイヤベースだった。
彼女はよくやっている。
結婚した当初、勤務時間が不規則な康徳のために食事や弁当をあれやこれやと工夫する彼女に無言で感謝していた。
最近は仕事のことで精一杯で、帰宅時間もスケジュールも伝えていない。
鍋から吹き出したブイヤベースの煮汁を側にあった布巾で拭き取るうちに、冷静になってきた。煮汁はコンロの側面にも吹きこぼれていた。汁を追ってすぐ下の引き出しを開けた彼の手が止まる。
「書類?」
何故こんな場所にと、ジッパー付きの小袋を手に取った。
入っていたのは書類ではなく、複数の免許証だった。
運転免許証と結婚前に取得したダイビングスクール発行の修了証、無線免許、船舶免許もある。しかも1級だ。そればかりでなく、都内の大学の海洋学部の学生証まで。
妻の陽に焼けた肌の色を思い出した。康徳の勤務する研究所は神奈川なので避けて、わざわざ遠くの学校を選んだのだ。
俺の妻は何をやっていたんだ。
違う。
俺だ。
俺は何をやっていたのか。
手にしたスマートフォンですぐさま映美の電話番号にかけた。
しかし出ない。
そのまま康徳は電話を耳に当てながら玄関へと走った。
※※※※※
毛布の上に発泡スチロールのパネルを敷いた荷台の上に、ゆっくりと大型のパソコンが降ろされた。
「今日は何の祭りだ」
声をかけながら安全に本体が置かれたことを確認した得馬が、聞き慣れた声に顔を上げる。
「得馬さんの古巣の引っ越しです」
相手が誰か確認するよりも早く、公宣が答えた。その口調から顔を見なくても相手が笠置だと確信する。
「ついにゼミは解散か」
「縁起の悪いことを言わないでください」
今日も柔道部で体を動かそうと来たのだろう。まだ着替えてもいない笠置がにやにやしながら眺めている。
「機器の入れ替えに伴う改装ですよ。まだ使う分を一時店で預かるんです」
月極駐車場の一角に停めてあった老店主の軽トラの荷台には、他に3台のPCの筐体とモニター、その間を埋めるように専門書が敷き詰められていた。話している間にも2人は荷台への幌かけの手を止めない。車はマニュアル式で、AT限定の公宣では運転出来ない。
「一部をネットワークに繋ぎ直す作業があるんで、今日は遊べませんよ」
まだ公宣に何か話しかけようとした笠置を冷たくあしらって運転席に乗り込むと、得馬はエンジンをかけた。名残惜しそうな公宣が助手席に乗り込んだのを確認すると、別れの挨拶として軽くクラクションを鳴らしてから出発させた。
「あの人、面白いよね」
笠置はあまり本を読む趣味はないらしいが、大学に来る途中でたまに店に寄ることがある。大抵は亞伽砂と無駄話をするだけだが。
「面白いというか、まあ、そうだね」
精密機器の運搬故にノロノロと走る車は、大学の門から出てそのまま道向かいの細い住宅街に入っていく。慣れないクラッチの扱いに集中しているのか、道を横断する得馬の返事はどこか上の空だ。
「昔はさ、この辺り畑だったんだよ」
住宅街の道に入り、やっと口を開く。「昔」なんていう単語を使うほど得馬は年老いていないが、要するに大学生だった頃といいたいらしい。
「学祭の屋台で使う野菜は、みんなここの畑のおじいちゃんちから仕入れてた」
大きな道を使わずにこの狭い道を選んだのは、人が歩く速度とほぼ同じ速度の運転で移動しても咎められないほど車通りが少ないからだ。
「あれでかなり稼いでたんじゃないのかな」
「地産地消だね。俺の大学の周りには畑なんてないや」
だがかつて畑だらけだった新興住宅街はすでに土地が売り尽くされ、畑どころか空き地さえ無くなっている。店に通っていた時分に祖母に連れられて散歩していたはずだが果たして長閑だった頃のこの辺りを歩いていたのか。公宣は自分が歩いた道さえ覚えていなかった。覚えているのは祖母の知り合いの商店街の老店主たちに可愛がられていたのと、角の駄菓子屋だけだった。
「それにしても、事前にいってくれれば車で来たのに」
住宅街を抜け、商店街に出る前の一時停止線で車を止めた得馬はひとりごちた。年末年始の休暇で実家に帰った時に自分の車を持ってきたのだ。ギアをローに入れ右を、左を確認した公宣の合図でゆっくりクラッチを戻す。車通りが少なくなったとはいえ、まったくないわけではないのだ。
店までの十数メートルの間はハザードランプを点滅させて移動した。
「お帰りなさい」
「定休日」の札を揺らして亞伽砂が出てくると、木戸を開けた。荷物は2階に置く予定のため、一度台所のテーブルに置く。
「得馬さんにお客が来てるけど」
自分の客でもないのに、幌を外す公宣の手が止まる。興味が引かれた顔で店の出入り口を見た。
白いカーテンの間から姿を表した女性は姉と同じくらいの背格好だが、少しばかり年上に見えた。
得馬の彼女だろうか。話題に出たことも聞いたこともないが、彼なら彼女がいても不思議はない。
「史織」
姿を認めた得馬の腕に、ロックを外し下げた荷台のあおりの荷重がやけに重く感じた。
真野史織。総務課の事務員の彼女は、本社勤務の時によく遊んだグループのメンバーだ。久々にかつての遊び仲間の集まりに顔を出した時に、彼女にこの店の話をした。興味のある顔をしていたが、まさか訪ねてくるとは思わなかった。
「営業所を見にいってみたら笠置さんに会ったんだよ」
わざわざ道場から離れた棟まで来た笠置のにやけた顔がチラつく。単なる冷やかしではなく、大いなる冷やかしをしようと思い待ち構えていたに違いない。きっと今頃はあまりに相手にされずに落ち込んでいるだろう。
まあ、あの場所で彼女が来たことを知らされてもどうにもならないが。
「遊びに来たの? こんなところまで」
呆れ顔でいう得馬の横に並ぼうとした公宣の脇腹を、亞伽砂がつついた。
「公は早く運ぶ。私も手伝うから」
言われて公宣は渋々書籍の束を抱え込んだ。PCは今日中に2階に設置して接続までする約束だ。
「まあ、散歩にね。お正月に話を聞いて、どんな感じのところかなって」
思った通りの答えに得馬は少し笑って頷いた。店の話をした時点で予測するべきだった。
久しぶりに顔を合わせた遊び仲間たちは、電話やメッセージの返信もしなかった得馬を責める事もなく、変わらず穏やかな時間を過ごすことができた。肩透かしを食ったような寂しい感じもしたが、それよりも強く感じたのは疎外感だ。いつもそうなのだ。彼らと会うことは楽しかったし刺激にもなったが、どこか外側から見ている自分を感じていた。
みんなと楽しんでいるはずなのに、ひとりだけ冷静に観察している自分が。おそらく彼らもどこかで、得馬の心が自分達とは違う次元にいるのだろうと感じていたのかもしれない。だから連絡をしても、彼から返事が来なければそれ以上連絡を入れることをしなかったのだろう。
そんな状況に心なしかほっとしている自分は、薄情ものかもしれないと考えながらこの店に戻ってきた。
「ごめん、先にこの荷物を片付けるよ。帰りは送ってくから」
PCの隙間にある本を取り出そうとする亞伽砂の手つきががどうにも危なっかしくて、得馬はひらりと荷台に飛び乗る。
「私も手伝うよ」
あおりを切った後部に近づくと史織も手を伸ばし、PCが無くなったことによって崩れた書籍の山を引き寄せた。
「そうしてもらうと助かる。置き場所は、公宣に聞いて」
その山をひょいと持ち上げて彼女に持たせてあげる。
すぐ横でモニターを抱える公宣に促され、史織は店に入っていった。
「お客さんに手伝って貰っちゃった」
亞伽砂に備品の入ったケースを渡し、一番奥のPCを持ち上げる。
「立ってる者は親でも使えっていうでしょ」
「得馬さんPCはこれで最後だね」
ちょうどきた公宣が得馬の抱えているものを受け取る。みんなで運んだせいで、残りは僅かな書籍類だけだ。彼はそれを戻ってきた史織に渡した。
「僕は車を置いてくるから、先に入ってて」
あおりを元に戻し運転席に乗ると、白い軽トラックは慎重に動き出した。
「史織さん、持ちます」
後ろから来た亞伽砂が手を出したので、半分持ってもらうことにした。
「コヤちゃんて、いつもあんなですか」
彼のことを名前でも姓でもない呼び方で聞くのは、新鮮だ。
「いつもああですよ。すごく助かってます。コヤちゃんて、小柳だからですか」
「そうそう。みんながコヤって呼ぶから」
隣の建物との間の狭い道から台所に入る。テーブルの上は本だらけだ。
「書籍と書類は奥の物置に保管するんです」
手の中の荷物を置くことなく、亞伽砂は奥の部屋を開けた。
駅のホームに立つと、線路を挟んだ向こう側のホームの上に星が見えた。屋根がないせいで地上の街の明かりと空の星とが対になっているようだ。
「結局話す時間なかったね」
隣に立つ得馬がいった。
預かったPCを研究室のネットワークに繋いだものの、そこからついでの手伝いをさせられて結局陽が暮れてしまった。その間ずっと、史織は亞伽砂と話をしていた。
「楽しかったら、別にいいよ。コヤちゃんとはあまり話すこともないって思ってたし」
確かに本社にいた頃も2人だけで話たことはあまりない。大抵みんなと集まる時に本に関する情報を交換していたくらいで、こんな風に同じ駅のホームに立っているなんて不思議な気分だ。
「じゃ何で来たの」
「だから、お店を見に来たに決まってるじゃない」
本当だろうか。
「そういえば公宣から、付き合ってるのかって聞かれたよ」
「本当? 彼いい子だよね。で、何て答えた」
「もちろん違うっていったよ」
「だよねぇ」と答えながら、史織は得馬の向こう脛を蹴った。
「痛っ! 何で蹴るの」
「別に〜」
もう一回蹴ろうとしたら逃げられて、つま先が空を切る。
「何で逃げるの」
「逃げるよ」
人気の少ないホームの奥から、ゆっくりと電車が入ってきた。
史織を送り店に戻ると、亞伽砂と公宣が難しい顔をしていた。
腕を胸の前で組んで同じ格好をしてパソコンを睨み付けている。
「お帰りなさい」
入り口の開く音に亞伽砂が気づいて顔をあげる。
「どうしたの、親の仇を見つけたみたいな顔をして」
「いたんだよ、本を確認したいって人が」
公宣が店側に出て作ってくれたスペースに入り、亞伽砂の顔を照らすモニターを覗き込んだ。
半年ほど前のことだ。ある夜、たまたま店の前を通った得馬は店から不審者が逃げていくのを見かけた。その人物は店の入り口のガラスを割って侵入し、店を荒らしていった。店には古書しか置いておらず特に盗まれたものも見当たらなかったため届出を出さないことにした。その後亞伽砂の祖父の遺言も見つかり、正当な後継者として店を継いだ彼女は預けられている本と、預け主を照合する作業を行っていた。だがどうしても祖父の残したリストの中で見つからない本が出てきたのだ。おそらく不審者が持ち出したであろうという結論に達したものの、売り物としていた本は閉店時に処分することになるので問題に入れないことにした。問題は預かり物の本だが、冊数もそれほど多くなくすでにメールや手紙で亞伽砂がお詫びと返金についての知らせを出していた。幸いにも店側に置いてある書籍類の預かり賃はどれも少額で、ほとんどの持ち主が返還を諦め預かり賃の返金もしなくていいと言ってくれた。だがでひとりだけ、どうしても自分が預けた本を確認したいという人が出てきたのだ。
返信されてきたメールには、時間がかかってもいいので何とか見つけて欲しいと書かれていた。
「どうするの」
半年前に盗られた本など、すぐに見つかるだろうか。
「何とか聞いてみる。キンノコ堂の意地よ」
答えた亞伽砂は得馬の顔を見た。公宣と同じように心配そうに見ている。
「やっぱり、その人だと思ってるんだね」
逃げ去った車の特徴から、彼らは店を荒らしたのが亞伽砂の元彼だと断言している。それも決して穏便な別れではなかったことが彼女の様子から窺えるが。
「他にいないもの。こんな幼稚なことをする人は」
苦々しい顔で亞伽砂は肩をすくめた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
