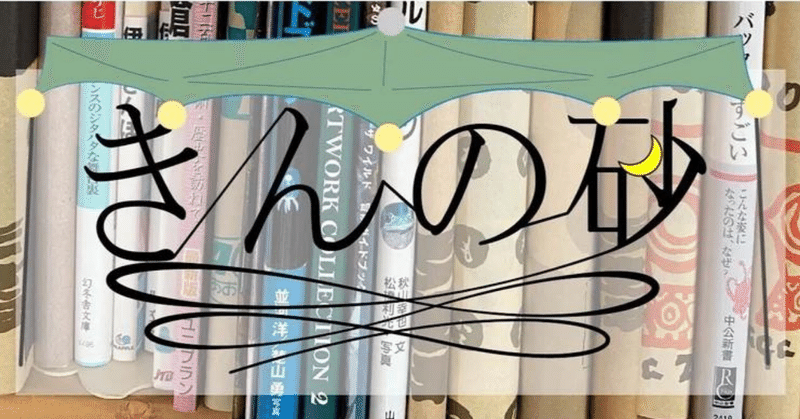
きんの砂〜4.刻の雪(4)
亞伽砂は史織と共に、2階の窓に暗幕を張っていた。
公宣はプロジェクターの高さを調整し、薄暗がりの中で得馬はパソコンに向かっている。
「やってるな。いい具合じゃないか」
予告もなく笠置が現れた。光が遮られた室内を満足そうに見渡す。
「勝手に入ってこないでくださいよ」
パソコンから顔を上げた得馬は、大きな笠置の背中に隠れるように立つ里子に挨拶した。
「声をかけても誰も出てこなかったんだ」
言い張るが、笠置ほど大きな声に気づかないわけがない。勝って知ったる何とかで台所側の入り口から入ってきたに違いない。
「あの灯りとりはどうするの」
里子が3階のバルコニーから繋がるガラスの柱に気づいた。
「これから暗幕で隠す予定です。あそこにあるから、手伝ってくれるならありがたいです」
手にしたケーブルで部屋の大半を占めるキャビネットの下にある暗幕を指し示す。張り切って持ち上げる里子が渋い顔をする笠置の尻を叩く。
「私たちは下で準備を始めるね」
照明を消して窓からの光の遮断を確認した亞伽砂が、史織と共に台所に降りていく。
テーブルと椅子も揃えたので、必要なものはお茶の類だけだ。
「私も呼んでもらって嬉しいな」
階段を下がる史織の声は弾んでいた。
「呼ばなければきっと怒るでしょ」階段したで顔を合わせると、「当然」と亞伽砂に向かって目を見開く。
キンノコ堂の本の返還は続いていたが、最近になってメンバーに詩織が加わった。家が都心の彼女は頻繁に来る事はできないが、たまに来ては郵送分の支度を手伝ってくれたり、亞伽砂とたわいのないお喋りをしたりしている。
「こんな楽しい場所、コヤちゃんだけ知ってるなんてずるいもの」
キンノコ堂のメンバーと話す時の得馬は、本社時代に集まっていた時とは全然違う顔をしていた。いつもみんながやることを観察し、自分のやるべきことをしっかり測った上で動いてたのだが、キンノコ堂では自然に、あるがままに動き話をする。どちらも小柳得馬という人間には違いないが、キンノコ堂にいる彼が本来の小柳得馬だと感じた。
「もうそろそろかな」
「私、ちょっと外に出てみる」
時計を見て呟く亞伽砂が止めるよりも早く史織が出ていった。
「寒いのに」
動いていたので薄着のままだと気づき亞伽砂は嘆息する。
初めて史織がキンノコ堂を訪れた日の夜、彼女からショートメッセージをもらった。SNSでお互いを登録したのにショートメッセージでのやり取りに意味があるのだろうか。
《キンノコ堂では、人を預ける事はできますか?》
《お客様が望むなら》
《では、小柳得馬を1人。無期限で》
《保管料がかかりますが》
《労働力でチャラにしてよ。安いでしょ》
《確かに。では、お預かりします〉
本人が知ったら面白がるものの嫌がるだろうが、メッセージはまだ消していない。
「亞伽砂、お客さん来たよ」
初冬の冷えた空気と共に詩織が戻ってきた。すぐ後ろから、飛騨映美が入ってくる。
「いらっしゃいませ」
ストールを肩にかけた彼女が、柔らかく微笑み返してくれる。
「お久しぶりぶりです」
表情だけでなく、映美は春に会った時よりも全体的にふっくらとしていた。
「お土産もらったの」
報告すると、自分の役目はここまでと史織は亞伽砂に役目を渡した。お客様を通すのは店主の仕事だ。
少しお腹が大きくなった彼女を亞伽砂は慎重に2階まで案内した。
笠置と里子がガラスの柱の暗幕張りを請け負ってくれたおかげで、作業はほぼ完了していた。
新しく購入したソファに案内された映美は慎重に腰を降ろし、柔らかな背もたれにゆったりと体を預ける。彼女の体調も考え、得馬と公宣の3人で訪問する形も考えたが、どうしてもキンノコ堂に来ることを映美自身が望んだのだ。
隣の机で作業をする得馬に様子を確認する。「繋がったよ」と頷けば、「プロジェクターも問題ない」と、部屋の後方で作業する公宣からも報告の声が上がった。
窓に張った暗幕の前のスクリーンに真っ白い光の四角が投影される。
映美を案内する亞伽砂と入れ違いに下に行った里子が詩織と共に戻ってきた。
まだ冬の寒さが残る季節、福島沖の海の上でキンノコ堂という古書店の店主から古びた本を受け取った飛騨康徳は、その後無事に航海を終え映美の元に戻ってきた。それから駿河湾沖を調査した彼らの研究チームは現在、日本海溝の生態系調査に出ているという。
出発前、康徳はキンノコ堂を訪れた。
「妻に渡したい本があるんです。いまはまだ日時も決まっていないが、必ず妻に手渡しで渡してほしい」
いつか海の上でちっぽけな漁船に立っていた店主の女性は、何も言わずに請け負った。
数週間後、キンノコ堂に一冊の本とメールが送信されてきた。メールには本を渡す日だけでなく場所と時間、追加の依頼が書かれていた。その追加の依頼を実現するために考えたのがプロジェクターによる上映会だ。ただし、スクリーンに映るのは映画ではない。
亞伽砂は映美の前のテーブルにポットに入ったティーセットとケーキ、それと一冊の本を置いた。
「飛騨康徳様より預かりました」
この即席の映画館には、もちろん集まったメンバーのための席もあった。映美のソファの後ろ用意された長テーブルの前の席にそれぞれが着席すると、公宣の声で照明が消えた。
まだ白いままのプロジェクターの光の中で、映美は懐かしい本を手に取りページを開いた。
古めかしくもおどろおどろしい挿絵の間にメモが挟まれている。
体の大きさに似つかわしくない、小さくて優しい夫の文字がそこにはあった。
最初、その映像を見せられても映美には理解ができずにいた。
どこかに固定されているビデオカメラ。正面に円形の小さな窓があるそこはかなり狭いらしい。
リズムを保つ音の中で交わされる、囁く人の声。
専門用語が多く、その上呟きに近いほどだが紛れもなく夫のものだ。
彼らの使う潜水艇は、日本人に馴染みのある「しんかい6500」ほど大きくはない。艇の半分を推進機関が占め、艇外には2本のマニピュレーターとカメラがあるのみ。操縦士は体を折り曲げ、バイクに乗るような格好で作業を行わなくてはならない。
飛騨康徳が妻に本を返すにあたってつけたもう一つの依頼。それは、初めて操縦士として潜る自分の姿をリアルタイムで見せる事だった。
船の衛星通信は一般には開放されていない。通信は一度研究所で受診した後、得馬の母校である裏の大学の研究室を経由して配信されている。
今夜、映美のためだけに開かれた回線だ。
「距離、3000……3100……」
妻を意識してか、時たま康徳は感想めいた独り言をいう。
ゆらゆらと半透明の生き物が通る。管クラゲやサルパの類だろうか。波打つ線毛がライトを反射し虹色の幻影を作るのだ。
深海の生き物達は気まぐれに円窓から艇内を窺い、誰も覗かない時はマリンスノーが微風に揺れる雪の如く舞う。これらは一般には海のゴミとされているが、深海に住む生物にとっては栄養価の高い食物となる。
「しばらく生物の姿を目にしないと、時間の雪に戸ざされた別世界のようだ」
康徳の声は緊張しているのか少し息苦しそうで、映美は思わず歯を強く噛み締めてしまう。夫のメモを持つ手にも力が入る。
「地上では太陽が巡り生物は生と死の時間を常に測ることができるが、光を失った世界はまるで生も死もない、時間の存在そのものが忘れられたような世界だ」
続けて康徳が専門用語で何かいうと、円窓の中に白い煙が静かに立ち上る。
海底にたどり着いた艇の底によりシルトが舞い上がったのだ。
「人間が地上に現れる遥か昔から、この雪は積もり続けている。そしてこれからも降り続けるんだ。音もなく、静かに」
※※※※※
「こんにちわ」
キンノコ堂に客が来た。
黒いスーツを着て黒いネクタイを締めて黒いサングラスをかけた男だ。
「検めの連絡を受けたものだが」
「三來様ですね。お連れ様はまだいらしてませんが、お待ちになりますか」
「まだ来ていないのか、あの者どもめ」
亞伽砂に目配せされ、公宣が三來という客を2階に案内した。
「こんにちは」
次に来たのも黒いスーツに黒いネクタイをした男だった。ただしサングラスはかけていない。
「えーと、紺日様ですか」
「いかにも。私がわかったというのなら、三來と加古はもう来ているのですね」
「お待ちになっているのは三來様です」
「やっぱりそうなのか、三來め。あやつはくるのが早すぎるのだ」
三來を案内してきた公宣が、三來と背格好が全く同じ男を見てギョッとした。
「ちょうどよかった。紺日様もお通しして」
先に通した三來という客のサングラスの下も、紺日と同じ顔なのかと公宣は考えながら2階に案内した。
「こんにちは」
3人めの黒づくめの男がきた。3人同時の検めの予約が入っている最後の1人、加古だ。加古は黒いスーツに黒いサングラス、ノーネクタイだった。
「加古様ですね。三來様と紺日様はすでにご到着しています」
「そうですか。なら勝手に上がらせてもらいます」
加古という男はさっさと店を出ると台所の方に回った。階段の下で公宣とあったのか、挨拶を交わしているのが聞こえる。
「今日の本、持ってきたよ」
外部に預けている本を取りに行っていた得馬が戻ってきた。
「ちょうどよかった。いま揃ったところなの」
「あの3人三子かなぁ」と、公宣も店に入ってくる。「そんなに似てるの」
公宣は得馬の抱えている本に目を向けた。大判でそれぞれ色の違うケースに入っていて重そうだ。
「体格がそっくり。2人はサングラスしてるんだけど」
本を抱える得馬の好奇心がウズウズとしているのがわかる。
「本が重そうだから、2人で持っていったらどう?」
店長席を離れるつもりのない亞伽砂が提案した。あの3人の客の検めは、毎年同じ日付の同じ時間に行うと決まっている。一度休日が合わないからと別の日を提案したが、頑として譲ってはくれなかったし、本を返すことも受け入れてはくれず、連絡は一方通行で、誰にどの手段ーメール、電話、郵便、電報ーで連絡をしても返事を貰えたことは一度としてなかった。
「今年もまた今日という日がやってきた」
2人の男が持ってきた本をそれぞれの前に置き、紺日が口を開いた。
「今日は未来に」
「未来は過去に」
「過去は今日に」
三角形にした机の上に置いた本を反時計回りに動かし、続ける。
「世を検める鐘が鳴り」
「世の姿を可視とし」
「世をここに留めん」
本をそれぞれの体の真正面に置く。
「ここに刻は生まれ」
「ここに刻は生き」
「ここに刻は死す」
ケースから本を取り出すと、同時に開いた。
「我、ここに在りきは罪悪なり」
赤と黒と白の何かが本の中から飛び出し、世界は闇に包まれた。
亞伽砂の背後で、2階から降りてくる足音が聞こえた。
「やあ店長さん」
「やあ店長さん」
「やあ店長さん」
亞伽砂と得馬と公宣の前の前でカウンターの前に横一列に並び、彼らは本を出した。
「今回も滞りなく行うことができました」
「次回もよろしくお願いします」
「ではごきげんよう」
三來と紺日と加古は寸分違わぬ手の振りで隊列を組んで出ていった。加古の背中が見えなくなるや否や、公宣が入り口に走る。
「本当に本、見たのかな」
彼らに本を届けてから3分も経っていない。
「もう姿も見えないよ。タクシーでも待たして置いたのかな」
怪訝な顔をして戻ってくる。
「僕がきた時には車一台なかったよ」
公宣は本を重ねる亞伽砂の手つきを見た。
「ダメよ、公ちゃん」
弟の考えていることなんて、姉にはお見通しだ。
「少しだけ見たいじゃん」
「見てはいけない約束なの」
「バレないよ、そんなの」
なおも手を伸ばす公宣のほっぺたを、得馬が思い切り叩いた。
「あ、ごめん」
「何⁉︎ 得馬さん、俺悪いことした⁉︎」
公宣の手を叩こうとした亞伽砂もいきなりなことに手を引っ込めないで驚いている。
「いや、ほっぺたに虻みたいのが」
得馬も自分の手の平を不思議そうにみているが、虫を叩いた感触も後もない。確かにいたと思ったのだが。
「いないよ、そんなの。俺叩かれ損じゃん」
「ごめんごめん。今度はよく見て追い払うよ」いつまでもぐずぐず文句をたれる公宣を他所に、得馬はカウンターの本を見た。
「じゃあ、また預けてくるんだね」
「俺も行くよ。今日はもう店は閉めるんだろ」
本来なら平日は店を開けないことになっているのだが、今日は3人の同時検めのために特別に開けたのだ。
「君も一緒に行くかい」
「私は電車で帰る。2階の窓を閉めてくるね」
店主席を立ち台所の方へ移動すると、得馬は本を抱き上げて外に出た。持ってきた時よりも若干軽くなっているのは気のせいだろうか。
階段を上がる亞伽砂の背中で、公宣が内側からシャッターを下ろす音がした。
2階の部屋は客人が去った後のままで、三角形に置いた机と椅子を元のように隅に移動する。
開け放たれたままの窓を閉める時に下を見ると、ちょうど公宣が店の外に出た時だった。
2人して2階の窓を見上げているので手を振りかえす。
古い商店街に寂しい影を落としていたアーケードは、老朽化と商店街消滅の事実のもとに先月取り払われた。
屋根に隠れていた祖父の掲げた看板は陽のひかりを浴びて、少し色がつき始めたニスのせいで金色に見える。
「じゃあ、気をつけていってきてね」
駐車場へと連れ立って歩く2人の姿を見送り、亞伽砂はもう一度店の面構えを見た。
アーケードの屋根によって長い間押し殺されていた何かが外れたのか、以前より面構えが若返って見える。毎月公宣が何らかのディスプレイをしてくれるショーウィンドーには、可愛らしい絵本とぬいぐるみが置かれていた。
店を継いで1年と少し。
条件付きでなら預かり業を再開してもいいと、亞伽砂は思い始めていた。
〈完〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
