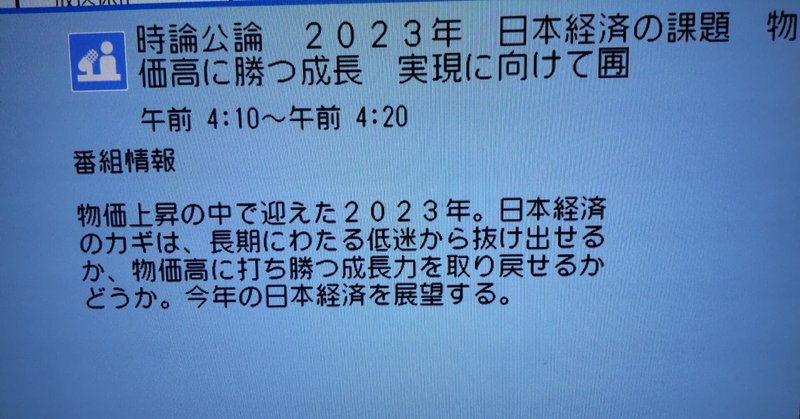
No.184【NHK総合 時論公論 2023年日本経済の課題 《物価高に勝つ成長 実現に向けて》視聴備忘録】
2023年となりもう1週間が経ちました。2022年はコロナ禍足掛け3年目となり、昨年初からのロシアのウクライナへの侵攻も収まらず、燃油やガスや電気等のエネルギー代、食料品代をはじめあらゆる物価が高騰しています。
しかしながら、日本ではバブル期以降30余年間、賃金はほぼ据え置かれ、また一人当たりGDPのランキングは30位辺りにまで大きく後退してしまいました。
対馬の経済も、小泉政権の三位一体改革で公共工事の急激な減少、様々な複合的要因による水産業の衰退、大型店舗出店ラッシュ等による地域小規模事業所の相次ぐ廃業が進行しています。
また、今世紀に入って対馬〜釜山間の国際航路の発展に伴い、観光業は対馬経済の大きな柱の1つとなるまでに成長を遂げました。しかし、日韓関係の悪化、更にはコロナ禍に突入して、未だ先が見通せない状況に陥ったままです。
さてそれではどうすれば、対馬の経済を回復させることができるのでしょうか⁉️
対馬市に限らず日本全体も各地方(自治体)で人口減少に歯止めがかからないことが、根本的問題であると様々な専門家が述べています。現在約2.8万人まで減少してしまっているのですから、何も大幅人口増加を目指すのではなく、約3万人が生活できる規模の島の経済圏の確立を目標に取り組んで行けば良いと割り切るべきだと私は感じています。
それを踏まえて、対馬経済の将来ビジョンを示し、具体的にどんな経済施策を実践しようと思っているのか、市長及び議員は喧々囂々議論を戦わせる使命があると、私は思います。
《1.市内の事業者に補助金に頼らずとも経営が持続できることを目指させる(個の経営状態の改善)》

《2.地域事業者の共存共栄体制の構築》

《3.グローバルな視点での事業展開》

②ESG投資に適う事業を考案して投資を呼び込む(海洋漂着ゴミ回収と処理、再エネ生産体制構築、森林再生、有害鳥獣駆除と利活用、磯焼け海藻消滅阻止等、対馬市はESG投資の宝庫)
③求人と求職のマッチングを支援の体制の構築
(「対馬に仕事が無い」のではなく、「その求人に見合ったスキル等を保持した求職者がいない」ことが先ずは問題。雇用関連公的機関が協調して、求職者へ資格や技術取得勧奨を強力に推進する。)
ESG投資とは?👇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
